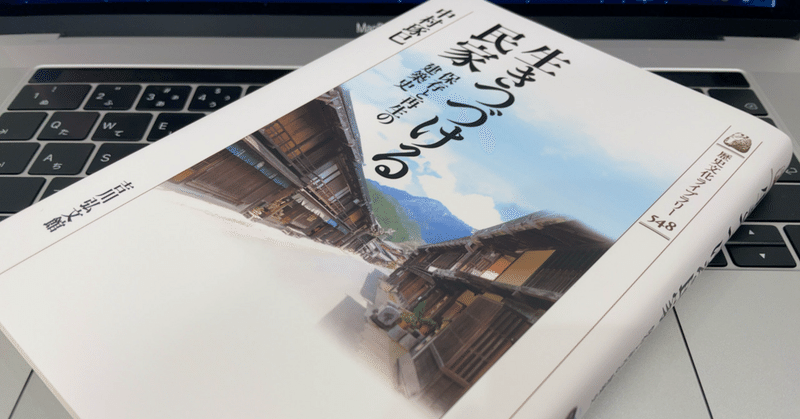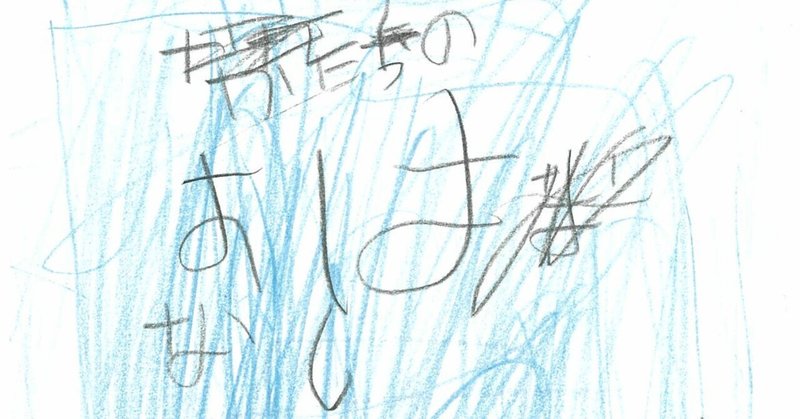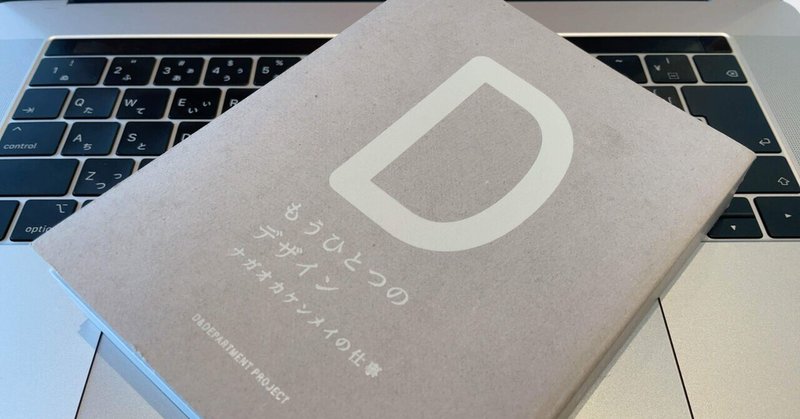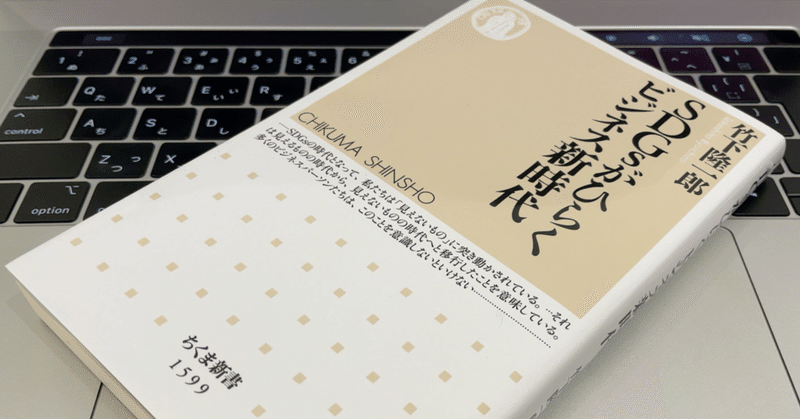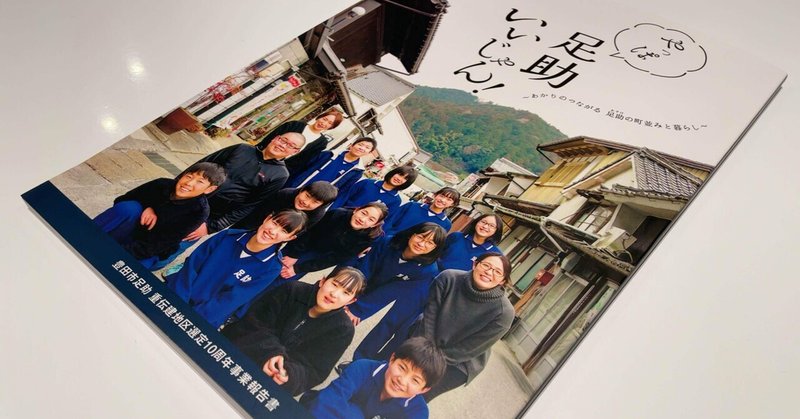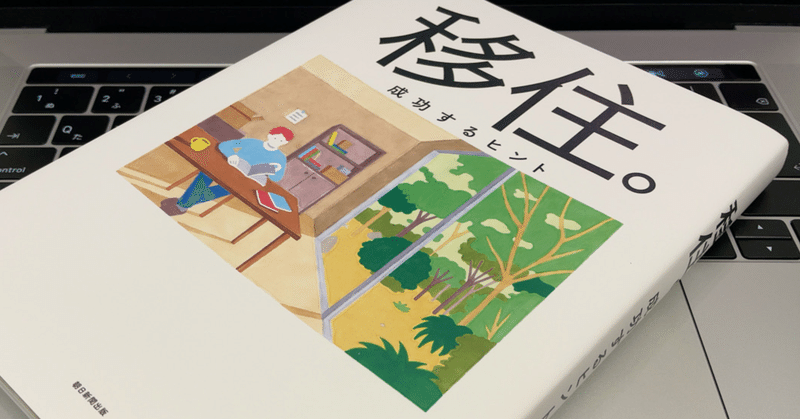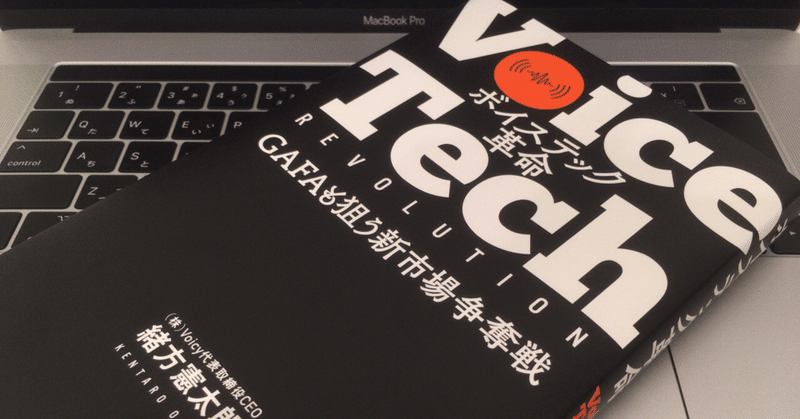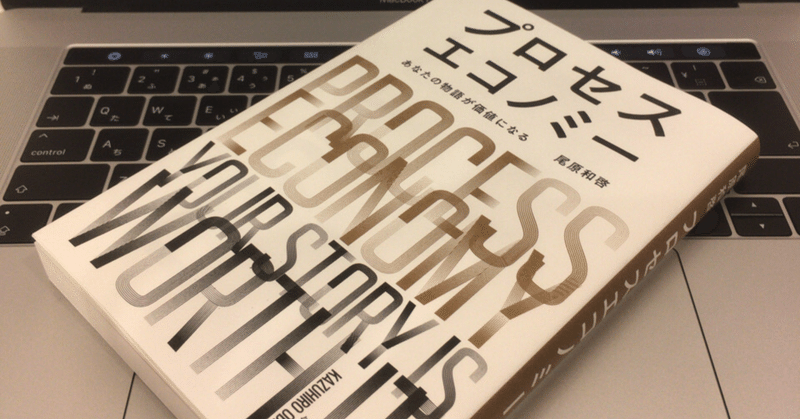記事一覧
「つくらない」をつくるデザインへの挑戦 -ナガオカケンメイ 著『もうひとつのデザイン』-
人々が日々の暮らしを営むために必要な、身の回りにある数々の「モノ」と、それらを形づくるうえでの重要な構成要素となる「デザイン」。
この『もうひとつのデザイン ナガオカケンメイの仕事』という本は、モノとデザインのより良い関係性について、あらためて読者に考える機会を与えてくれます。
以下に、この本の読書を通じて気づいたことや感じたことについて、メモしておきたいと思います。
【Discove
キレイごとで終わらせないために -竹下隆一郎 著『SDGsがひらくビジネス新時代』-
近年、日本国内においても随分と認知が広まってきたSDGs(Sustainable Development Goals / 持続可能な開発目標)。
この『SDGsがひらくビジネス新時代』という本は、SDGsが急速に広まっていく過程で起こった数々の出来事を考察しながら、この大きな社会変化の行く末について、いくつかの重要な視点を提供してくれています。
以下に、この本の読書を通じて気づいたことや
地域住民と行政の共働で、1冊の本をつくりました -『やっぱ 足助 いいじゃん! 〜あかりのつながる 足助の町並みと暮らし〜』-【無料デジタルブック】
この度、自分が長期間に渡り携わってきたプロジェクトの集大成として、1冊の本が完成しました。
本のタイトルは『やっぱ 足助 いいじゃん! 〜あかりのつながる 足助の町並みと暮らし〜』です。
この本は「Catalog Pocket(カタログポケット)」というアプリを通じて、パソコンやスマートフォンがあれば、全国どこでも無料で閲覧することができます。
※「音声読み上げ機能」「多言語自動翻訳
こどもを通して見えてくる「ことば」の不思議 -広瀬友紀 著『ちいさい言語学者の冒険』-
皆さんは、自分がこどもだった頃に、どのようにして言葉を話せるようになったか、覚えていますでしょうか??
この『ちいさい言語学者の冒険 -子どもに学ぶことばの秘密』という本は、こどもたちが話す言葉づかいをつぶさに観察しながら、こどもと言葉の不思議な関係性について迫っていきます。
以下に、この本の読書を通じて気づいたことや感じたことについて、メモしておきたいと思います。
【Discover
「空家法」の手に負えない空き家にご用心 -鈴木庸夫・田中良弘 編『空き家対策』-
総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」の直近のデータ(平成30年)によれば、今や7戸のうち1戸は空き家ともいわれている、日本の住宅事情。
この『空き家対策 自治体職員はどう対応する?』という本は、いまや全国共通の地域課題ともいえる空き家問題に取り組む際の、実務上の基礎知識を教えてくれます。
以下に、この本の読書を通じて気づいたことや感じたことについて、メモしておきたいと思いま
仮に誰も信じられなくなったとしても -峰宗太郎・山中浩之 著『新型コロナとワクチン 知らないと不都合な真実』-
2019年末以降、引き続き余談を許さない状況が続く、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック。
この『新型コロナとワクチン 知らないと不都合な真実』という本は、このパンデミックを収束させるために重要なツールとなり得る新型コロナワクチンについて、基本的な知識や向き合い方を教えてくれます。
以下に、この本の読書を通じて気づいたことや感じたことについて、メモしておきたいと思い
モノが売れない時代の新たなマインドセット -尾原和啓 著『プロセスエコノミー』-
書籍の発売前から話題となり、「Amazon 総合ランキング 第1位」の帯も大きくついた、注目の1冊。
この『プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる』という本を読んで、SNSが隈なく広がった世界においては、モノの売り方自体も変えていかなくてはいけないんだなと、あらためて感じました。
以下に、読書を通じて気づいたことや感じたことについて、メモしておきたいと思います。
【Discove