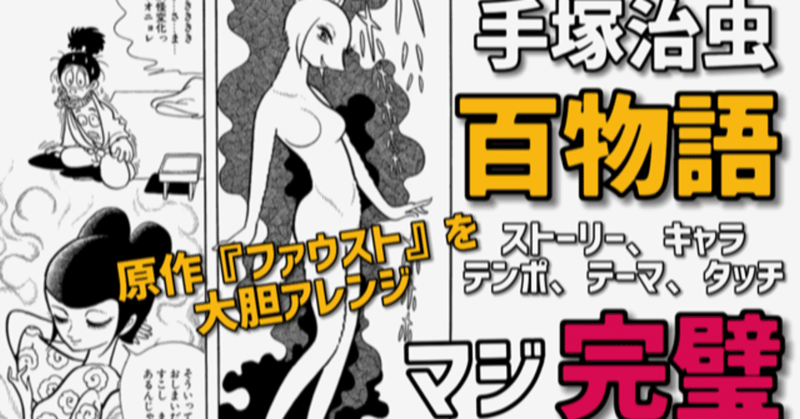2022年3月の記事一覧
第1170回 鳥の声のいろいろ
①https://www.photolibrary.jp/img436/185820_4203145.htmlより引用のイラスト
鳥類の声を分析してみると、高音で鳴くと遠くまで届かないですが、樹木などの遮蔽物(しゃへいぶつ)があっても届きやすいので、森や藪中でさえずりますウグイスやヒタキの仲間なんかは有利です。低音で鳴くと遠くまで届きますので、ビルなどの遮蔽物があると遮断されますので、カラ
第1168回 鱗のある鳥
①https://tsurinews.jp/110770/より引用の魚のタイの鱗
うろことネットで検索すれば「鱗」と漢字に変換されます。魚編だから当然に画像を検索しても①のように鯛などの魚の鱗が現れます。鱗を持っているのは、絶滅した恐竜は別として、鱗を持つ生き物は、そこから分かれた魚類、爬虫類、哺乳類では、ネズミ目の尾などに角質の鱗があり、センザンコウ類には、二次的に発達した鱗が背面全体を
第1159回 鳥の口
①https://oekaki-zukan.com/articles/9184より引用の鳥の口のイラスト
一般的に言いますと、鳥類の口腔は人で言う唇のような柔らかい口蓋を欠き、密閉出来ません。そのため、頭を下げたままでは吸水できない仕組みです。普通の鳥は水を含むと一々頭を上げ、重力で流し込みます。人なら口腔における消化は、消化酵素である唾液の中のアミラーゼがあり、少しは消化の助けになります
第1157回 鳥の聴力
①https://note.com/hiho2351/n/n0d1f9d9c62f8より引用の鳥の耳(写真はカワセミ)
①の写真のカワセミはこの項の話と直接関係ないものの、鳥類の耳はどこにあるのかの一例を示したものです。人と鳥類の耳を比較してみますと、人間の聴覚との大きな違いが5つあります。②の写真のような耳介とは、⑴人間の顔から突き出ている軟骨組織)がない。鳥類の耳な位置は目の後ろやや下
第1158回 鳥の舌と味覚
①https://www.google.co.jp/amp/fotrog.seesaa.net/article/473677691.html%3famp=1より引用のアオサギの長い舌
鳥の舌とネットで検索しますと、野鳥の部類では①の写真の大きなアオサギがぞろぞろ現れます。なるほど身体も大きい分、舌も長いです。舌は人でも鳥でも味覚を味わう身体の一部です。②のイラストは味を感じるための味蕾です
第1156回 鳥の視力
①https://www.google.co.jp/amp/s/gigazine.net/amp/20111029_birds_eyeより引用の野鳥の視力
私は自分の自己紹介をする時に「酉年生まれの鳥目」であると紹介しますが、本当に野鳥が鳥目であると言う事はなく、むしろ自然界に棲む野鳥は夜目も効くらしいです。人間の手により産まれるのも、育てられるのも人工的に飼育されている鶏などは、夜になる
第1153回 野鳥の羽根 ⑴
①https://global.canon/ja/environment/bird-branch/bird-column/kids1/index.htmlより引用の色んな野鳥の羽根
子供の頃に今みたいにに色んな遊び道具がない時代でしたから、お寺や公園に行って鳩と戯れたりした後に、鳩の羽根を拾って持って帰りました。今ではキジバトも街中に進出していますが、その頃にはドバトしかいなかったので、