
ジョルジョ・アガンベン 『瀆神』 : 「瀆神」と「瀆聖」の違い
書評:ジョルジョ・アガンベン『瀆神』(月曜社)
難解な書物である。哲学書なのだから、それは当前だと思われる方も多いはずだが、Amazonに本書のカスタマーレビューを寄せている人たちは、おおむね本書を「簡明」だと評している。「簡明」とは、無論「簡単明瞭」ということである「複雑ではなく明らかで、わかりやすい」ということだ。一一しかし、私はそうは思わない。

たしかに、140ページほどしかない本書には、エッセイとも詩文ともつかない思弁的な短文が10篇も収められている。つまり、個々の文章は短く、これを「小編」と書いているレビュアーもいる。
さらに、私が「エッセイとも詩文ともつかない」と評したように、文章的には、決して読みにくくはなく、むしろ素直かつ流麗な文体で書かれていると言っても良いだろう。訳文も良いのであろう。一一だが、「短くて読み易い」ということがそのまま「簡明」だとは限らないというのは、「文学読み」にとっては、常識に類する話だ。「長編小説より短編小説の方が、わかりやすいか?」といえば、無論そんなことはない、ということである
「わかりやすいか否か」というのは、その文章の「長さ」に比例するものでもなければ、「文体」的に「平明か否か(平明な文体か、晦渋なな文体か)」に関わるものでもない。
例えば「神は死んだ」という、ごく短い文章の意味を理解するのは、簡単なことだろうか? この文章は、内容的に「簡明」だと言えるだろうか?
「昔とは違い、もはや現代人の中には、神は生きていない、という意味だろう」と、そう答える人はいるだろう。たしかにテストの答案としてなら、それも間違いではないだろう。だが、そう答えた本人は自分も「現代人」のつもりでそう言っているわけなのだが、はたして彼の中でも「神は死んで、もういない」のだろうか?
彼は、いっさい「神頼み」も「縁起担ぎ」も「祭事」もしないのだろうか?
「いや、社会生活における方便として、やっているだけで、信じているわけではないよ。その意味では、私は、近代以前の人々、神が殺されるまでの人々とは違う」とでも説明するのだろうか? しかし、それは本当のことなのだろうか?
例えば、彼は、「世間の目」を気にする必要のない、自分一個の心の中でも、一切「神頼み」も「縁起担ぎ」も「祭事」しないのだろうか? また、それをしなかったがために「不安」を感じたりはしないのだろうか?
例えば、彼は、誰も見ていないところでなら、神札や曼荼羅やイコン(聖画)を踏みつけにできるだろうか?
「できる」という剛の者に聞きたいのだが、あなたは「親の位牌」や「親の遺影」を踏みつけ、踏み躙ることができるだろうか?
それが「できる」人はいないと思う。いたとすれば、もはやその人は精神を病んでいる。私のような、かなり頑固な「無神論者の無宗教者」であっても、そこまではできない。
なぜ、できないのかと言えば、どんなに「宗教」を否定したとしても、人間の「心の中」には「聖なるもの」が存在するからだ。
それは、「心の外」には存在していないのだが、「心の中」に存在しているので、世間の目が一切なくても、その「聖なるもの」を蔑ろにすることはできないのである。
では、そんな私たち自身にとって、本当に「神は死んだ」と言えるだろうか?

たしかに「キリスト教の想定する神」は、昔ほどの力を持たなくなったとは言えるだろう。いや、キリスト教だけではなく、多くの既成宗教の「神」や「仏」や「超越者」は、昔ほどの「信憑性」をもはや失ったと、そう断じても良いだろう。
だが、私たち現代人は、その代わりとなる「新しい神や仏」を発明しては、それを盲信することで、その「宗教心」を満足させているのではないのか。
のちに紹介する、本書所収のエッセイ「瀆神礼讃」によれば、「資本主義」こそが、何よりも強力な「宗教」だということのようだ。たしかに、なるほどと感じるところがある。
例えば、昨今はやりの「推し活」において、文字どおり「神」と呼ばれる存在に金を遣うことは「お布施」と呼ばれるが、ここまで来ると、彼ら彼女らは「存在しない神」に「お布施」を払うことで「救済の実感」を担保しているのだと、うすうす気づいてはいるのであろう。
本当は、それが「神」でも「仏」でもなく、「ただの人間」であるとか「ただのモノ」であると頭では理解していながらも、その理性的判断には目を瞑って、その「資本主義的な偶像の消費」に身を任せる快楽を選んでいるのではないだろうか。
だが、「目を瞑る」というのは、自覚的なものだからこそ、人から「そんなもんに貢ぐのは無意味だよ。愚かしい」などと言われると、「そんなこと、言われなくても、わかってやっているんだよ」と、腹が立つのではないだろうか。
そんなわけで、「神は死んだ」という言葉を知っている人は多いし、その「テスト答案」的な意味を理解している人も多いのだが、それで、自分も「神を殺し得ている」と考えるのは、いかにも浅はかで愚かなことだと言えるだろう。彼は、「神は死んだ」という言葉は知っていても、「神は死んだ」ということの意味を、まったく理解していないのだ。そもそも考えたことすらないのである。だからこそ、簡単に「知っている」と言い「わかっている」と言える。
彼の中では、「知っている」と「わかっている」は、ほとんど同義なのだが、ここまでの説明を読んだ人なら、それがいかに愚かな「無考え」であり「自己盲信」でしかないかがわかるはずだ。
例えば、次の文章は「わかりやすい」だろうか?
『 わたしが愛する写真の何がわたしを引きつけ、魅了してやまないのだろうか。それは単純にこういうことなのではないかと思う。写真はわたしにとって、どことなく、最後の審判の場所であり、最後の日、すなわち怒りの日に現れる世界を表象しているのである。それはたしかに主題の問題ではないし、わたしの愛する写真が重大で深刻な、悲劇的でさえある何かを表象していると言うつもりはない。そうではなくて、写真が表すのは、顔でも物でも、どんなできごとでもかまわない。』
(P31「審判の日」冒頭部)
私は、この文章が「わかりやすい」とは思わない。
そもそも、ここでのひとつの単語でしかない「最後の審判」という言葉の意味を、ひととおりでも理解している日本人など、ほとんどいないはずだ。かく言う私も、多少「キリスト教神学」を齧ったからといって、とうてい理解しているなどとは言えない。
しかし、それはキリスト教徒だって、じつは同じことであり、さらに言うと「キリスト教神学者」だって、じつは同じなのだ。現に、神学者の間でも「最後の審判」を「どう理解するか」については意見が分かれているし、そもそも「聖書」の読み方に「正解は無い」(神の言葉を人間が完璧に理解することはできない)のだから、「最後の審判」の意味を確定することなど、人間には、原理的に不可能なのである。
だから、ここでは、本書の著者アガンベンが、「最後の審判」というものを、どのように考えているのかということを理解しないことには、この文章の意味を理解することはできない。
ところが、この短文に書かれていることは、少なくとも私には「簡明」ではないから、アガンベンの「最後の審判」理解も、よくわからない。

なのに、この「簡潔」であり「懇切丁寧」とは言いかねる文章を読んで、「簡明」だと評するような人たちは、どうして「理解できた気」になれるのだろうか?
彼ら自身「キリスト教神学」に熟達しており、「最後の審判」と言えば「これだ」という確信を持っていて、その「自身の定義」をもとにして、アガンベンの議論を理解したと、そう思っているのだろうか?
ある意味では、それしかないのだが、それはそもそもアガンベンの文章を理解したことにはならないだろう。
ならば、せめて「自分なりの理解」を示すべきなのだが、彼らがそれを示すことはない。ただ「アガンベンの書いていること」が「わかった」と言っているだけで、根拠の提示などは、どこにも無いのである。
そんなわけで、私に関して言えば、本書に収められた10篇の中で、多少は「わかる部分もあった」と言えるのは、最後に収められた「瀆神礼讃」だけだった。それ以外は「わからなかった」のだ。
それにしてもなぜだか、「瀆神礼讃」の冒頭は、スッと入ってきて、ハッとさせられ、なるほどと納得させられた。
次のような文章である。
『 古代ローマの法学者たちは「神聖を汚す[profanare]」という語が何を意味するかを完壁に知っていた。神聖な事物、あるいは宗教的な事物とは、なんらかの仕方で神々に属する事物のことであった。そのようなものとして、それらは、人間たちの自由な使用と商取引の対象から除外され、売ることもできなければ、抵当に入れたり、使用権を譲渡したり、地役権を課したりすることもできなかった。瀆聖とは、それらを利用することのこの特別な不可能性に違反するあらゆる行為のことだった。それらは天上の神々または地獄の神々に独占的に与えられていたのである(天上の神々のためのものがまさしく「神聖な」と呼ばれ、地獄の神々のためのものはたんに「宗教的」と呼ばれていた)。』(P105)
痛快なほどに、わかりやすかった。
しかし、それまでの9篇があれほど理解不能だったのに、どうしてこの文章だけが、全部とまでは言わずとも、その一部でも「わかった」と言えるほど理解できたのか?
この文章が、特に平易に書かれていたからだろうか? そうかもしれないが、たぶんそうではないだろうと私は思う。
要は、私はこの文章が扱っているテーマに関しては、それだけ深く考えてきたから、そのぶんだけは、わかりやすかったということだったのではないだろうか。
この「瀆神礼讃」が何を語っているのか、「聖なるもの」について考えたことのない人、無自覚に「神頼み」や「縁起担ぎ」や「祭事」をやれる人には、たぶん理解不能だと思うので、私なりの説明をしておこう。
「瀆神」とは「神を瀆す(汚す・穢す)こと」であり、要は「聖なるもの」であるはずの「神を瀆すこと」である。
「聖なるものを瀆す」というと、「清純派女性タレントの写真の顔部分を、別のヌード写真に貼りつける」とか「キリスト像にウンチをなすりつける」とかいったようなことを、私たちは思い浮かべるだろう。映画『エクソシスト』(ウィリアム・フリードキン監督・1973年)で、悪魔に憑かれた少女の発する「冒瀆的(瀆聖的)な言葉」とは、この種のものである。「清潔なる神父さま、あなただって、この美しい女の体が欲しいと思うでしょう?」などというやつだ。
しかし、アガンベンがここで言っているのは、『神聖な事物、あるいは宗教的な事物』『なんらかの仕方で神々に属する事物』を『人間たちの自由な使用と商取引の対象』とする等のことであり、『瀆聖とは、それらを利用することのこの特別な不可能性に違反するあらゆる行為のことだった。』のである。
つまり、「聖なるもの」で「金儲け」をしたり、「自分を権威づけたり」するようなこと、元来『特別な不可能性』を持つ、人間の生活とは切れたものであるはずの「聖なるもの」を、「世俗的に利用する」ことは、すべて「聖なるものを、人間の手垢に塗れさせる」行為として「瀆聖」なのである。一一したがって「宗教」とは、すべて「瀆聖」なのだ。キリスト教以下、すべての「宗教」が、である。
では、私たちは、「聖なるもの」に、どのように対すればいいのだろうか?
「敬遠」すればいいのである。文字どおり「敬して遠ざける」。要は、気易く近づいたりはしないということだ。それが、私の考えだ。
「聖なるもの」を、文字どおり「畏れ多い」ものあり「自分などが、知り合いヅラをして擦り寄ったりはできないもの」であると理解して、あえて、それについては、近づきもしなければ、語りもしないのである。
そもそも「聖なるもの」は語り得ないのだ。語りうる「聖なるもの」とは、人間の捏造した「偶像としての神」でしかなく、それを語ることは、当然「瀆聖」でもなければ、本来の意味での、つまり、「瀆聖」という意味での「瀆神」でもない。
そもそも、人が「利用」できるものなど、それは「聖なるもの」ではなく、「聖なるものの偽物」なのである。
だから、「無神論者」が「神などいない」と言う場合の「神」とは、人間の都合ででっち上げられた「宗教」の語る「偽物の神」のことであり、本物の「神」のことではない。
無神論者が「神はいない」という場合の「神」とは、「宗教が言うところの(偽の)神」のことであり、そんなものは「いない」、「嘘っぱちだ」という意味なのである。
だから、こうした「無神論者」的な意味での「瀆神」は、じつのところ「瀆神」ではなく、アガンベンが言うとおり『神聖な事物、あるいは宗教的な事物とは、なんらかの仕方で神々に属する事物のこと』だと正しく理解して、身の程わきまえ、それを『人間たちの自由な使用と商取引の対象から除外され、売ることもできなければ、抵当に入れたり、使用権を譲渡したり、地役権を課したり』しないこと、つまり「敬遠」することなのであり、しばしば「瀆神」だと誤解される「宗教」批判は、じつのところ「聖なるもの」への、正しく「敬虔」な態度だと言えるのである。一一「私なんぞが軽々に、神を知っている(理解している)、などと言うことこそが、何よりの瀆神なのだ」と、そう理解している者の態度だということなのだ。
本書が「簡明」だというような評価を「語った」人たちは、たぶん「訳者あとがき」の次の部分を、そう早とちりしたのであろう。
『 本書の内容については、とくに解説の必要はないとおもう。著者みずから「とても大事におもっていることです」と私信でうち明けていることがらが簡潔ながらもわかりやすく語り出されている。』(P138)
この『簡潔ながらもわかりやすく語り出されている。』という部分を「簡潔でわかりやすいことが書かれている」と「誤読」したのではないか。
だが、訳者が書いているのは『簡潔ながらも』であって「簡明に」ではない。しかも、「ながらも」という反語表現が意味しているのは、「本来ならば、詳しく説明しなくては、容易には理解しがたい内容なのだが」、『簡潔ながらも』ひとまず書かれてはいるということであり、要は、この「簡潔」な語りに込められたものは、むしろ「意味深長」で、その意味で「難解」なのだ。
それは、アガンベン自身が『とても大事におもっていること』だと言うほどなのだから、当然の話ではないだろうか。
また『わかりやすく語り出されている。』というのは、「内容がわかりやすい」という意味ではなく、「語り出し」が「わかりやすい」ということであり、言い換えれば、語り口自体は「晦渋なものではない」というほどの意味なのではないだろうか。
このように、訳者のこの言葉は、本書に収録されていた10篇の文章を、「簡明」だと保証するものでは、まったくなかったのだが、それを読み取れなかった人たちが、語り口の平明さ見て、中身まで「簡明」だと思い違いし、それでわかったつもりになって、「簡明」だと口真似的に評したのではないだろうか。
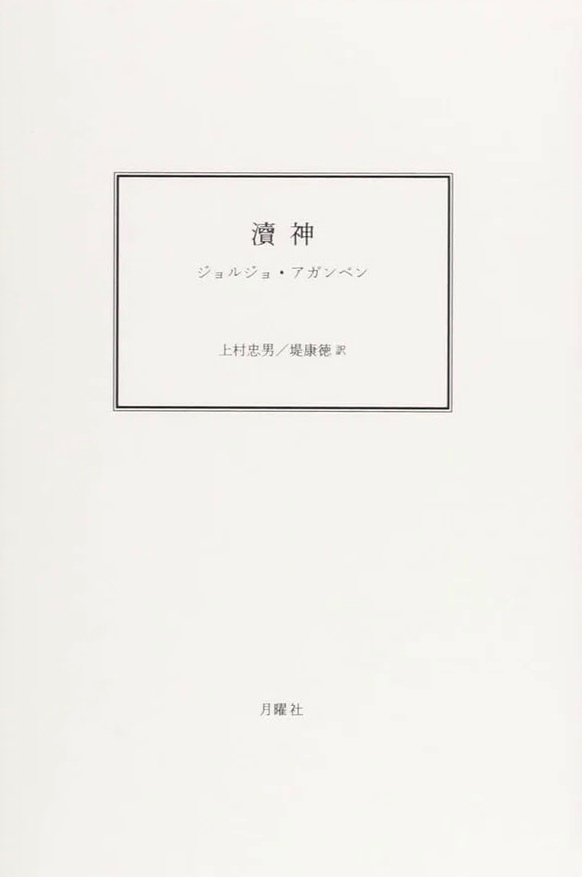
私自身は、アガンベンのファンだから、私のような者が「全部わかりました」などという、身の程をわきまえぬ言葉を軽々に口にすることはできず、「難しい」「わからない」と「敬遠」の言葉を口にするしかないのだが、安易に、アガンベンを「わかった」などという人は、アガンベンを、「自身の身を飾る道具(装身具)」くらいにしか考えていないから、そんなことを平気で言えるのではないか。
つまり、「聖なるもの」を『人間たちの自由な使用と商取引の対象』とし、『売ることも』すれば、『抵当に入れたり、使用権を譲渡したり、地役権を課したりすること』もする人たちなのではないか。『瀆聖とは、それらを利用することのこの特別な不可能性に違反するあらゆる行為のことだった。』のだが、アガンベンを「簡明」に理解できるなどと言って、その権威の「人間的な取引き」に利用しようという態度こそ『特別な不可能性に違反する』行為の一種であり、要は「瀆聖」そのものなのではないだろうか。
安易に「神を語る」ものは、「偽の神」を語ってみずからを権威づけるのだが、その「神」が偽物だとはまったく気づいていない。たぶん彼は「資本主義」という強力な「偽の神」を心から信じ、帰依しているのである。
ともあれ、「聖なるものの道具化」一一これが、私の理解した「瀆聖」ということの意味である。
そして、「聖なるものの道具化」に対抗するのは「偽の神を瀆すこととしての瀆神」なのではないか。そのことによって、「偽の敬虔」に陥らない、ということなのではないだろうか。
「瀆聖」とは、「聖なるものを道具化できるという、その傲慢」から出るものなのであろう。
「俺だって、神になれる」という「サタンの傲慢」が憑いた時、人は「瀆聖」に走るのである。

(2024年5月28日)
○ ○ ○
● ● ●
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
