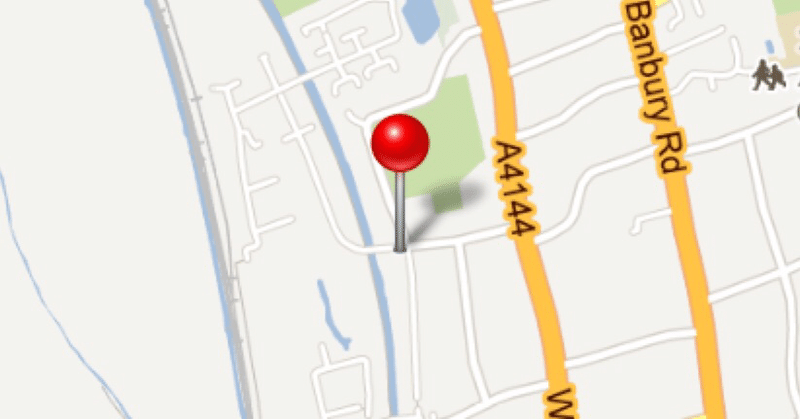#練習
感じられないものはない?
感覚として感じられないものは、
ないものとしてしまうことってありませんか。
例えば肩こり。
肩が凝ってしまい痛みとして
感じられて、初めて
「あ、肩凝ってるな」と認識します。
でも、感覚として感じないけれど、
肩が凝り始めた時ってあるはずです。
その凝り始めに、気づけたら。
なにをしている時に
凝り始めることになっているのかを
知ることができたら。
肩が凝ると思うまでに
そのこり始めた原因
姿勢が良くなり呼吸がラクに。
アレクサンダーテクニークで自分自身を再教育していくと
なぜ姿勢が良くなり呼吸がラクになることがあるのか。
習慣的なものは強く
新しいものは弱い
この考えをもとに機能的に有利に動こうとすると
どうしても今までやっていた機能的に不利なものを
やめていかなければならなくなります。
習慣的にやっているものの方が強く働くからです。
新しくやろうとする機能的に有利な動きをしようとすると
習慣的にやって
すぐに上達するって。
専門性の高いものはなんでもそうですが、
「すぐに上達する〜」というもの、みなさんはどう思いますか?
これさえやればオッケーみたいなやつです。
タイトルで釣っているものは別として
そんなものあったら私が欲しい。
地道に続けるしかないことって意外とたくさんある。
それでもやっぱりコツがあるなら知りたいし、
近道があるなら教えて欲しいというもの。
コツを聞いてできる人はいます。それは間違いないです
正解を選び続ける? ②
ここで言う正解は
それが真実であるということではありません。
一般的に言われる正解とは意味が違います。
「自分にとっての」とカッコ付きです。
慣れ親しんだものや、
習慣でやっているもの
知らず知らずやっていることなどの
無意識とも言ってもいいかもしれないこと。
間違いではないと思っていること。
疑問も持つことがないこと。
歩き始めを右足から出すこととか、
コップは左手で取るとか。
意識せず
ラクに吹きたい! エンドピン問題
アルトクラリネットを手で持っているかのように吹くことが
少しわかってきました。
エンドピンを使って床に置いて吹いているんですが、
そのときに姿勢よく座った時の口にマウスピースを持ってくると
そこから動きづらかったんです。
姿勢良く座った時というのは
一番背が伸びている状態なので、
呼吸やその他の動きに対応できなかったんです。
エンドピンでおいているところ、
一番背が伸びているところ、
そこにマ
意図していない動き③ やめたいのにやってしまう。
やりたくなくても、やらないと決めても、やってしまうこと。
歩き出すときにどちらの足から出しますか?
特に決めていなくても大体同じ方の足から出すのではないでしょうか?
いつもとは違う方の足から出すと違和感がすごいと思います。
習慣的な動きって何も考えなくてもできるようになっているから便利なんです。
考えなくてもできるので、その分他のことにまわせる。
車の運転なんかもそうですよね。
アクセルブレ