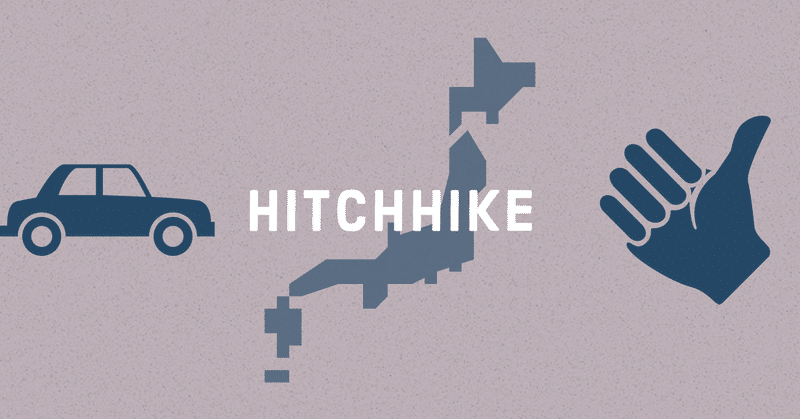2020年10月の記事一覧
アレクサ、電気をつけて
家に帰って玄関のドアを開けると、家の中は真っ暗だった。
おかしいな、と思って足元を見る。
玄関には妻の靴が奇麗に揃えられてお澄まししていた。という事は、妻はもう帰宅しているという事だ。
僕たち夫婦にはまだ子供がいないので、二人ともフルタイムで働いている。
ただ場合によっては夜勤もある不規則な僕の勤務体系と違って、妻の仕事は定時が決まっているので大概は家に帰るのは妻の方が早い。
だから僕よりも先に
冬を迎えるタイミング
炬燵を出すタイミングが分からない。
それはもう毎年のように悩みに悩んで炬燵を出している。
最近では足の高い机に後付けで取り付けるタイプもあるけれど、我が家にあるのは昔ながらのローテーブルのタイプだ。
ライターの仕事をしている私は最近もっぱら家で執筆することが多いのだけど、私の作業はリビングに置いたローテーブルでやることが多い。
たまにソファに座ってノートパソコンを膝に置いて作業するくらいか。
い
「彼女の傘のゆくえ」~江戸傘張り恋慕情~
傘を広げたのは、ぽたぽた、と雨の音が聞こえたからだ。
しかし傘を広げたところでお清(きよ)が目にしたのは、何の拍子にか先の所の油紙が破けてしまっており、最早その傘が役目を果たさなくなった、という事実だった。
「ああ、なんてこと。せっかく善次郎様が仕立てたものなのに」
しかし傘張りの腕も名高かった青山の善次郎はもうこの町にはいない。
ある日突然、お清の父親の清兵衛が営む長屋から忽然と姿を消して
ほろにがいココアをひとくち
台風が日本列島を頻繁に訪れる様になり、季節はすっかり秋の衣を纏っている。街路樹の葉っぱも頭の上から順番に色づいてきていて、ときおりかさかさと茶色の落ち葉が落ち始めているのを見かけるようになった。
そろそろ手袋も必要かな、と自分の手を見ると小さいささくれが出来ていて、見ているうちに私の心もささくれてくるのが分かる。
「……いや、なに浸ってるのよ透子」
「いいじゃない、ちょっと浸るくらいさせてよ」