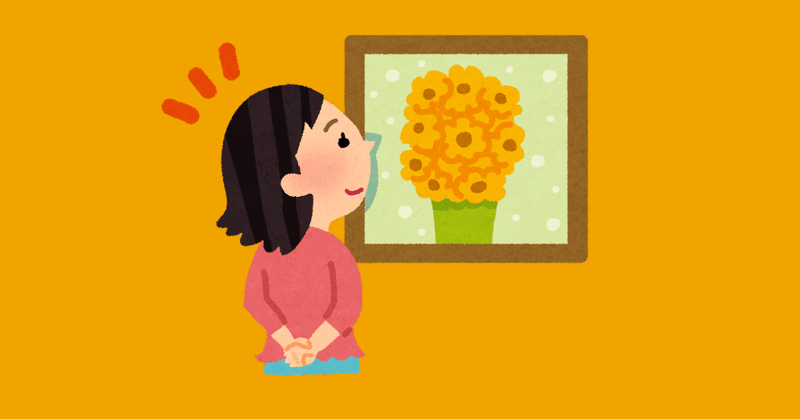
美への認知と正しさの価値基準
これまでも何度もこのコラムでは「気づき」をテーマに取り上げてまいりました。
気づきは、比較から生じるということ。
そして、その比較は「正しいものさし」を身につけておくことで、正しくない事象が判別できるようになるということ。
ものさしとは、思考や価値観、そして価値基準のこと。
そして、つい最近読んだ記事にとても興味深い一文を見出しました。
中野信子さんという脳科学者の対談コラムでしたが、そこにあったのが
脳内で美を認知する領域と、倫理的な正しさを判断する領域は、ほとんど一緒
という衝撃的な言葉でした。
環境は心のあらわれ
考え方が行動となり、その行動の積み重ねが環境に反映されます。
上記の方程式にはプラスとマイナスの要素があります。
つまり、
正しい考え方が正しい行動となり、正しい行動の積み重ねが正しい環境となる。
そして、誤った考え方が誤った行動となり、誤った行動の積み重ねが誤った環境となる。
ということです。
これを前述した言葉に当てはめて考えてみると、
正しい環境を美しいと認識できる人は、正しさを判断できる倫理的な基準を持っており、反対に倫理的な基準を持っていなければ、美しさとは何たるかの認識が働かないがために、正しい環境の判別がつかない
という解釈になります。
ここにまさに、「職場環境を正しく保っておく意味」というのがあるのだな、とあらためて考えさせられたわけです。
ひとつには、礼儀や規律。
正しい、丁寧な言葉遣いをお互いが意識してみる。
決められたルールや約束は必ず守る。
以前、「礼節の効能」というテーマでも触れましたが、無礼は無礼を生み、礼節は礼節を生み出します。
もうひとつは、整理と整頓。
職場の環境を常に清潔に保つこと。
不必要な物や使用予定のない物、特に一年以上未使用のものは全て捨て去ること。
捨てるだけではなく、普段使いのものについても、今その時点で不要な物は置かない。
使用していないものを放置しない。
例えば、退社時には机の上はパソコンのみの状態に戻して、それが正しい状態であるという基準にして、それが美しい状態であると認識できるようにする。
ゴミ箱も業務終了時には空にして、翌朝出社した時には何もない状態を当たり前の環境としておく。
こうしたことを徹底することで、職場の環境が正しく保たれるようになるのだと思います。
まさに、美への認知と正しさの価値基準というのは連動しているのだなと感じます。
今日も読んでくださいまして、ありがとうございます。
嬉しいです。 サポートしていただきまして、ありがとうございます。 こちらからもサポートをさせていただくことで返礼とさせていただきます。 どうぞ宜しくお願い致します。
