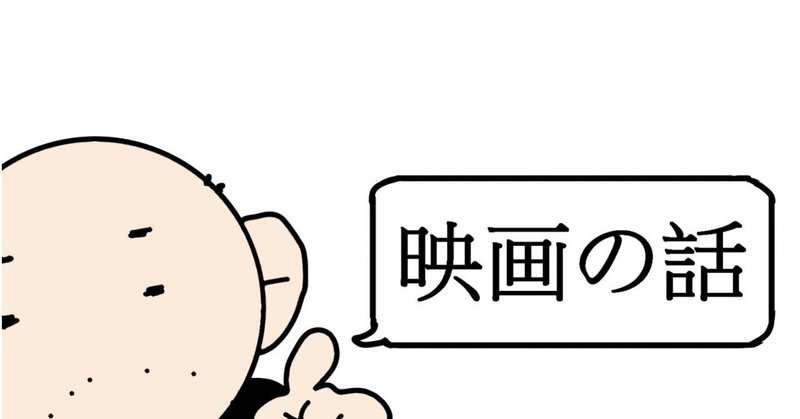2020年4月の記事一覧
\【毎週水曜日配信】ポッドキャストはじめました!/
始まったステイホーム週間のリラックスのお供に。
そしてZOOM会議などで目が疲れているみんなに、耳からクリエイティブなアイデアや取り組みをお届けする音声メディアを。
話題のプロジェクトや、アートやカルチャーにまつわる情報を掘り下げる、ポッドキャスト番組『MOTION GALLERY CROSSING』スタートします!
ナビゲーターは、編集者・武田俊さん&演劇モデル・長井短さんです!
是非、Spo
カンフーと私の歴史。
先日の金曜日の夜、夫とジャッキーチェンの「酔拳」を見た。
今はパソコンでいろんな映画を見られる。
この映画は、私にとってすごく人生への影響が大きかった大好きな映画なんだ。
酔拳を始めて見たのは、中学2年生の頃。
ジャッキーチェン扮する主人公は不真面目で、とても厳しい師匠のところに酔拳を学ぶために修行に出るという話。
酔拳はまるで酔っているように見えるカンフーの流派。
当時の私はアクショ
ある意味駄作なんだけど偏愛してる映画『ボルサリーノ』
いままで観てきた映画の中で、自分的に「座右に置いておきたい映画」を少しずつ紹介していくコーナーです。
なんか、言っちゃえば「駄作」なんだけど、どこかで深く愛している映画ってありませんか?
ボクはわりとたくさんある。
その中でもこの映画は最右翼。
大好きだけど、見直すたびに「うわ、こんな駄作だったっけw」って笑っちゃったりする。
でも、なんか好きなんだよなぁ、この映画。
たぶんこの映画、ボ
大林宣彦監督、、、φ(..)
角川映画全盛期に育ち、尾道三部作はテレビ放映で見る程度の接し方ではありましたが、当時女子大生だった私は、関西の劇場でこの映画を観ました。
そして忘れえぬ場面、、、
「弟なんて、いなければよかった」
普段喧嘩ばかりしている弟が行方不明になったときの、姉(伊藤歩さん)の台詞です。字面は素っ気ないのに、行間から「心配でたまらないよ!」という悲痛な声が聞こえてくるようでした。
愛情がなければ希望が