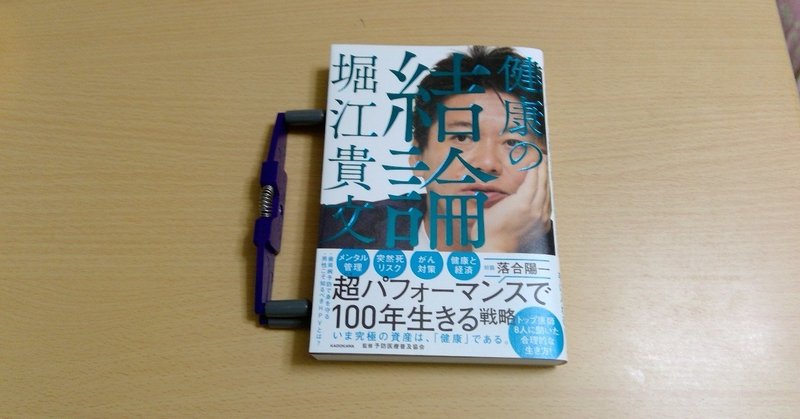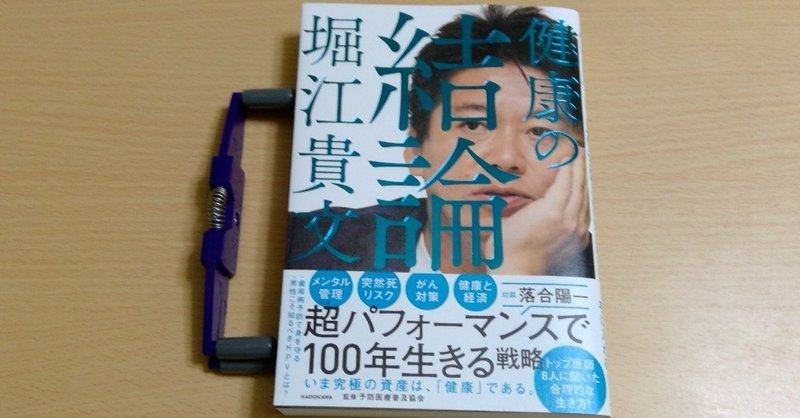2018年8月の記事一覧
健康の結論を読んで5 リスカと自殺。過度な共感や、「自分がなんとかしてやる」という気持ちは逆効果
日本人の自殺リスクを考慮する上で一つ注目すべき現象が若者の「自傷行為」だ。
日本では10代のおよそ10人に1人は自傷の経験があるという。
自傷行為の中で最も多いのは刃物で手首に傷をつける「リストカット」だ。
自傷とは、心のつらさ、苦しさを何とかしようとしたときに代替的に行う行為である。死にたいほどつらい気持ちを体から切り離そうという気持ちから派生することが多い。
時折、SNSで「死にたい」と
健康の結論を読んで3 人間、ずっと若者ではいられない
今、職場でメンタルヘルス不調の人のほとんどが
「一人で抱え込みすぎました」と語るそうだ。
特に男性は弱みを見せたくない、という人が多い。
エリートタイプの人ほど感情を押し込めがちなので注意してほしい。
自分の感情を抑える事が「大人」と思い込んでいる人も多いだろうが、もっと日頃から感情を外に対して見せるべきだ。
言ってしまえば「社会人としていかがなものか」という考え方自体がもはや死語と化してい
健康の結論を読んで2 「長時間労働時代」から、「長期間労働時代」へ
この70年ほどで日本人の平均寿命は約30年も伸びた。
このままいくと国内では2050年までに100歳以上の人が100万人を超えるという予測があるそうだ。(国連推計)
以前、落合陽一氏が「ワークアズライフ」(睡眠時間以外は全て仕事で、仕事=趣味の生活)という概念を提唱したが、最近はその考え方が一般のサラリーマンレベルにまで浸透しつつある。モチベーションのある人は中高生でも起業する時代だし、定年後に
「海馬/脳は疲れない」を読んで15 天才とは「思わずやりすぎてしまった人」の事
あることを覚えさせたネズミの脳を取り出して、すりつぶして、もう1匹のネズミに飲ませて記憶が移るかどうかの実験をしていた。
これは20世紀中の実験と、そう昔の事でもない。
それくらい脳の研究はここ近年で急成長している。
心とは心臓にあると信じられていたが、脳の事がだんだん分かり、
「心とは脳が活動している状態」のこと、というのが認知されつつある。
本書の著者、池谷さんは「東大薬学部に進学する時
「海馬/脳は疲れない」を読んで13 やる気を出す為に
神経細胞の可塑性を増やす(記憶力を増す)食べ物として、イチョウの葉、茯苓(ぶくりょう)という漢方薬があるそうだ。
しかし効果を出すためには非常にたくさんの危険量を飲まないといけないという。他に朝鮮人参、サフランがあるそうだがサフランはお酒を飲むときに効くそうだ。
記憶力を高める、という以外にも、「やる気を出す為には」
というのが多くの人々を悩ませる課題かと思う。
実は、やる気を生み出す場所が
「海馬/脳は疲れない」を読んで12 旅は人を賢くする要素をもっている
海馬の大きさについて有名な話が「タクシードライバー」。
タクシードライバーの海馬を調べると、一般人より大きいそうだ。いろんな道を通るとか、いろんな人に会うというような新規の刺激にいつもさらされている為だ。
その証拠に、海馬の大きさはタクシードライバーになってからの勤続年数に比例して増えているという。
海馬が一番大きかったのは50年以上もタクシードライバーをやっていた人だとか。
そういった意味で
「海馬/脳は疲れない」を読んで10 偏桃体について
面白いことに、感情の記憶に海馬は関係していない。海馬のない人がヘビに出くわして「怖い目」にあったとしても、ヘビに出会ったこと自体は憶えていない。
しかしそれ以降、会うたびに怖いなということは感じているという。
印象は憶えているけど内容は憶えていない。
その謎を解き明かすカギが偏桃体と言われる部分である。
感情を司るこの偏桃体の「感情の記憶」というのはより本質的で、生命に直接関係があるのでよりい
「海馬/脳は疲れない」を読んで9 海馬の魅力について
脳の記憶の仕方にとって、とても大切な特色は「可塑性」である。
可塑性とは、形が変わること。粘土なんかを想像してもらうと分かりやすい。
脳は変化したものを変化したままにしておく。
例えば、一度「ヘビは怖い」とか「蜂は怖い」という記憶が出来上がると、これをなくすことはできない。
もし克服したいなら、その記憶の上から「怖くない」という回路を作らなければいけない。
それでも、ある時に突然また怖くなって
「海馬/脳は疲れない」を読んで8 脳の成長スピードは非常に速い
脳は複雑に見えるが、脳の機能を分類していくとたった2つしかない。
「情報の保存」と「情報の処理」だ。
そしてよりどちらが大切か、というと「情報の保存」、つまり記憶。記憶がなければ処理もありえない。記憶がなければ言葉も話せず、話せなければ思考には制限が出てくる。
あらゆる処理も、その方法を記憶してはじめて可能になる。
記憶がどうして重要なのか、それは脳のはたらきのほとんどが記憶で説明できるからだ。
「海馬/脳は疲れない」を読んで7 脳は疲れない
考えが煮詰まった時など、人は「脳が疲れた」という表現をするが、実際には脳が疲れるという事はないそうだ。
寝ている間も脳は動き続けて、夢を作ったり体温を調整したりしている。脳は一生使い続けても疲れない。疲れるとしたら「目」だそうだ。
目の疲れ、同じ姿勢をとった疲れを癒す方が実践的という。
なので、例えば「いったん忘れる」というのはよくない。席を立って歩きまわるとか、考えたまま違うことをする方が