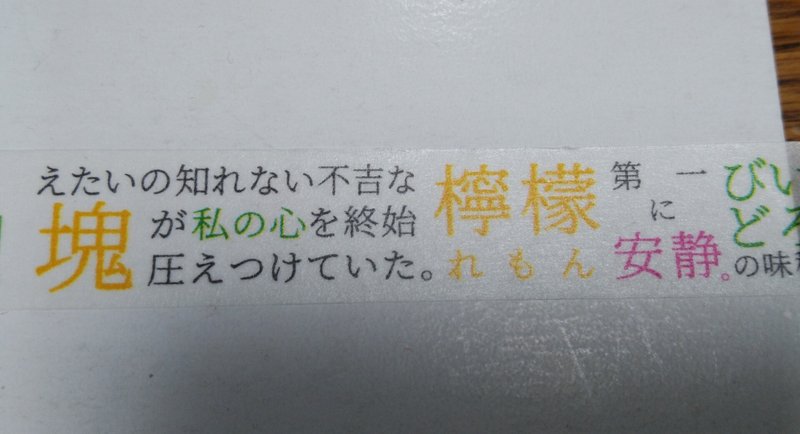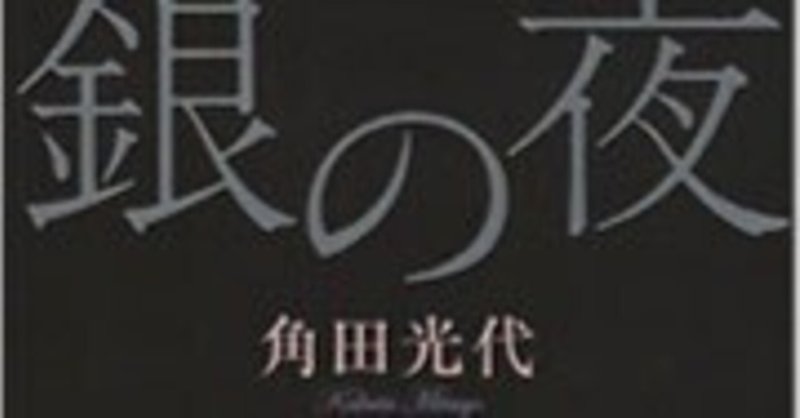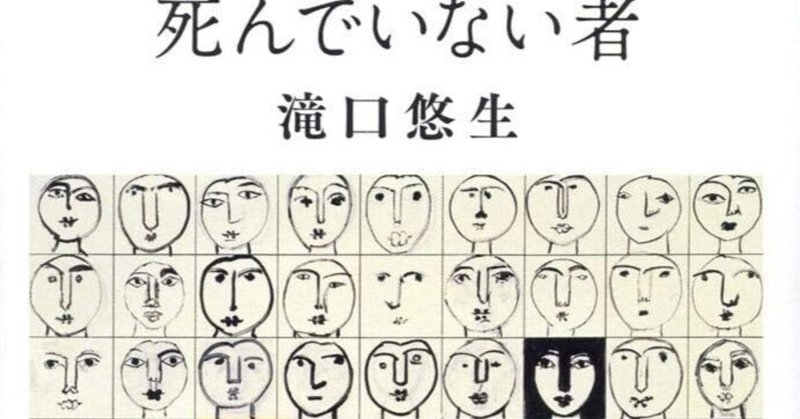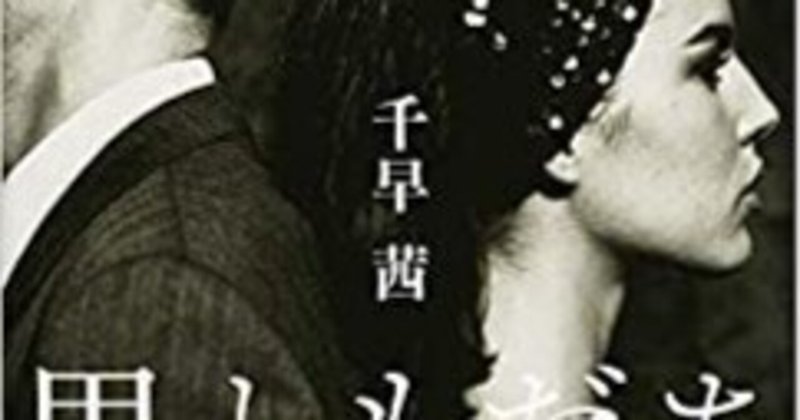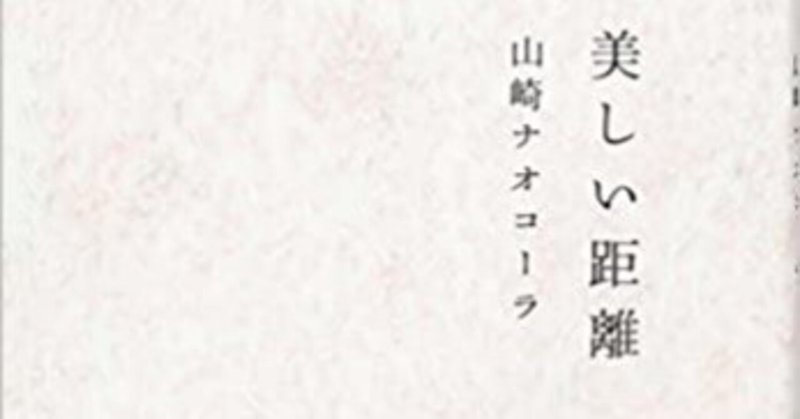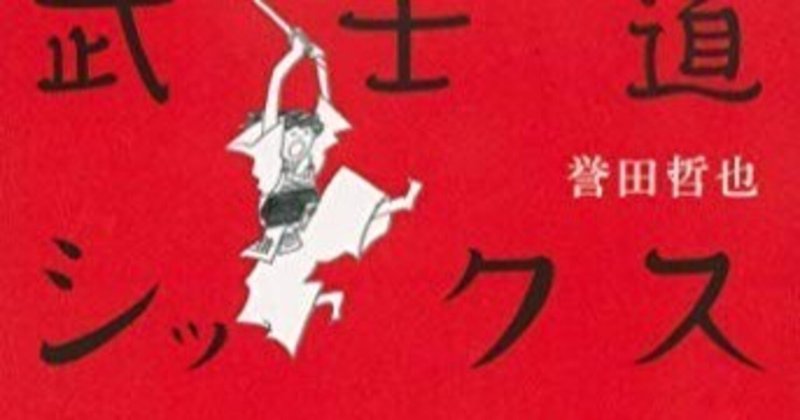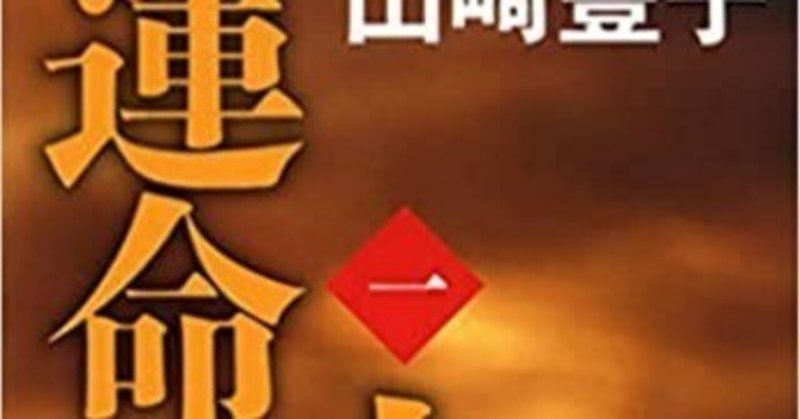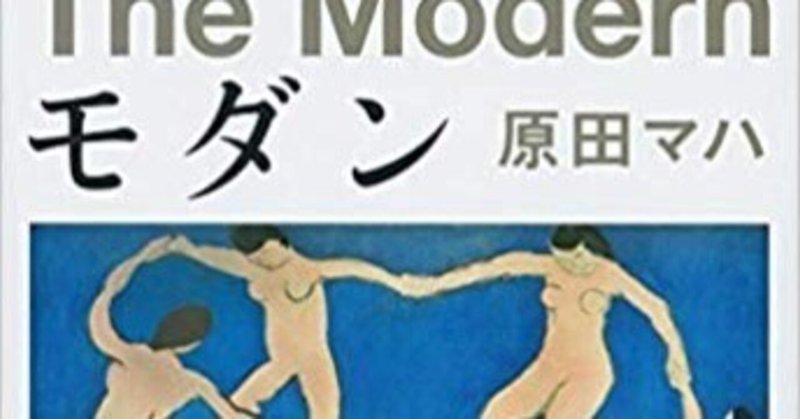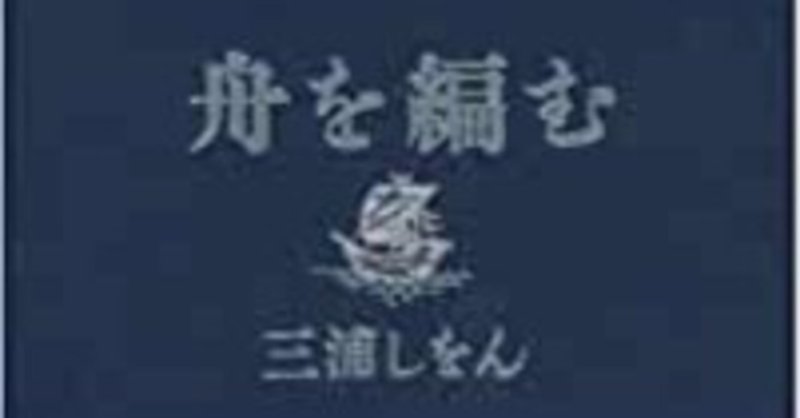#文春文庫
角田光代『銀の夜』を読んで、『対岸の彼女』を思い出した(毎日読書メモ(515))
読んでから少し時間がたってしまったのだが、角田光代『銀の夜』(光文社、そして感想を書けないでいる間に光文社文庫になった!)を読んだ。光文社、というところでピンと来る人もいるかもしれないが、女性誌「VERY」に連載されていた小説だったそうだ。連載していたのが2005年から2007年、そして単行本が刊行されたのが2020年、文庫になったのが2023年。
単行本には珍しく、作者のあとがきが付いている。2
滝口悠生『死んでいない者』(毎日読書メモ(494))
滝口悠生が『死んでいない者』(文藝春秋、のち文春文庫)で芥川賞をとったのが2016年下期、本谷有希子『異類婚姻譚』と同時で、ちなみに1期前が又吉直樹『火花』と羽田圭介『スクラップ・アンド・ビルド』だった。
最近あんまりきちんと芥川賞受賞作をフォローしていなくて、この頃の受賞作、あまり読んでなかった。評判の良かった『長い一日』(講談社)を読んだのをきっかけに、近作『水平線』(新潮社)も読み、満を持し
村上春樹『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(毎日読書メモ(426))
『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集1997-2011』(文藝春秋、のち文春文庫)。
世界の色々なメディアで発表された村上春樹インタビューの集大成。企画を立てた編集のオガミドリさん(として昔よくエッセイに出てきた)の病気の話を後書きで読んで切ない。広告批評の島森さんも亡くなってしまったし。長いタイトルだが、この通りのことを何回もインタビューの中で述べていて興味深い。タイ
山崎ナオコーラ『美しい距離』(毎日読書メモ(352))
山崎ナオコーラ、続く。2016年に、5回目の芥川賞候補となった、『美しい距離』(文藝春秋、現在は文春文庫)。芥川賞は逃したが、島清恋愛文学賞を受賞している。先日『母ではなくて、親になる』を読んだ時(感想ここ)に、この『美しい距離』が芥川賞候補になって落選して島清恋愛文学賞をとったあたりの経緯が書かれていて、気になったので読んでみた。
生命保険会社に勤める夫と、サンドイッチ屋さんを経営している妻。
誉田哲也『武士道シックスティーン』『武士道セブンティーン』(毎日読書メモ(345))
誉田哲也『武士道シックスティーン』『武士道セブンティーン』(文春文庫)の読書メモ。この後更に『武士道エイティーン』、『武士道ジェネレーション』(文春文庫)と続くが未読。いい小説だったけど、スポーツ少年少女の物語には飽和量があるようです>自分自身。いつか読むかもしれない(人の評を読むと、後になるほどよくなるっぽいので)。
『武士道シックスティーン』:磯山のオレサマぶり、早苗の天然ぶり、どちらにも深
乾くるみ『イニシエーション・ラブ』『リピート』(毎日読書メモ(299))
乾くるみ『イニシエーション・ラブ』(文春文庫)。書店の店頭等で話題の本として取り扱われ、新刊でもないのに、なんだろう、と思って読んだ。
もうこれは、何も紹介できない。読んだ人すべてが、最後の一行で唖然として、慌ててページを返して、自分がそこまで何を読んできたのか、反芻してしまう、ある意味トンデモ本。読んだ人すべてが、そうそう、と、肯定的であれ否定的であれ、そのエンディングを忘れない一冊。読んでない
毎日読書メモ(250)『モダン』(原田マハ)
実家に帰って、父の本棚にあった原田マハ『モダン』(文春文庫)を読んだ。ニューヨークのMoMA(近代美術館)を舞台にした、5つの短編からなる作品集。主役はMoMAそのものである同時に、MoMAで働く人々。原田マハの他の作品と同様、史実と違うフィクションを物語の中心に据えてはいるが、狂言回しとなる美術作品はすべて実在のものなので、検索しなくてもわかるアンドリュー・ワイエス『クリスチーナの世界』、ピカソ
もっとみる毎日読書メモ(224)『舟を編む』(三浦しをん)
三浦しをんの職業小説が好きだ。職業、と呼ぶにはちょっと微妙な『仏果を得ず』とか『神去なあなあ日常』とか、会社員小説の極みのような『星間商事株式会社社史編纂室』とか、『愛なき世界』も職業を極めている物語だ。
その中でも、本屋大賞をとった『舟を編む』(光文社、のち光文社文庫)は特に、プロフェッショナルの何たるかを教えてくれる。最後は勿論大泣き。
本屋大賞受賞直前に図書館に予約を入れ、それからでも随分