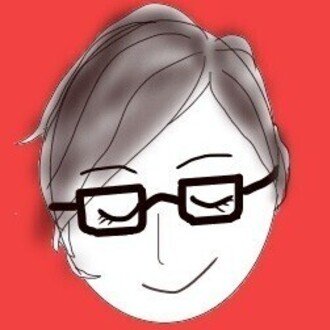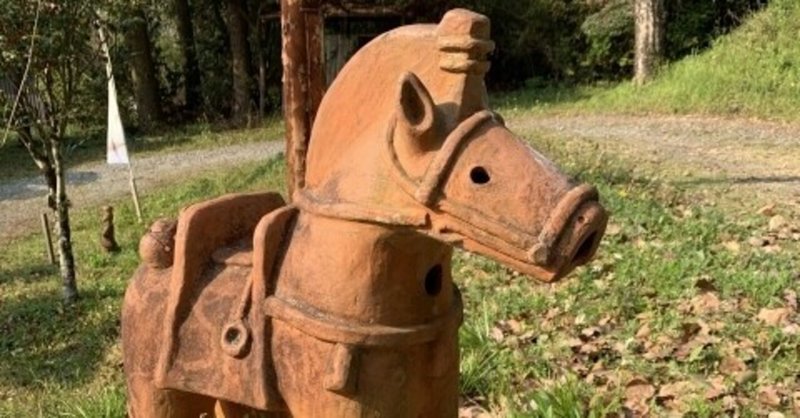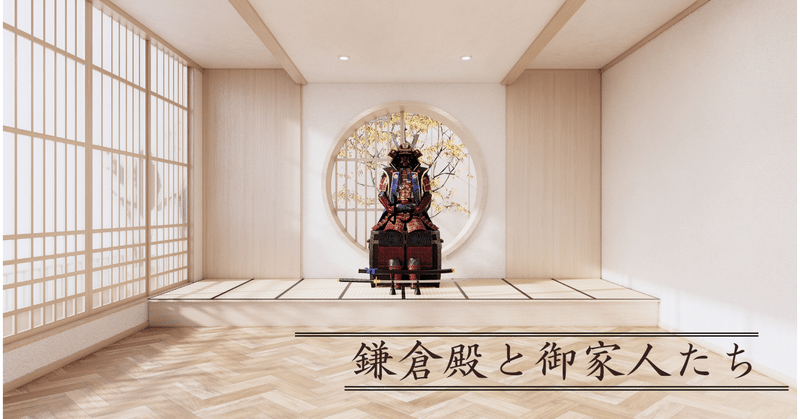2022年6月の記事一覧
奈良時代、「鬼」として滅ぼされた縄文王国・長野県の鬼無里(きなさ)
・奈良時代、次々と姿を消していった日本各地の縄文王国
奈良時代、日本各地にあった古代王国は次々と姿を消していきます。
そのきっかけは、西暦645年に行われた「大化の改新」。
「大化の改新」とは、中大兄皇子(のちの天智天皇)と中臣鎌足らよって行われた、大きな政治改革です。
まず中大兄皇子と藤原鎌足は、絶大な権力を持っていた蘇我家を倒し、その後、大王家を中心とする国家づくりに着手します。
彼らが目指し
歌人 平忠度(たいらのただのり)と右腕(その3 全3回)
忠度はね、薄らいでいく意識の中ではて西はこちらかやと体の向きを変えるとね、こうして静かに念仏を唱え始めたんだ。忠度の白い顔は青ざめていったんだよ。
忠澄はね、勢いあってこそ撃てる首も念仏を唱えられるとね。やりずらかったよ。
「名のある大将軍に違いあるまい。」
忠澄はね、首を撃つとその体を調べてみたんだよ。するとね、箙に結びつけられた短冊があったんだ。箙とはね、矢を入れて背中に背負っておく細長い入れ
歌人 平忠度(たいらのただのり)と右腕(その2 全3回)
忠澄は大声で呼びかけたよ。それは、色白く、ひげをたっぷりとたくわえ、白月毛の馬にまたがって、赤地錦の直垂に黒糸威の鎧をつけて、兜をかぶりもしないでいる。名のある大将に違いなかったんだ。
「私は、お前の味方ぞ」
忠度は落ち着いて答えたんだ。そうさ。嘘を答えたんだよ。その時チラリと口元が見えてしまった。忠度は歯を黒く染めていたんだ。源氏には歯を黒く染めている者なんてなかったからね。平家の者に間違いなか
歌人 平忠度(たいらのただのり)と右腕(その1 全3回)
行き暮れて 木の下陰を 宿とせば
花やこよひの 主ならまし 忠度
今日はね、この歌を詠んだ平忠度のお話だよ。忠度は戦いなんかしたくはなかたっんだ。お花や雪を見てロマンチックに歌を詠んでいたかったんだよ。
ポンと昔。源氏に追われた平家たちは京都から兵庫へと逃げて行ったんだ。平家たちはもう一度都の京都を奪い返してやるぞと兵庫の福原に集って東の生田の森と、西の一之谷に砦を築いていたんだよ。そうし
源氏の身内争いが戦国時代を招いた?
ご先祖を辿られるなかで、どうしても史実と重なる部分もあり、その時に触れられる歴史が、簡潔で秀逸な筆致でまとめられています。
ご自分のご先祖が岡山県の八幡神社の氏子である事から、
源氏の血筋が後に「室町幕府」を創建した足利氏に繋がるという事を、わかりやすく知る事ができます。
私もずっと以前に、何かの本で知った時、「へぇ~!」と感心した記憶はあり、その時はあまりのややこしさにまとめられず、その系図