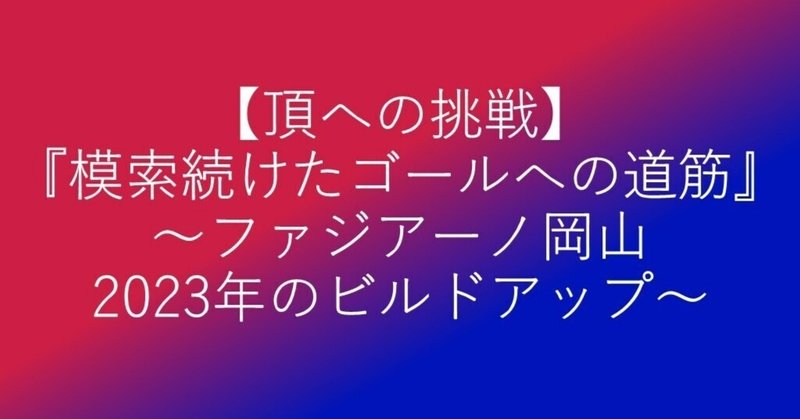
【頂への挑戦】『模索続けたゴールへの道筋』~ファジアーノ岡山2023年のビルドアップ~
着手した自陣からの攻撃の構築
2023シーズン、ファジアーノ岡山はゴールへの道筋を模索し続けた。着手したのは、自陣からの攻撃の構築だ。
木山隆之監督が就任した昨季は、ロングボールが主体だった。前線にはJ2離れした空中戦の強さを誇るFWミッチェル・デューク、最終ラインには高精度のロングフィードが持ち味のDFヨルディ・バイスが君臨する。“相手コートでサッカーをする”というコンセプトのもと、彼らをはじめとした選手の力を最大限に引き出すためには、手数を掛けることなく相手陣内にボールを入れることが効果的だった。もっとも、チームは大きな力を発揮し、クラブ史上最高の3位(勝点72も史上最多)でリーグ戦をフィニッシュ。しかし、昇格プレーオフ1回戦でモンテディオ山形に敗れ、悲願のJ1昇格は叶わなかった。

木山体制2年目の今季は、最前線のターゲットがチームを離れ、テクニックに優れた選手が加わった。また、昨季の成績と試合内容を精査した結果、自動昇格を勝ち取るためには、主体的に攻撃を展開するチームに成長しなければならないと判断。昨季に足りなかった力を身につけるため、今季の戦力の最大値を引き出すため、木山監督はJ2優勝を掲げた今季、自陣から攻撃を組み立てることを取り入れた。
ショートパスと立ち位置の重視
重視するようになったのが、ショートパスと立ち位置だ。
前線に浮き球、ロングパスを蹴り込むのではなく、芝生を走るパスを近くの味方に出す。ロングパスは前方の味方に通れば、一気に相手ゴール前に到達できる。その反面、ボールが空中に浮いているため、まず受け手のボールを止める(以下:コントロール)動作が難しくなる。さらに、滞空時間が発生するため、出し手から受け手に届くまで、ある程度の時間がかかってしまう。その間に相手選手に寄せられてしまい、パスカットやクリアされるケースも生じてくる。
一方、ショートパスは出し手から受け手に届くまでの時間を大幅に短縮できる。人が走るよりも、ボールを走らせた方が速い。なおかつ、目的地が出し手の近くにいる味方であるため、ショートパスの方がロングパスよりも成功率は高まる。
※素早いショートパスの交換は、インサイドキック(足の内側を使ったキック)の技術の高さが必要になる。したがって、技術レベルによっては必ずしも成功率の面でロングボールを上回るとは限らない。
ボールを失わないまま確実に相手コートに進入する。ショートパスを用いる大きなメリットだ。
ただ、それだけではパスはつながらない。どこからパスを出すか。どこでパスを受けるか。立ち位置(ポジショニング)が重要になる。サッカーは相手がいる相対的なスポーツであるため、自分たちだけのことを考えていてはうまくいかない。ここでは簡単な記述に留めるが、相手のプレッシャーを受けない位置から、相手のいない場所にいる味方にパスを出す。これによって、ショートパスの成功がさらに高まるのだ。
[4-4-2(ダイヤモンド)]と[3-5-2]の行き来で開幕
今季は、ボール保持時に[4-4-2(ダイヤモンド)]から[3-5-2]に変化する形でスタートした。
形の変化は主に3つ。1つ目は4バックが右片上がりで、横にスライドする。2つ目は右SHの田中雄大が内側に入り、右SBの河野諒祐が右サイドの高い位置に張り出す。3つ目はトップ下のステファン・ムークが中央から少し左にズレ、左SHの佐野航大が左サイドのタッチライン沿いに立つ。このとき、左SBの鈴木喜丈が状況を判断して、アンカーの輪笠祐士の隣で2人目のボランチとして振る舞う“偽SB化(喜丈ロール)”も特徴的だった。


選手の個性を最大限に引き出しつつ、ショートパスをつなぎやすい配置とは何か。プレシーズンから模索した中で、開幕戦を一つのターゲットに導き出した解答が、ボール保持時の[4-4-2(ダイヤモンド)]から[3-5-2]への変化だったのだろう。実際に宮崎キャンプでの練習試合では狙いを体現して強みを発揮し、開幕戦のアウェイ磐田戦(〇2-3)では結果をもたらした。しかし、それは長く続かない。全戦力が揃わなかったことも理由として考えられるが、それだけではなかっただろう。ボール保持時とボール非保持で形が大きく変わるため、[4-4-2(ダイヤモンド)]と[3-5-2]を行き来する間にスキが生じる。攻守の切り替えで相手に上回れて、岡山が形を変えて攻撃態勢を整える前に相手にブロックを作られる。岡山が守備態勢を整える前に攻められて失点を許す。大胆な構造の変化の強みよりも、弱点が浮き出てしまった。
基本システムの変化
そこでボール保持時に[4-4-2(ダイヤモンド)]から[3-5-2]への変化をおこなわず、第10節アウェイ仙台戦(△1-1)から[4-4-2(中盤フラット)]に移行し、大きな形の変化を起こさないオーソドックスなスタイルで戦う。そして第19節・ホーム徳島戦(〇2‐0)で[3-5-2]を基本システムに採用する。ボール非保持は[3-5-2]だが、ボール保持時には[3-2-5]に変化する新たな形を見せた。この試合では、今季は右SBで定位置確保を目指していた本山遥がヨルディ・バイスに代わって先発し、3バックの右でプレー。結果的にこれが最終的な基本システムとなった。


[3-5-2]と[3-2-5]を行き来する3つの理由

ボール非保持時の[3-5-2]

ボール保持時の[3-2-5]
では、なぜ[3-5-2]から[3-2-5]なのか。理由は3つ。
1つ目は、相手のプレスに対する数的優位を作りながらビルドアップ(攻撃の組み立て)をおこなえることだ。現代サッカーは、前線から相手のボールを奪いに行くとき、相手のパス回しに制限をかけたいとき、基本的に2人の前線の選手が相手ボールホルダーに距離を詰めていくことでスタートする傾向にある。パスをつないで安全に相手のプレスを掻い潜るために、数的優位となる3人でパスを回すことが有効になる。つまり、柳育崇、鈴木、本山の3選手が相手2選手に対して常に+1を作りながらパスをつないでいくということだ。
※GKがPA(ペナルティーエリア)の外でビルドアップに参加して数的優位を作るチームもある。
2つ目は、中盤中央におけるビルドアップの出口(相手のプレスを掻い潜ってディフェンスラインから前方にパスをつなぐ際の受け手になる選手・ポイント)を二つ作れることだ。ビルドアップの出口となる選手は、主に中盤の底(以下:アンカー)の輪笠とインサイドハーフ(以下:IH)の1選手で、左IHの田部井涼が担うことが多かった(右IHの仙波大志が担うこともあり、そうなれば左IHの田部井は前方に上がる)。
中盤中央におけるビルドアップの出口が一つだと、相手が的を絞りやすく、「奪う」という狙いをもって縦パスにアプローチしてくる。しかし、出口が二つあると、相手がケアしないといけないポイントが増えることになる。アプローチしてくる相手選手はボランチが多く、ボランチ2人が同時に前に出て奪いに来ると、CBの前のスペースを空けてしまい失点の危険が伴う。輪笠と田部井(時々、仙波)は縦関係になることもあり、中盤中央におけるビルドアップの出口の場所を変化させる動きからは相手をかく乱させる狙いも感じられた。
※右IHでの出場が多かった仙波は、右サイドの内側にポジションを取り、右CBの本山、右ワイドの末吉塁をつなぐ(コネクトする)役割を担っていた。足下の技術に自信があり、ボールを失わないという絶対的な自信をもちながらボールキープやターンでチームに貢献する。相手のプレッシャーにビビらない。勝気なメンタリティはボールを前進させるうえで欠かせなかった。
3つ目は、5トップで4バックの相手に対して数的優位を作り、中央とサイドの両方から攻めれることだ。J2の22チーム中、4バックを基本システムに採用していたのは15チーム。つまり、4バックのチームとの対戦が多いため、5トップに変化すれば多くの試合で、アタッキングサード(ピッチを横に3分割したときに、相手ゴールに最も近い3分の1のピッチ)で数的優位を作りながら攻めれる。5トップだと、4人の相手ディフェンスに対してズレを作った状態から攻撃をスタートできるため、相手は横のスライドで対応するか、中盤から1人を下げるかして対応しなければならない。主導権を握りつつ、左右に揺さぶり、中央を使ったりして構造上は変幻自在な攻撃が可能となる。
そして、前提の話にはなるが、[3-5-2]から[3-2-5]の変化は立ち位置を大きく変えないで済むというメリットがある。基本は縦の上下動であり、横に大きくズレたりする必要はない。そのため、形を変える段階でスキが生じにくい。
“ショート”とロング”。パスの使い分けを可能にしたルカオ
[3-5-2]と[3-2-5]を行き来するようになって、序盤戦の形と比較すると、ショートパスへの固執は弱まったように思う。基本的には自陣からショートパスをつないで相手コートへの進入を目指すのだが、適宜、ロングボールを織り交ぜながら縦に早い攻めも使った。目標は、あくまでもゴールネットを揺らすこと。状況を判断して2つのパスを使い分けられるようになった。
前述したようにロングボールは成功率が下がる。しかし、それを担保したのがルカオだった。強靭なフィジカルをもつ背番号99が相手を背負いながら、なぎ倒しながらボールをキープして力強くゴールに突き進んでいく。相手を凌駕するルカオのパワーとスピードという質的優位がロングパスでの前進を可能にさせた。
ただ、2トップを組んで先発することの多かったチアゴ・アウベスと坂本一彩は、相手と競り合いながらロングボールを収めるというプレーを強みとする選手ではない。スピードのあるチアゴは相手の背後やサイドのスペースに流れるプレー、足下の技術に優れる坂本は中盤や相手ブロックの間などの狭い場所でパスを引き出すプレーを得意としている。そのため、彼ら2人にロングボールを蹴り込んでも、セカンドボールの回収率を含めてマイボールにする確率が上がらない。そこで、前線へのロングボールはルカオ投入後の後半途中から見られることが多かった。
ルカオと同時投入されることが多かったステファン・ムークと木村太哉の貢献も忘れてはならない。ムークは球際とルーズボールワークで強さを発揮期し、木村は泥臭くもガムシャラなドリブルでサイドを突破する。広大なスペースが生じるオープンな展開になった後半終盤に、三銃士としてチームに推進力をもたらして劇的な勝利に導いた。
2023年のビルドアップ(攻撃の構築)の特徴
本山遥と鈴木喜丈のプレス回避力
今季の戦術の生命線だ。3バックの右と左を務める本山と鈴木は、相手のプレスを受けても、それを苦にしない。相手がどちらのパスコースを切っているのか、どちらから奪いに来ているのか。それらを認知して、横パスをつないで相手を揺さぶるべきか、縦パスを打ち込んで相手のプレスを突破するべきか、適切なプレー判断を下す。
なぜ、慌てずにプレーできるのか。試合中に彼ら2人を観察すると、首を振っている回数が多い印象を受けた。顔を上げて周囲の状況を確認し、首を振って瞬間的な状況変化を把握している。相手を見ながらプレーすることができているのだ。
また、彼らが違いを見せた最大の強みは、独力でプレス網を突破できること。いわゆる「ハマった」状態を打開できるところにある。ドリブルでボールを少し前のスペースに運んで、相手のプレスの矢印を折っていく(アプローチしてくる相手の逆を突く)。自陣低い位置でのドリブルは失うリスクが高く、DFの選手は選択しにくいプレーだ。しかし、彼らには周囲を正確に把握する視野の広さとボールタッチミスをしない技術がある。本山はプロ1年目の昨季にアンカーを経験しており、鈴木はそもそもボランチとしてFC東京の下部組織からトップチームに昇格した選手だ。ディフェンスラインよりも相手の厳しいプレッシャーを受ける中盤でのプレー経験が今に生きているのだろう。
今季、相手の強烈なプレスを受けて行き詰まりそうになるシーンはあった。しかし、抜群のプレス回避力を有する本山と鈴木が運ぶドリブル(筆者は「キャリー」と呼んでいる)で局面を打開してボールを前進させた。
下りる坂本一彩と抜け出すチアゴ・アウベス
ショートパスをつないで相手ゴールに進入するためには、縦パスが必要不可欠になる。そこで鍵を握ったのが、坂本だ。2トップの一角で先発すると、ボール保持時、背番号48は瞬間的に下りる動きを見せる。中盤の空いているスペースを見つけて、後方からの縦パスを引き出す。前線から下がってボールを受けるということは、相手ゴールに対して背中を向けたままボールをコントロールすることになる。DFのセオリーに「背中を向けた相手選手には後ろから強くアプローチする」というものがある。前を向かせないためであり、ボールを奪いやすいからでもある。要は、DFにとっては狙い目なのだ。
しかし、坂本はボールを失わない。パスをコントロールするタッチが乱れず、そのまま軽い身のこなしでクルッと前を向ける。その一連の動作が非常にスムーズで、巧みなターンでDFを翻弄してゴールに向かっていく。空いているスペースを見つける目と繊細で正確なボールタッチを武器に、グラウンダーでの縦パスの受け手として前線に起点を作った。
ただ、坂本の起点作りは彼が特長を発揮するだけでは成立しない。相棒のチアゴ・アウベスの存在も欠かせない。背番号7はライオンである。常にゴールという獲物に飢えている。ピッチに立っているとき、いつもゴールを決めることを狙っている。ゴールへの強い意志をもつチアゴの持ち味は、日本人離れしたバネを生かしたスピードだ。虎視眈々とネットを揺らすチャンスを伺うチアゴが、相手の背後やサイドのスペースに走り出す。勢いよく快足を飛ばすチアゴは、昨季16ゴール(リーグ2位)を決めたストライカーだ。相手DFは、そんな彼を放っておくことはできない。もし、相手が厳しくマークしてこなければ、チアゴにパスを出して、一気にゴールを陥れてしまえばいい。
チアゴが走るから、相手ディフェンスラインは下がり、坂本が下がって縦パスを受けやすくなる。坂本が下がるから、相手DFが食いつき、チアゴが抜け出しやすくなる。G大阪にゆかりのある2トップの相互関係がボールの前進、ひいては攻撃に欠かせなかった。
岡山の槍を務めた両ワイド
[3-2-5]で攻めるにあたって、欠かせないのが幅を取る両ワイドの選手だ。右サイドは末吉塁、左サイドは高橋諒が担った。彼らがタッチライン沿いに立つことで、相手の守備網を横に引き延ばす(ストレッチ)ことができる。彼らを起点に左右にパスをつないで相手を揺さぶっていくボールの動かし方は、一つのルールになっていた。それによって、中央にスペースを生み出し、仙波、田部井、坂本といったテクニカルな選手の引き出す狙いもあっただろう。
末吉、高橋は立ち位置によってチームにメリットをもたらすだけではない。ボールを持ったときのゴールに向かって“仕掛ける”プレーで相手に脅威を与えた。
右サイドの末吉は、量で勝負する。爆発的なスピードを生かしたドリブル、スプリントを90分通して何度も繰り返す。試合終盤になっても、スピード、キレが全く落ちない。無尽蔵のスタミナで切れ味抜群の突破を仕掛け続けられるほど、相手DFにとって嫌なものはない。一人だけコマ送りなのではないか。そう疑ってしまうほど足を高速回転させて、右サイドを制圧していく姿は観るものを魅了した。
今夏に千葉から期限付き移籍で加入した背番号17がファジサポを驚かせたのは、そのスピードとスタミナを守備でも存分に発揮していた点だろう。本稿はビルドアップがテーマであるため深くは言及しないが、快足を飛ばして自陣に戻って粘り強く守る献身性に心を掴まれた人は少なくないだろう。
左サイドの高橋は、質で勝負する。決して相手をスピードで置き去りにするタイプではない。しかし、とにかく技術が高い。なおかつ、状況把握に優れており、常に適切な判断を下す。プレー時に背筋が伸びて顔が上がっているため、相手の重心の逆を突いて突破することができ、味方の動き出しを見逃さずに好連係を生み出す。鈴木(43番)、田部井(41番)、高橋(42番)の“連番トリオ”によるコンビネーションは相手を惑わせた。
そして、左足の高精度クロスである。カーブ回転をかけたボールを相手GKとDFの間に流し込むキックは一級品。きれいな弧を描いてスペースに走り込む味方にピタリと届けるクロスで、今季は3アシストを記録した。また、第18節・アウェイ栃木(△1-1)では、左サイドから切れ込むと、右足でゴール前に蹴り込んだボールがそのままゴールに吸い込まれる得点も決めた。利き足ではない右足でも、ゴールに結びつけられる精度を出せる。チームを救う“シュータリング”(シュートとセンタリングを組み合わせた造語)だった。
ドリブルで相手を抜き切らなくても、精密機械のような左足でチャンスを演出する。1試合に蹴り込むクロスの数は、それほど多くないかもしれない。しかし、その少ない1本でも確実に結果を出す。J1通算97試合出場は伊達ではない。“必殺仕事人”は頼もしい存在だった。
右サイドと左サイドで異なる性質をもつ岡山の両サイドは、それぞれの強みを存分に発揮してゴールに向かった。先陣を切って相手の守備網に突入し、サイドからゴールへの道筋を切り拓く。まさに岡山の槍だった。
ゴール前の崩しという課題と来季に向けて
上記のような仕組みや特長をもとに、主体的にゴールに迫る回数を確実に増やした。第26節・ホーム長崎戦(△2‐2)で、ニアゾーンに進入した佐野の折り返しを坂本が決めた得点や、第36節・ホーム磐田戦(○2-1)で鈴木が決めた得点のように、チームとしての狙いを体現した得点も生まれている。これは肌感覚なのだが、昨季よりもゴール前にボールと人が同時に入っていく回数が増えたとも思う。
しかし、得点は伸びなかった。今季は昨季の61得点にプラス10点することを目指したが、結果は49得点。初めてプレーオフに進出した2016年から見ると、得点数は昨季に続く2番目になる。だが、序盤戦をはじめ、たくさんチャンスを作れていたことを考えると、「もっと決めれたのに・・・」と物足りなさを感じるのが正直なところ。
ただ、攻撃の最後にあたる、ゴールネットを揺らす部分は、必死に守る相手を超えていかないといけないため、難易度が高い。ましてや、力が拮抗するJ2において、簡単に得点を奪える試合はない。そのため、木山監督は主体的に攻めてチャンスの数を多くし、得点数を増やすというアプローチを採用したのだろう。
どこからでも得点が取れる。多彩な攻撃ができるのも一つの理想だが、ゴールに最も近い位置でプレーするFWの選手には得点を取る活躍を期待したい。その彼らがコンディション不良などによって思いのほかシュートを決められなかったことは、得点力不足に陥った要因の一つだ。
また、最後の崩しを選手の判断に委ねる構造の影響もゼロではないだろう。PA手前やPA内でのプレー選択は、ピッチに立つ選手が即興的に味方と連係を合わせながらやっていたように見えた。クロスを入れる場所、入っていくポイントなどには、ある程度の決まり事があった。しかし、シーズンを通して試合中にそれを徹底してできていたとは思えない。右サイドをえぐったルカオがマイナス方向に折り返すも、味方が誰もいなかったシーンは記憶に残っている。前述したニアゾーンを突く攻撃も毎試合のように見られたわけではなかった。
ある程度の基準となるポイントは提示する。そこからはピッチでプレーする選手が最良だと思った判断を下して崩していく。複数人が同じ絵を描いて、それがピタリとハマったときは相手を凌駕する華麗なコンビネーションでシュートまでもっていき、ゴールを陥れる。その反面、アイディアを共有できないとき、うまく連携が合わないときは一気に難しくなる。良くも悪くも、選手の調子次第という不確定要素が大きかったのかもしれない。
ただ、どれだけチームとして形を構築していても、選手がシュートを決めないと得点にはならない。最後は人に依存する部分が出てくる。さらに言ってしまえば、個の力に依存しようが、チームとして形を作り込もうが、得点を決めてしまえば、それが正解になる。サッカーとは、そういうものだ。
今年はゴール前までボールを運ぶ作業をチームとして落とし込んだ。そこから得点を奪うところは属人的だった。その結果としての49得点。これをどのように捉えるか。今年1年間で積み上げてきたものは確実にある。その中で、得点を決めるかという課題が浮き彫りになった。
シュートを決める力に優れた選手を新たに獲得するのか。崩しの形をチームとしてデザインして落とし込むのか。来季のさらなるパワーアップ、そして、その先にあるJ1昇格という悲願達成に向けて、ゴール前の崩しの向上がカギを握るに違いない。木山体制3年目も、岡山はゴールへの道筋を模索し続ける。
読んでいただきありがとうございます。 頂いたサポート資金は遠征費や制作費、勉強費に充てさせていただきます!
