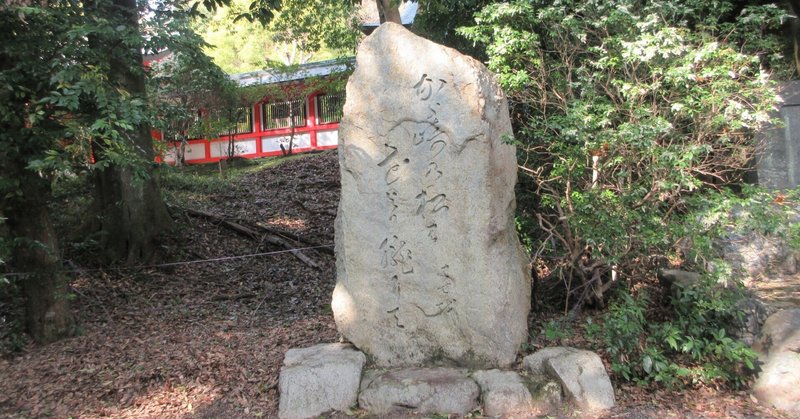2023年4月の記事一覧
無罪~読書記録269~
2011年 推理作家・深谷忠記氏によるミステリー小説である。
息子と妻をシンナー中毒の通り魔に殺された新聞記者の小坂は、ある大学准教授の家を見張っている女性に出会った。准教授の妻は11年前、我が子2人を殺しながら心神喪失と判断され、無罪判決を受けていた―。無罪判決が下された時、本当のドラマが始まる。愛する息子と妻を通り魔に殺された男。我が子を殺しながら、心神喪失で無罪となった女。刑法第39条の壁
地方消滅~読書記録262~
2014年、元建設省官僚で岩手県知事の増田寛也氏の著書だ。
このままでは896の自治体が消滅しかねない―。減少を続ける若年女性人口の予測から導き出された衝撃のデータである。若者が子育て環境の悪い東京圏へ移動し続けた結果、日本は人口減少社会に突入した。多くの地方では、すでに高齢者すら減り始め、大都市では高齢者が激増してゆく。豊富なデータをもとに日本の未来図を描き出し、地方に人々がとどまり、希望どお