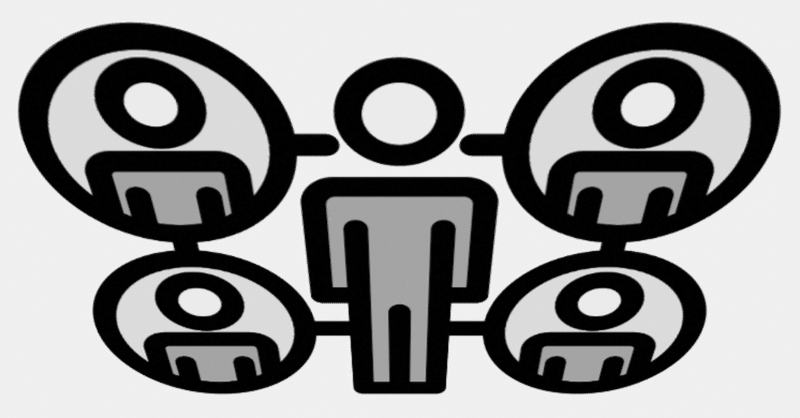#読書感想文
コミュ力は「副詞」で決まる を読んで
めちゃくちゃざっくり要約すると、あらゆる人が人間関係で悩む中で、それらを改善するために必要となるであろうコミュニケーション能力を、言葉使いの質を高めることで身につけようというものだ。本書では「副詞に」着目して種類や使い方について展開されている。
本書では、書き言葉と話し言葉の副詞について取り上げられていた。話し言葉では、僕としては「まあ」「ちょっと」「たぶん」「けっこう」「とりあえず」なんかはよ
「人は聞き方が9割」を読んで
おそらく、「人は話し方が9割」:永松 茂久(著)というタイトルの方が有名だと思うが、何となく同じ著者の「人は聞き方が9割」を購入した。
上のタイトル2つを並べるとどっちやねんとなるが、僕はどっちでもいい。
この本は、「会話がなかなか続かない」「ついつい話しすぎてしまう」「自分から話題を作ることに苦手意識がある」「もっとコミュニケーションが楽になる方法を知りたい」といった思いをもっている人に贈り