
アーマンド・M・ニコライ・ジュニア 『フロイトかルイスか 神と人生をめぐる問い』 : 中立を装った 〈隠れ護教家〉の子供騙し
書評:アーマンド・M・ニコライ・ジュニア『フロイトかルイスか 神と人生をめぐる問い』(春秋社)
端的に言って、程度の低い、人品卑しき著作である。
通俗キリスト教書によくあることだが、肩書きだけは立派な「護教学者」の手になるもので、フロイトをダシにした、キリスト教信仰の自己正当化論。さらに言えば、カトリックの最悪な部分たる「善人ぶった悪意」の書である。
中世の「異端審問官」というのは、きっとこういう手合いだったのだろうと、そう思わせるものであった。

「プロローグ」において著者は、しきりに自身の「中立性」を強調するのだが、自分が「クリスチャンか否か」については、素知らぬ顔でスルーして、読者に開示しようとしない。
この段階ですでに、著者がクリスチャンであろうことは容易に推測しうる(なぜなら、クリスチャンでなければ、そう断るだろうからだ)し、それならそれで、よほどの覚悟をもって最後まで、自制的に「中立」を貫くのなら良い。だが、本書の場合、そんな期待は(第2章で)すぐに裏切られてしまう。
この本を読んで、著者が「中立」だと思うのは、よほど「読めない」クリスチャンか、おめでたい読者だけだろう。
実際、本書を最後まで読んでも、著者の口から、著者自身が「クリスチャンか否か」については、一言半句語られてはいない。
著者がクリスチャンだと窺わせるのは、「訳者あとがき」(P356)と巻末の「著者紹介文」での『クリスチャンの非営利ロビー団体である「家庭調査会議」の創立メンバー』という、ささやかな一文だけで、後は「学者」としての経歴アピールのみ。つまり、カトリックかプロテスタントかさえ書かれていないのだが、著者がカトリックであろうことは、本書の内容に照らして、おのずと明らかなのだ。
ともあれ、これはもう、「中立」を装うために(訳者も含めて)故意に「カトリック信者」であるという事実を隠している、としか思えない。
自身の信仰に自信のあるカトリックならば、本書著者による、この姑息かつ見え見えな「中立偽装」による「欺瞞的読者誘導」を、苦々しく思うこと間違いなしだ。「なぜ、堂々と身元を明かして、正面切って戦えないのか」と。
○ ○ ○
さて、本書の「表向きのテーマ」は、「無神論者フロイトと回心者ルイスの、どちらが選択(生き方)が正しかったのか」というものだが、無論、「中立」を装ってはいるものの、カトリックである著者にとっては、これはあらかじめ答の出ている、結論ありきの誘導的問題設定でしかない。

(無神論者 ジークムント・フロイト)

(カトリック護教家 C.S.ルイス)
だが、この問題設定は、そもそも根本的なところで、無理がある。
と言うのも、フロイトであれ、ルイスであれ、どちらも多かれ少なかれ「誤り」を抱えた人間でしかなく、その両者を単純に比較し、優劣判定をして、どちらかを一方を選んだところで、それが「正解」でなどないというのは、理の当然なのだ。
言い換えれば、多かれ少なかれ「宗教という誤謬」に呪われた二人(フロイトとルイス)がいて、一方は、生涯その「呪い」に抗い続け、もう一方は、その「呪い」に屈して(「愚者の楽園」的な)安寧を得たのだが、そんな両者を比較して、後者の方が「一貫している(矛盾が無いし、幸福そうだ)から、こちらの選択が正しい」と評するようなレベルでしかないのが、本書なのである。
例えば、「良心」と呼ばれる道徳律の問題は(本書著者の意図に反して)、フロイトが言うように「人間(人類)が作ったもの」でもなければ、ルイスが言うような「普遍的な道徳律(=神が与えし戒律)」などでもない。つまり「二者択一」ではあり得ない(P73)。
なぜなら「良心」とは、「進化によって生成された、種の保存のための(生存)本能」の「人類段階での形式化の産物」だからだ。
つまり「種の保存に従った行動には快感(肯定感・幸福感)が与えられ、種の保存に反した行動には不快感(負の感覚・罪悪感)が生起されるように、進化生成された」ものであり、その人類段階における発展形が「良心(という、脳内現象の仮象)」なのであって、そこには、「普遍的道徳律」を人間に与えたとされる「神」の出る幕などないのだ。
したがって、フロイトもルイスも、半分正解で半分間違いでしかない。言い換えれば、どちらも「正解ではない」のである。
同様に、「神」とは、巨大な脳を持ってしまい、ある程度は自己を客観視できるようになってしまった動物としての(人類の)、過剰なまでの被害予測(不安)をなだめるための、脳科学的虚構という安全装置であり、精神安定剤なのだと言えよう。
例えば「あの草むらの中に(そこにもあそこにも)、私を狙う狼が隠れているんじゃないか」といった、防衛機制の過剰亢進を抑制するための、中和的安全幻想が「神」であり、「世界は悪意に満ちていると同時に、神が見守ってくれてもいる」と感じることで、人間は精神のバランスを取ってきたのである。
そんなわけで、「無神論者」であるフロイトの理論がいかに「不完全」かをあげつらったところで、あるいは、フロイトが性格的に問題のある気難しい人であろうと、それで「神」の存在が証明されるわけでもなければ、「盲信」に安らぐことを決めて知的闘争を放棄し、ひたすら「無神論のあら探し=信仰の自己正当化」に走ったルイスの「生き方=選択」の方が正しい、ということにもならない。
フロイトは、自分一人の力で「科学的世界観」の正しさを十全に立証することは出来なかったものの、「科学的」方法を堅持することによって、後の科学者たちに、その健康かつ堅実な「科学的懐疑」のトーチを引き継いだ、先駆者の一人と呼ぶべき人なのだ。
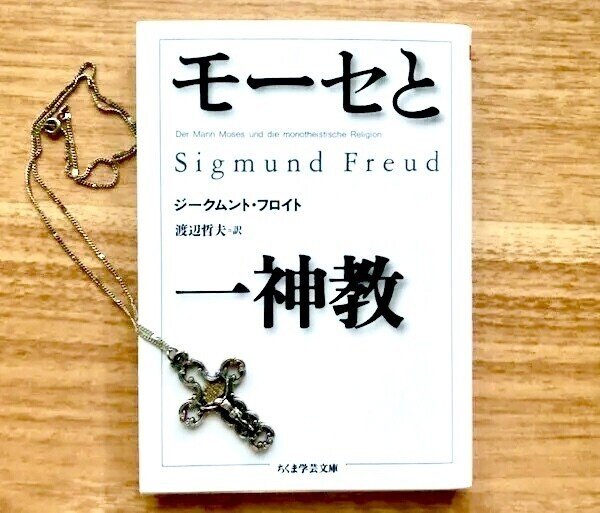
本書著者は、アメリカでは「神」の存在を信じる人が8、9割に達しており「それでも、皆が間違えていると言うのか」などとつまらないことを言うのだが、その通り、みんな間違えているのである。前述したように、人類には全員、多かれ少なかれ「神」という「虚構」が組み込まれており、言い換えれば「呪われている」のだ。
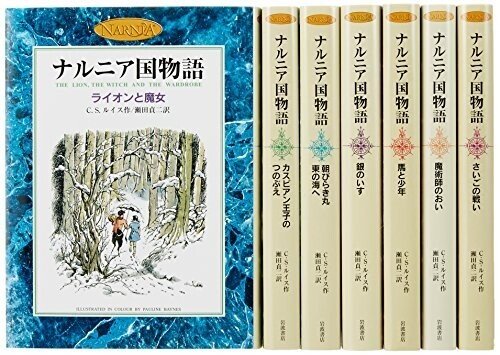
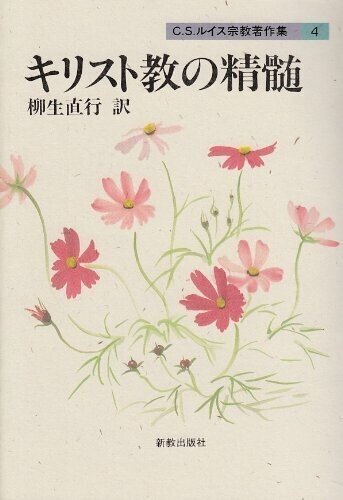
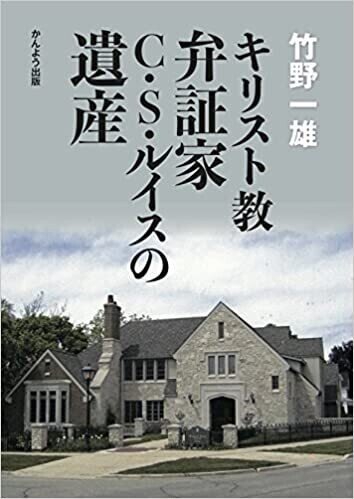
なるほど、その「虚構」は「種の保存」に役立つことが多いだろう。だからこそ、多くの人は、自ずとそれを信じるのだが、「役に立つ」ものが「存在」するとは限らない。「お伽噺のヒーロー」は、なるほど教育上有効な「虚構」ではあるけれど、存在しているわけではないし、大人になれば、それを理解して、その「わかりやすい、仮の理想」を卒業すべきなのである。フロイトがこだわったのも、そうした「理想」なのだ(ちなみに、「理想」とは元来、達成できるものではなく、目指すべきものである)。
フロイトに対する、著者の陰険かつ執拗な、カトリック的サディズムは、ニーチェの言うとおり、キリスト教が「ルサンチマンの宗教」であるという側面を、とてもよく表していると言えるだろう。
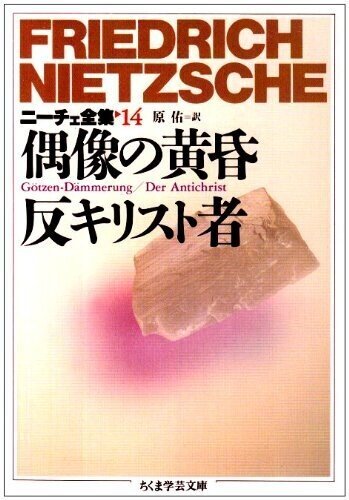
そして、いくらご立派な肩書きの持ち主であろうと、本書著者のような、「フェア(公正さ)」を欠き、なおかつ、ご都合主義的偏見に凝り固まった「精神分析医」には、私は、いくらお金を積まれても、金輪際お世話にはなりたくない。「無神論者」と知られた途端、どんな悪意ある「物語(恣意的解釈フィクション)」をでっち上げられるか、知れたものではないからである。
だから、このレビューをお読みくださったら皆さんには、読むのなら、直接フロイトやルイスの著書を読むことを、是非ともオススメしておきたい。
だが、「カトリックの陰湿さ」を知りたければ、是非とも本書を読むべきである。
なお、4年ほど前に、ルイスの『悪魔の手紙』のレビュー「ルイスの悪魔堕ち(憑き)、あるいは自己賛美とルサンチマン」を書いているので、併せてご笑読いただければ幸いである。
-------------------------------------------------------------------------
【補足】(2021.4.11)
なお、私は本稿で、本書著者のアーマンド・ジュニアが「カトリック」であろうと推認したが、無論「福音派プロテスタント」である可能性も否定できない。
なぜなら、プロテスタントというのは、一般には、カトリックに比べてリベラルなのだが、しかしその一方、プロテスタントには、右から左まで幅広く各種の教会が存在し、その総称が「プロテスタント」でしかないからだ(さらに言えば、アメリカの「福音派」は、プロテスタントが中心ではあるものの、その政治的保守性において「超党派・超教派」であり、内部に、保守派のカトリックやイスラム教徒、ユダヤ教徒なども含んでいる)。
つまり、アメリカ大統領であったブッシュJr.やトランプを支えた、超保守の「福音派」ならば、カトリックのルイスを利用したり、カトリックになりすますことも(日本の読者を相手になら)十分可能だからである。
そして、さらに言うなら、本書を刊行した「春秋社」は、主にプロテスタント系のキリスト教書を刊行しており、業界的な縄張りからすれば、カトリック系の本は出しにくいかも知れない。
しかしながら、その一方で、福音派牧師である鈴木崇臣の『福音派とは何か? トランプ大統領と福音派』や、「日本会議」の会合に呼ばれて講演をするような「日本の福音派」とでも呼ぶべき、プロテスタント信者の保守系評論家・富岡幸一郎の著書を刊行するような出版社でもあるから、福音派や保守派が嫌いなわけでもない。

したがって、春秋社が「隠れカトリック」の本を出したと考えるよりも、「なりすましカトリックである、福音派プロテスタント」の本を出したと考える方が、自然かも知れない。
ともあれ、著者や訳者が、著者の信仰的立場を隠蔽している以上、正確なところはわからないが、本書著者が、保守派の陰険なクリスチャンであることに、大きな違いはないと言えるだろう。
これで、著者のアーマンド・ジュニアが、クリスチャンですらなかったなら、かえって驚きであり、どんな裏があるのかと空恐ろしくもあろう。
初出:2021年4月12日「Amazonレビュー」
(同年10月15日、管理者により削除)
再録:2021年4月26日「アレクセイの花園」
(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
