
村田沙耶香『信仰』 : 内攻する〈孤独〉
書評:村田沙耶香『信仰』(文藝春秋)
タイトルが『信仰』。帯には「なあ、俺と、新しくカルト始めない?」という妙に軽い、内容にそぐわないセリフと、「米シャーリィ・ジャクスン賞中編小説候補作」との文言が、惹句として並ぶ。
「クレイジー沙耶香」の異名を持つ村田沙耶香の、中短編小説プラスエッセイが本書で、表題作が「米シャーリィ・ジャクスン賞中編小説候補作」だ。
まず、「あの」村田沙耶香が「宗教」を扱うようだというので、強く興味をひかれた。もちろん、私の守備範囲だからだ。しかも「米シャーリィ・ジャクスン賞中編小説候補作」。
シャーリィ・ジャクスンは、以前からずっと気になっている作家で、かなり前に1、2冊読んだはず。ずば抜けて面白いということはなかったものの、「薄暗い気味悪さのただよう、独特の作風」という印象が残っていて、その後も文庫や単行本を4、5冊買っているはずなのだが、それらはすべて積読の山に埋もれさせてしまい、未読である。
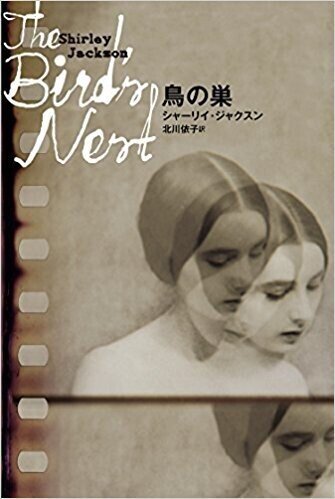
そんなわけで本書は、「あの」村田沙耶香、宗教、シャーリィ・ジャクスンの三つが合わさって、瞬時に私をとらえて逃さなかった。
しかしながら、少々ひっかかるところもあった。
それは「なあ、俺と、新しくカルト始めない?」というセリフが示唆しているように、「信仰」というタイトルでありながら、この作品は「ニセモノのカルト(営業カルト)もの」のようで、その意味では「ニセ宗教」であって、そこに「信仰心」はなく、「信仰」というタイトルには、どこかそぐわないものが感じられた。
だが、読んでみて、その矛盾は解消した。
要は、語り手の女性・永岡、彼女を「なあ、俺と、新しくカルト始めない?」と「ニセ宗教詐欺」の仲間に勧誘するいかにも軽い男・石毛、長岡以前に石毛の仲間になっていた女・斉川、一一この三人の、「信仰」に対する態度が、極端に違うのだ。
言うまでもなく、石毛は「信仰」心など持たない、いいかげんで無責任な男。
「ニセ教祖」予定者の斉川は、かつて「浄水器販売のカルト商法」にハマり、熱心な販売員となった経験を持ち、それに挫折したものの、それでも本気で「ニセ信仰により、救済願望のある人々を救いたいと考えている」奇妙に歪んだ、一種の不思議ちゃん。
そして語り手で主人公の永岡は、あらゆる「幻想」や「夢」を極限まで排除して、その潤いを欠いた即物主義ゆえに周囲の人から嫌われてしまった、(「幻想」や「夢」の一種として)「信仰」の持てない、「怪物的リアリスト」とでも呼べる人物だ。
で、この三人の中で、「信仰」というテーマを担うのは、普通の小説なら斉川なのだが、本作では、語り手の永岡である。

斉川は、「信仰」というものを「頭では信じていないのに、本能的に信じている」といった感じの、捉えどころのなさを持つ女で、たしかに「教祖」にぴったりのキャラクターではあるけれど、村田沙耶香の小説の主人公らしい「つき詰めた極端さ」といったものはない。
ところが、語り手の永岡は、すべての物事から「幻想」や「夢」を極限まで排除した「現実」に生きることが「理想」なのだと長らく信じてきた、極端な女である。
永岡は、あらゆる商品について「原価」を問題にする。つまり、あらゆる「商品」は、「原価」との差異が小さいものほど「現実」に近く、理想的である、と考える。
たとえば、化粧水なら、容器やパッケージや広告イメージなどに金のかかっているようなものは、インチキなのだ。同じ成分の化粧水なら、空き瓶でも持参してそれに入れてもらって、原価に近いかたちで購入できるような商品の方が良いし、そうした買い方こそが、現実的であり正しい、ということになる。

私の場合だと、装丁に凝った本の購入など、何の意味もない無駄遣いであり、本は読めればいい、ということになって、カバーも何も必要はなく、極端に言えば「紙束」でいいのだ。もちろん「初版本」とか「希少本」などに価値を見いだすのは、愚かしさの極みということになるだろう。
そして、こうした価値観は、購買行動だけではなく、長岡のそれまでの生き方すべてを覆っていた。「実質的」であること「合理的」であること、「損を徹底的に排除する」ことが正しい。そのためには、「感情」的な判断や「気分」的な満足感など、愚劣の極みということになる。
これが、長岡が長らく持っていた価値観であり、他人にも奨めなければならない「正義」だったのだ。
しかし、こんな味気のない価値観を奨めてくるリアリストが、常にそばにいたのでは、たまったものではない。
「それの原価がわかっているの!」「それと同じ成分のものが、もっと安く買えるよ」「そんなものを買うのは、ドブにカネを捨てるようなものだよ!」などと四六時中言われていたら、「うるさいな、放っといて! 私は無駄遣いがしたいの! 夢にカネを払っているのよ!」と、キレてしまうのも当然だろう。
それで永岡は、妹や親友に見放された女であり、どうやら、世の中や人は「実質的価値」だけで動いているわけではないと気づいて、その「幻想」の「価値」をも認める世間的な生き方に迎合順応するため、自分を変えようとする。
だが、これが、どうしてもできない。
長岡には「実質的現実」しか見えず、感じられず、そうした「幻想」や「夢」を実感すること、まったくができないのだ。
そして、そんな時に、石毛から件の「偽カルト」の誘いを受けた。
当初は、そんなことうまくいくはずばないと断っていたのだが、斉川の不思議な魅力に惹かれて、そのカルト商品に大金をつぎ込む信者たちが出てくると、永岡は、自分も、そんな「信者」たちのようになりたい、斉川なら自分に「信仰」を持たせてくれるのではと、期待するようになる。
つまり「信じていないカルトを、必死に信じようとして、決意して、のめり込んでいき」、その果てに、村田作品らしい、狂気の破局がおとずれる、というお話である。

したがって、本作「信仰」は、「信仰の狂気」を描いた物語ではなく、「どうしても信仰を持てない人間の狂気」を描いた作品なのだ。
「宗教的狂気」を描いた、よくあるパターンの「宗教小説」とは真逆の、「徹底したリアリズムの地獄とその狂気」を描いた作品だと言えるだろう。
そうした意味で本作は、非常にトリッキーでユニークな、たしかに村田沙耶香にしか書けない作品であり、なるほど「シャーリィ・ジャクスン賞」の候補作になったというのも、うなづける佳作である。
一一だが、私としては、ちょっと「作りすぎ」という印象が残って、傑作と呼ぶほどの「深み」は感じられなかった。
○ ○ ○
本書の中で、際立って「面白い」と感じたのは、エッセイという形式で書かれた「気持ちよさという罪」である。
この「(たぶん)エッセイ」では、書き手・村田沙耶香の、子供の頃の「怯え」が描かれる。
彼女には、自分が「変な人間」だという自覚があり、そんな「変」さを必死で隠し、周囲にその正体がバレないよう、ビクビクしながら成長した。
ところが、彼女が大人になってからのある時期から、つまり、具体的には書かれていないが、芥川賞受賞作家として人気作家になった後、彼女は、その「変」さを周囲から受け入れられ、むしろ、そうした「異質さ」を歓迎され、愛される存在になった。
「クレージーさやか」というあだ名も、肯定的な意味でつけられたものであり、決して彼女を否定し排除するためのものではなかった。それで彼女も、そのあだ名を受け入れた。また、そうしたことで、昔から憧れながらも信用することのできなかった、「多様性」のある社会に、近づけたように思えたのだ。

だが、そうした村田の「受け入れられ方」を、歓迎できる共感者ばかりではなかった。
「変わり者=逸脱者」であるがゆえの悩みや苦しみを反映した、村田沙耶香の作品に共感し、それに救われてきた読者の中にも、「クレージーさやか」というあだ名が歓迎される状況に、違和感や抵抗や寂しさを感じるような者がいたのだ。
そして、そうした読者の反応から、村田は、「クレージーさやか」というイメージの社会的受容は、本当の意味での「異質なものの受け入れ」ではなく、「異質なものを、キャラクター化して消費する」ことでしかなかった、と気づく。そして、だからこそ「クレージーさやか」と言うあだ名の受け入れによる自分の「幸福」とは、「変わり者=逸脱者」への裏切りであり、彼ら彼女らを傷つけるものでしかなかったことに気づくのだ。
自分は受け入れられ、幸福になったように思い違いしていたけれど、じつはそれが「偽の多様性」でしかなかったことに気づいた結果、村田は、その救いのない現実を直視し、引き受けることで、傷つけてしまった同類への「罪滅ぼし」をしようと決意する。
一一これは、そんな「(たぶん)エッセイ」である。
私が、この「エッセイ」を読んで感じたのは、「繊細ゆえの痛ましさ」である。
私は、子供の頃から、自分が「凡庸」であり、それは嫌だから、人に抜きん出たところのある「個性的な人間」になりたいと思ってきた。だからこそ、徹底的に趣味に淫してきたのだと思う。
勉強や運動では、到底トップにはなれそうにないから、好きな趣味の部分において、非凡な人間になりたいと思ったのだろう。
だから私は、自分の本性を隠そうなどとは考えたこともなかった。そもそも隠すほどのものがなく、そこが問題だったので、私は周囲など気にぜずに、自分の道を突き進んだのだ。
また、その意味で私は、鈍感であり得たし、幸福であったとも言えるだろう。要は、村田沙耶香とは、真逆と言っていい、良くも悪くも図太い人間だったのだ。
そのため、私は、周囲に気を使うことは少なかったと思うし、何も考えずに凡庸の中で安らいでいられる周囲の人たちを見下してさえいた。「しょうもないヤツら」だとしか思わなかった。だから、そんな奴らと仲良くなりたいとも思わなければ、興味もなかった。さらには、彼らには、何も期待しなかったのである。
だから、私は幸せだったのであり、今も幸せなのだと言えよう。
そんな私からすると、村田沙耶香の苦しみは、無用な引き受けのように感じられて、痛ましいものとして同情させられた。もっと気楽に、自分勝手に生きればいいのに、とそう思い、しかし、それは性格的に不可能なのだろうなと理解もした。そして、世の中には、こんな人が少なくないのだろうとも理解した。なんとも不幸なことであり、可哀想である。

だが、私には、それをどうすることもできない、というのもわかっていた。
だが、せめて、こうした「解説文」を書くことで、こうした不幸な人たちへの理解が進めばいいと期待し、これを書いている。
この「可哀想」という感覚は、いかにも凡庸であり、ある種の傲慢さに発するものでもあろうけれど、それでもいいじゃないか、私はそんな人間なんだから。一一そう思えてしまうところが、私の強みなのだろう。そして、私はそうした強みに、一抹の申し訳なさを、感じているのである。
(2022年6月18日)
○ ○ ○
○ ○ ○
