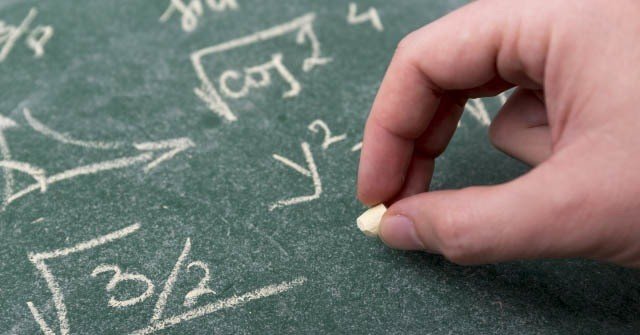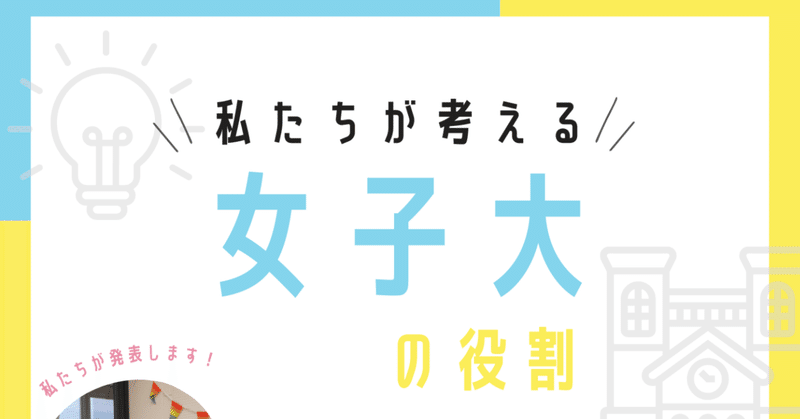#大学改革
変化の過渡期だからこそ考えたい。フェリス女学院大が取り組む、学生の発表で問いかける”我々とは何か?”
歯止めのきかない少子化、コロナ禍を経ての学びや学生意識の変化、にわかに高まっている学び直しへのニーズなどなど。大学の置かれた状況が刻々と変わってきているのは、大学関係者でなくても、なんとなく感じている人は多いように思います。今回、見つけたフェリス女学院大学の取り組みは、こういった変化の過渡期だからこそ、より大事になる取り組みだと感じました。大学はどうあるべきかを考えるのは、大学のマネジメント層だけ
もっとみる大学は学び場から、目的を見つけ備える場に変わる?立命館のイベントで感じた、これからの大学がめざす姿。
大学広報というのは、言ってしまえば大学が何をめざしていて、何をやっているのかを伝える活動なわけで、私立大学の場合その根っこにあるのは教育活動になります。そのため、大学関係者とあれこれ話していると、教育は今後どうなっていくのか、という話になることがよくあります。つい最近、縁があって立命館のイベントに参加したのですが、教育の今後を考えるいいきっかけになりました。今回はこれについて取り上げたいと思います
もっとみるオンライン授業に必要なのは監視か、信頼か。テレワークとは異なる、オンライン授業ならではの難しさ。
オンライン授業が、コロナ後の大学教育にどんな影響を与えるのかは、大学関係者でなくても興味のあるトピックです。今回、取り上げる早稲田大学のニュースは、そんな大学のオンライン授業の今後を考えるうえで、しっかり議論した方がいいもののように感じました。こういったニュースを、大学そして社会がどう受け止め、どうやって未来への肥やしにしていくかが、大学教育を豊かにしていくうえで必須なような気がします。
ニュー
これから支持される学びは、いち大学では成立しない?学びのオンライン化がもたらす、新たな学びの評価軸を考える。
魅力的なオンラインの学びにある2つの共通点オンライン授業という学び方が大学教育に本格的に取り入れられるようになり、なんだかんだでもうすぐ1年が経とうとしています。当初は対面授業の代替として、対面でやってきたことを何とかしてオンラインに置き換えようとする取り組みだったように思います。でも、時間が経ち、学びのコツや特徴がわかるようになってきて、じわじわと内容が変化してきているようです。今回はそんな新し
もっとみる大学にとって起死回生のきっかけになる!? アフターコロナに生まれるだろう、大学と学びの新常識を考える。
新型コロナの蔓延によって、急速にオンライン学習が普及しはじめています。大げさでも何でもなく、おそらく現在、人類が誕生して以来、最も多くの人がオンライン学習をやっているのではないでしょうか。大学に関していうと、オンライン授業用にコンテンツをつくるだけでなく、学生たちが受けられるように資金や機器の援助にまで取り組んでいます。
この一連の出来事は一過性のものなのか、それとも今後も続く変化のきっかけなの
大学の在り方を根本から変える! 大学4年間を“学び続けるための最初の4年間”だと捉え直す。
大学関連の仕事をしているとリカレント教育の重要性が年々高まっているのを感じます。18歳人口が減る大学にとって、社会人学生は新たな財源になるし、国はできるだけ多くの人に効率よく働いてもらいたい。人材が流動化し、実力主義になってきている世の風潮とも合致している。すべての思惑が合っているんだから、そりゃあ重要だと、みんなが言うのも頷けます。
でも、これだけ求められているのに、リカレント教育が盛り上がっ