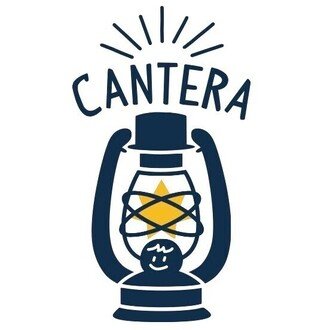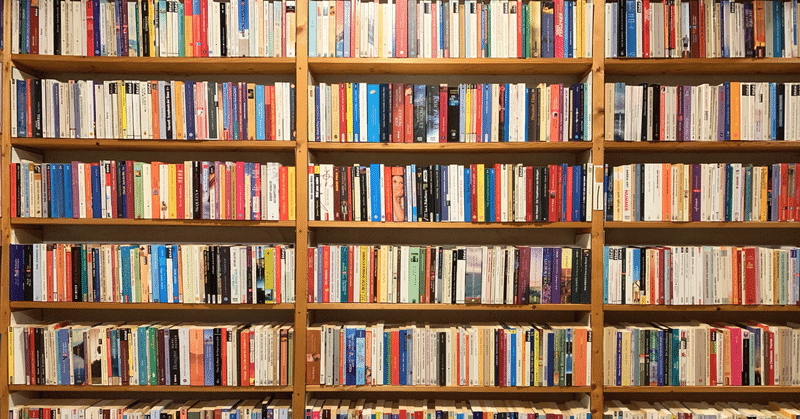本をクリティカルに読むには、ツッコミながら読むのが最適だと思う。自分と意見が違っていても、ツッコミどころ満載な本は良書だと思うし、ツッコミ入れているだけで、思考させてもらえている…
- 運営しているクリエイター
記事一覧
#7 『一流の育て方』ムーギー・キム ミセス・パンプキン
よく、「本は読むだけでなく、読んで実践しないと意味がない」と言われます。確かにな、と思うものの、読んだら忘れてしまうのも事実で・・・
子育て本、勉強本、中学受験本なども多数あります。でも、個別具体的すぎる事例の話で役立たなかったり、一般論すぎてやっぱり役立ったなかったりすることが少なくないです。
「親の教科書」として、学力だけでなく、自主性や習慣、自制心などの非認知能力の重要性に至るまで、網羅