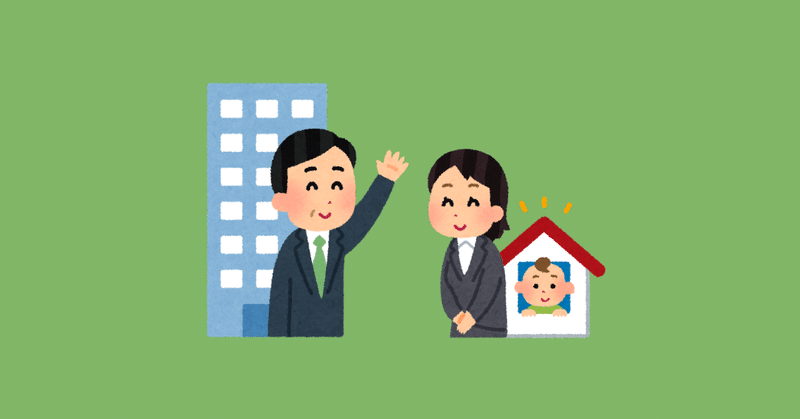
自ら決められるよう相手を支えていく
以前のコラムで、教育ママが子供の進路を勝手に憂いて、子供の意思そっちのけで朝から晩までスケジュール漬けにしてしまっており、それを旦那に咎められたと愚痴られましたが、「毒親はむしろあなたの方だ」と大人げない対応をしてしまった話をさせていただきました。
その時の話の続きとはなりますが、ここで問題になるのは親としての子供への向き合い方。
これは同じく先日書かせていただいた「過保護な上司による弊害」と同様のことが言えます。
子供への向き合い方は、部下への向き合い方にも重なります。
何から何まで親の方で全てを決めてあげるから、いつまで経っても自分自身では決められない子になる。
子や部下が決めるのを待てない親や上司には何が足りないのでしょうか。
もしくは、どのような思考状態にあるのでしょうか。
この子は、この部下は、「ひとりでは何もできないから」。
相手ができないと勝手に決めているのは誰ですか。
決めつける前に、チャンスを与えたことはあるのでしょうか。
その結果、相手をできない状態にしているのは誰ですか。
果たして、本当に自分では何もできない相手のせいなのでしょうか。
そして、これらの向き合い方は、我が子や部下に対してのみならず、私たちの仕事上ではお客様に対しても同様のことが言えます。
特に認知症のお客様に対して。
認知症というのは、風邪と同じような単なる症状のひとつです。
ひとそれぞれによって物覚えが悪くなったり、それに伴って運動機能も低下したりと、その症状の軽重はありますが、例え少し物覚えが悪くなったからといって、全ての機能が失われたわけではありません。
にもかかわらず、「この人は何もできないから」という決めつけのもと、何でもかんでも手を出してしまう。
ご本人の意思を尊重せずに、決める機会を奪ってしまう。
これは、認知症への理解のないご家族など、言い方が悪いですが「素人がする判断」です。
子供や部下やお客様、向き合っている相手のことをああだこうだ言う前に、まずは今の自分の在り方を見つめ直していく必要があります。
「パーソン・センタード・ケア」という言葉があります。
これは、1980年代末にイギリスの臨床心理学者のトム・キットウッド氏によって提唱された、認知症ケアの考え方の一つです。
認知症のある方を、ひとりの「人間」として尊重し、その人の立場に立ってケアを行う。
認知症イコール何もわからなくなる訳ではなく、「自分のことをうまく表現することができないだけ」と捉える。
相手の立場をきちんと理解しながら向き合っていく方法を知れば、向き合う私たちの考え方が変わるはず。
ここで紹介した認知症ケアの在り方と、我が子や部下に向き合う姿勢と、その両者に大きな違いはないのではないかと思っています。
今日も読んでくださいまして、ありがとうございます。
嬉しいです。 サポートしていただきまして、ありがとうございます。 こちらからもサポートをさせていただくことで返礼とさせていただきます。 どうぞ宜しくお願い致します。
