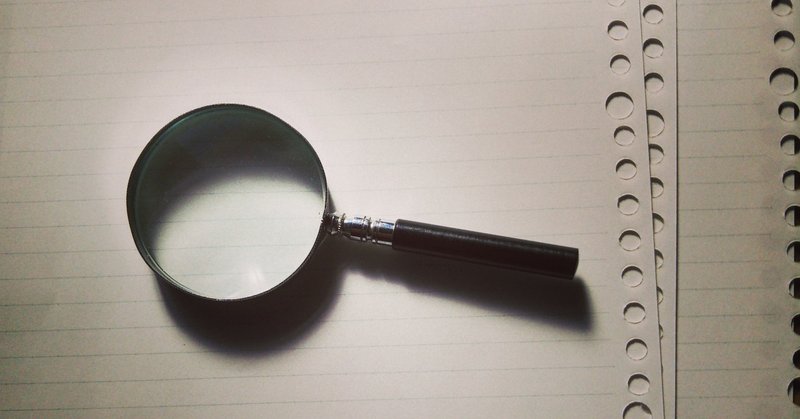#コラム
他者をジャッジしないという能力
本当にたくさんの人と関わりながら仕事をしている友人がいる。議員さんから、社長、アーティスト、関わる人の職種も多様だ。
たくさんの人と関わりながら仕事をするには、体力がいる。お互いの長所や短所を理解し、意思を尊重しながら成果には妥協しない、そんな精神的なタフさも求められる。
さらに言えば、「この人はこういう人だ」と、一方的にジャッジせず、真摯に向き合う姿勢が必要だ。
自分に近い意見を持っている
楽しいと安心のあいだを埋める
市の家庭教育委員として活動している。先日、そのメンバーとのミーティングで、自分たちの活動の目的を改めて考える機会があった。
「楽しいことは他のところがやっているから、自分たちは困っている人をサポートしていくことが大事だよね。」
と、1人のメンバーが話してくれたのだけれど、この言葉を聞いて、自分自身も楽しいことより、「安心」を感じられることに興味があるなと改めて気づいた。
安心は買えるとは限ら
「本音」について思うこと
経営者の本音。
女の本音。
現場の本音。
移住者の本音…
本音という言葉に、惹かれる人は多いと思う。それは日本の社会に、本音と建前という文化があって、空気を読むことをよしとされ、自分の胸の内をぐぐっと押し込める機会を経験する人が多いからだろうか。
一方で、今の私の周りには、本音全開で生きている人たちが多いのだけれど。それはそれは潔く、とても心地がよい。
◯◯の本音と銘打った情報は、たいていの