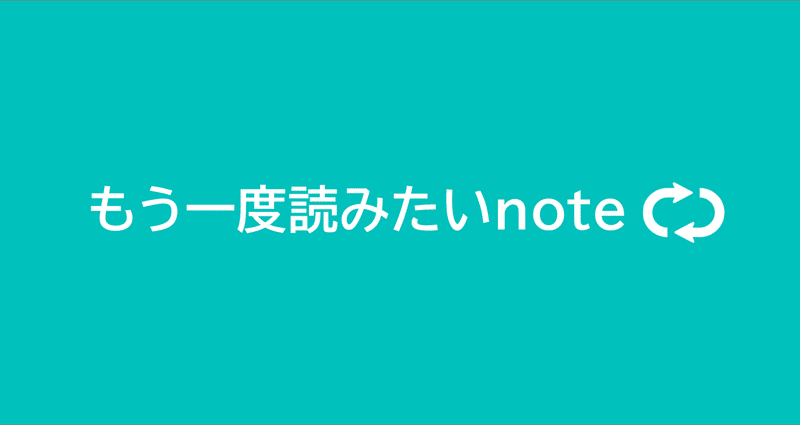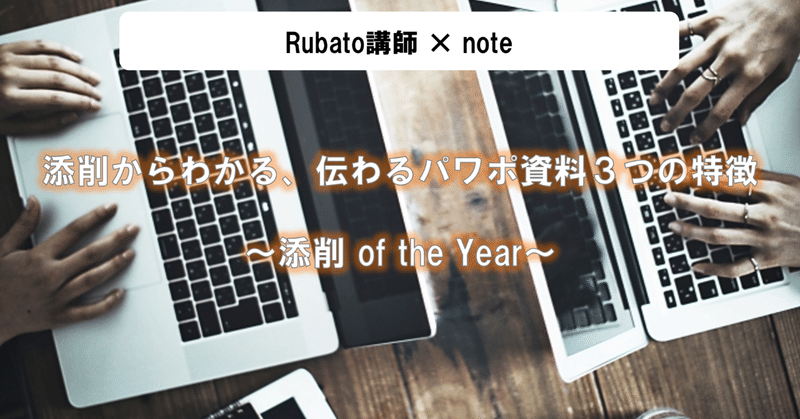2020年2月の記事一覧
添削からわかる、伝わるパワポ資料3つの特徴~添削 of the Year~
「戦略的プレゼン資料作成講座」2日間集中講義ではBefore-After添削というものを行っています。1日目に宿題を出して、作成したスライドを事前に提出していただきます。2日目の講義の時までに複数の講師で添削し、どのようにスライドを修正したかを『Before-After』としてお返ししています。
講師陣から戻ってきたAfterの資料をみて「こういう直し方があるのか」「なるほど、こればいい」と思わず
流せるだけの余白をもって。
他人のささいなミスを「そういうときもあるよね」と思えるのは、心が広いからじゃなくて、心に余裕があるからだろうな。
心の広さなんてどうやって測るのかわからないから、ほんとに広い人とせまい人がいるのか、みんな一緒なのかわからないけれど。
でも、広さはあってもぎゅうぎゅうにいろんなものを詰め込んでいたら、そこに他人のミスへの対処を入れるすき間がなくて、「そういうときもある」とは思えない気がする。
土に学ぶ、プロジェクトのつくり方/自然栽培とファシリテーションの関係
はじめにこんにちは。内村です。だいたいうっちーだったりうっちゃんだったりします。あと百姓だったりファシリテーターだったりもします。
はじめてのnote記事となる今回は、自己紹介を兼ねたファシリテーションの探求記事です。
いまの自分を形作る根幹になっている個人的な経験と、そこから気づいた土と人の関係性について考察してみたいと思います。
有機農業に憧れて「方向性の違い」というバンドみたいな理由で
「残りの人生、少しだけ好きにさせてもらいますね」
ばあちゃんには、自由がなかった。結婚をしてから70年近く、ずっと。
じいちゃんは人にも、自分にも厳しく、すべてが自分の思い通りになるものだと信じて疑っていない人だった。
ぼくがまだ子どもだった頃。じいちゃんは歩くのがものすごく早かった。小さなぼくは小走りにならないとその歩みについていくことができない。後ろを振り返ることは一切なく、家族をどんどん引き離しながら目的地へ向かって立ち止まることなく突