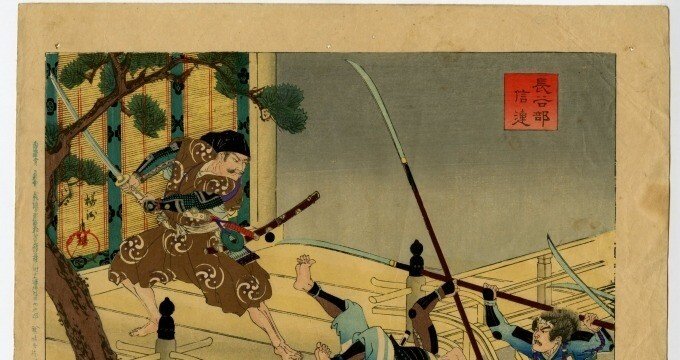
1男1女の子供を持つ平凡なサラリーマンと、父で作家の「長谷部さかな」は、不思議なキッカケから毎日メールをやりとりすることに。岡山県の山奥にある見渡す限りの土地や山々はどのように手…
- 運営しているクリエイター
2022年7月の記事一覧
【268日目】:原点は大井町
ご隠居からのメール:【原点は大井町】
「息子へ紡ぐ物語」がはじまるきっかけになったのは、大井町だったが、昭和三十七年に上京し、しばらく入居していた会社の寮も大井町にあった。正確にいえば、JR大井町から徒歩十五本の立会川の社員寮だ。八畳の部屋に台所があって、二人の同僚とともに三人で暮らしていたが、炊事なんかするわけがない。それよりも大井競馬場の近くなので、せっせと競馬場に通った。
わい雑な場末の
【264日目】結婚式の演出
ご隠居からのメール:【結婚式の演出】
「結婚式の演出」はブライダル関係者が読んだら、結婚式のスタイルがこの二十年間で変化していった歴史をふりかえることができて、参考になると思う。しかし、創作大賞の審査員のこころをつかむためには、語順をもう一工夫したらどうだろう。
「結婚式の演出」で伝えられているのは、
・プロフィール映像
・墓参りの映像
・生まれてくる息子へ
このうち「映像」はありきたりの
【263日目】起承転結
ご隠居からのメール:【起承転結】
それでは、365日目を「終点は浅草」というタイトルにしてエンディング候補とすることにしよう。
もちろん、その後も隠居がパソコン操作不能にならない限り、メールのやりとりは続けることにし、面白そうな話題があれば、365日のどこかに挿入すればよい。そうすることによって、全体の構成を見直しながら、起承転結のメリハリをつける工夫をするのだ。
365日の話題は、なるべく















