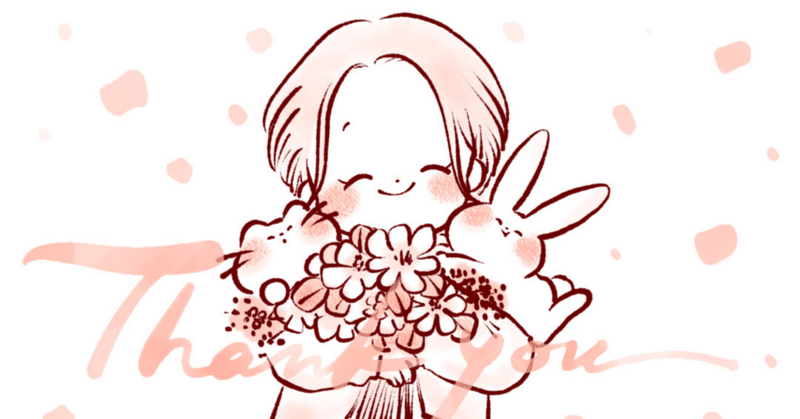
幸せになるためのたった一つの方法は、幸せとはなにかを知ること。
幸せとはなにか?という問いは、私たちの人生における一大テーマだと思います。
しかしながら、幸せとはなにか?という問いに価値が生まれる瞬間は、例えば「深夜まで眠れなくてなぜか不安になってしまって、自分が生きる意味や目的を見失ってしまったとき」・あるいは「しばらく家から出ておらず、人に会っていないのでなんだか虚しい気持ちになってしまっているとき」
そんな、自分が何のために生きているのかわからないという疑問符がつきつけられるような瞬間、そのときに「幸せとはなにか?」という問いに価値が生まれてくると思うんです。
なので、この先、進むべき道が分からなくなってしまったとき、この内容を思い出してみてください。きっと、あなたが足を一歩前に踏み出して、進んでいくための手助けができると思います。
それでは早速、本題に入っていきたいと思います。
まず、自分にとっての幸せとはなにか、漠然とでもいいので考えてみてください。
家族や友人との大切な時間のことでしょうか?
それとも、毎日健康に過ごせることでしょうか?
活動の中で充実感や達成感を得られることでしょうか?
自分が大事に思っている人や活動にしっかりと向き合うことでしょうか?
言ってしまえば、このどれもが正解です。それどころか、みなさんの頭に浮かんできた全ての「幸せ」だと思ったものが「幸せとはなにか?」という問いへの答えになります。
なぜなら、「幸せ」というのは、どこまでいっても〈主観的〉な概念であって、周りの人や社会からどう見られるかなどは関係なく、その人自身が「幸せ」という感覚を持っているかどうかを基準としているからです。
ここで、人間の〈主観的〉な感覚が幸せだということは、人間がどのような仕組みで〈主観〉を形成しているのかについて理解が深まらなければほんとうの意味で「幸せ」とは何かを知ることはできません。
なので、ここからは人間の〈主観〉が形成される仕組みについて考えていきたいと思います。
まず、人間は脳の機能を中心として、身体活動を行なっています。この身体活動には様々な活動があり、例えば〈五感を通した外部環境や現状への知覚〉・〈思考〉・〈発話〉・〈行動(意図+動作)〉・〈情動(感情や気分)〉など、種々の活動を行なっています。
ここで何を言いたいのかと言うと、これらの複数の様々な活動が、ときに同時発生的に行なわれ、重層的かつ複雑なプロセスで行なわれているということです。
例えば、幼稚園生のAちゃんとBくんが、手を繋ぎ・歩きながら楽しそうに会話をしているとします。このとき、手を繋いで歩いているというこの身体活動は、
〈前に進めるよう両足に働きかけ・Aちゃんから手を繋ごうとして右手を動かし・Bくんが左手で右手を掴み返してくれていると知覚し・さらにBくんと会話をするために言葉を考えて発話し・外部環境や内部活動を通した種々の入力情報から結果として楽しいという感情の出力を返している〉
というようなたくさんの身体活動が複雑に重なり合った結果、統合的な活動として実現されています。そして、この全ての活動のプロセスにおいて、Aちゃんは説明しがたい複合的な〈感覚〉を感じています。
〈手足を動かしている〉という感覚・〈発話をしている〉という感覚・〈楽しい気分を感じている〉という感覚
Aちゃんという主体は、これらの感覚を同時並行的に感じ、たった数秒間・たった数分間ほどのこの身体活動と外部環境の相互作用を、記憶として自身の身体に刻み込み、生まれてから死ぬまでこの学習を繰り返していくことで、人ひとりの人生が形成されていくわけです。
ということで、議論するべきなのは、〈私〉という主体によって行なわれている種々の〈活動〉とその〈感覚〉を、充実したものにしていくことができるかどうか・それが私たちが「幸せ」でいるための重要ポイントとなるんです。
ここで、少し自分語りになるんですが、私が一番幸せを感じる瞬間は、例えば一日かなり疲れて家に帰ってきたときに、あったかいお風呂に入るとき。あるいは、自分が大事にしている人たちに対して、少し気の利いたことや喜ばせられるようなことをして、幸せな気持ちになってくれてるかな~と思うとき。そんなときに一番幸せを感じます。
このようにして、その人にとっての幸せは人それぞれ違う主観的なもので、ところどころ共感できるもの・共通のものがあったり、本質的には同じような喜びをもたらすものであったり、たくさんの小さな幸せがこの世界には溢れています。身の回りを見渡すだけでも、自分の笑顔に気づくだけでも、そこらじゅうに幸せなことが転がってたりするんですね。
ところで、それぞれの人間にとっての主観的な幸せが、それぞれ異なっているのはなぜかというと、みんな持っている価値観や感じ方が十人十色で違うからです。
例えば、それぞれの人の中で価値観の優先順位というものがありまして、ある人にとっては趣味のゴルフが一番かもしれないし、ある人にとっては家族との時間が一番かもしれない。ある人にとっては仕事第一かもしれないし、ある人にとっては健康が一番、プライベートが一番だったりするかもしれない。他にも、美容・ペット・恋人・食事など…。
そのようにして、それぞれの人が幸せな感覚を得る条件というのは、それぞれの価値観や感じ方によってかなり変わってきます。だから、自己理解を通して自分の価値観を知ったり、日々の自分の気持ちをウォッチしていったりすることが大事になってくるんですね。
しかしながら、人間という生物に共通して存在する重要な性質というものもあって、人間への理解を深めていくことでより充実した活動と感覚を得ていくことが可能となります。
その重要なポイント3点というのは。
すべての活動は身体のコンディションに依存している
人間は群れる生き物なので、人との関わりを通して生き生きとした感覚を持ちやすい
1日24時間という制約の中で、どのような活動をするかは自ら選択することができる
という3点で、
まず、例えば
〈昨日2時間しか寝れていなくて、今日の大事な会議では全然頭が回らなく、仕事に支障が出てしまった。食生活と運動習慣が乱れていて、生活習慣病を併発してしまい、日々の活動と感覚の質が低下してしまった〉
というような事態は、「すべての活動は身体のコンディションに依存している」という前提を顕著に表しているものだと思います。
つまるところ、幸せな感覚を得たければ、その土台となる健康を十分に考えた生活を送らなければならないということです。
次に、例えば
〈今月は誰ひとりとも会っていない〉
というとき、孤独を感じて幸せとは程遠いような感覚を持つと思います。
これは、人間が進化してきた過程の中で、人間同士が共生し協力しあわなければ生き残ることができなかったため、本能的に人と人が集まりたいという気持ちを持つようになったという背景があり、
人は社会的に交流しあって、他者に支えられたり、利他的な振る舞いをしたり、もしくは単純に会話を交わすことで幸せな感覚を得られるという根本的な性質を持っているということを示します。
最後に、〈1日24時間という制約の中で、どのような活動をするかは自ら選択することができる〉というのは言葉の通りで、
例えばその人自身が身体のコンディションを整えたいのであればそのための活動を選択することができるし、あるいはもっと良好な人間関係を築きたいのであればそのための活動を選択していくことができる。また、自分の価値観を踏まえて、家族を大切にしたいのであればそのためにどうすればよいのか考えて・あるいは直接何をしてほしいか聞いて大事にしてあげれば良いし、仕事のことが大事なのであれば一生懸命に仕事を頑張れば良い。
というように、自分自身の幸せな感覚は、自らどの活動を選択して時間を投資していくかという主体的な態度によって掴み取っていくことができるんです。なので、人間は無力なんかではありません。少しの工夫が、小さな幸せを生み出していくんです。
結びに、最後まで読んでいただいて本当にありがとうございます。みなさんの人生が幸せで溢れますように。また他の記事でお会いしましょう!
参考:自分の価値観を知るための質問リスト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
