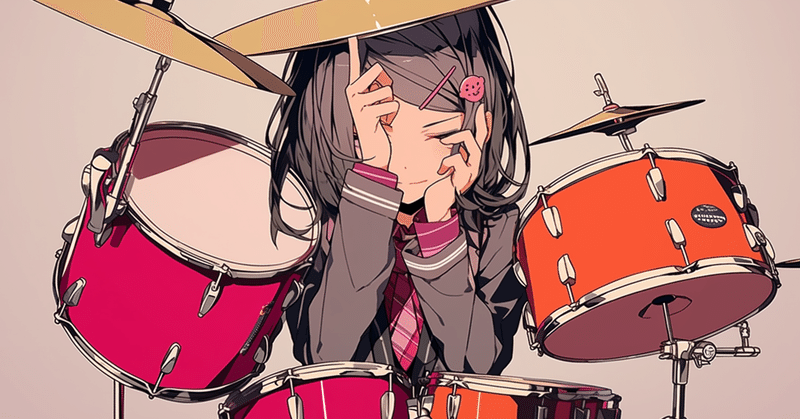
マインドフルネス実践(応用編①)
得意な感覚を使ったマインドフルネス
下記の章で解説しましたが、マインドフルネスの訓練は「頭をよぎる嫌な思考を受け流し、心の平穏を手に入れる方法」です。
思考を受け流すためには五感の感覚に集中します。
今回は自分の得意な感覚(マシな感覚)を利用した様々な方法を紹介します。
こういうのは手札が多ければ多いほど、自分に合ったものを見つけられるし、飽きないようにルーティンを組むこともできます。
片っ端から試してみてください。
また、どのやり方を行う際にも マインドフルネスの注意点 に記した注意点は共通なので、必ず意識してください。
レーズンセラピー(味覚・嗅覚・触覚・その他)

PTSD・トラウマ治療につなげるマインドフルネスの訓練法として、海外の臨床治療で有名な手法です。
やり方は単純で、1粒のレーズンを15分以上かけて食べることです。
まず口に入れる前によく観察します。
表皮の光の反射、しわの模様、嗅いだ時の匂い、指に触れる柔らかさに集中します。
口に入れてもすぐ噛まず、舌や口の粘膜に触れる感覚、唾液の感触、息を吸うときに感じる香りを楽しみます。
やがてゆっくりと時間をかけて噛みます。
歯に伝わる感覚を味わい、味や香りや口の中の感覚が、噛む前と比べてどう変化していくかを感じ続けます。
そして少しずつ飲み下します。喉を通る感触、口の中の後味、気づけるものすべてを感じ続けます。
以上をできるだけゆっくり丁寧に行いますが、15分という時間には特にこだわらなくても大丈夫です。
当然ですが、レーズンである必要は全くありません。
好きな食べ物を使って行うのがベストです。
これは味覚だけでなく、人体のほとんどの感覚を総動員する訓練法なので、うまくはまって習慣化できる可能性は高いと思います。
そうなれば儲けもの。食べるということが、単に空腹を満たしストレスを解消するためだけのものではない、と実感できるでしょう。
トラタカ瞑想(視覚)

視覚に集中する瞑想で、ヨガが起源です。
部屋を暗くしてローソクに火をともし、火のゆらぎと液体化して形を変えていくロウの様子を見つめ続けるという、いたってシンプルなものです。
ローソクの火というのは観察していると意外と飽きないもので、どの瞬間、どの方向に揺れるかまったく予測がつきません。
それが古来からひとつの瞑想のバリエーションとして採用されている理由だと思います。
ADHD的なうっかりで火事を心配する人もいると思いますが、ご心配なく。
燃えるローソクの動画はYoutubeでいくらも出てきます。動画だとリラックスBGMがついているものもあります。
時間は5分くらいから初めて構いません。慣れてきたら時間を伸ばしていき、30分も続けられるようになったら大したものだと思います。
僕は視覚認知が大の苦手ですが、逆にそれを克服するためにトラタカ瞑想を行っていました。
瞑想を終えるたび、周りの風景がはっきりと見え、活力が湧いてきました。
また、視覚を使ってマインドフルネスしたい、という人へのヒントですが、Chromecast を自宅で使っている場合、画面に映るきれいな画像を眺め続ける、という方法もあります。
一定時間で画像が切り替わるので「飽きない」という観点からはとてもやりやすいと思います。
部屋を暗くして、画像の細部まで細かく観察しましょう。
ちなみに、視覚が得意というのはどういう人か?
イラストや漫画を描く人は間違いなく得意です。
写真を撮るのに凝りまくってる人もそうです。
そういう人たちが頭の中のイメージを平面に落とし込めるのは、脳内の活動に視覚の占める割合が大きいからです。
作品のクオリティは関係ありません。
そのような作業に集中を続けられるという時点で、少なくとも他の五感と比較して視覚が優位な人なのです。
音ゲー(聴覚・反射神経)

聴覚は僕にとって一番効果的だったマインドフルネスです。
科学雑誌ナショナル・ジオグラフィックの記事でもテトリスがPTSDに効くと言われてます。
これは視覚に集中しながら次々と対処をせまられる状況を強制的に作り出すからです。
嫌なことを考える暇を強制的になくす、これはマインドフルネスそのものです。
そして、その聴覚バージョンが音ゲーになります。
音ゲーは、降ってくるもの(ノートと言います)を見ながらタイミングよくボタンを押すゲームですが、やり始めて気が付いたのは「画面は意外と見なくてよい」ことでした。
ゲーマーには常識かもしれませんが、ノートはほとんど曲のリズムにハマっています。
なので、音7:画面3くらいで意識を向けるればよいことに気づいたとき、ぐっと上達しました。
上記のナショナルジオグラフィックの記事によると、トラウマは時間経過によって形成されるので、心理的な傷を負った直後の実験例が挙げられています。
ですが、トラウマ経験がある人は、すでに時間が経った後でも傷を深めないためにマインドフルネスの実践をお勧めします。
打楽器の練習(聴覚・触覚・運動神経)

打楽器の練習は音ゲーに触覚と運動神経を加えたマインドフルネスです。
これも僕の話ですが、音ゲーに物足りなさを感じめたころ、刺激を求めてドラムを始めました。
(つまり、その頃には自分に「楽しい、幸せ」が少しは想像できるようになっていたのです)
始め方ですが、
・音楽経験がないからといって、教室に通う必要は特にないと思います。
・最低限の知識はネットやYoutubeで簡単に仕入れられます。
・スティックを持って時間500~600円のスタジオに行けばドラムセットは置いてあります。
・ものすごくゆっくりのテンポからリズムパターンを練習しましょう。
・お金がない人は3000円くらいでダンホンというダンボール製のカホン(ストリートミュージシャンがよく使う打楽器)が買えます。
・近所迷惑になる場合は近所の川原とかでやりましょう。ちょっとカッコいいです。
やり方は上のテトリスの理屈と同じで、必ず「何かに合わせて叩くこと」です。
曲に合わせるのは難しいので初心者はメトロノームを使いましょう。技術の習得を目的に練習をする人もメトロノームは常に使っています。
そうして音の大きさ、迫力、残響、手に伝わる刺激、それらを残らず感じ取るよう集中しましょう。
スキルの上達が目的ではないので、それらを味わう余裕がなくなる複雑なパターン・高速テンポでの練習は避けてください。
それは結果としてスキルが上がってきてからにしましょう。
音ゲーよりずっと気持ちよく、僕は何年かハマっていました。
分量が長くなりましたので、次章へ続きます。
頂いたお金は新しい治療法の実験費用として記事で還元させていただいております。 昔の自分のようにお金がない人が多いと思いますので、無理はしなくて結構です。
