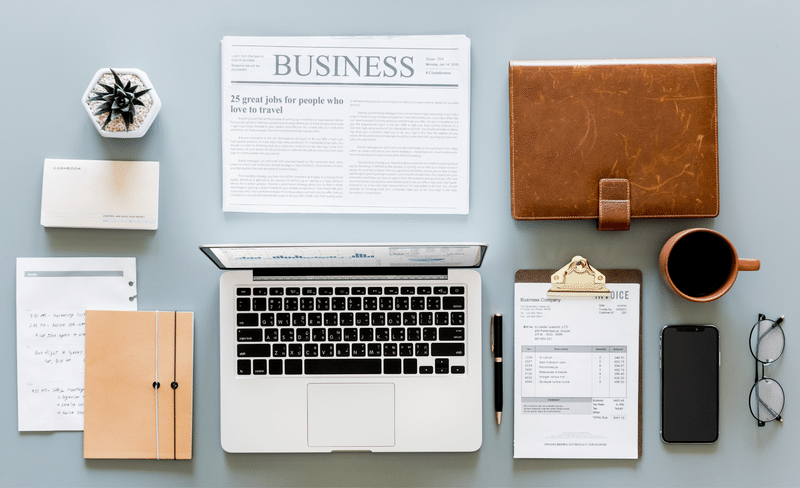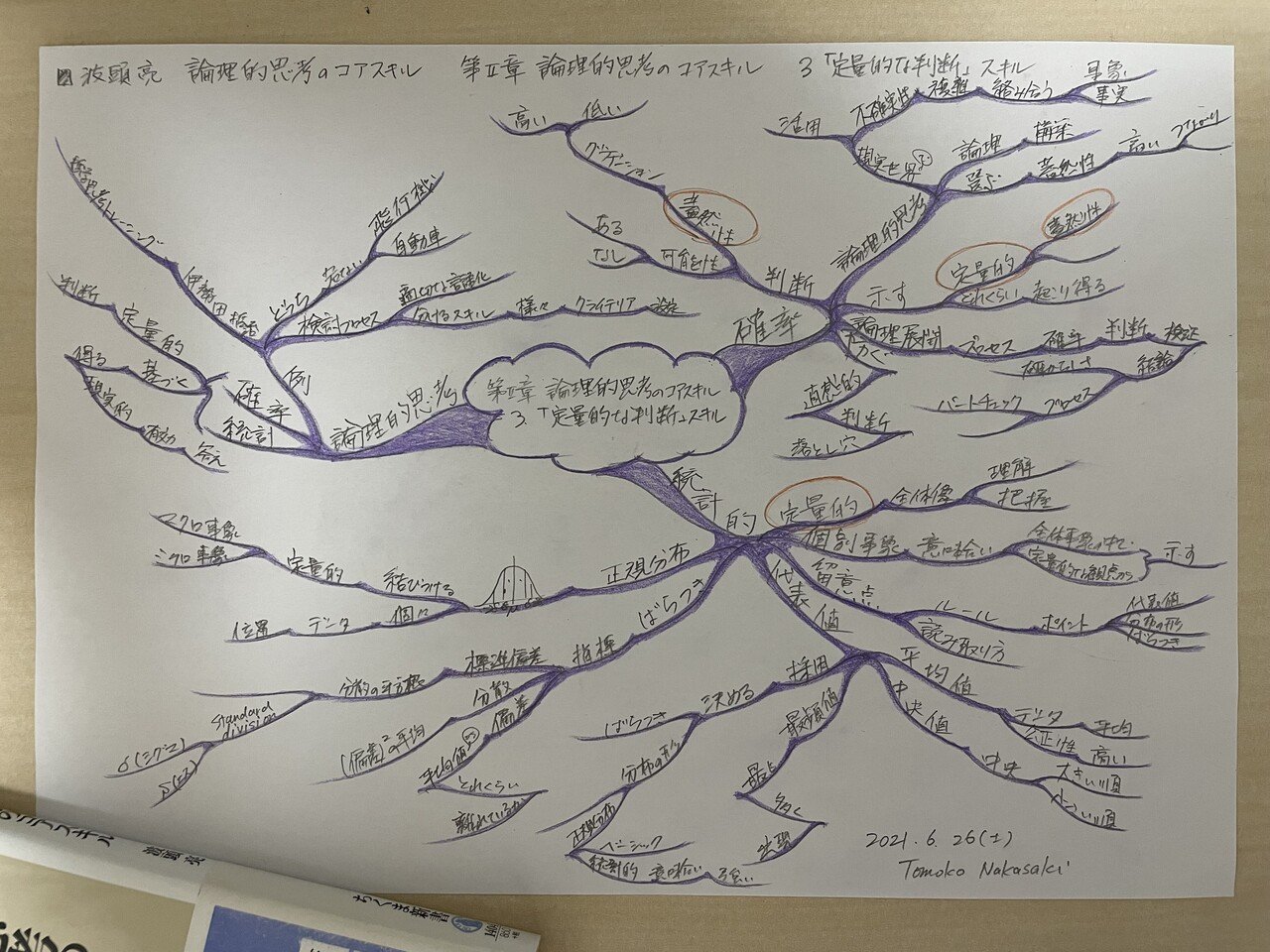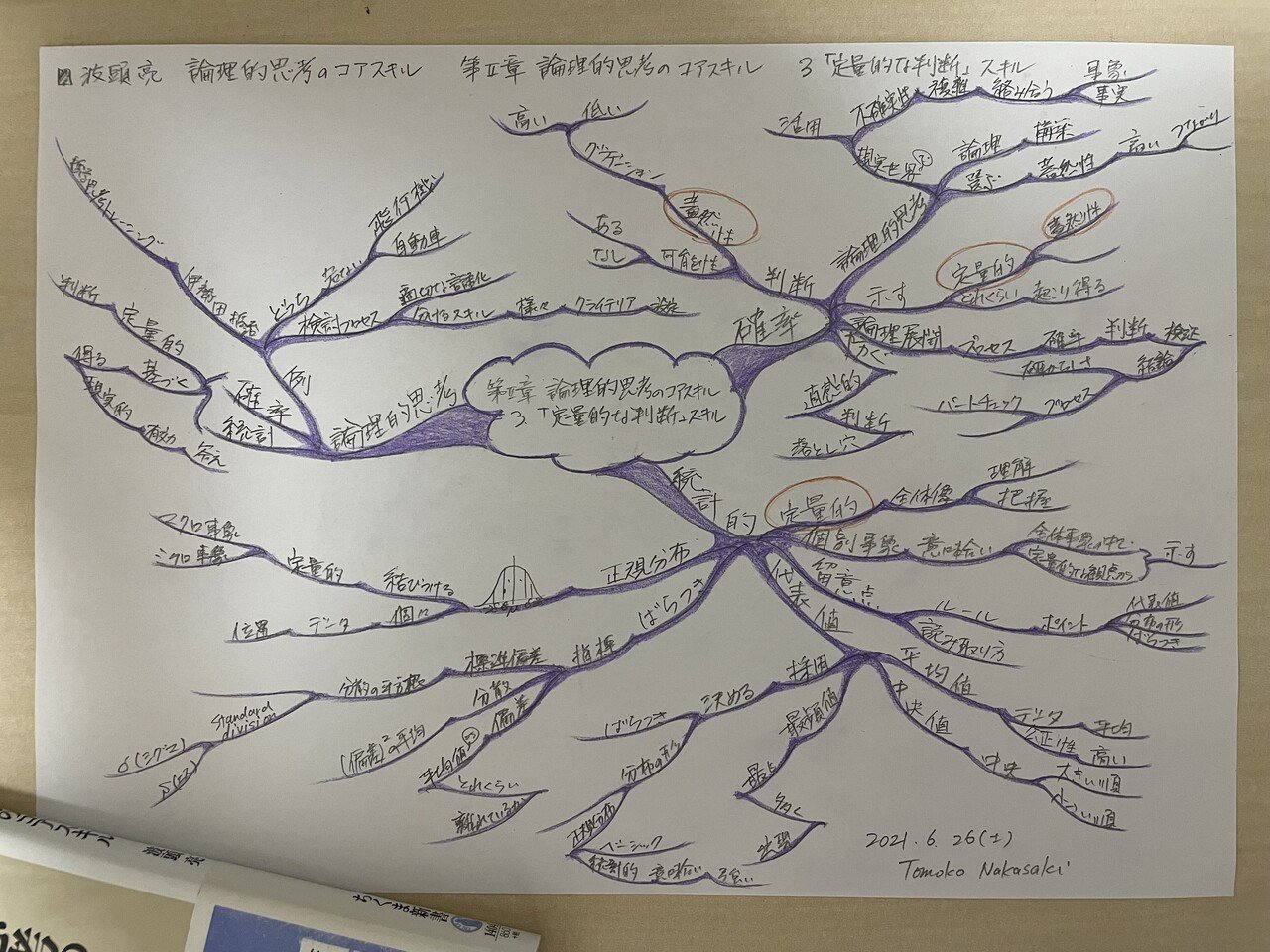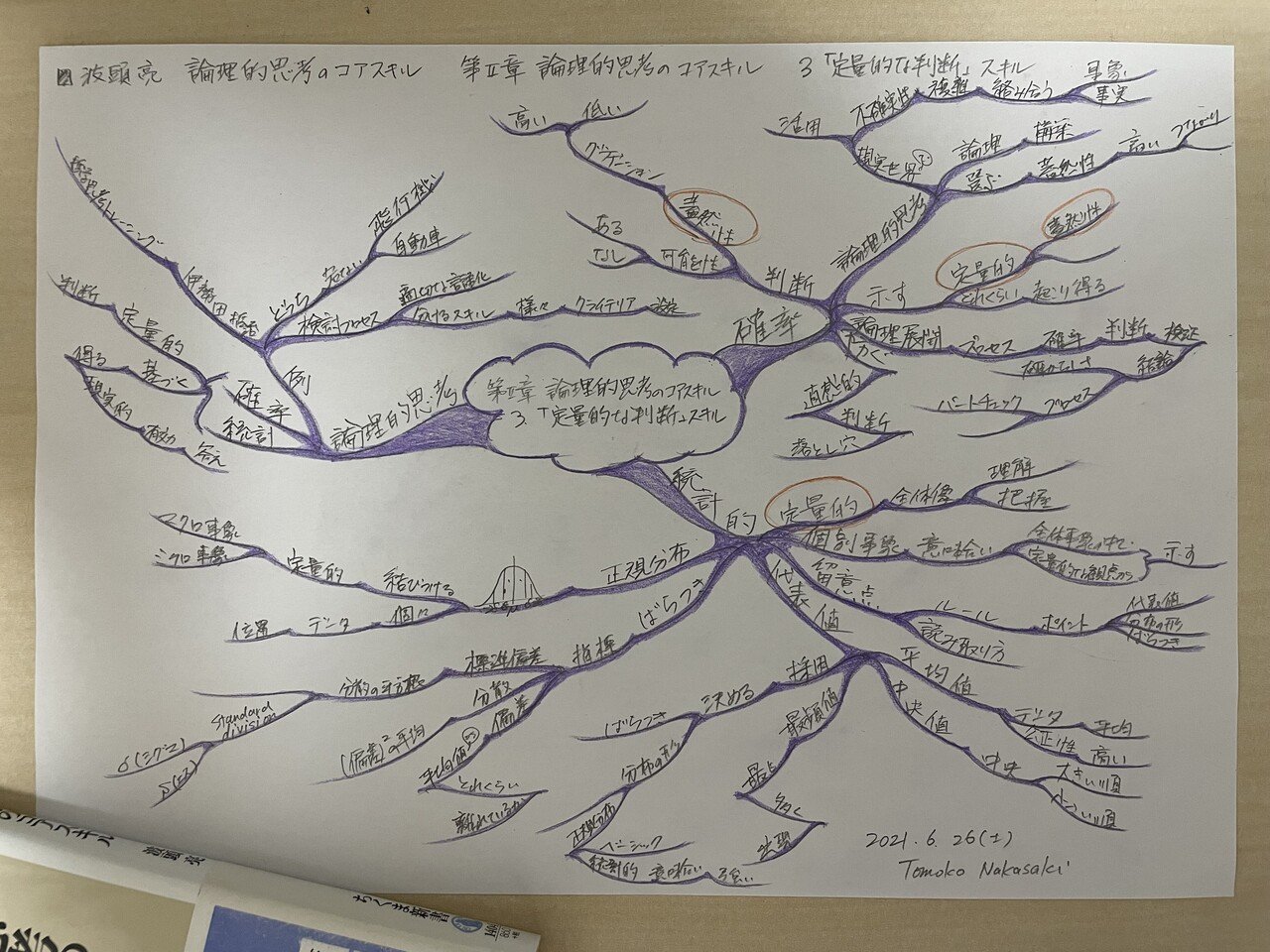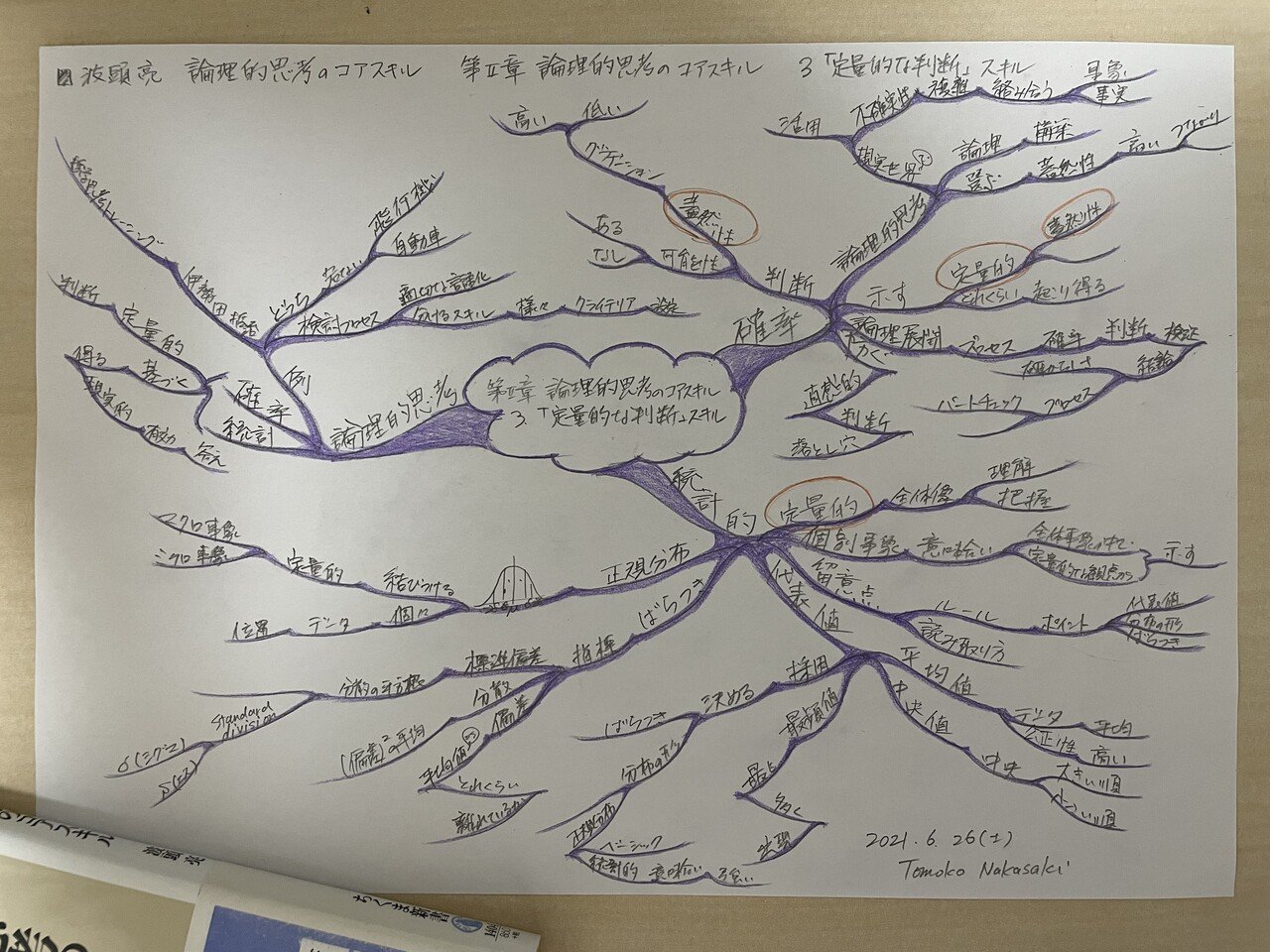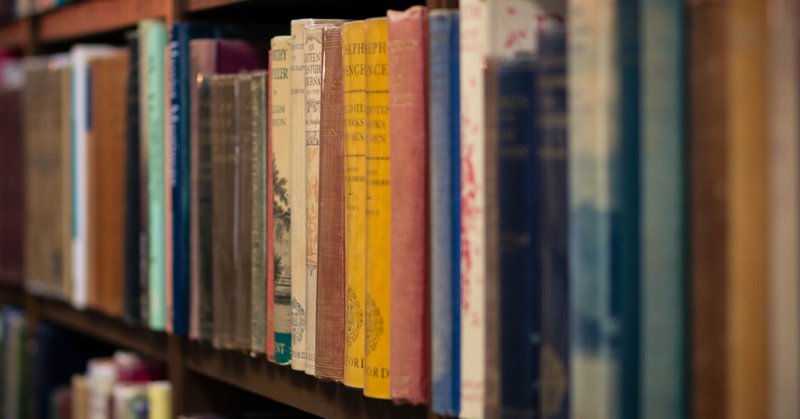2021年6月の記事一覧
調べ方を調べるには?
何か課題が出て調べ物をしなければならないとき、国立国会図書館のリサーチ・ナビが便利です。テーマ別に参考図書や参考サイトが集められているため、どの資料にあたったらよいかの指針になります。
トップページからのリンクだと見つかりづらいこともあるので、検索窓にキーワードをいれて調べ方のタブから探したほうがぴったりの情報が見つかります。
伝えることの極意
凝ったことをしなくても本意を伝えるのが伝えることの極意だと、古典から教わりました。ついいろんなことをあれこれ盛り込んでしまうので自戒します。
142 数少ない口数で多くを理解させるのが大才の特質なら、小才は逆に多弁を弄して何一つ語らない天分をそなえている (二宮フサ訳『ラ・ロシュフコー箴言集』 p.48)
【仕事術メモ】
■Google Keep で情報収集
・Google Keep Chrome 拡張機能
→保存したいウェブページ上で右クリック
→コンテクストメニューに「Save to Keep」があるのでクリック
→URLが保存され、サムネイルと本文の一部がパネル形式で表示

大学図書館員が使うレファレンスツール3選
日本十進分類法探している資料がどの分野に分類されているのかを調べる。図書館は同じ分野の本がまとめておいてあることが多いので、本棚(書架)を実際にみて資料を探すとき便利である。
JapanKnowledge複数の辞典・事典などを一括検索できるデータベース。日本国語大辞典など、定評のある辞典・事典などが一度に端末上で検索できるため、とても便利。
自分の未知の分野について質問されたら、まず Japa