
364.ねえ、ねえ。みんな、みんな~お話好きなんだね。
(17)人生に奇跡を呼ぶ方法
1. みんな、お話し好き
coucouさんの先輩にとても話し好きの人がいる。
いつも同じような話ばかりしているのだけれど、まるで機関銃のように話しまくり相手に話す隙を与えてくれない。
話している最中は、相手が興味あるかないかはまるでお構いなしで自分の自論を話し続ける。
coucouさんはこのような人が相手の場合、一切目を合わせないようにして合図をしているのだけど、相手はそれに気づかない。
その人はただ、話し続けるんだ。
もはや、相手が聞いている、聞いていないなんて関係ないようなんだ。
難しい専門用語やあるときは英語などのため、またあまりにも早口なので意味不明の場合もある。
おそらくメモを取ろうとしてもメモにはならないと思う。
coucouさんはね、わざと意地悪して、横を向いたり下を向いたり、ノートに落書きしたり、スマホ画面を見続ける。
それでも、その人にはcoucouさんが何を考えているか、相手に迷惑をかけているかどうかはわからない。(ちゃんと息をしているのだろうか?)
とにかく、いつまでも話が終わらない。
確かに素晴らしい内容かもしれないけれど、このような場合ほとんどの人は耳を塞ぎたくなってしまうだろうね。
この先輩は、「伝えたい」「知らせたい」「知って欲しい」という強い気持ちと、自分はこれだけ知識を持っている、という上から目線という押しつけもあるような気がする。
もし、疑問や反論などしようものなら話はさらに倍増してしまう怖れも持ち合わせているんだ。(だから、絶対質問しない…)
また、時間の観念が低いのかな?自分の時間はたっぷりとあるのかな?1時間でも2時間でも講演会のように話続ける。
相手はその話を望んでいなくとも、勝手にこの話は知っておいた方がいい、と解釈しているようなんだ。(悪意はない)
でも、coucouさん自身もこの先輩と同じような素質があり、あまり偉い事はいえないけれど、今はあまり自分から進んで話さないようにしているんだ。
まさに人は自分の鏡なんだね。
こうして話す事、聞く事に注意して意識していると大概の方々は、話をするのが好きな人が多いというのがわかるようになった。
例えば、coucouさんの講演会や会議などでも、人が話をしているのに即発されて自らも我慢が出来ず話したくなる人たちもいる。
他人が話をしている最中にも拘わらず、他の人と話したり、大切な部分を聞かずに、自分の都合の良い部分だけ聞き、反応する人も多いよね。
確かに、人前で話すことを嫌いでない人以外は話し好きの人が多い。
coucouさんが講演会をしているときに、質問があるというので司会者がその人を指名したらまるで講師のような話し方となり、質問とは関係のないその人の講演会になってしまった場合もあった…。
司会者の方は、何度も時間短縮のお願いをしているのに拘わらず夢中で話続ける。
会議や座談会の場合にもこのようなことが良くあるよね。
「自分は凄いのだ」
「自分はこれだけの知識や理論を持っている」
「こうあるべき…」
「ああ、あるべき…」だと演説をし始める。
会議や座談会においてはそれぞれの目的と時間の制約があり、主催者にしてみればとても迷惑な話なのだけど、その大切な時間を奪われてしまう。
講演会、座談会、会議などで人の話を聞いていると、自分もどうしても話したくなるという衝動があるようだ。でも、主催者には目的と時間があるわけだから現実的にはどんな良い話であっても、意味を失う無駄話となってしまうよね。
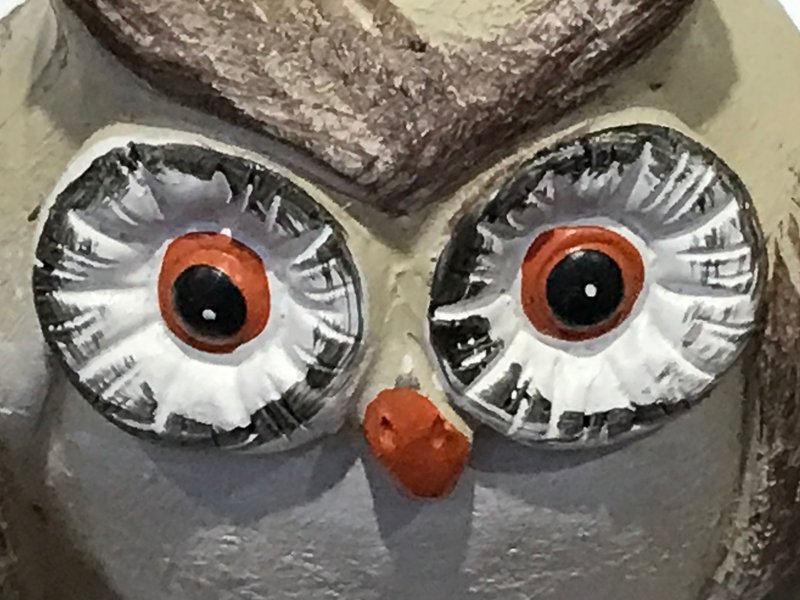
2. 話し好きの人の共通点
話し好きの人の共通点がある。
それは、自分が話す場がないことと、満足感を得る場がないという点。
普段から自分の話に共感してくれて話している人には、話を聞いてくれる人がいるから、そんなことはないけれど、話す場のない人は、そのような違う場所、人が集まっている場所で話したくなってしまうようだね。
そして、話尽くすと自分勝手な満足感に浸ることができるようだ。
話しというのは、
「話をするのが好きな人」と
「話を聞くのが好きな人」
「その両方」という人に分かれる。
「話をするのが好きな人同士では」争いが起こるか、どちらかに不満が残る。また、「話を聞くのが好き人同志」だと、互いに盛り上がりませんね。
また、「その話を必要として聞く人」と「その話が不必要な人」もいる。不必要な人にいくら必要性を説いたところで、まるで意味をなさないことがわかるはずだけど、相手が何を求めているかがわからない人は、不必要な話でも話続けてしまう。
「話す場のない人」の共通点は、相手が共感していないのに拘わらず自分の考え方や知識を押し付けている人たちといえるかもね。
だから、その場がなくなるんだ。
このように自己中心的な人の話ほどつまらないものはないし、誰も必要としていないという結果がそうさせてしまう怖れがあるのだと思う。
残念ながら、自己中心的な人はそのことを絶対に認めませんが…。

3. 終わりを考える話し方
話しの上手い人にはある共通点がある。
1番は相手が求めている、「必要としている話」をする。
2番目は「わかりやすく説明」できる。
答えのない哲学では困るよね。
自分にとっての答えは必要だけど、伝わらなければ意味がない。
3番目は「時間を意識する」こと。
大きな講演会ですと1時間から2時間ぐらい。
小さな講演会や座談会であれば20分~30分、レクチャーであれば10分~15分、あとは内容によるけれど、それを考えないと、長すぎてしまう場合が多分にある。
話す人が変わるならば変化があるけれど、同じ人の話を長時間聞き続けるのはよほど必要とされている内容でない限り、結果、何も伝わらなくなる恐れがある。
だから、話をするには「はじまり」があり「終わり」があるという前提であまり詰め込んだ内容は避けねばならないんだ。
範囲の広い内容だと、一つを正確に説明することができなくなり時間も長くなり、相手の心に届かない恐れがある。
それではせっかく一生懸命に話しても意味がなくなるのはとても残念だと思う。

4. 「はじめ」と「終わり」
coucouさんはね、どんな小さな会議でも「はじめ」と「おわり」にはけじめを必ずつけるようにしているんだ。
また、「はじめ」と「おわり」のない会は、会ではなく井戸端会議で済む話だものね。
井戸端会議であれば好きな時にはじまり、好きな時におわり、途中参加でも、途中退席でも自由。進行も決まりもない井戸端なのだから、それでかまわないよね。
coucouさんの場合、どんな大きな会議でも基本は約1時間(長くて90分)を目安にしている。それ以上は緊張感もなくなり、だらだらと進んでしまう恐れがあることと、せっかく貴重な時間に集まってくれた方々の貴重な時間でもあるからね。
そのわずか1時間に討議する内容や質疑などを中心に時間割を行う。
また、会である以上は雑談会ではない以上決定する事、相談する事が中心となるわけだし、時間は自分だけのものではないからね。
集まってくれた方々すべてにも時間がある。
また、世間話や雑談であればあえて会議にしなくとも良いもの。
でも、会議なのか、雑談会なのか本筋から話題が離れてしまう会議も多いような気がするね。
coucouさんは年間100本以上の会議をしている。人数は少数で4人から5人、大人数で10人から100人以上の会議だけど、どんな小さな会議であっても「はじめ」と「おわり」だけはしっかりとするようにしている。
雑談したい場合、個人的な話の場合はその会が終わってからすればいいことだから。
それがなければお互いの時間を、貴重な時間を大切にすることができないからさ。少数であってもわざわざ集まって頂いているわけなのだから、その方たちへの感謝の気持ちも込めて、互いの時間を大切にするための「はじめ(開会)」と「おわり(閉会)」なんだ。
ただの雑談の会になると、それに参加する人と参加できない人が生じ参加できない人はつまらなくなり、逆に、自分中心(自慢や意味不明、わかりにくい)の話となると、自分では夢中になり話続けますが、結果相手の顔がわからなくなるようだ。
このように単なる雑談と、どなたかが中心の座談会や卓話としての話なのかの区別がつかないと相手に不快感を与えてしまう怖れがあるんだよ。
自分にも時間があるかもしれないけど、参加している相手にも時間があることを忘れてはならないよね。
coucouさんね、は毎月第1月曜日にある事務局で毎月会議を5人で行っている。時間は30分。
はじめは、「おはようございます」「ご苦労様です」と開会の挨拶とともに始まり、終わりは「ご苦労様でした」「ありがとうございます」と閉会の挨拶となる。
貴重な30分間には大切な内容と、一人一人が意見や発言できる時間を設けてるようにしている。女子が中心なので、お茶やお菓子付きですが楽しい会議にしている。
これが時間に対するけじめであり、相手に対する配慮だということをあまり知る人がいないけれど、会という名が付く限り規模の大きさは関係なく「はじめ」と「おわり」は感謝の気持ちを表す大切なものだと思う。
いつのまにか会がはじまり、
いつのまにかけじめのないまま会が終わる。
これでは会とはいえませんね。


coucouさんです。みなさん、ごきげんよう~
本日も、オンライン講演会。
昨年から地方遠征はなくなり、ほとんどの講演がオンラインとなった。
まだまだ、続いている567~
でもね、味気ないよね~
だって、相手の顔がわからない。
寂しいね~
coucouさんはアナログ人間だから、どうしても対面に拘る。
だって、みんなの顔が見えるのだもの。
その顔は、つまらなそうな顔、眠そうな顔、瞑想している人?
メモを書き続ける人、スマホの画面を見ている人と、様々。
でもね、真剣にcoucouさんの言葉を聞いているまなざし、学ぼうという姿勢。少しでもこの講演内容を生活や仕事に役に立てようという意識が現場だとよくわかる。
また、あまりにも反応がない場合、内容をまったく切り替えることができるのがライブの良さであり面白さなんだ。
でも、こんな失敗もあるんだ。
都内にある服装学園、ファッション専門学校、デザイン専門学校などにも講師で出向いているのだけれど、学生さん相手は難しい。
つまり、つまらなければ誰も聞いてくれない。
あるデザイン専門学校の講義の時のこと、休憩をはさんで2時間の講義の1時間目は誰もcoucouさんの顔すら見ない、クラスメイトと話しまくる。
担任の先生が慌てて怒り出す…。
でも責任はcoucouさんにある、それだけ必要性と魅力がないってことだもの。落ち込んだcoucouさんは、2時間目は全く内容を変えてみた。
その内容とは、漫画やイラストの話に切り替えた。
すると、生徒さんの目が輝いた…。
これで1勝1敗となった。
次に、小学生を対象とした講師を頼まれた。
こどもたちは生まれて初めてのcoucouさん。
困った…。
誰も振り向いてもくれない。
そこで急遽、みんなで絵を描くことにした。
子どもたちは夢中で絵を描き始め、楽しそうだったので安心した。
これが対面、ライブの面白さ。
本日の講演は小さなパソコン画面、相手側は大きな画面らしいのだけれど、どんなに見つめられても感じない、無反応なオンライン。
だからね、もう講演はしない。
おしゃべりをしょうと思う。
大好きな人を思い浮かべて、その人に話しかけようと思う。
上手くいくかな~
みんな、読んでくれて、感謝致します。
また、あしたね~
※coucouさんの電子書籍のご案内「~人生を幸せに生きる方法~「YES」全3巻好評発売中!下記URLにて検索してください。
人生を楽しく明るく!幸せになるための物語。
https://www.amazon.co.jp/s?i=digital-text&rh=p_27%3ACou+cou&s=relevancerank&text=Cou+cou&ref=dp_byline_sr_ebooks_1
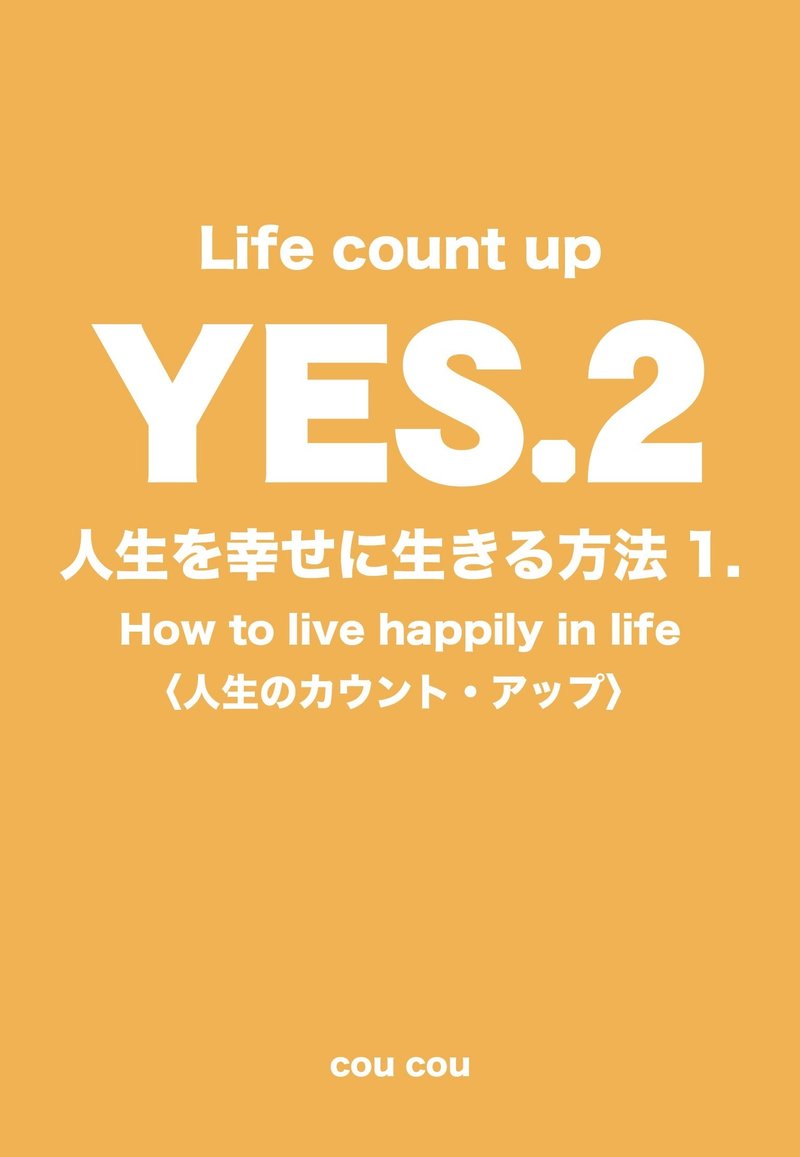
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
