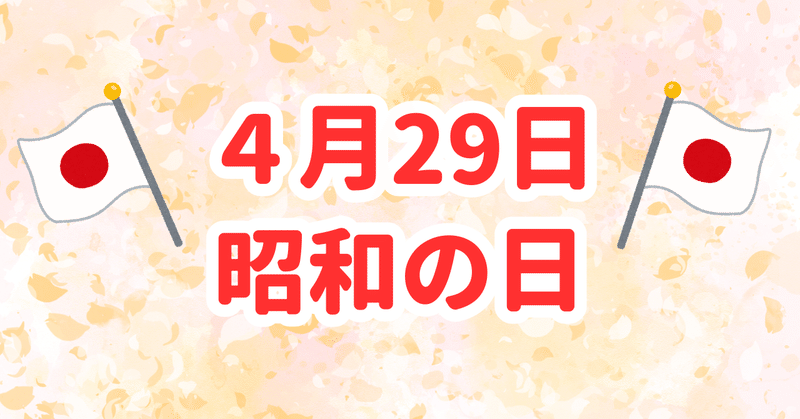#写真
夏越の祓 六月三十日半年ごとに穢れを祓い清める行事
六月三十日と十二月三十一日は、半年の間についた国家や万民の罪や穢れを祓うために「大祓」という神事が行われてきました。
六月は「夏越の祓」、十二月三十一日は「年越の祓」といいます。
奈良時代には、親王と大臣、従五位以上の役人が宮中の朱雀門に集ってこの儀式が行われたと伝わっています。
現在も宮中を初め各神社で行われていますが、一般的には神社からいただく紙片の形代に身の穢れを移し、これを大祓の当日
野遊び(磯遊び) 四月上旬〜下旬頃農業や漁業の繁忙期前の物忌みの日
現在は行楽の意味合いが強くなっていますが、昔から農業や漁業が忙しくなる前に、春の一日を物忌み(心身を清め不浄を避けること)の日にあてる習わしがありました。この日は、野遊び(磯遊び)で過ごすとともに食事の宴を開きます。
これは田の神様や海の神様を招いてお供えをし、自らも神様と同じものをいただくことで神様との結びつきが強くなり、加護が受けられると考えられてきたためで、この飲食のことを「直会」といいます
春のお彼岸(3月17日頃から23日頃まで)
彼岸は、
中日を挟んだ7日間のこと「春分の日」と「秋分の日」を中心とした、
それぞれ前後3日間の計7日間が「彼岸」です。
春の彼岸は新暦3月17日頃から23日頃まで、秋の彼岸は新暦9月20日頃から26日頃までです。
春分の日・秋分の日を「彼岸の中日(ちゅうにち)」といい、彼岸の初日を「彼岸入り」、最終日を「彼岸明け」といいます。彼岸の中日は、もともと国の大祭日の一つ春季皇霊祭(しゅんきこうれい