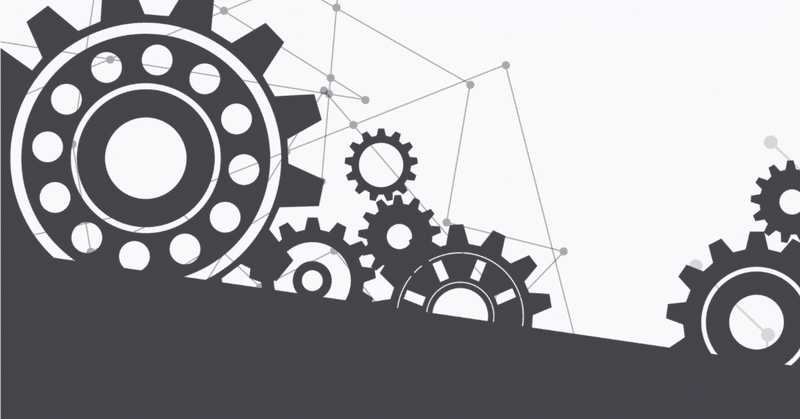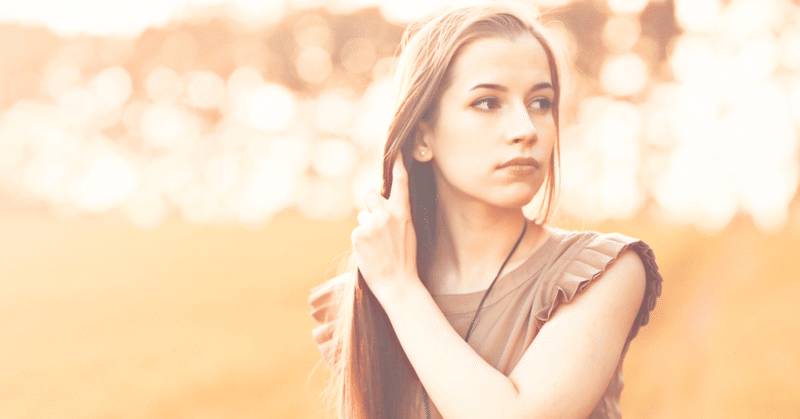#脳科学
HSPのライトサイドとダークサイド"傷つきやすいナルシスト"
HSPについて「おさらい」「敏感な人」「繊細さん」などの言葉で近年話題となったHSPという言葉ですが、今回はHSPのライトサイドとダークサイドをご紹介しようと思います。
HSPは1996年にアメリカの心理学者エレイン・N・アーロン氏が提唱した言葉です。
アーロン氏のホームページ文章を一部引用すると、下記のようなことが記載されています。
・HSPは、全人口の15~20%に見られる
・病気ではな
色々なキャラクターを分析すると面白い"パーソナリティパターン"
ここで扱う「パーソナリティパターン」という言葉は、一般的にはパーソナリティ障害と呼ばれているものです。
「障害」という言葉を使用しない理由は、その言葉を使うことによって、「障害=悪い」という思い込みを強めてしまわぬようにしたかったからです。
色々な特性を理解をすることによって、「差別・偏見の改善」「より良いコミュニケーション」「自己認識」「自己修正」などの役に立てばと考えています。
「パーソ
コンフォートゾーンとエフィカシーで限界突破する
認知科学において、居心地よく自然に振る舞える意識の中の範囲を「コンフォートゾーン」と言います。
さらに、そのコンフォートゾーンの水準を「エフィカシー」と言います。
エフィカシーとは、簡単に言うと「自己評価」で、詳しく言えば「自分のゴール達成能力に対する自己評価」です。
今のコンフォートゾーンのままだと…
例えばAさんが、「この分野はどんなに頑張っても上達するのに3年かかる」というエフィカシ
「脳と心」は同じもの それをあらわすものが「内部表現」です
「脳と心」?「脳」と「心」?ひと昔前までは、「脳」は物理世界のもので、「心」は心理世界のものという、別々のものとして考えられていました。
しかし、現在「脳と心」は、もともと同じものとして考えられています。
では、「脳」と「心」で何が違うのかと言うと、表現をする際の範囲・領域・分野の違いということが挙げられます。
それは、言葉や文章にする時、物理的な表現をする場合は「脳」で、心理的な表現の場合
心の知能指数とエモーショナルインテリジェンスを向上させる
エモーショナルインテリジェンス(EI)は、自分や他人の感情を認識し、理解し、管理し、人間関係を構築し、維持し、他者に影響を与える上でとても重要なものです。
前回はエモーショナルインテリジェンス(EI)の概要と4つの構成要素である、自己認識、自己規制、社会意識、ソーシャルスキルなどをお伝えしました。
↑コンテンツの最後に、自分で「自己認識をどれだけできているか?」これを認識する事は難しいとお伝え
"論理脳"をアプデする+「ひとりツッコミトレーニング」
論理脳のメリット
論理的思考は、物事や問題を正しく把握したり、その問題を解決する際に役立ちます。
それ以外にも、感情的な思考への対抗策、コミュニケーションの効率化、変化が多く予測不可能な現代を豊かに生き抜くための基本的な考え方として欠かせないスキルと言えるでしょう。
論理的思考のメリット
・分析能力向上
・問題解決能力向上
・説得力向上
・コミュニケーション能力向上
・積極性向上
・理解力、