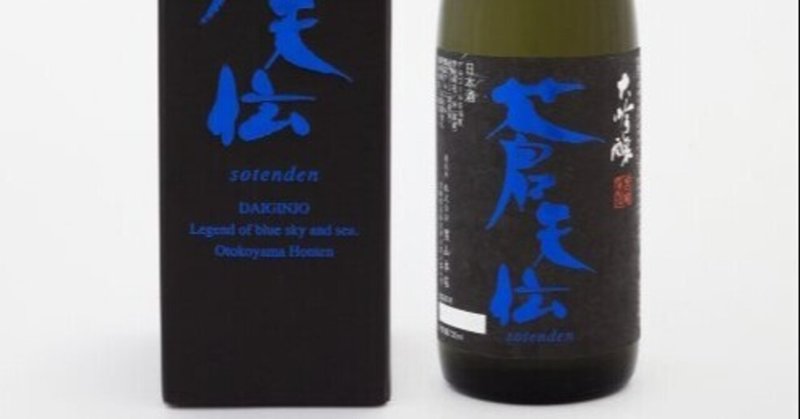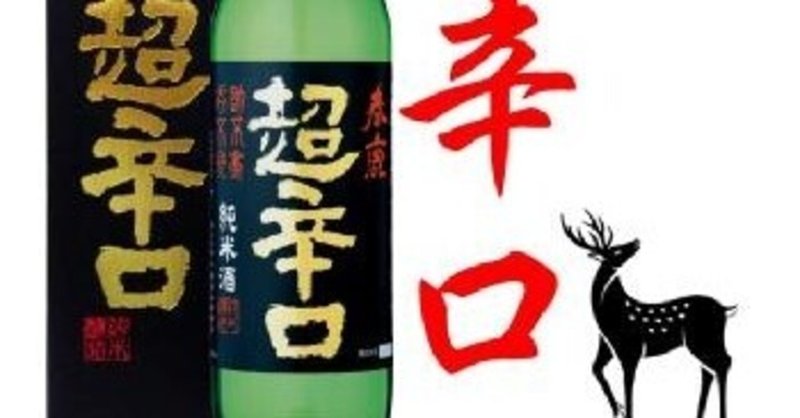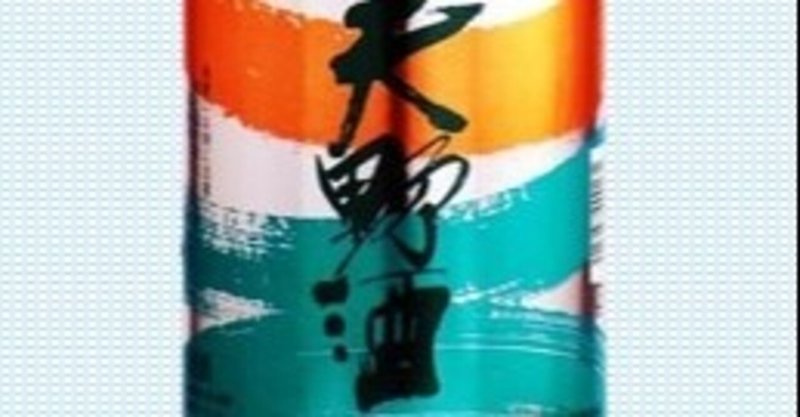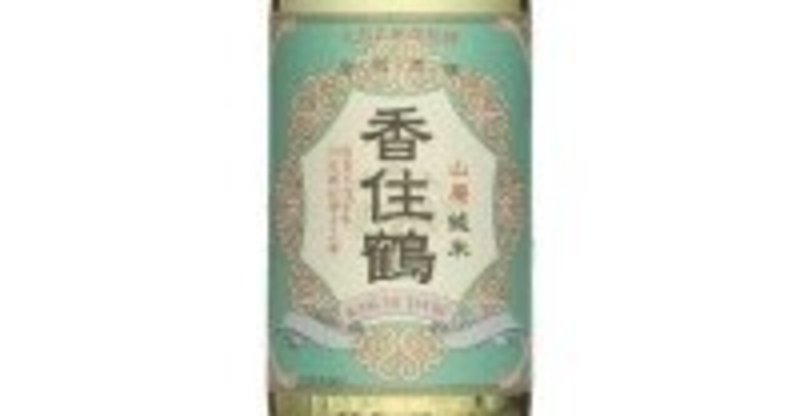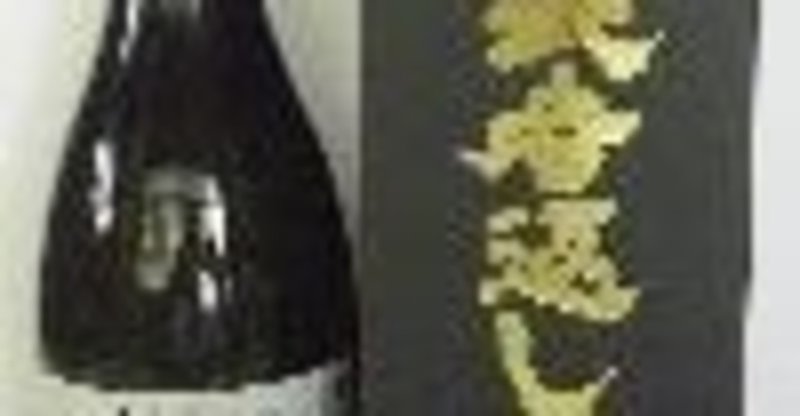- 運営しているクリエイター
#日本の食文化
生酛造りで造られた日本酒の味わいとは その4 山卸の作業はどのように進化したのか 本日の紹介酒 蒼天伝 大吟醸 (宮城県 気仙沼市)
足で酛摺りを行うようになった機会を作った出来事 本格的に足で酛摺りを行うようになったきっかけを考える場合、可能性が一番高いのが、伊達政宗公によって行われた慶長の遣欧使節です。
何故、慶長の遣欧使節が派遣されたのかこの使節に関しては伊達家がスペインと組んで天下を取りに行ったが故に行われたのではないかという説もありますが、(実際に家康公の体調が悪い時に本当に仙台藩と江戸幕府の間で戦争に成りかけたが、
生酛造りで造られた日本酒の味わいとは その2南都諸白の酒造り 本日の紹介酒は春鹿 超辛口 純米酒
江戸初期の南都諸白の酒造り江戸初期に置いて主流となっていたのは、菩提酛から酛立て法を用いて寒造りで造られた南都諸白へと進化した奈良正暦寺流の南都諸白をベースにした酒造りで、この酒造りの方法に関しては全国へと広がり各地で○○諸白と言われるようなお酒が各地で出ています。
江戸初期に行われた奈良から東北へ蔵人の招聘南都諸白の酒造りは当時として非常に画期的な酒造りの方法だったと思われますし、東北地方の一
生酛造りで造られた日本酒の味わいとは その3マニュファクチャーによる生酛造りが行われるまで 本日の紹介酒は天野酒クール(大阪府 河内長野市)
初期の生酛造りは試行錯誤の末従来よりも安定した乳酸発酵できる方法を色々試して模索したのが、寒造りの酛立て法を用いた南都諸白の酒造りで、伊丹に於いてさらに改良を加えられた山卸の手法を用いて、その後生酛の酒造りの技術として進化していきます。勿論そこに至るまでに色々試し試行錯誤しながらたどり着いたと考えられます。
菩提元から進化した水酛の技法また、その後も大正時代に至るまで酒造りの技術として用いられた
生酛造りで造られた日本酒の味わいとは その1生酛造りのお酒の味わいとは 本日の紹介酒 香住鶴 山廃純米 (兵庫県 香美町)
生酛造りのお酒の味わいとは生酛造りのお酒について、よく目にするのが生酛本来の味わいとか生酛らしい香りとか、伝統的な古式造りとか、よく目にします
実際にテイスティングしてみると、結構厚みが有って重たい味であったりしますが、本来の生酛の味わいってそもそも重たい味わいなのかを考えると疑問があります。
私の考える本来の生酛の味わいとはでは、私の考える本来の生酛の味わいとは、味に深みと柔らかさがあり、後
goo ランク王で焼酎30選の記事公開しました。
https://ranking.goo.ne.jp/select/200
gooランク王焼酎きき酒師お薦めの焼酎30選私、実は、焼酎の仕入れからこの業界入っていまして、若い頃は試飲会などで一日150~200種類くらいの焼酎のテイスティングを普通にやっていました。
今となっては考えられない事ですが、未だに毎年11/1の焼酎の日の日経新聞に載っている焼酎に関しては9割方テイスティングしたことが有りま
実はあまり知られていない三増酒が造られた経緯と特定名称酒制度ができるまでの流れ その1 本日の紹介酒は特選 剣菱
1、初めに
日本酒が低迷した原因を作ったのは三増酒と言う意見は多いですが、意外にどのような経緯で三増酒が造られ、どのように特定名称酒制度が登場したのか、意外に知られていない気がします。
実際に、三増酒登場までの流れを検証してみて感じるのは、従来言われている三増酒が日本酒低迷の原因を作ったとは必ずしも言い切れない部分があるように個人的には感じました。
現在、和食ブームとともに海外でも日本酒が認められ
生酛本来の味に対する疑問 その3江戸の食の発展の側面から 本日の紹介酒は天狗舞 山廃純米酒(石川県)
読者の皆様、ファーストフードと言えば、イメージするのはマクドナルドや吉野家の牛丼、くら寿司等を想像すると思いますけど、江戸時代にもファーストフードは有りましたし、現在のような定食が出来たのも江戸で江戸の街を作るための人夫さんの為に考えられた奈良茶飯が最初だったと言われています。
※下記映像に関しては、お江戸系Youtuber堀口茉純さんのページより引用いたしました。
江戸幕府が開府したのが16
生酛本来の味に対する疑問 その2経済成長の側面から 本日の紹介酒は 櫻正宗 焼稀 生酛純米 協会1号酵母
2019年現在の日本の人口は約1億2700万人、GDPは約550兆円となっていて、国民一人当たりのGDPが約433.7万円となっていて、普通に働いて生活していれば、少々貧しくても一定のお金さえ出せば、欲しいものは買えますし、余程のことが無ければ食に困ることも、ほぼ無いと言えると思います。
※下記画像は東京の高層ビル群 じゃらんネット(https://www.jalan.net/kankou/sp