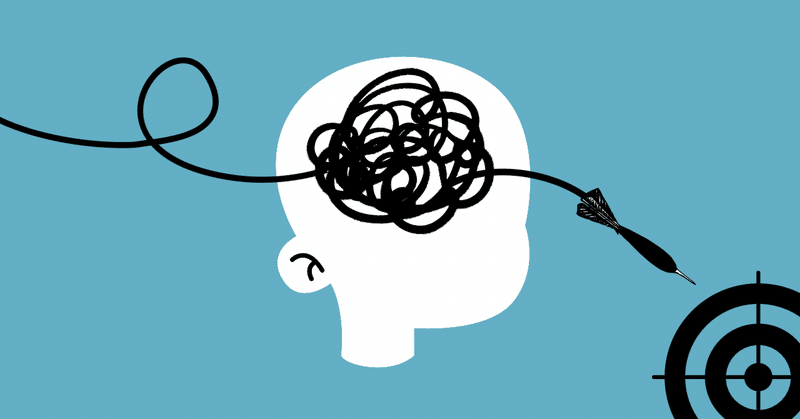
稼ぐ人のセルフブランディング”基本のキ”
今日からGWの人も多いようですね。
まとまった休みのときこそ、自分のことについてじっくりと考える時間を持つことも大事ですよ。
というわけで、起業家やフリーランスのためのセルフブランディングとして、入門的なお話を整理したいと思います。
※どちらかといえば、専門家的な仕事の方(コンサルや講師・コーチ・士業など)向けのお話ですが、事業を営む経営者でも共通する「絞り込み」についてのお話です。
1.絞り込むことの効用
大前提として、セルフブランディングとは「自分がデキる人」に見せるための演出やキラキラ日常をSNSで投稿してフォロワーを増やすことをココでは意味しません。
「自分の強みを明確にして、世間に認知してもらうこと」をセルフブランディングの定義としていますので予めご理解くださいね。
個人のブランディングだけでなく、ビジネスの特徴を磨くという事業展開の点でもお話は共通します。
自分のスキルが高い、商品力があるということは前提として、「あの人といえば?」「あの企業といえば?」で即答してもらえるレベルで認知されるには、「強みが発揮できる(発揮したい)領域を絞り込むこと」です。
今日の投稿の結論はこれだけです。(;^_^A
絞り込むことで、いくつかの利点が得られます。
1.何屋さんか理解されやすい
2.事業の説明がしやすい
3.専門スキルの習熟度が上がる
経験的には、とにかくこの3つです。
1と2は似ているのですが、1が他人視点で2が自分視点という違いがあります。
簡単に言えば、幕の内弁当よりウナギ弁当の方がインパクトがあります。お弁当の特徴が明確だからです。
何をやっているのですか?特徴は?と聞かれて、「いろいろやっています」「一言で説明しづらいなぁ」と答えていては、いつまでたっても理解も認知もされません。
ましてや口コミすらされないでしょう。口コミするときに、長時間の説明が必要なヒトやモノは面倒くさいからです。
2.実録・絞って稼げた過去
理論的には絞り込みの有用性は昔から言われていましたので、今さら感があることでしょう。
ただね、すべて実体験で痛感したことなので、改めて声を大にして伝えたいのです。
僕は、23年前に起業してから事業内容がいくつか変遷しました(さまよいました)。
当初はパソコン教室の経営やインストラクターの派遣業だったのですが、紆余曲折があって他社に譲渡した後になぜか「経営コンサルタント」に。
はい、経営コンサルタントといっても幅が広くて世間には伝わりませんよね。しかも当時コンサル経験もない26歳の若者。看板を掲げたところで誰もオファーなどしてくれないわけです。
今度は、社会人になってからわずかな経験があった営業を軸に「営業コンサルタント」に看板をつけかえ。
ところが、どのような分野に強いのですか?実績は?と聞かれて何も答えられない日々。
”営業”といっても、BtoCの集客を意味する場合もあれば、BtoBの提案営業を意味する場合もあります。しかも、新規開拓が得意なのかリピート対応が得意なのか、さらには対人営業?WEB営業?など領域の裾野が広いのです。
そのいずれにも実績と経験に乏しい僕は途方にくれました。
「いったい自分は何者でどこへ向かっていくのだろう?」と。
3~4年ほど試行錯誤した後、とりあえず当たり外れは無視してもっと具体的に絞り込むか、まだ他の人は開拓が手薄な領域を強引にでも絞りこもう!と考え抜きました。
その結果、「社内新規事業専門コンサルタント」を名乗るようにしたのですが・・・
とつぜんオファーが増え出したのです。
経営や営業領域は百戦錬磨で実績があるライバルが多すぎます。名も無き実績もない人間では太刀打ちできません。
ところが、新規事業というテーマは新しい発想や若い人間の感覚も求められるため、それほど過去の実績や経験が問われることが少なかったのです。
当時、世間ではフジテレビの買収などホリエモンが大暴れし始めた頃で、「若い人間に任せれば何か起爆剤になるかも」という風潮が世間では広がり始めた頃。タイミングもバッチリでした。
絞り込み方が見事にハマったのです。
なお、戦略をつくり事業計画を提案するレベルのコンサル業務は、経験値が少なかったため、「新規事業を立ち上げる人材を育成します!」と、「新規事業×人材育成」という掛け算でさらに絞り込みました。
もっというと、「大企業の・社内ベンチャー制度を活性化すべく・新規事業を志す・30代~40代の次世代リーダーを・社内起業家にまで育成する」という絞り込みようです。
これが、ハマりにハマって名だたる大企業から受注が続き、食えない時代を卒業できたという起業前半の時代がありました。
「新規事業コンサル”も”やりますよ」という会社は多かったのですが、「新規事業に特化した人材教育”のみ”やります!」という専門特化型は、当時はコンサル会社も研修会社でも少なかったのです。
※現在は、ニーズが減ったため撤退済み
3.どのように絞ればよいか?
大胆にシンプル化するなら「強み×成長市場×ニッチさ」の視点で絞ります。
もちろん、自分の強みは何か?成長市場はどういう領域で、どこにニッチがあるのか?の研究は必要ですよ。
ただ、僕なりに思考を整理するとこの3つに行き当たったというわけです。
強みは、自分の実績がない場合は、他人や他社から評価された(褒められた)ことをそのまま強みと解釈するとよいでしょう。
いくら自分の強みを言い張ったところで、世間からの目が自分のブランドを決めますので、違和感があっても一旦そこに乗ってみることが大事です。
成長市場は、ニュースなどで見聞きする情報から判断はできます。
雑な発想になりますが、企業向けの研修講師業であれば、領域は「AIをビジネス化できる人材教育」や「リモートワーク時代のコミュニケーション方法」などと、世相にひっかけていくイメージです。
最後に「ニッチさ」の発掘なのですが、これは提供する領域をさらに掛け算のイメージで探っていきます。
たとえば先ほどお話した僕の場合は、「新規事業経験(強み)×大企業による社内ベンチャー制ブーム(成長領域)×社内起業家の育成(ニッチさ)」という仮説を立てて検証してハマっていきました。
今なら、「思考の整理術(強み)×情報過多や頭を悩ます不安が多い世相(成長領域)×思考の整理専門のコンサル・講師(ニッチさ)」です。
ただし、「強み」を除く「成長領域×ニッチさ」部分は、机上で正解が出ることはありません。
あくまでも仮説を立てる時のキッカケにすぎないのです。
大切なことは、この仮説が正しいかどうかを競合視点と顧客視点で検証するからこそ、「よし、これでやっていこう!」と腹をくくれる決断ができますので、そこは誤解がないように。。
4.絞らなければいけないのか?
ここまでお話してきたことのちゃぶ台返しになりますが、最後に「絞らなければブランディングはできないのか?」という点を補足しておきたいと思います。
結論から言えば、絞らなくても大丈夫な場合もあるでしょう。事実、このような投稿も過去にしていますからね。
絞るだけが能じゃない!と。
なので、大事な点は「タイミング」にあります。
もし、あなたが起業初期、あるいはまだ自分の存在や商品が認知されていないということであれば、絞った方がメリットは大きいと思われます。
ただし、軌道に乗ってきた、あるいはそれなりに認知されているというのであれば、手を広げることも有益でしょう。
細かい点はケースバイケースでご判断いただくとして、いま自分はどのような状況で、どのタイミングかで絞り方を十分検討してください。
一つ言えることは、大谷翔平の”二刀流”という言葉に影響を受けすぎたら危険だよ!ということです(笑)
では、自分のそして自社の可能性を最大限引き出すために、絞り込みの仮説を手始めに3つほど考え、ノートに書き留める休日にしてみませんか?
おしまい。
さて、今回の内容は
いかがだったでしょうか?
少しでもお役に立てば幸いです。
それでは、また会いましょう!
著者・思考の整理家® 鈴木 進介
P.S.
毎週水・日曜日に「メルマガ」でも思考整理のエッセンスを配信中です!
以下よりご登録ください↓↓↓

「LINE」でもショートコラムを毎朝7時に配信しています!
以下よりご登録ください↓↓↓

最新刊はこちらより↓
フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/
