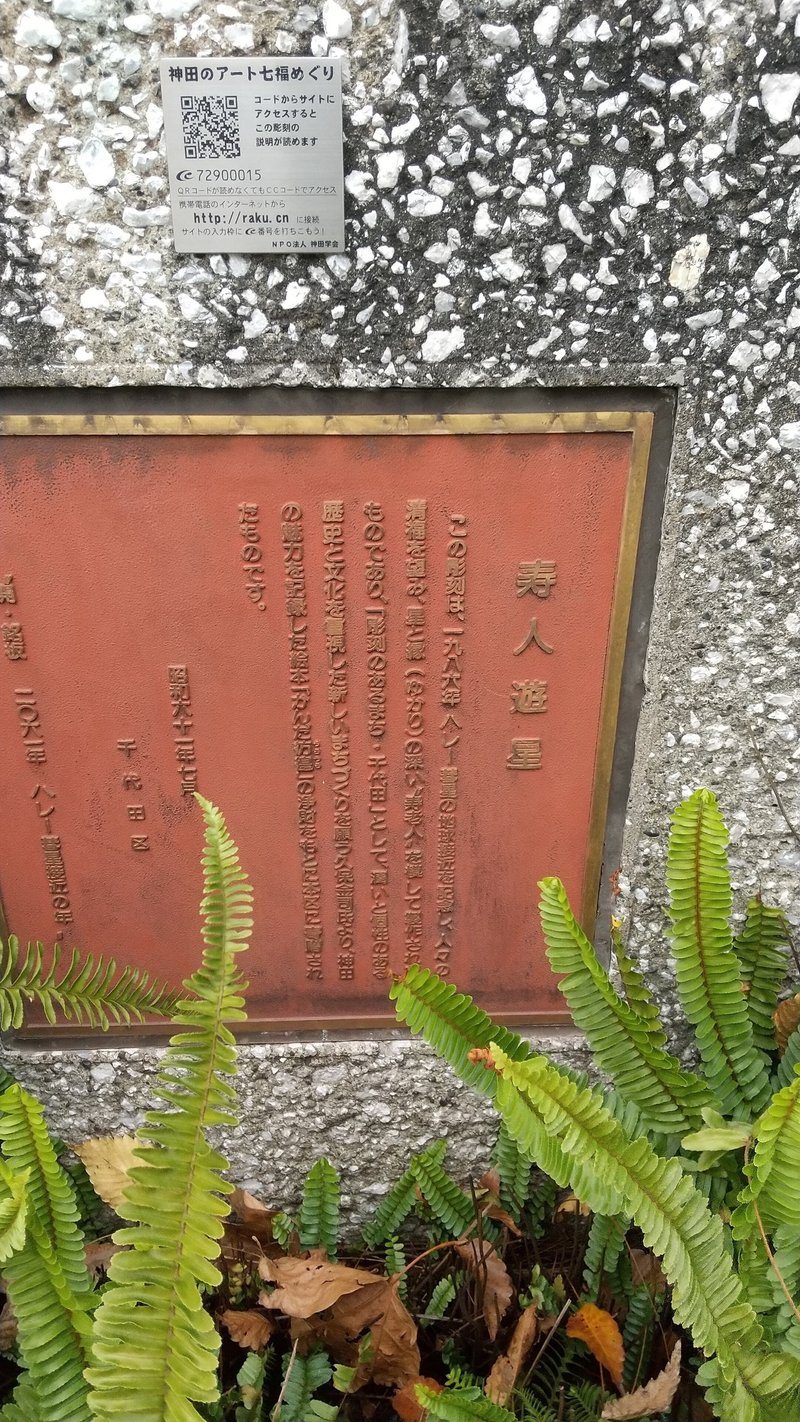#書評
【読書録】ミシェル・ド・セルトー『ルーダンの憑依』
僕が私淑している作家の佐々木中という人が、ツイッター上で勧めていたので読み始めた。あまりこの、セルトーという人の研究領域について詳しくは知らない。最初の方を読んだ感じは、フーコーに近い。遡るべくもない過去について、徹底して資料を頼りにして、目の前に見えるように再現して見せる。しかし、佐々木中は、まさにその、歴史上あったことの、再現のしにくさというものが一番わかると言って、本書を紹介していたのだっ
もっとみる【読書録】ルナン『キリスト伝』
長いこと図書館で借りていたけど、ようやく読み始めた。
キリスト教史の古典で、この人自身は十九世紀の人だけど、その時期に最大限深掘りをして、例えば福音書のうちヨハネの福音書は、前半は実は誰によって書かれていて後半は……などという話が始まる。
今やそのような見方が当たり前になったが、当時で考えて、キリスト教者にとったら、完全な冒涜の書になっていたのではないだろうか。
前に読んだ幸徳秋水の『基督
【読書録】井筒俊彦『イスラーム哲学の原像』
宣言通り、読書録を久しぶりに更新しようと思う。
だが、読書録って、こういう系の記事を書いたことのある人はわかるだろうが、その場で読んでその場で書くという感じより、だいたいひと月前までの以前の蓄積から、引っ張り出して再生するという感じの方が近い、その場でいっぺんに読むというのは、自分が相手にしているような本だと難しい。今急に書こうと思っても、その以前の蓄積というのがなければ、急には立ち上げられな
【読書録】豆腐色戦記(白)
封筒は茶色、豆腐色は白を塗布しろと。
ふうろいとに憑りつかれておる。もともとは、ドゥルーズの『千のプラトー』を読んでいて、狼男の章を読んだ時に、元ネタを読んでおくべきだと考えて開いたフロイト全集だったが、そこから逸れるようにして開いた西谷修の『不死のワンダーランド』にも、「〈不安〉から〈不気味なもの〉へ」と題して、またしてもフロイトを読めと促される。フロイトならもう読んだよ、と、「夢判断」を
【読書録】フロイトから逃れたつもりがフロイトに戻ってくる
気分転換というか、少し気ままに本が読みたくなって、あるいは、つい今しがた本の整理をしたからという物理的な動機もかかわってくるのかもしれない、とにかく西谷修の『不死のワンダーランド』を読み始めた。いや、前に半分以上読みかけていて、放っていた。こんな本はたくさんある。あまり途切れ途切れに本を読むのはよくないと決め込んでいたけれども、割合悪くもないかもしれない。本の種類による。ある種の散漫な意識に貫か
もっとみる