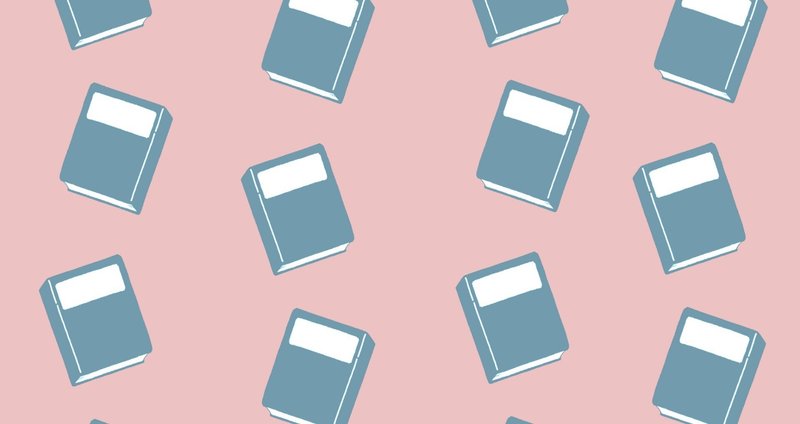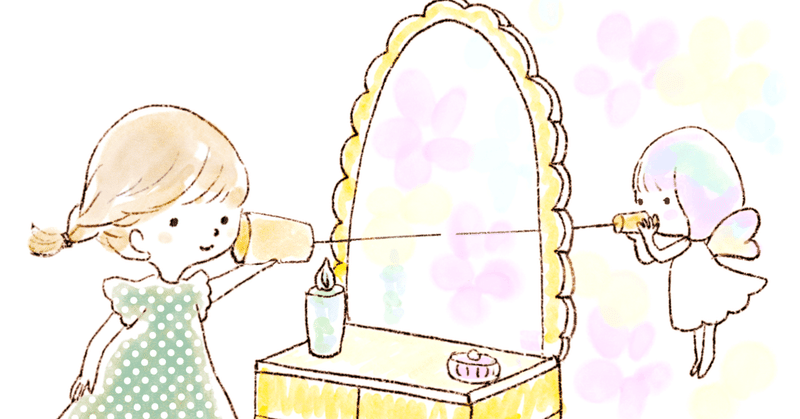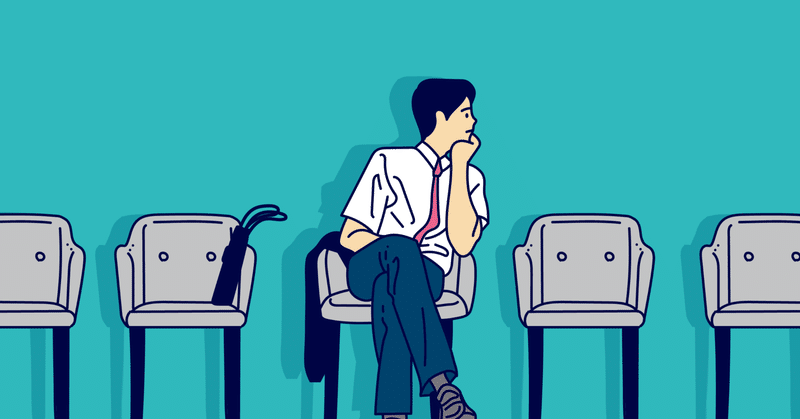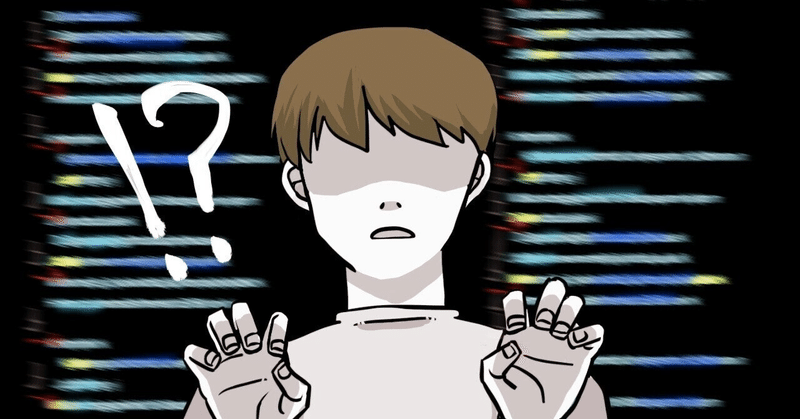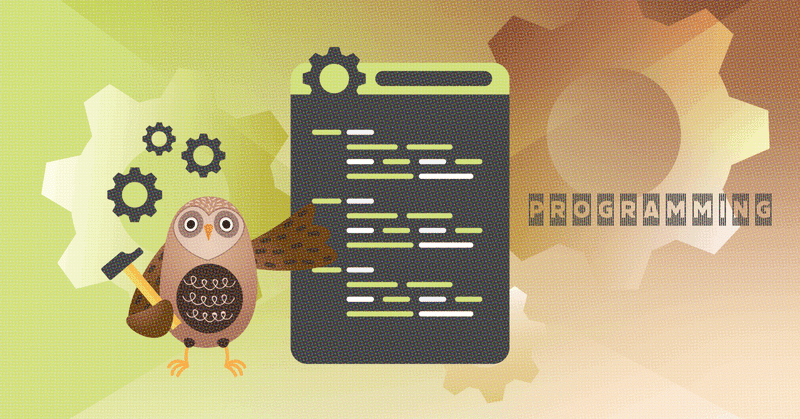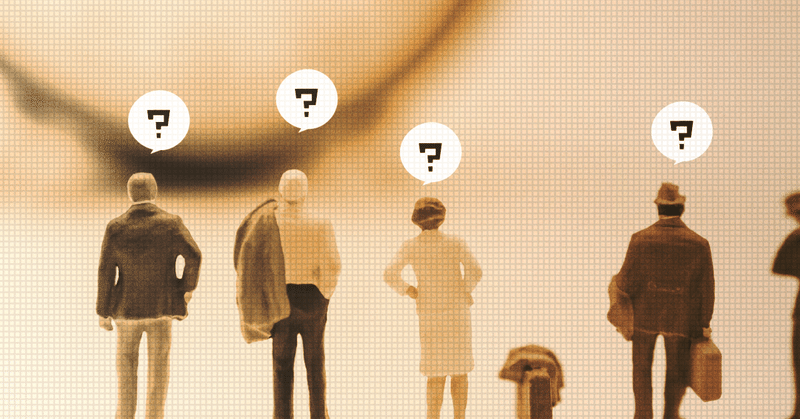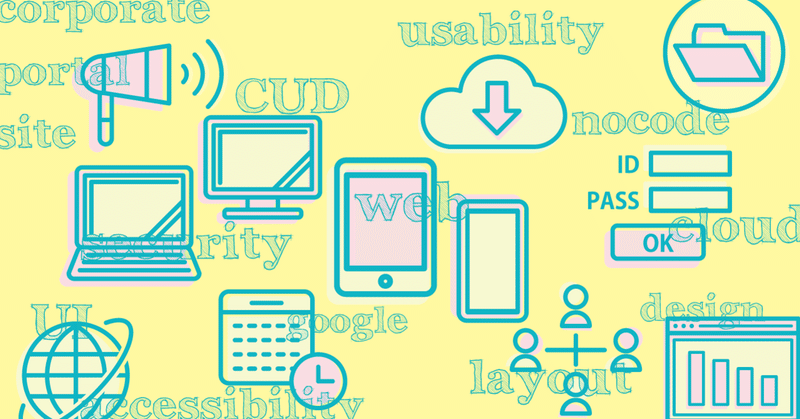#DX
トップに信頼される人になると仕事はもっと楽になるという話
日本の組織の基本はボトムアップだけど、トップダウンの考え方も必要不可欠 これ、最近思っていましてですねえ。やっぱり日本の組織ってボトムアップ型で、だいたいきちんと回っている組織は、実務でちゃんとした人たちがいると思うんですよ。
でも大きく舵を切るようなときには、トップがえいやって決めてくれないと困ることもあるわけで。
この使い分けが大事なのだと思っております。ええ。
しかし、トップで
心ならずも情シスへ配属された君へ その2
昨日の記事はこちら。
何でも知っていると思われがちです いわゆる「企画」と「保守」どちらに行くかで大分イメージは違うかなあなんて思ってます。
しかし、この「何でも知っている感」って何なんですかねえ。
あなたの業務のことだったらあなたの方が知ってるでしょみたいに思うこともなくはありませんが、情シスにいる以上しょうがないよねって思ったりしています。
ちなみにこの本を見ると、どんなことをし
情シスって異世界なんですかね?
なんか別世界扱いされることが多い気がするぞ これは、事業会社の情シスあるあるだと思うのですが、同じ世界(=会社)にいるのに情シスって異世界扱いされることが多い気がするぞ。
外部のサポートデスクみたいに扱われがち 以前は、サポートデスクが「なんでもやってもらって当然!」みたいに思われていたりしました。
そのために専任のサポートデスク要員を派遣で来ていただいたりしていたのですが、ここに書いた通
DXを成功させるためには「推進できる情シス」にならなければいけない
意見はないけどあなたの意見には合意できない はい、これ業務システムのヒアリングなんかだとよく言われるやつですね。よく聞くと「今の仕事をそのまましたいだけ」だったりします。
じゃあ、どうしたいの? こんなとき、相手の「これが問題だ」という議論に向き合っても大体の場合無駄な時間を過ごすことになります。
ハナっから意見をあわせるつもり、ないんですもん。
なのでこういったときには「じゃあどうした
DXが進まない理由の一つは「深刻な人材不足」
やることはわかっている、人がいないだけ 個人的な感覚としてはこれなんですよね。こんな記事をみるとわかりみしかありません。
弊社でいうとこの3点。
たとえば、ELTツールを導入して、本来プログラムでやるデータ処理なんかはもう自動化したりする基盤は導入済になっています。
でもそれと「個別の案件で活用できるか」というのは別の問題。
具体で依頼が来たときに「これを使ってこうできる」というのがで
情シスって何しているの?と言われたから業務内容を書いてみたい
おいふざけんな案件ですよ ここでも書きましたが、昇格試験の相談をするときに同期に言われたわけです。確かに伝わりづらい件ではある。
まあ、職種によっても違いますけどね。。。いろんな仕事がある。
機器の保守とかって何やってるの?サーバ直したりするの? ハードウェアの面倒は見ませんが、ステータスを監視して、何かあれば初期切り分けをしてベンダに通報したり、ログ管理とか対応したり、新規物件の要件定義と
これからの業務システムと情シスのありかたを考えてみる
徒然と書いてみる。
業務システムの要件を把握するためには、業務そのものを知ることが大事 私はお客様向けのサービスと、いわゆるバックヤードのシステム双方を経験していますが、業務システムがいわゆるお客様向けサービスと違うところは「業務」そのものと大きく直結していることだと思います。
スタッフ部門のユーザは、業務の話はできても、それにともなってどういった機能が必要かはうまく表現できないケースが多い
40代情シス女子、この1年間を振り返ってみる
With コロナが見えてきた 去年、コロナで振り回され感と若干の停滞を感じていた部分があったので、3月くらいから少しずつ再始動をはかっていました。
コロナ後の世界が見えてきて「ああ、元の世界に戻ることがないんだなあ」って思ってから、停滞してきたものを動かし始めた感じ。
一つ明確に加速したのがペーパーレスですね。書類を捨てまくったのは大変だったけど、気持ちが大分すっきりしたよ。
ちなみに今