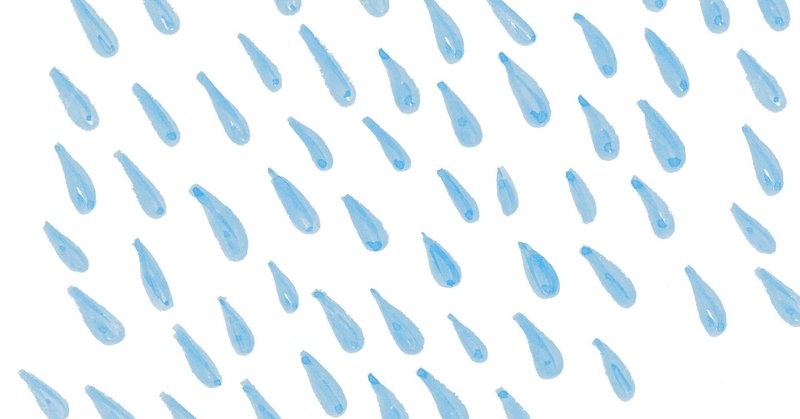- 運営しているクリエイター
2020年4月の記事一覧
気づいたらそうなっていた。
昨日の『声で逢いましょう』の最中に、また「草」の話になった。
どんな野草がおいしいとか、どれは食べられるとか。
そんな中、ある参加者さんが
「こういう状況になって食べることを見直した。」
と言っていた。それまでは仕事などにかまけて、今みたいにゆっくり立ち止まって料理をしたり食事をすることはなかったと。「食べることってすごく大事だと気づいた」とも言っていた。
わが家もおなじだった。奥さんの勤
キャッチする時にあわてないこと。
今日、奥さんと近所の公園に行ってフリスビーをした。
フリスビーを投げるというのは、なかなか難しいもんで、僕の投げるフリスビーも奥さんの投げるフリスビーもあちこちに飛んでいった。何投かに一回、とてもうまくいくことがあって、その時にはフリスビーはびゅっと真っ直ぐ飛ぶのだけれど、なんでそう投げられたのか分からない。
飛んできたフリスビーをキャッチできると、うれしい。まるで出来のいいワンちゃんになったよ
ほんのちょっと声を出す。
平日毎朝6時半から「英語発音チューニング体操」という動画をアップしている中島小百合さんが、夜の6時半からこんな動画を上げはじめた。
以下、中島さんによる解説。
Anne Peckham の執筆したヴォーカル学部の必修科目 "Elements of Vocal Technique"の教科書「ザ・コンテンポラリー・シンガー」の日本語版(ATN刊、中島小百合翻訳)から毎回3分、よきエクササイズを見繕
クリエイティブの雨。
まだ昨日のミスチルのライブの余韻が残っている。
前・後編に分かれていたから、一本のライブの半分のはずなのに、二本ぶんライブを観たような感じがした。そのくらい濃厚で、強烈だった。
25周年。その25年かけて紡ぎ出された曲の数々が惜しげも無く披露される。どれもが時代に響いたヒットソングばかりで、その質と量に驚く。
ほんとうに驚く。これほどの数の名曲を、どうして一人の人がモノにできたのか。自分も素