
ロバート・アルトマン監督 『M★A★S★H マッシュ』 : 笑うな!
映画評:ロバート・アルトマン監督『M★A★S★H マッシュ』(1970年)
「反戦映画」の名作である。
ただし、「反戦映画」と聞いてイメージするような作品ではない。そしてそここそが、本作と、凡百の反戦映画とを隔てる大きな違いである。
要は、ご立派な主張を掲げた作品などではなく、本作は、本気で怒っている作品であり、本気だからこそ「笑い飛ばすしかない」という悲しみを抱えた作品なのだ。

本作についての「Wikipedia」には、次のようにある。
『『M★A★S★H マッシュ』は、1970年のアメリカ映画。朝鮮戦争を舞台に、3人の軍医を描くブラックコメディ映画。
リチャード・フッカー原作の小説をロバート・アルトマンが映画化し、カンヌ国際映画祭パルム・ドールやアカデミー脚色賞を受賞した。
タイトルの「MASH」とは、陸軍移動外科病院 (Mobile Army Surgical Hospital) のことを指す。』
この映画を評する場合に、しばしば「ブラックコメディ」という言葉が使われる。
たしかにそれでも間違いではないのだが、非常に誤解を招きやすい言葉として、私はこの言葉を使いたくはない。どういうことかというと、「ブラックコメディ」とは「黒い喜劇=悪意ある喜劇」ということであり、そのイメージは「嘲笑的」あるいは「冷笑的」という感じが強いからだ。
批判対象を見下す立場で、余裕を持って、対象の「喜劇性」を暴き出すような作品。それが「ブラックコメディ」というものの中心的なイメージだと思うのだが、本作は決して、そんな作品ではない。
本作は「戦争という逃れ難い運命=召集」の中にありながらも、なんとか正気を保とうと、戦争が押しつけてくる「規律」に反抗し、これを笑い飛ばし続けた「外科医師」たちの奮闘の物語なのだ。
たしかに彼らのやることは、馬鹿馬鹿しいイタズラに類したことばかりではある。だが、そんな彼らの前には、毎日毎日、途切れることなく、大きな傷を負った兵隊たちが運び込まれてくる。彼らはそんな負傷兵たちを必死になって助けようとするが、しかし、このベルトコンベアでの流れ作業のごとき治療行為に、彼らが虚しさや怒りを感じるのは当然だろう。「自分たちは、なんのために彼らを助けているのか? 戦争をスムーズに遂行するために、負傷兵の救護をしているだけではないのか?」。

だから、彼らが、毎日毎日途切れることなく続く流れ作業のことき外科手術の中で、つまらないジョークを口にしたりするのは、そうでもしないとやっていられない、からなのだ。彼らは口で何を話しておろうと、最善の手術を負傷兵たちに施している。なぜなら、彼らの負傷は、前線では手の施しようもない命に関わる大きなものばかりであり、気楽にこなせるようなものではなかったからだ。
まただからこそ、それに向き合い続ける彼ら自身も、精神的には疲弊しきっていたのである。
次に、「Wikipedia」から「あらすじ」を紹介するが、たぶんこれを読んでも、この映画がどんな映画なのかは、わからないだろう。映画を観た私の印象としても、この「あらすじ」から窺えるイメージは、映画の本質をとらえ損ねているとしか思えないものだからだ。
『朝鮮戦争下の米陸軍移動外科病院にホークアイ、デュークの2人の軍医大尉が配属されるが、到着早々に女性将校に色目を使い責任者のブレイク中佐に睨まれてしまう。2人はバーンズ少佐と同室になるが、厳格なカトリック教徒のバーンズの小言に辟易して、別の部屋に変えて欲しいとブレイクに直訴する。その後、バーンズは別室に移動になり、代わりに軍医大尉のトラッパーが同室となる。3人とも腕前はピカイチの名医だが、他の仲間とつるんで日々軍紀を無視してやりたい放題の騒ぎを起こしていた。
そんなある日、新任の看護師長・フーリハン少佐はやりたい放題の3人を目の敵にするバーンズと共に、上官であるハモンド准将に病院の軍紀の乱れを訴えようと告発状を用意する。2人は告発状を用意した後に一夜を共にするが、ホークアイたちが2人の部屋にマイクを仕掛け、ベッドシーンを軍放送で流してしまう。それ以来、フーリハンはベッドシーンでの発言から「ホットリップス(熱い唇)」というあだ名を付けられてしまい、ホークアイからベッドシーンのことをからかわれたバーンズは、彼を殴り倒して本国に強制帰国させられる。
ホークアイは多忙な日々を過ごす病院で、従軍神父のデイゴから歯科医のワルドウスキー大尉が深刻な悩みを抱えているという相談を受ける。ホークアイはワルドウスキーに話を聞きに行き、彼が「男性的不能」に陥っており、「自分はゲイなのではないか」と悩んでいることを知る。ホークアイは仲間にそのことを話し平静を装うとするが、ワルドウスキーは悩んだ挙句に自殺を決意する。ホークアイとトラッパーはワルドウスキーを助けるため、彼の「お別れパーティー」を開き、青酸カリと偽って睡眠薬を飲ませる。そのまま眠ったワルドウスキーのために、ホークアイは不倫を持ち掛けていた女性将校マリアに「彼の命を救って欲しい」と依頼し、彼女はワルドウスキーと一夜を共にして「男性的不能」問題を解決する。
マリアが帰国した後、ホークアイたちは「フーリハンの髪の色は本当に金髪なのか染めているだけなのか」という話で盛り上がり、彼女がシャワーを浴びているテントを壊して彼女の全裸を衆目に晒す。我慢の限界を超えたフーリハンは、彼らの行動を放置するブレイクに怒りをぶつけハモンドにも直訴する。
ホークアイとトラッパーは負傷した連邦下院議員の息子の治療をするために日本の小倉市に派遣される。2人は早く仕事を終わらせてゴルフと芸者遊びをしようと、責任者である大佐の許可を得ずに勝手に手術を始めてしまう。手術を終えた2人は早速ゴルフに行こうとするが、激怒した大佐に軍法会議にかけられそうになる。大佐は2人から「文句があるなら議員に言いつけるぞ」と脅され退散する。ゴルフを終えた2人は芸者遊びを楽しむが、そこで「アメリカ兵と芸者の間に出来た気管食道瘻の赤子の治療を手伝って欲しい」と依頼され、軍病院で治療しようとするが、再び大佐に反対されてしまう。2人は大佐を睡眠薬で眠らせ、その隙に「大佐と芸者との不倫現場」を撮影し、赤子の治療を認めさせる。
ホークアイとトラッパーは仕事を終えて朝鮮に戻ったが、そこではフーリハンの直訴を受けたハモンドが病院を訪れていた。2人はブレイクと共に話をごまかすが、話の流れでアメリカンフットボール好きのハモンドの部隊と5,000ドルを賭けて試合をすることになってしまう。ホークアイは元プロ選手のジョーンズ大尉を補充として呼び寄せ、ハモンドのチームと試合をすることになる。ブレイクのチームは相手を油断させて掛け金を吊り上げた後に逆転勝利する計画を立てるが、ハモンドのチームにも元プロ選手がおり、序盤から劣勢に立たされてしまう。ホークアイは試合中に元プロ選手に薬物を注射して強制退場させ、後半戦でジョーンズを投入して追い上げ逆転勝利する。
数日後、ホークアイとデュークに帰国命令が届き、2人はトラッパーと別れを交わして病院を去っていく。2人が乗ったジープが走り去るシーンを背景に、軍放送から本作の内容とキャストの情報が流れ、物語が終わる。』
本作は、ホークアイとトラッパーという二人の「変人」軍医を中心にして展開する「群像劇」である。だから、一貫したストーリー展開があるのではなく、エピソードの積み重ねによって「大状況の不条理さ」を描いた作品だと言えるだろう。

「MASH」とは、陸軍移動外科病院 (Mobile Army Surgical Hospital) であり、要は、最前線の戦場から少し距離をおいた後方に設置される、テント建ての臨時病院であり、言うなれば「外科医療部隊」である。
そのテントには、大きく「赤十字」のマークが書かれているが、これは、この部隊が「戦闘部隊」ではなく、戦時国際法によって攻撃を禁止された対象であることを示している。ここを攻撃すれば、明白な「戦争犯罪」なのだから、敵国も野戦病院を攻撃することはない。
したがって、「MASH」は、戦場近辺の後方(約5キロ)にあって、例外的に安全な場所ではある。ただ、そこには緊急の外科手術を必要とする負傷兵が、次から次へと最前線から運び込まれてくる。それ以外は「戦場ではない」とも言えるのだか、だからこそ「たまらない」とも言えるのだ。「なんなのだ、この無意味は現実は」と。

「軍医」というのは、軍隊の中でも「偉い」部類に入る存在だ。何しろ「尊敬すべき兵隊さん」の命を救う存在なのだし、「使い捨てにできる兵隊」とは違って、簡単に補充できるような存在ではない。だから、普通にしておれば、部隊の中で威張っておれるし、大切にもされる存在なのだが、それがホークアイたちには我慢ならないことだった。
彼は、最初から「大尉」だったが、だからといって、急に、他の兵隊たちに対して威張るなんてことはできなかったし、ことさらに上官にひれ伏すなんてことはできなかった。
彼らは一介の医師が戦場へと駆り立てられ、軍隊の駒にされたわけだが、彼ら個人からすれば、「軍隊」という組織の「規律=軍律」や「階級」などというものは、所詮「いかに効率よく敵国人を殺すか」という大目的のためのものでしかないから、自由人として、また医師の良心としても、できればそんなものには服従したくはない。
しかし、毎日毎日途切れることなく前線から運び込んでこられる負傷兵たちの存在を目の前にしては、そこから逃げ出すこともできず、そうしたジレンマの中で、彼らは「笑うしかない」「ふざけるしかない」状況におかれていたのである。
「あらすじ」の中でも紹介されているとおり、物語の前半で、看護師長・フーリハン少佐が赴任してくる。名前だけではわからないが、フーリハンは金髪美女なのだ。しかも階級はホークアイたちより上。

彼女は、やりたい放題のホークアイたちを、なんとか「軍の規律」に従属させようとするが、ホークアイはそんな彼女さえ「普通の女」のように口説こうとする。それに対してフーリハンが「大義名分」で反論すると、ホークアイは腹を立てて、おおよそ次のように返すのである。
「俺は、いい女だったら、それが何様であろうと口説くことにしている。だけど、あんたみたいな軍隊バカは、こちらから願い下げだ!」
また、このように罵られたフーリハンは、食堂テントの席を立って、次のように捨て台詞する。
「あなたみたいな人が、どうして軍にいるのか理解できない!」

すると、別の兵隊が、ボソリというのである。一一「召集されたからさ」。

この後、フーリハンは、頭が硬い者どおし、ホークアイたちを敵視している者どおしである、ホークアイたちの同僚医師でカトリック教徒のバーンズと意気投合し、その勢いでちちくり合うことになるのだが、その様子を部隊中に(音声)放送されて赤っ恥をかくことになる。
また、フーリハンが、シャワーテントに入ってシャワーを浴びていた時、ホークアイたちはテントがいきなり捲れ上がるというイタズラを仕掛け、重ねて赤っ恥をかかされたフーリハンは、ついに恥も外聞もなくなって、泣き喚きながら部隊長のブレイクに、ホークアイらを厳しく処分してくれと直訴するのだが、ブレイクは、安全な野戦病院の長であることに満足している、これもまったく軍人っけのない人だったので、フーリハンの訴えなど、右から左に聞き流すという態度。ブレイクとしても、腕の良い外科医であるホークアイたちは、是非とも必要な人材であり、役に立つ部下であったが、ホークアイより階級が上だといっても、フーリハンの替えならいくらでもいるのだから、「何を言ってるんだ、この女は」くらいの感覚だったのであろう。



ブレイクの態度を見てフーリハンは、ここでは、自分の方が「異端」なのだと気付かされ、上部組織に告発状を送ることを決意する。
この他にも、ホークアイたちは『負傷した連邦下院議員の息子の治療をするために日本の小倉市に派遣され』たり、部隊長を飛び越えて提出されたフーリハンの告発状を受けて、「MASH」を訪れていたハモンド准将も、もとより告訴状の内容などどうでも良いものと思っていたから、「MASH」のブレイクとの雑談の中で、部隊対抗のアメフトの賭け試合をしようなどという話になってしまう。彼らにとっても、戦争とは、その程度のものであり、軍隊の規律というのも、じつのところ、その程度の「タテマエ」でしかなかった。「気を抜けるときは抜いたらいい」一一それが、現場の軍人の本音だったのだ。
○ ○ ○
この映画は、「朝鮮戦争」を舞台としている作品なのだが、しかし、物語のほとんどは部隊内でのものだから、戦闘シーンは無いし、朝鮮人もほとんど登場しない。そのため「朝鮮戦争」という大文字のイメージは、ほとんど感じられないものとなっている。
しかしこれは、アルトマン監督が意図してそうしたのであり、要は、観客に同時代の「ベトナム戦争」を重ねて観てもらおうとしたのである。
ここで、歴史のおさらいをしておくと、「朝鮮戦争」つまり、朝鮮が北と南に分かれて、ソ連とアメリカの代理戦争を戦ったのは、第二次世界大戦終結(1945年)の5年後、1950年から1953年までの3年間ということになる(停戦はしたが、いまだ終戦には至っていない)。
この間、日本は、この近隣国の戦争のおかげである特需景気によって、大いに潤った(朝鮮特需)。また、これ(や、その後の「ベトナム戦争特需」)があったからこそ、日本は「奇跡的な経済復興」を果たせたのだということを、日本人は、決して忘れるべきではない。日本は、戦争中に朝鮮を植民地化しただけではなく、「平和主義」を掲げた戦後においても、近隣国民の生き血を吸うようなことをして、豊かになったのである。
また、だからこそ、ベトナム反戦運動は、日本でも広がりを見せたのだ。

閑話休題。では、アルトマン監督が、この映画の舞台である「朝鮮戦争」に重ねて描いた「ベトナム戦争」とは、いつ頃のものかというと「1954年から1975年までの20年間」ということになる。
つまり、「朝鮮戦争」が終結した翌年には「ベトナム戦争」が始まっているのだ。
これはいうまでもなく、第二次世界大戦の戦勝国である、アメリカとソ連という二大大国による「戦後世界の覇権争い」の一部であった。アメリカを筆頭とする西側「資本主義」諸国と、ソ連を筆頭とする東側の「社会主義」諸国との「陣取り合戦」が、戦後5年しか経たない時期に「朝鮮戦争」となって顕現し、それ以降、核兵器の保有国であるアメリカとソ連による直接対決の回避から、代理戦争を中心とした「東西冷戦」が、延々と続くことになるのだ。
で、本作『M★A★S★H マッシュ』が作られた1970年といえば、「ベトナム戦争の泥沼」がすでに15年も続いて、まだまだ先の見えない時期であり、アメリカ国内にも「嫌戦・反戦」ムードが高まっていた時期だった。
一一しかし、だからといって、そうした需要によって、本作のような「反戦映画」が作られたというわけではない。逆である。
この当時、『M★A★S★H マッシュ』を製作した「20世紀フォックス」社は、3本の「戦争映画」を同時に製作していた。
他の2本とは、「日本との合同スタッフ・キャストで制作された」大作映画『トラ・トラ・トラ!』(監督・リチャード・フライシャー、舛田利雄、深作欣二)であり、もう一本は、第二次世界大戦のヨーロッパ戦線において、有名な「ノルマンディー上陸作戦」や、無敵のドイツ戦車軍団を撃破した「バルジの戦い」などの功績によって、アメリカ軍のヒーローとなった、パットン将軍の活躍を描いた、これも大作映画『パットン大戦車軍団』(フランクリン・J・シャフナー監督)であった。
つまり、この大作2本に共通して言えるのは、アメリカ軍の勝利を華々しく描く「戦意高揚」のための娯楽映画であったということであり、当時の「20世紀フォックス」社の上層部の考えも、そうした方向のものであったということである。


ところが、3本目の『M★A★S★H マッシュ』だけは、低予算映画であった。
もちろん、「20世紀フォックス」社としては、戦争映画を作るからには、『トラ・トラ・トラ!』や『パットン大戦車軍団』のような、戦意高揚につながる娯楽映画を作るつもりだった。
ところが、根っからの反骨心の持ち主であり「リアリスト」であったアルトマン監督は、そんな「綺麗事の絵空事」映画を作るつもりはなかった。つまり、自分の好きなようにするつもりだったのだが、しかし、それをそのまま表に出せば、作らせてもらえないのはわかりきっていた。だから彼は、わざわざ低予算映画として企画を通すことで、他に大作を2作も抱えていた会社の目をそらし、「20世紀フォックス」社の撮影所を使わずに、外での撮影を行ったのである。

そして、出来上がった作品は、当然のことながら会社上層部によって「最低の作品」だと評価された。
上層部が否定的に評価した、本作の次のような特徴も、しかしそれはアルトマン監督が意図した演出であった。
(1)色づかいがくすんでいる
(2)リアルな外科手術のシーンが無意味に多くて、観客に不親切だ
(3)ふざけていて、話もわかりにくい
(1)については、当然「戦争のリアル」を描こうとすれば、ぱりっと糊のきいた制服を着た軍人が活躍するようなものなど、アルトマンは撮る気がなかったということであり、(2)についても「戦争のリアル」とは、まさにこの「延々とつづく、悲惨な外科手術」のシーンにこそあると考えていたから、アルトマンはむしろ、外科手術のシーンを専門家を招いて、可能なかぎりリアルに描いていたのだ。また、(3)については、「戦争のリアル」は、物語のような「起承転結」の定式で描けるものではない、という信念に出たものであったのだろう。
アルトマンのこうした意図は、会社上層部にはまったく理解されることなく、「低予算だったのが、せめてもの救い」だとされたのである。
したがって、本作『M★A★S★H マッシュ』は、興行的にも会社からはまったく期待されなかったのだか、だからといって、公開もしないで捨てるわけにもいかなかった。
だが、「変な戦争映画」が作られたという口コミが広がり、『M★A★S★H マッシュ』は、同時代の「嫌戦気分」と結びついて大ヒット。ついには、カンヌ国際映画祭パルム・ドールやアカデミー脚色賞を受賞し、反骨の人・アルトマンの出世作となったのである。
○ ○ ○
しかし、後年、アルトマンは語っている。
『時代と合って成功する時もあれば、ひどく失敗する時もある』
『私はまっすぐ歩んでいるだけ。他の人はよくブレるけどね』
まったくそのとおりであろう。
アルトマンの作風は、明らかに「反時代的」であり、時代に迎合せず、広く喜ばれるようなものを撮ろうとはせず、ただ、自分の目に映った「リアル」を、そのまま描いた。
言い換えれば、彼には「普通の娯楽映画」は撮れず、また撮りたくもなかったから、『M★A★S★H マッシュ』のように、たまたま時代が「反体制」に傾いた時には歓迎されたけれども、「平和で、満たされた時代」の観客には、彼の「妙なこだわり」が理解されず、低い評価しか与えられなかったのである。
だが、それは、彼のいうとおりで、
『私はまっすぐ歩んでいるだけ。他の人はよくブレるけどね』
ということだったのだろう。
一一私にとってのアルトマンは、作品そのものよりも、むしろその生き方において、憧れを抱かせる真のヒーローの一人であると、そう言える存在となったのである。
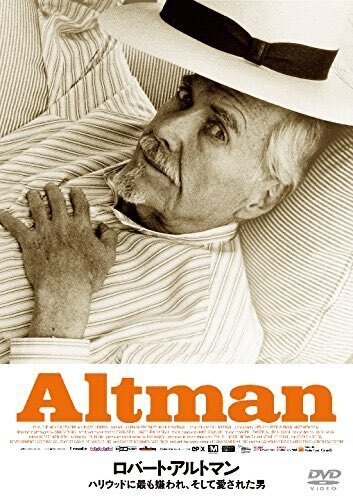
(2023年9月9日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
