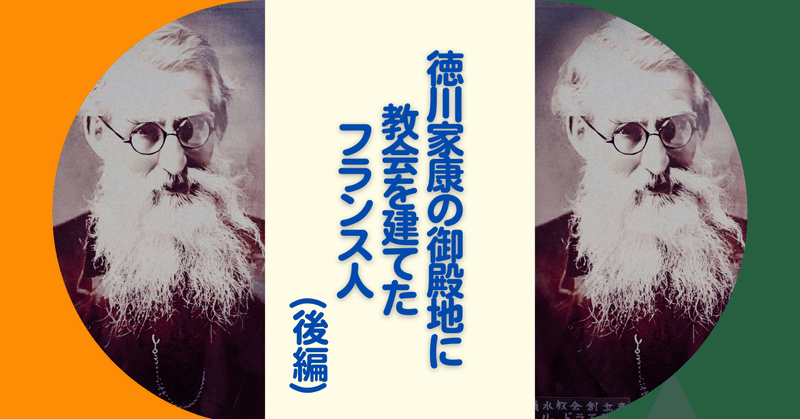
家康の御殿地に教会を建てたフランス人(後編)
1935年(昭和10年)、ドラエ神父が私財を投じて建築した木造のカトリック清水教会聖堂は、見事に完成した。
ドラエ神父が双塔ゴシック様式の木造教会を設計し、それを清水の船大工、宮大工が日本の木造建築技術の粋を集めて建てた、ヨーロッパにも誇れる木造教会の誕生であった。
徳川家康が終の住処に選んだ静岡には、【特に優れた宮大工】が日本中から集められたのだという。
また清水港は徳川の軍港でもあったため、御船蔵が建てられ関船が停泊していた。
清水湊旧記には、1620年(慶長6年)「清水湊で造船された長永丸や大広丸などの軍船が停泊していた」と記録されており、朝鮮通信使の記録には、「清水湊に外国船が入港し美しい姿を海上に浮かべていた」とも記されている。(「南蛮船駿河湾来航図屏風」九州国立博物館所蔵)
つまり徳川の時代には、【特に優れた宮大工】だけでなく【特に優れた船大工】も清水に集められていたのであろう。
カトリック清水教会の聖堂を建てたのは、彼らの子孫たちだったのかもしれない。
この聖堂のアーチリブ・ヴォールト天井の曲線を木材と漆喰だけで造る、、、。
これこそまさに、当時の日本の宮大工、船大工の誇っていた最高技術の結集だった。
(注 アーチを基本形とした屋根で、アーチを水平に押し出したカマボコの形状の屋根を「ヴォールト」と呼ぶ。 リブヴォールトは、横断アーチとその対角線のアーチをリブとして、その隙間をセルによって覆う「ヴォールト」。)

そして清水の宮大工、船大工たちは、それを見事にやり遂げたのである。
ドラエ神父は、このヨーロッパの聖堂にも劣らない美しい聖堂の守護者を「ブローニュの聖母」に決めた。
ここで、「ブローニュの聖母」について説明をしておきたい。
時を更に遡り、633年のことである。
663年の日本は、天智2年。飛鳥時代だった。
が、場所は日本ではなくドラエ神父の故郷、ブローニュ=シュル=メール。
633年、帆も漕ぎ手もいない一隻の船が、ブローニュ=シュル=メールの砂浜に座礁した。
そして夕刻、ブローニュの村人たちが村の高みにある礼拝堂に集っていたところ、信者たちの前に聖母が出現し「聖母マリアの像を乗せた舟が漂着しているので、舟の中の御像を礼拝堂に連れてきて永久に崇拝してほしい」と告げた。
村人たちが砂浜に確かめに行くと、そこには聖母の言葉通り、帆も櫂も無い無人の小舟が流れ着いており、舟の中には木彫りの聖母子像があったのだった。
像は木で出来ており高さは1メートルほどで、幼子イエズスを左腕に抱く聖母の姿を刻んだものだった。
像はこの世のものとも思えない妙なる光に包まれていて、あたりには幸福な安らぎが満ちていたと伝えられている。
村人たちはこの像を村の礼拝堂に運び、安置した。

これが「ブローニュの聖母」の伝承と【ブローニュのノートルダム】の700年の歴史の始まりである。
https://notredamedeboulogne.fr/notre-histoire/
ドラエ神父は、ブローニュ=シュル=メールと同じ海の町である清水に、故郷ブローニュの守護者である「ブローニュの聖母」を選んだのではないだろうか。
ドラエ神父が「ブローニュの聖母」を聖堂の守護者に選ぶと、ブローニュ=シュル=メールの信徒たちが新聖堂のお祝いとして、真新しいブローニュの聖母子像を贈ってくれた。
下の写真が、そのブローニュの聖母子像である。
聖母は船の中央に御子イエスを抱いて立っており、左右には天使が跪き祈っている。

このブローニュの信徒たちがお祝いとして贈ってくれた「ブローニュの聖母子像」は、聖堂の完成以来ずっと、カトリック清水教会の聖堂の真正面、中央祭壇の上壁に安置されていた。
「安置されていた」と過去形なのは、このブローニュの聖母子像を【聖堂を解体した後に建てる新しい教会に安置する】ことが決定され、2023年8月に聖堂から移されてしまったからである。

さて、話を昭和35年に戻そう。
翌年1936年(昭和11年)2月、2.26事件というクーデター事件が起こる。
この事件によってクーデターの恐怖が政界に影を落とし、軍部の発言力がさらに増すこととなった。
軍部による政治介入は一層エスカレート。
国家神道の思想に反するキリスト教は危険思想として、またも糾弾の標的とされていくのである。
1938年(昭和13年)、清水港は軍の指定港となる。
世の中は日増しに戦争の色が濃くなっていき、ドラエ神父は官憲に見張られ(外国人=スパイ容疑)、空腹の中、長時間の尋問に応じなければならなかったこともたびたびあったという。
1939年(昭和14年)9月、遂に第二次世界大戦が始まる。
が、ドラエ神父は祖国フランスには帰国せず、第二次世界大戦中も日本(清水)に留まっていた。(いてくれた。)
ドラエ神父は教会の空き地に作物を作ったり、教会の鐘を軍事工場に送らせまいと思案し、近所の消防団に警報を鳴らすために使って欲しいと頼み込んだ。
そして「戦争が終わったら、必ず聖堂に返して欲しい」と。
ドラエ神父からのこの頼みには、近所の消防団もさぞかし驚いたことであろう。
が、消防団は快諾し、約束通り聖堂の鐘は守られた。
1942年(昭和17年)6月のミッドウェー海戦で、日本海軍は大打撃を受ける。
この戦いで日本海軍は空母4隻、航空機約300機等を失い、以後、戦局の主導権はアメリカ軍に移る。
ミッドウェー海戦はまさにターニングポイントとも言える戦いであり、1944年(昭和19年)からB29の日本の本土空襲が始まる。
戦局が日本にとってずんずん不利になっていくにつれ、陸海軍や警察の教会への介入も酷くなっていき、ドラエ神父は教会の建物の使用をも要請されるようになっていった。
そんな時だった。
1944年(昭和19年)2月、どこの土地でも断られた東京(三河島)からの疎開児童たち50人を、ドラエ神父は引き受けたのである。
東京から地方の数多くの教会に児童疎開の依頼状を送ったものの、受け入れの返事はたったの1通。
そのたった1通の受け入れの返事が、ドラエ神父からの返事だったのである。
私が調べ得た限りでは、いや、調べれば調べるほど、ドラエ神父はどんな時にも何をも恐れることなく、惜しげも無く自分の全てを差し出し、日本人のため、清水、静岡の人々のために生きてくれた外国人、フランス人、人間だった。
その理由を【彼の神父としての天職ゆえ、、。】と解釈してしまうのは、あまりにも安易だ。
そこには、神父としての天職、教え、役割以上の何か、、、ドラエ神父の想像出来ないほど大きく、強い人間愛があると私は思う。
1945年(昭和20年)7月7日、清水はかつてないほどの酷い空襲に遭う。
B29による焼夷弾の投下。
約3時間半に渡った大空襲により、市街地の大半が焼失される。
被災者3.4000人。死傷者440人。
7月31日からは艦砲射撃と機銃掃射を受け、教会付近はほとんど焼け野原と化した。
私はアメリカ空軍の計画した空襲プラン地図、リト・モザイクと、現在の清水とカトリック清水教会の位置を比べてみた。
地図の赤い円が空爆予定地であるが、カトリック清水教会も円の中に位置している。

が、カトリック清水教会は、空襲を免れ奇跡的に残った建築物だった。
清水空襲で負傷した市民たち、家を失った人たちは聖堂に逃げ込み、教会は被災者、負傷者で溢れた。
聖堂の円柱は負傷者の血で染まったほどだった、と言われている。
が、ドラエ神父は聖堂を救護所、避難所とし、近くの医師と共にひたすら救護、看護に当たった。
信徒であるかないかは、全く関係なかった。
そこにいたのは、【救いを求める人間たち】だった。
【救うべき人間たち】であった。
ドラエ神父は傷つき苦しむ人々を救助し、聖堂でただただ看護し続けたのである。
そして毎朝ミサを捧げ、祈り続けたのだった。
が、それにしても、どうして聖堂は空襲で爆撃されなかったのか、、。
石垣の高台の上に建っていて、しかもあんなに高い双塔の建築物がアメリカ空軍のパイロットに見えなかったなんて、そんなことはないだろう。
事実、教会の周りは辺り一面焼け野原になっていた。
まさにドラエ神父の聖堂だけが残ったのだ。
ということは、、、?
ひょっとしたら、「アメリカ空軍が聖堂を意図的に残してくれたのではないか?」という疑問が浮かぶ、、。
だとしたら、何故?
何故、敵がわざわざ残した?
その答えは間違いなく、「それが教会だったから。」だろう。
人が逃げ込める場所、負傷者が救助される場所、何もかも失った人が居られる場所、祈れる場所、泣ける場所、どんな絶望の時にも温かく迎え、受け止めてくれる場所。
そしていつか平和な時が訪れたら、共に喜びを分かち合う祝いの場所にもなるだろう。
【万人のためにいつでも扉が開かれていて、喜びも悲しみも苦しみも全て受け止めてくれる場所。】
それが本来の「教会」の役割であり、その存在の真の意味である。
【万人のために、、。】
それこそ、まさにドラエ神父が望んだことではなかったか?
そういう場所を、敵であるアメリカ軍が清水に残してくれたのではないだろうか?
カトリック清水教会聖堂は【奇跡的に残った】のではなく、アメリカ空軍が【意図的に残してくれた】のだと、私は確信している。
だが、アメリカ軍も知っていた聖堂の真の価値、真の存在の意味を、どうして我々が今までわからなかったのか!
戦後、1948年(昭和23年)10月、ドラエ神父は休暇を取り祖国フランスに帰国。
が2年後の1950年(昭和25年)には再び日本に戻り、伊東市で新教会の経営に当たった。
1955年(昭和30年)パリ宣教会静岡支部で静養することになり、1957年(昭和32年)に彼の第二の故郷、谷津に引退。
そして1957年(昭和32年)12月8日愛する谷津にて、長年ドラエ神父を敬愛し続け、支援し続けた内科医に看取られ、帰天。
友人でも主治医でもあった医師はキリスト教信徒ではなく、仏教徒であった。
だが宗教を越えてただただ人を助け、万人に愛を与え続けたドラエ神父にとって、それは何も不思議なことではなかった。
行年73才。
25才で日本の地に降り立ってから、48年。
自分の人生の約3分の2の時間と、自分の命と持てる愛の全てを日本人のために捧げてくれた人だった。
ドラエ神父、今も静岡市谷津墓地に眠る。

サポートがとても励みになります。頂いたサポートは大事に使わせて頂いています。
