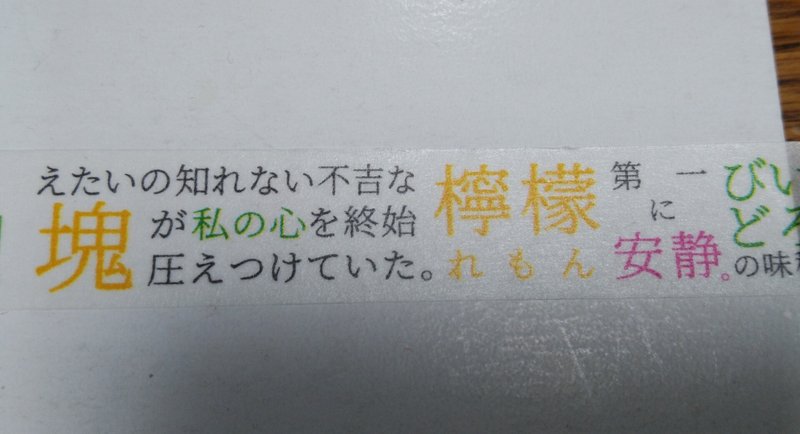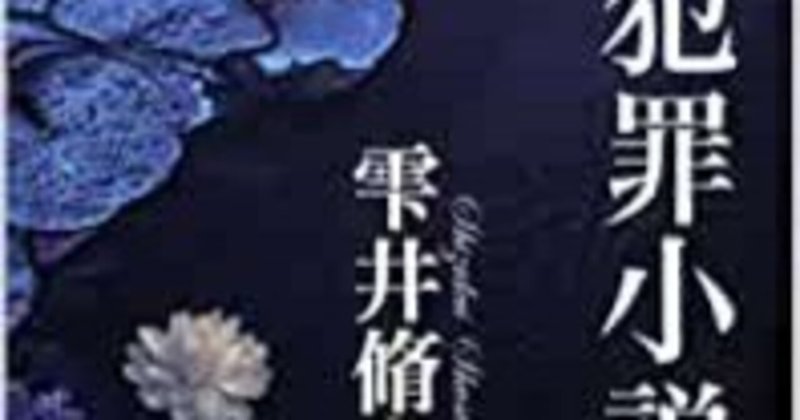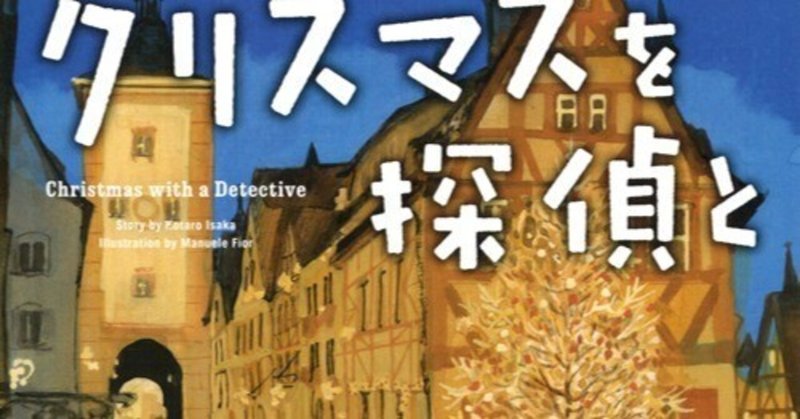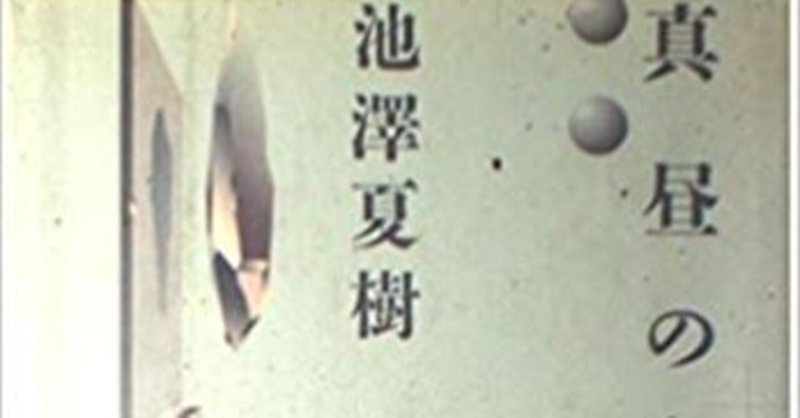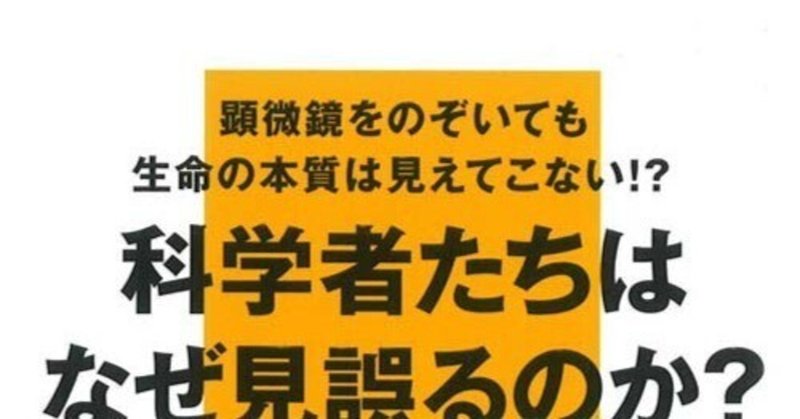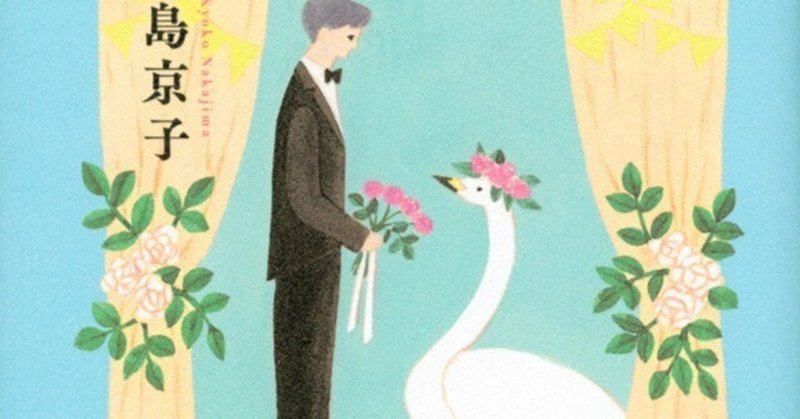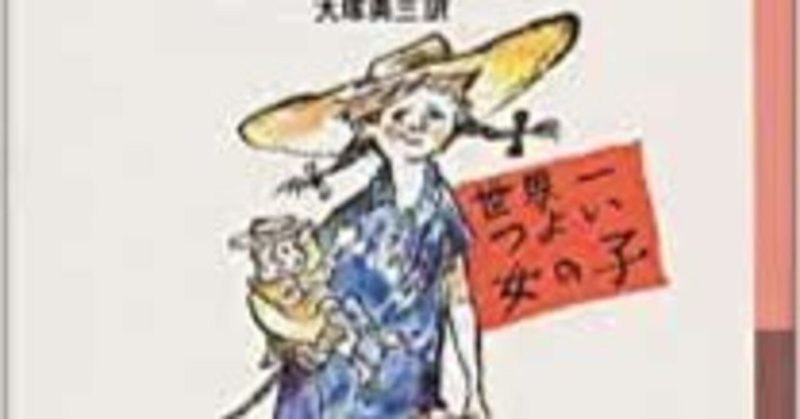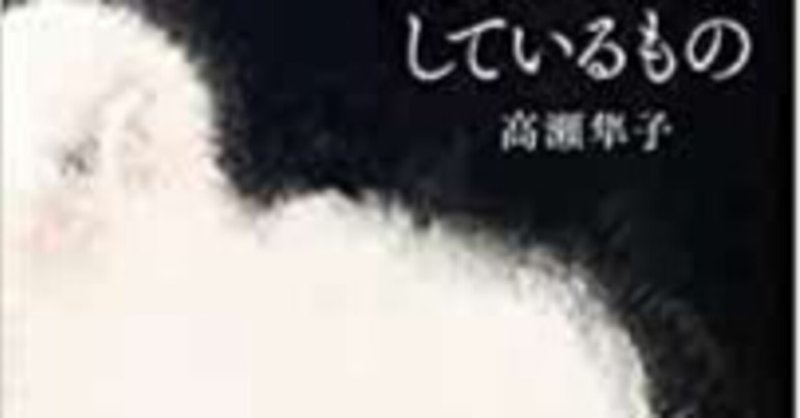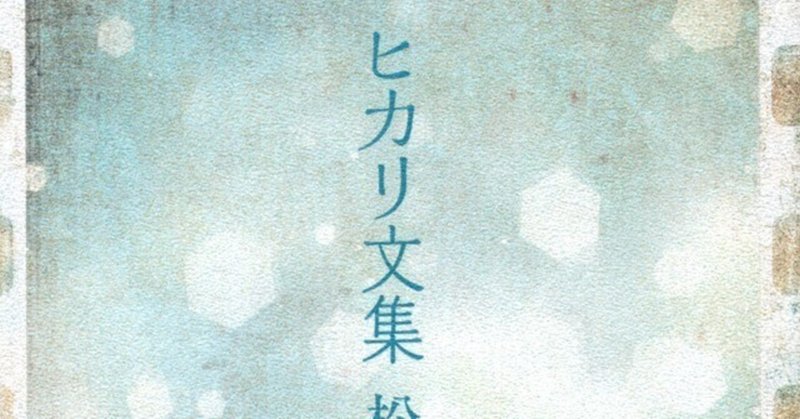2022年11月の記事一覧
伊坂幸太郎『クリスマスを探偵と』(毎日読書メモ(441))
伊坂幸太郎著、マヌエーレ・フィオール絵の、絵本『クリスマスを探偵と』(河出書房新社)を読んだ。舞台はドイツのローテンブルク。クリスマス間近。私立探偵のカールが、浮気調査で追跡している男を、入って行った屋敷の前で張り込みながら、同じベンチにかけていた男と話を始め、自らのクリスマスの想い出を語ると、相手の男が、カールの中に出来上がっている物語は別の角度から見るとこういう解釈も出来るのでは?、という不思
もっとみるサラ・ピンスカー『いずれすべては海の中に』(毎日読書メモ(440))
今年2回目、朝日新聞のSF小説新刊紹介コラムで池澤春菜が推していたのをきっかけに読む本(1回目は『プロジェクト・ヘイル・メアリー』)。サラ・ピンスカー『いずれすべては海の中に』(市田泉訳、竹書房文庫)。作者名も知らなかったが、これが作者初の著書(短編集)だが、長編『新しい時代への歌』(村山美雪訳)が、先行して同じ竹書房文庫から刊行されているようだ。
13編の短編がおさめられていて、「オープン・ロー
『ふしぎ駄菓子屋銭天堂17』(廣嶋玲子・jyajya)(毎日読書メモ(439))
廣嶋玲子・jyajya『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』(偕成社)今年の4月に刊行された17巻読了。ここ10巻くらい、図書館で予約すると即日届いていたが、新しい方から2番目の本(かつ最新刊は先々月出たばかり)なので、予約が結構いっぱい入っていてしばらく待った。
16巻の終わりで、紅子の商品デジタルトの効果で手痛い被害を受けた六条教授、態勢立て直しにちょっと時間がかかっているが、ただ黙って耐えている訳ではなく
福岡伸一『生物と無生物の間』、『世界は分けてもわからない』、『動的平衡』(毎日読書メモ(437))
しばらく前に朝日新聞で連載されていた福岡伸一『新ドリトル先生物語 ドリトル先生ガラパゴスを救う』(朝日新聞出版)、展開にやや乱暴なところがあったり、ドリトル先生やスタビンズ君に話しかけてくれる生物たちがあまりに理路整然と俯瞰的に語ってご都合主義きわまれり、とは思ったが、数十年ぶりにドリトル先生の新しい冒険を読んだようで、予想以上に愉しかった。ゾウガメとアタワルパの涙のつくり話はある意味抱腹絶倒。
山崎ナオコーラ『かわいい夫』(毎日読書メモ(435))
山崎ナオコーラ『かわいい夫』(夏葉社、その後河出文庫)を読んだ。単行本の表紙はチッチとサリーだよ、これは萌える!(ちなみに河出文庫版は表紙がヨシタケシンスケでこれもいい。ヨシタケシンスケは『母ではなくて親になる』の表紙も描いているので、つながってる感はある)
元々、西日本新聞に連載していたエッセイを単行本化した本で、新聞連載時のイラストはちえちひろ。ちえちひろも『鞠子はすてきな役立たず』などの表紙
ピッピと休暇(毎日読書メモ(434))
たぶん、有給休暇をとるために仕事している。
今の職場、最初の6ヶ月は休暇がなくて、その間に仕事に行けないときは欠勤の届を出していた。6ヶ月たって有給休暇が取得できるようになったときは嬉しくてそのために休暇をとったりした。
今は、待遇改善(給与を上げられない分そのほかの部分の福利厚生を改善したみたい)で、仕事についた初日から有給休暇がとれるようになったのだが
そうじゃなかった時代に就業して、初めて休
高瀬隼子『犬のかたちをしているもの』(毎日読書メモ(432))
この夏、『おいしいごはんが食べられますように』で芥川賞を受賞した、高瀬隼子のデビュー作、『犬のかたちをしているもの』(2019年にすばる文学賞受賞)が集英社文庫になったので買って読んでみた。純文学の新人賞によくある、自分と他者の関係を色んな角度から考察する文学、なのだが、当然、「よくある」、では文学賞は取れない。わかりやすい状況説明で、とても非現実的な設定をどんどん書き進める。主人公の戸惑い、動揺
もっとみる滝口悠生『長い一日』、そして君はこの2週間何をしていたのか(毎日読書メモ(431))
滝口悠生『長い一日』(講談社)を読んだ。結構分厚い本で、まさか一日に起こった出来事をこの1冊かけて書いている? それじゃジェームズ・ジョイスの『ユリシーズ』だろ、とか思いつつ読み始めた。
結果的にそんなことはなく、「長い一日」はいくつもの章に分かれた物語の一つの章のタイトルであった。小説家滝口とその妻の生活を中心に、滝口の高校時代の同級生の窓目くんとけり子(けり子のパートナーの天麩羅ちゃん)、窓目