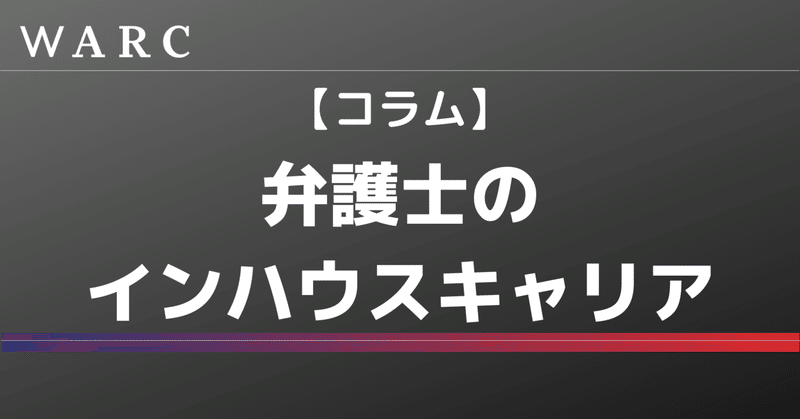
【コラム】弁護士のインハウスキャリアを考える(ベンチャー転職の注意点)
【SYNCAオープン!】
経営管理部門・バックオフィス特化型の転職サイト「SYNCA」(シンカ)がオープンしました😁
皆様是非ご活用ください!
はじめに
前回、公認会計士のインハウスキャリアについて考えてみました。
今日は弁護士・裁判官・検察官などの法曹経験者のインハウスキャリアについて考えてみましょう!
といっても、検察官・裁判官は、定年近くなって退官するか、問題を起こして辞めるか、その他よほどのことがない限り辞めることはないので、原則として弁護士のインハウスキャリアについて考えてみようと思います😁
弁護士は2021年時点で約43,000人で、その中でインハウス(企業内弁護士)をやる人は極一部ですから、かなり限定された人間を対象とした記事ですが、おそらくベンチャーを経営する経営者の皆様、CFOの皆様にも参考になると思うので、書いていきたいと思います。
今回は、ベンチャーの経営者視点と弁護士としての視点を行ったり来たりして書いていく予定なので、若干わかりにくいところもあるかもしれませんがご了承ください。

1.インハウスが必要になるとき
まずは、ベンチャー企業の経営者としての視点でインハウスについて考えていきたいと思います。
大前提として、ほとんどのベンチャー企業にインハウスは必要ありません。
法務事務をこなしてくれるスタッフが1名いれば十分で、難しいところだけスポットで顧問弁護士に依頼をすればそれで足ります。
もちろん、そのベンチャー企業が行う事業やビジネスモデル次第で早期からインハウスを必要とすることはありますが、ほとんどのベンチャー企業にはフルタイムの法務専門職は不要でしょう。
規模がある程度大きくなったとしてもそれは変わりません。
では、インハウスが必要になるときはどういうときか🤔
それは、大きく2つの場合があります。
(1)IPOを目指し始めたとき
一つはIPO(上場)を目指し始めた段階です。
単にVC(ベンチャーキャピタル)から出資を受けたから形式上IPOを目指さないといけなくなったという場合は除きます。
本気でIPOをするぞという覚悟が決まった段階です。
その時点から内部統制を構築し始めないといけないので、社内の法律問題のほぼすべてを解決しておく必要があります。
例えば、情報管理体制の構築、契約締結フロー、実印の管理方法、各種契約書の雛形作成、条文の整理、過去の契約書の整理などなど。
弁護士又はそれと同等の知識がある人間がいた方が回しやすい業務が出てくるので、インハウスが居たほうが良いでしょう。
ただ、この場合でも、よほど規模が大きく無い限りは週2~3日の勤務で十分対応できる量です。
そのため、この時点でも常勤インハウスまでは必要ありません。
N-2(上場前2期)くらいから常勤で雇えば足りるかなと思います。
なお、上場後は常勤でいてもらった方が良いかと思いますが、弁護士資格まで必要かと言われると、別にいらないです🤔
弁護士資格があれば尚良しというくらいで、必須ではないというニュアンスです。
というのも、弁護士資格があったからといって、上場企業で起こるすべての法的問題に対処できるはずがないので、どちらにせよ顧問弁護士を頼ることになります。
そう考えると、わざわざ弁護士資格を必須にしなくても企業の内部の日常的な法務業務は回せます。
よって、必須ではないという感じです。
司法試験等を目指していた元ガチ勢で、かつ、企業法務経験が3~5年ほどある人ならば十分対応可能だと思います。
今でいうと、東大・京大・一橋・慶應・神戸あたりのロースクールを卒業した人の中から、法務経験が十分にある人を選べばある程度機能すると思います。
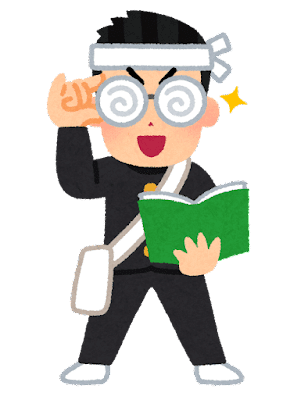
(2)事業難易度が高いとき
主にインハウスが必要になるケースはこちらの方です。
ベンチャー企業の多くは、比較的シンプルな事業を行っていることが多いので、事業難易度はそこまで高くありません。
そのため、インハウスも不要です。
しかし、一部、複雑なビジネスモデルを採用し、まだ法整備もあまり整っていない領域を攻めて行っているベンチャー企業や、特許や商標等の知的財産権が絡む事業を行っているベンチャー企業が存在します。
そういった事業難易度の高い企業については、早期にインハウスを入れておく必要があります。
日頃から法的な論点がポンポン出てくるような会社では、何か事業を始める前にリーガルチェックを通した方が良いですし、そのリーガルチェックに高度な法的知識が必要になるので弁護士資格を持っている人材が必要になるでしょう。
そういうケースではインハウスを常勤で雇っておくメリットがあります。
もし日々発生する法的相談を全部顧問弁護士に依頼していたらとんでもない金額になると思うので、そうなるよりはインハウス一人分の人件費をかけた方が安く済みますし、社内に弁護士がいればスピード感を保ったままリーガルチェックを行うことができる可能性があるので、費用対効果も高いでしょう。
なお、後述するように、弁護士の能力はピンキリなので、スピード感を維持できるかはその人の能力次第です😱


2.インハウスキャリア
続いて、弁護士視点でインハウスキャリアを考えてみましょう!
弁護士視点でのインハウスについては書きたいことが山ほどありますが、重要な論点に絞って書いていこうと思います。
(1)弁護士にもいろいろある
まず、意外と知られていませんが、弁護士にもいろいろなタイプがいるということを改めて解説させていただきます。
弁護士が専門としている「法律」という世界は、極めて広い世界です😱
日本の法律・政令だけでも4,000以上あって、府省令まで入れると8,000を超えます。
そこに国際法まで絡んでくるともうどれだけの専門分野があるかわかりません。
しかも、一つ一つの法令が分厚い本になるほど深い学問分野なので、一つの法律を理解し、使いこなせるようになるのに普通は数年かかります。
実務の豊富な経験となると10年や20年かかることも多いです。
だからこそ、弁護士にもそれぞれ得意とする分野があって、それぞれの分野に専門弁護士が存在します。
そして、企業が欲しがるような専門分野の案件数には限りがあるので、ニッチな企業法務系分野の経験を積める弁護士は極僅かです。
例えば、企業の法律案件を中心に取り扱う企業法務(企業同士の訴訟やM&A、資金調達などの難易度の高い法務業務)というジャンルは、弁護士の中でも花形分野で単価も高く、専門性も高い分野なので、極一部のエリート層だけが案件を受任できます。
知的財産権分野や国際法務もそういう色彩が強いです。
そのため、美味しい分野の実務経験を積めるのは極々一部の弁護士で、それ以外の弁護士は原則として一般民事(離婚、相続、交通事故など)や一般刑事事件(国選弁護や詐欺、窃盗などの私選の刑事事件)を扱うことになります。
ということは、企業が欲しい「インハウスに適合している弁護士」は、弁護士の中でも極々一部の人達だけということになります。
そして、そういう人たちの大半は大手事務所や専門事務所で高い年収(2,000~8,000万円くらい)を稼いでいるのでインハウスになろうとは普通は思わないです🤔
このあたりの状況について、経営者と弁護士との間で認識の齟齬があることが多いので、実情を知っておくと良いかと思います。
同じバッジを持った弁護士でも能力や専門分野は千差万別です。
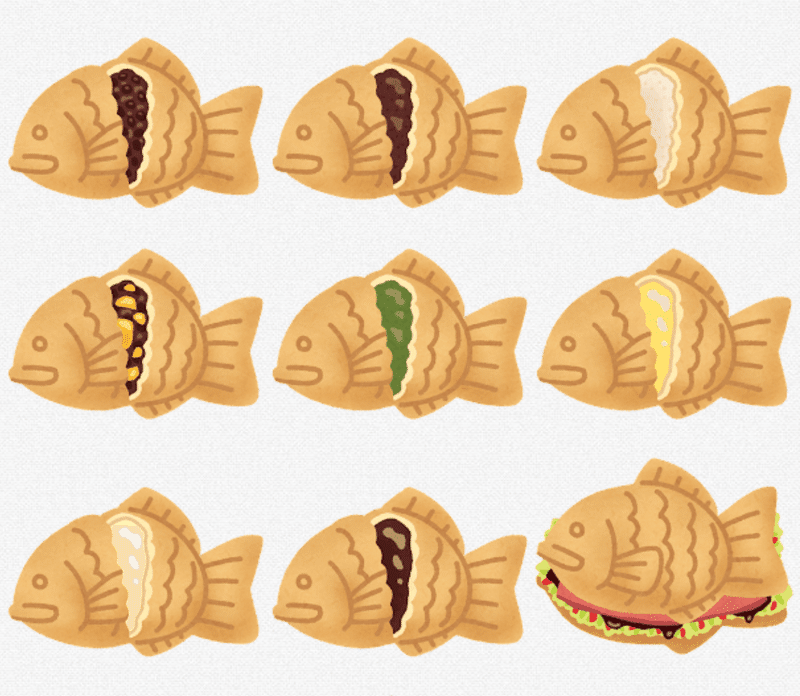
(2)なぜインハウスなのか
続いて、企業が欲しがるような経験を持っている一流の専門弁護士がなぜインハウスに行くことがあるのか、そして、一般的な弁護士がなぜインハウスを目指すのかという点を考えてみましょう。
まず、一流の専門弁護士がインハウスに流れてくる理由についてですが、私が知っている限りでは「熱心に誘われたから」というのが一番多いです。
大手事務所や専門事務所で、10年ほど実務を経験すると、よほどの無駄遣いしなければ1億円くらいの貯金が貯まります。
多少お金を使っても、5,000~7,000万円くらいは貯められるでしょう。
そして、ある程度まとまった貯金が出来ると、心に余裕ができて、毎日明け方近くまで働く弁護士の生活に疑問を持ち始める人も出てきます。
そういうタイミングで会社の経営者から熱心に声がかかったりすると、ひょいと転職してくれることがあります🤣
これは経営者側からすると、超ラッキーです。
経営者の皆様は優秀な弁護士を見つけたらしつこく声をかけておきましょう(笑)
ある日ふと転職してくれることがありますので。
ちなみに、基本的に大手事務所や専門事務所の弁護士は超優秀層なので、大学在学中又はロースクール在学中に司法試験を突破している人が大半です。
ゆえに、10年の実務経験を経たとしても、年齢はまだ30代前半~30代半ばくらいなので、まだまだ現役としてバリバリ働けます😁
ベンチャー企業にはちょうどよい年齢帯だと思います。
一方で、一般的な弁護士がインハウスに行こうとする場合は、私が知る限りで最も多い理由は「事業会社での法務経験がほしい」という建前ですが、その実質的なところでは「インハウスの方が所得が安定しているから」または「弁護士業がしんどい」という点が大きいと思います。
当然の話ですが、弁護士の大半は法律事務所に所属する(雇用ではない)個人事業主ですから、所得が安定しませんし、社会保険等の福利厚生も原則としてありません。
※弁護士国保や弁護士国民年金基金等はある
そして、基本的には当事者間で話し合いができないほど揉めているネガティブな案件を受け持ちます。
それゆえ、タフなメンタルがないと続けられない職種です。
それほど大変な仕事なのに、実質的な年収で1,000万円以上を稼げている弁護士は全弁護士の中でも半分以下です。
残念ながら、経費を差っ引くと多くの同級生サラリーマンより所得が低くなってしまうケースが多いでしょう。
弁護士になれているような人たちの多くが有名大学卒の人たちなので、同級生の平均年収が高いのです。
そのような状況下で弁護士業務を続けるというのはちょっとしんどいですよね。
弁護士になってみて初めて「自分はこの仕事好きじゃないかも」と知ることも多いです。
弁護士も40代以降になると経験値が上がって、年商(売上)1000万円を安定して超えられるようになることが多いのですが、そこまで続けるのもしんどいという精神状態になることは比較的多く見られます。
そういうときにインハウス転職が候補に挙がってきます。
なぜなら、インハウスの方が圧倒的に所得が安定しており、かつ、社会保険・厚生年金等の福利厚生も充実しているからです。
しかも、事務所の家賃や事務員の給与などの経費がかからない🙄
もっと良い会社だったら、法律系の書籍代も全部会社が出してくれる。
一般的な弁護士から見ると、最高の状態です。
「今月は受任数が少ないな…」と毎月の売上を気にしなくて良いですし、「今月勝訴する予定だったのに負けた…」と成功報酬を気にする必要もありません。
営業活動が苦手な弁護士にとってはこれは大きなメリットです。
ただ、残念ながら、前述したとおり、企業法務(インハウス)と一般民事では業務内容が違いすぎるので、一般民事や刑事事件等で身につけた様々な事務処理能力はあまり役に立ちません😱
もっといえば、司法試験や一般民事・刑事で学んだ法学知識の8~9割くらいが役に立ちません🤣
もちろん基本的な法的思考力などは大いに役に立ちますが、知識的な意味では全体的な学び直しが必要です。
なので、企業法務の経験がない弁護士の場合、インハウスに入ること自体が難しい状況です。
企業法務に必要な分野を学び直し、かつ実務経験を3年以上積まないとインハウスで採用されるのは難しいでしょう。
そのため、今まで一般民事や刑事弁護しか担当したことがない弁護士が、身分や所得の安定を目的としてインハウスにキャリアチェンジすることは難易度が高いといえるでしょう。
特に大手企業のインハウスを目指している場合は難易度が非常に高いです。
一方で、ベンチャー企業ならばまだチャンスがあります。
次はその話をしましょう。

(3)大手かベンチャーか
インハウスを目指そうと決めた場合、前述の通り、インハウスを常勤で必要としている企業はそこまで多くはありません。
上場企業といえど、全社がインハウスを必要としているかというとそうでもなく、肌感でいうとベンチャー企業で1~2割、上場企業で2~3割程度の会社がインハウスを必要としているという感じだと思います🤔
中にはコンプライアンス意識がとても高い企業もあって、そういう会社は社内にインハウスを5名以上雇っていることもあるのですが、大半は弁護士資格がなくても良い(あれば歓迎程度)と考えている会社が多いです。
弁護士資格を必須としている企業は少数派で、その少ない選択肢の中で、どうやってインハウスの求人案件を探すか。
選択肢は大きく分けて大手かベンチャーかです🤔
大手企業の方がベンチャー企業よりも待遇や福利厚生が優れていることが多いので、インハウスで入るなら大手の方が利点が多いかと思います。
キャリア的にも有名企業の方が箔が付きますからね🙄
弁護士にとってはそういうのも重要な要素なので、大手の方が良いと思います。
それに、安定を求めているなら尚の事大手の方が良いでしょう。
ということでまずは大手企業のインハウスを目指す方が効率的です。
ただし、大手企業がインハウスを募集する場合、原則として企業法務の実務経験を3年以上積んでいないと応募できませんし、応募者も多いので意外と狭き門です😱
企業法務を専門としている大手事務所等の弁護士であれば比較的簡単に転職できますが、一般的な弁護士の場合はなかなか厳しい現実が待っています。
そこでベンチャー企業が候補に挙がってきますが、ベンチャー企業でインハウスを必要としているところは事業難易度が高いケースが多いので、司法試験や一般民事で学んできた法律の基礎的なところでは太刀打ちできないことが多いです。
その結果、転職できたとしても期待に応えられず、企業側を失望させてしまうことが多くあります。
一般的には弁護士は「天才」だと思われているので、弁護士資格さえあれば「何でもわかるでしょ」というとんでもなく高いハードルを敷かれていることも多いです🙄
なので、インハウスに入る前に企業法務で必要となる法律(膨大なので分野は絞った方がいい)は一通り学んでおいた方が良いかと思います。
また、有名なベンチャー企業の場合、採用要件がかなり厳しく、かつ、入った後の法務実務の難易度が高いことが多いので、最初から有名なベンチャー企業の法務職に就くのは難しい上にあまりオススメもしません🤔
そのため、最初は小規模スタートアップかまだ知名度の低いベンチャー企業を狙うと良いでしょう。
先々上場可能性がある拡大期に入る前のスタートアップを狙うと尚良しです。
スタートアップが拡大していく過程や上場プロセスを経験できるというメリットがありますし、内部統制を一から構築する経験はきっと後々役に立ちます。
何より、小規模スタートアップならば、面倒な上司がいません🤣
小規模スタートアップでは、原則として法務担当は一人ですから、自分で全部やれます。
社内で最も法律に詳しいのが自分で、全部自分で調べて、自分で決断できます。
そういう経験の方が大手企業の中の細分化された業務の一部を担当するより良い経験だと私は思います。
小規模ベンチャー企業で3~5年、企業法務全般の経験を積ませてもらい、ある程度自信がついたら、インハウス同士の縁をつたって有名企業や大手企業に転職すると良いキャリアが描けると思います😁
私はベンチャー界隈の法務ならある程度詳しいと思うので、私で良ければいつでも相談に乗ります。
気軽にお声掛けください。
FacebookでもLinkedInでも👍
なお、私自身は人材紹介を行っていないので、法務案件に強いエージェントに繋ぐかくらいしかできませんが🤣
https://www.facebook.com/harukazutakita
https://www.linkedin.com/in/harukazutakita/

(4)良い経験は積めるのか
では次に、インハウスで良い経験が積めるのか?という点についてお話していきます。
弁護士にとって「良い経験」とは何か🤔
これは難しい論点です。
なぜなら、その人の価値観に依存するからです。
もし仮に、訴訟弁護士として将来活躍したいのであれば、インハウスは絶対に辞めた方が良いでしょう。
インハウスでは、訴訟を担当する能力はほとんど使いませんし、むしろ能力が落ちます。
先々訴訟で食っていきたいなら方向性が違うので、辞めておいた方が良いと思います。
そもそもインハウスに向いているのは、以下のような人たちかなと思います。
将来企業内弁護士として法務実務の専門家になりたいと思っている人
高くはないけど安定した所得がほしい人
激務とは無縁でいたい人
ワーク・ライフ・バランスを整えたい人
将来ベンチャー企業の経営者になろうと思っている人
ベンチャー企業の経営に参画したい人
将来ベンチャー企業専門の弁護士として活動したい人
など
上記のような人たちにとっては、インハウスは良い経験が積める場所だと思います。
もちろん会社にもよりますが🙄
一般民事・刑事を専門とする弁護士の皆さんも同じだと思いますが、インハウスの仕事の8~9割は雑務や事務です。
例えば、インハウスで行う業務内容のメインは、契約書作成、チェック、管理、雛形作成、各種許認可届出書類作成、法務相談の対応、各種規程作成、新規事業のリーガルチェック、登記書類作成などですから、ほとんど机の上で完結する作業です。
なので、そういう事務仕事が好きな人にとってはかなり良い職場だと思います。
インハウスでは、一般的な弁護士事務所より多くの人間とコミュニケーションを取らないといけないですし、部署間の利害調整をしないといけないので、その点は大変ですが、基本的に争ったり、揉めたりなどはないので、平和なものです😁
争いが好きではない温厚な弁護士にとってはインハウスは楽園だと思います。
また、インハウスというポジションは、経営陣との距離が近いです。
何なら、経営メンバーの一人としてCLO(Chief Legal Officer)という役職を付けられることもあります。
そうなると経営者の一人として活動しないといけないので、法務知識だけでなく、経営知識も必要になってきます。
経営者と1on1で話す機会も多いので、非常に勉強になります。
経営者の皆さんのぶっ飛んだ思考法に毎回驚かされますが、それもまた良い刺激になって楽しいです。
そして、他の経営陣(CFOやCOO)も何らかの専門家であることが多いので、他の士業・専門家の皆さんの価値観にも触れられて知的好奇心をくすぐられることが多いです。
特に公認会計士の皆さんとの会話は楽しいですよ!
インハウスでは、会計、ファイナンス、経営学、組織論に関する様々な知識を応用しないといけない場面も多いので、新しい知識を得ることが幸せという方にはインハウスはとても良いと思います。
有り難いことに法務で激務ということはあまりないので、勉強する時間は確保しやすいです。
私はインハウスではなくただの法務ですが、そんな私でも法務7年目になりまして、その間に6つくらい資格や学位、Certificateなどを取得できています。
会社の理解があってこそできたことなので、本当に有り難いことです。
インハウスはビジネスに関する様々な知識を学び、それをすぐに実践できる職種だと思うので、私はとてもオススメできます😁

(5)どのような会社を選べば良いか
では次に、どのような会社を選べば良いかという点についてお話します。
結論的には、Googleなどの世界的有名企業に行けるならそれが一番良いです。
年収も1,500万円くらいになるので大手弁護士事務所に引けを取らないくらいもらえますし、福利厚生は充実しすぎているくらい充実しているので🙄
Googleさんはご飯タダですからね!
最高かよ!
でも、9割くらいの弁護士はGoogle等には行けないので、現実的なお話をすると、最初はやはり小規模ITベンチャー企業の方が良いと思います。
というのも、小規模ITベンチャー企業は採用に苦労していることが多いため、交渉がしやすいからです。
弁護士が完全に弁護士業をお休みしてインハウスに行くって相当な勇気が必要じゃないですか。
言うてしまえば弁護士バッジを一旦返納するのと同義なので、それだけキャリアには空白ができてしまいますし、メリットがあまりありません。
だからこそ、週に1~2日は弁護士業務を続けた方が良いと思うのです🤔
小規模ITベンチャー企業の場合、フルタイムで弁護士を雇えるほどの資金的余裕はないですし、法務業務もそこまで多くありません。
だからこそ、週に3~4日程度の非常勤でインハウスを雇うという選択肢が生まれます。
弁護士側から「非常勤もできますよ」という提案をしてあげると喜ばれることも多いです。
中にはフルタイムで働いてほしいという企業もあるかもしれませんが、その場合でも「弁護士としての活動は続けないといけないですし、続けていきたいので、週に1~2日、訴訟等で数時間抜ける日がありますが許していただけますか?法務としての仕事は時間調整してきっちりやりますので」と聞いてみてください。
小規模ITベンチャー企業の多くは、創業者もまだ20~30代で若く、柔軟性が高いので結構すんなり許してくれることが多いです。
それに、今の時代、フルタイムでオフィスに常勤しないといけないなんていう方がナンセンスだと思うので、弁護士活動を全否定するような会社でインハウスをやってあげる必要はないと思います🤔
私の視点では、そういう会社はイケてないです。
なお、大手企業や中規模以上のベンチャー企業の場合、副業が全般的に許されないことが多いです。
組織の規模が大きくなると、組織の柔軟性よりも「公平性」の方が重視されがちで、弁護士だけ特別扱いはできないという判断になりやすいです。
でも、小規模ITベンチャー企業なら柔軟性抜群なので、大抵は許してくれます。
それに、週3~4日勤務の方が報酬も安く済むので双方にとってメリットがあると思います。
なお、弁護士基準で報酬を考えるとミスマッチが起こりやすいので、その点は注意が必要です。
弁護士にとって、報酬800~1000万円は普通の金額ですが、小規模ITベンチャー企業にとっては凄く高い金額です。
なので、週3~4日勤務なら年収400~500万円がいいところだろうと思います。
フルタイムでも600~800万円くらいが妥当かなと思います。
最初はその辺りからスタートです。
そして徐々に経営層に入っていって、報酬も上がっていくという流れです。
CLOクラスまで行けば1,000~1,500万円くらいになりますから、十分でしょう。
弁護士の場合、副業で数百万くらいはすぐ稼げますから、最初の数年間報酬がちょっと安くてもあまり支障もないでしょう🤔
上記のような条件で小規模ITベンチャー企業を狙って転職活動をすると、比較的良い案件に巡り会える可能性が高くなります😁
インハウスをしつつ、かつ、訴訟弁護士もちょいちょいやるという美味しいコースです。
訴訟弁護士をやる気がない人はフルタイム案件を探すと良いかと思います。

(6)転職サイト
弁護士の多くは、転職活動にひまわりを活用すると思います。
しかし、残念ながら、ベンチャー企業界隈ではひまわりの認知度はほとんどありません🤣
そのため、原則として、企業側は転職サイトを活用して法務人材を探します。
ここにミスマッチが起こっています。
そんな今だからこそ、弁護士資格保有者は転職サイトを活用すべきなんです。
転職サイトで弁護士資格を持った人はほとんどいませんから、いわば売手市場で求人を獲得しやすい状況です!
小規模ITベンチャー企業を狙うなら、以下の3種類の転職サイトを活用すると良いでしょう。
【SYNCA(シンカ)】
こちらは株式会社WARCが運営する転職サイトで、ベンチャー企業の経営管理部門(経理・財務・法務など)に特化した求人案件を取り揃えています。
登録料や利用料はもちろん無料です。
SYNCAはダイレクトリクルーティングサービスなので、企業側から直接スカウトが届きます。
ただ、弁護士資格を有するユーザーは極めて少ないので、あえて自分から応募した方が圧倒的に成功確率が高くなります。
ベンチャー企業からも大歓迎されるでしょう。
【Wantedly】
こちらもベンチャー企業に特化した転職サイトで、どちらかというと転職SNSに近いサービスです。
もちろん無料です。
Wantedlyはすでに規模が大きなサービスなので、自分で応募しないとなかなか企業側からは見つけてくれません😱
【Green】
こちらはITやWEB系の企業に特化した転職サイトで、デザイナーやプログラマーなどに強いサイトです。
ただ、経営管理部門の案件も多く載っているので活用すると良いでしょう😁
インハウスやりたいなぁと思ったら、まずは上記3つの転職サイトに登録してみて、日々求人を見て回ると良いと思います。
100社くらい見ればある程度傾向がわかると思うので、自分の好きな分野や業種を選んでカジュアル面談を申し込んでみると良いと思います。
SYNCAやWantedlyは、「カジュアル面談」という制度があって、これは応募の一歩手前の段階「御社に興味がありますよ」という意思表示なので、そこまで堅苦しく考えなくてOKです!
一度会って話を聞いてみようかな程度で面談を組んで構いません😁
ベンチャー業界では、このカジュアル面談が一般的な選考方法です。
応募前に一度カジュアルにお話して、お互いに良さそうだったら本選考に進みましょうという流れです。
なので、まずはいろんなベンチャー企業の人と繋がりを作って、話を聞いてみると良いですよ!
ちなみに、ベンチャー企業の面談担当は弁護士の皆さんよりかなり若いことが多いので、そのカルチャーギャップは前もって覚悟しておいてください(笑)
人事が20代とか普通です🙄
あと、基本的にベンチャー企業は「私服」なので、スーツで面談すると若干違和感がありますので、その点も知っておくと良いでしょう。

おわりに
ということで、今日は弁護士のインハウスキャリアについていろいろと私見を書いてみました。
公認会計士がベンチャー企業に来るケースはここ数年で爆発的に増えたなと思いますが、弁護士はまだまだケースが少ないですね😁
規模的に法務がそこまで必要とされていないということでもありますが、ここ1~2年で状況も少しずつ変わってきていて、法務求人が増えつつあります。
その流れに乗っかって、インハウスも増えると良いんですけどね🤔
ただ、公認会計士がインハウスに行くことと、弁護士がインハウスになることは根本的にリスクの大きさが違うのでちょっと熟慮が必要です。
私でよければいつでもベンチャー界隈のインハウス事情お話しますので、弁護士の皆さん気軽にご連絡ください🙆♂️
チャットでもオンラインMTGでもどっちでも対応可能です。
弁護士のインハウスにはリスクが伴うので、しっかりその点を考慮して自分のキャリアを決めてくださいませ。
では、また書きます!
【お問い合わせ】
この記事は、株式会社WARCの瀧田が担当させていただいております。
読者の皆様の中で、WARCで働きたい!WARCで転職支援してほしい!という方がいらっしゃったら、以下のメールアドレスにメールを送ってください😁
内容に応じて担当者がお返事させていただきます♫
この記事に対する感想等もぜひぜひ😍
【WARCで募集中の求人一覧】
【次の記事】
【著者情報】
著者:瀧田 桜司(たきた はるかず)
役職:株式会社WARC 法務兼メディア編集長
専門:法学、経営学、心理学
いつでも気軽に友達申請送ってください😍
Facebook:https://www.facebook.com/harukazutakita
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/harukazutakita/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
