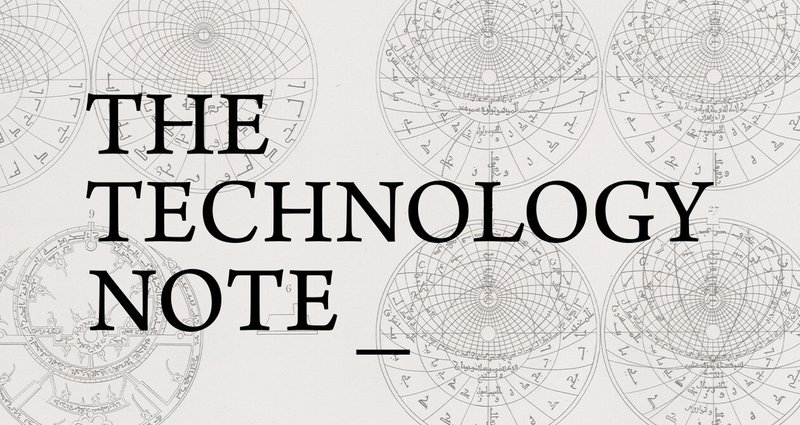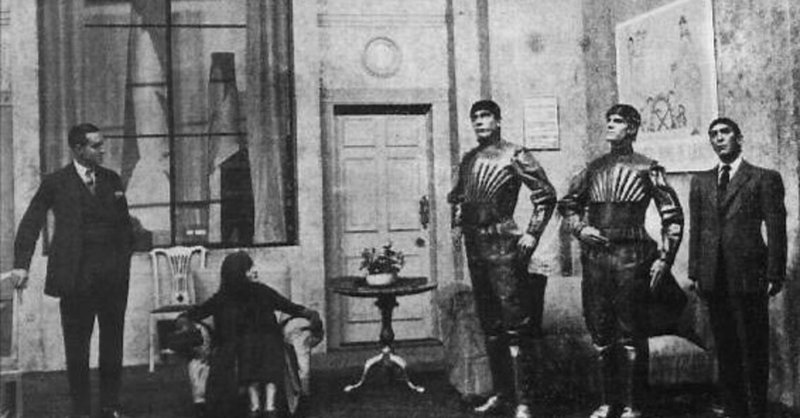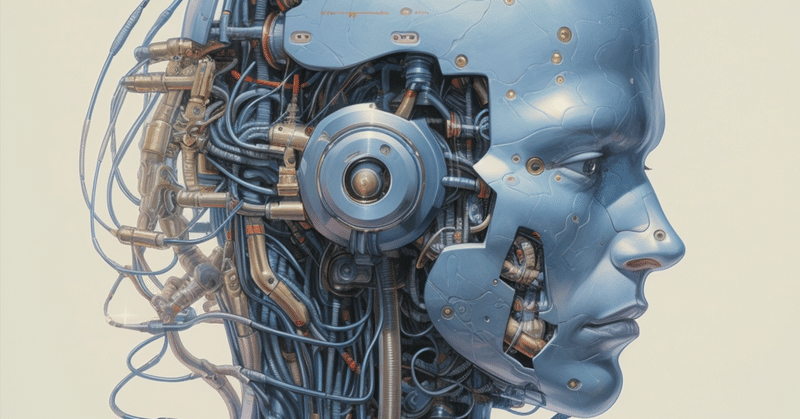#ロボット
じつは『ターミネーター』を初めて観たので「ロボット」について改めて考えてみた
筆者はテクノロジーと人との関係を考える仕事をしているため、余暇にはSF映画や小説をなるべくチェックするようにしています。
ただ、育った家庭の方針が "中学生以下の子どもが観ていい映画は暴力表現やベッドシーンがないものに限る"だったため、80-90年代前半に観る機会を逸したままの映画がたくさんあります。
『ターミネーター』シリーズもその一つです。
TTR編集部のnoteマガジンでは、
ロボットに愛着してしまうわたしたち
ロボットについて話していると、気付いたら人工知能の話になってしまっていることがしばしばあります。人工知能はロボットを構成する要素のひとつですし、特段おかしいことではありません。人間について話すときにその知能や思考についての話題になることはおかしくないですしね。
このテキストは「THE TECHNOLOGY NOTE」の「ロボット」特集の記事です。過去に「人工知能」をテーマにした回はあり、また今回
朝は四本足、昼は二本足、夕は三本足。この生き物は何か。
インホイールモータをご存知だろうか。
その名の通り、ホイールの中にモータが内蔵され、タイヤとモータが一体化した部品のことを指す。
元来、モータとタイヤは別れていた。モータがあって、そこからシャフトが伸び、その先にタイヤが付いている構造だ。
また、モータというのはそれ単体では動作しない。例えばどんな速度で回したいか指示をうける通信回路だったり、モータの回し方を決める制御回路だったり、回転数を監視する
おしゃべり人工知能の憂鬱
キャラクター設定が好きなロボットに「マーヴィン」がいます。1978年にBBCラジオドラマとして発表されたスラップスティックSF『銀河ヒッチハイクガイド』シリーズに出てくるシリウス人工頭脳株式会社製のロボットです。
マーヴィンは、人工知能に感情を与えるためのプログラム"GPP(Genuine People Personalities):本物の人間の個性"の試作機として作られました。惑星1個ほどのサ
人ではないものたちとの話し方
ChatGPTに調べ物の下拵えをお願いしながら、ふと疑問に思ったことを聞いてみました。
スマートスピーカーが家庭に入りはじめた頃、子供が音声アシスタントに何かをお願いする際に「please」を付けないということがアメリカで問題視されたそうです。その結果、AlexaにもGoogle Assistantにも子供達が乱暴な話し方をするとたしなめ、"please" をつけるとほめる機能が盛り込まれるこ