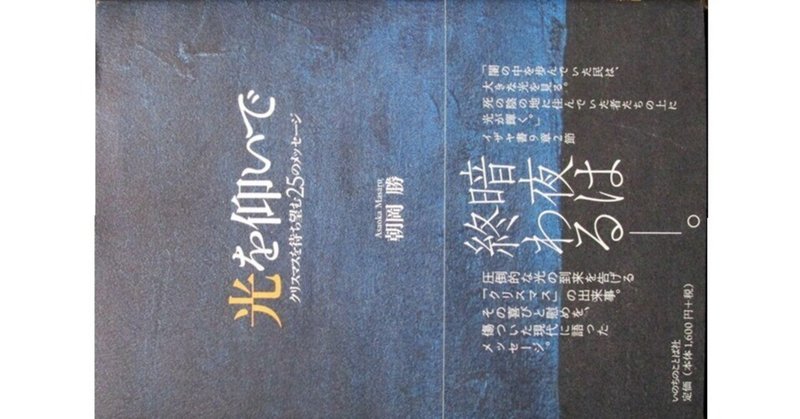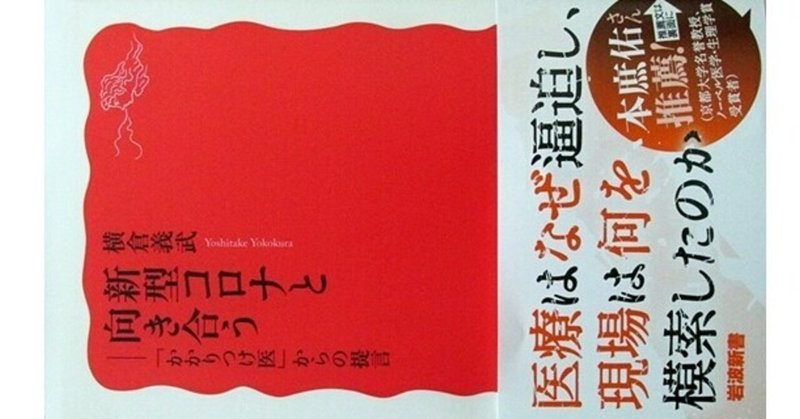- 運営しているクリエイター
#コロナ禍
『現代思想2020年11月号 特集・ワクチンを考える』(青土社)
様々な論者が力のこもった文章を載せてくれる「現代思想」、テーマに関心が強ければ時々買うことにしている。新型コロナウイルスの感染拡大の年の秋に編まれたそのテーマは、ズバリ「ワクチン」。その後、ワクチンが供給され始めた頃に私がこれを読みたいと思い、手配した。が、実はこの編集がなされたときには、ワクチンが本当に接種されるのかどうか、未定だったのだ。それは常識的にはそうである。あまりにも治験期間が短すぎる
もっとみる