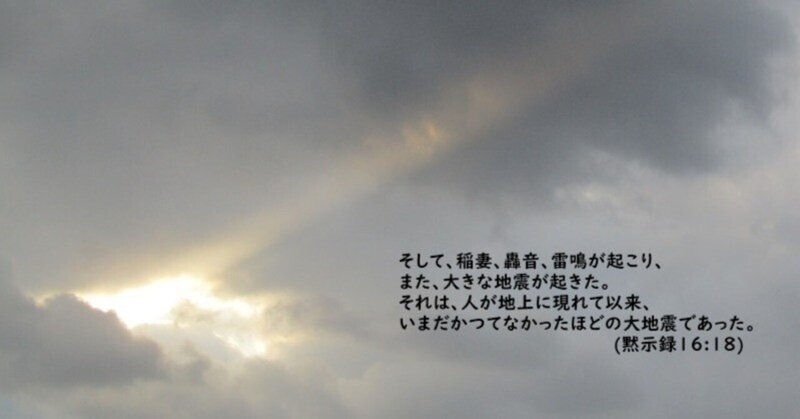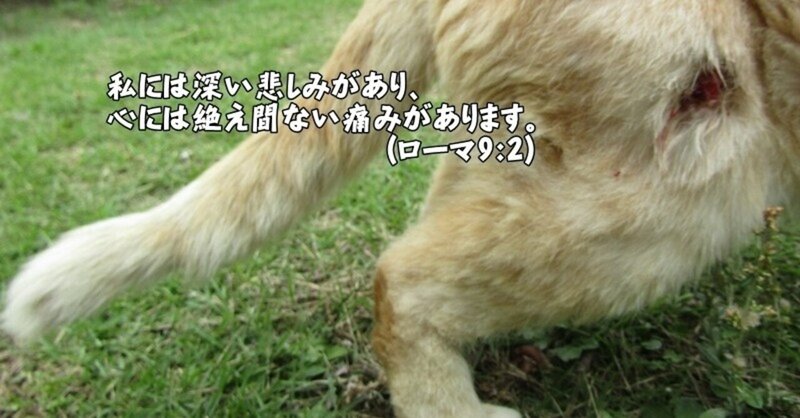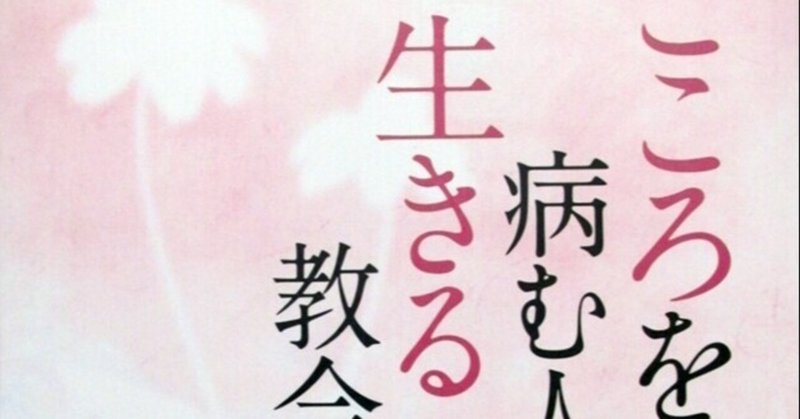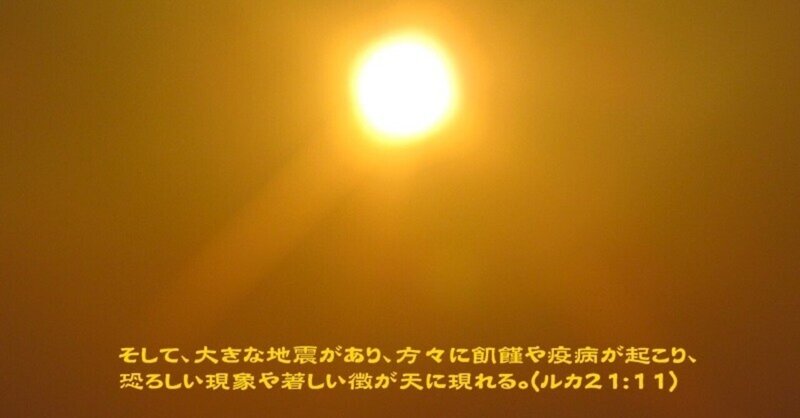ひとのこころ、見つめてみます。自分のこころから、誰かのこころへ。こころからこころへ伝わるものがあり、こころにあるものが、その人をつくり、世界をつくる。そんな素朴な思いに胸を躍らせ…
- 運営しているクリエイター
#阪神淡路大震災
阪神淡路大震災、そして
https://www.nhk.or.jp/kobe/shinsai/
1995年1月17日。歴史のひとつとして、教科書にも載っている。生徒はそれをテストにために憶える。もちろん、憶えてほしい。だが、そこから想像力も働かせてほしいと願う。
これを何らかの形で体験した、と言える世代は、もう30代以降ということになるだろう。あの日、燃える町は一日中テレビ画面に映し出された。まだインターネットは
阪神淡路大震災を伝えなければならない
ライブでのテレビ中継が特別に組まれなくなった。震災25年の年はずいぶん取り上げられていたのに、一年でこの閑散とした有様だ。もちろん、報道番組の中では取り上げられるだろう。だが、もう一般ニュースの一つにしかならないのだ。
2012年の成人の日、朝日新聞の社説が「尾崎豊を知っているか」というタイトルだったというところに絡んだコラムが先日「文春オンライン」(https://bunshun.jp/ar