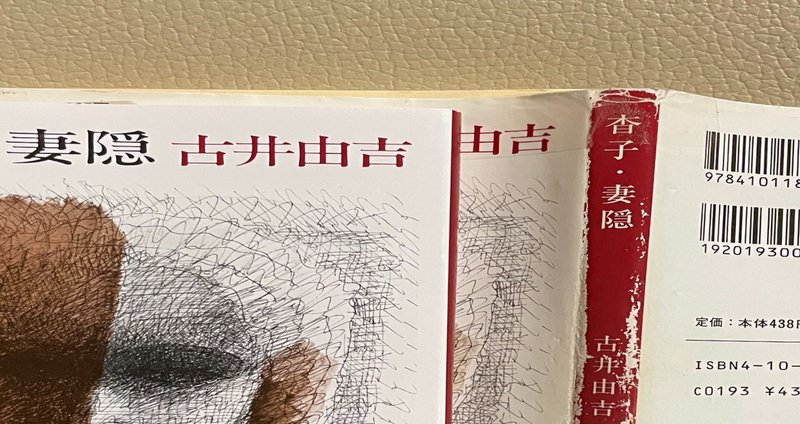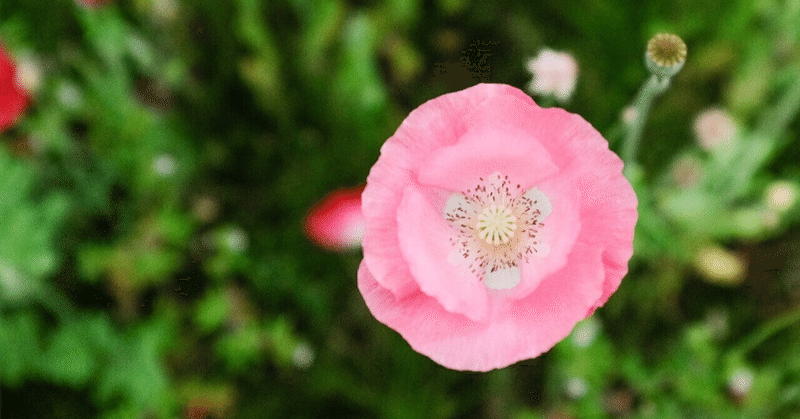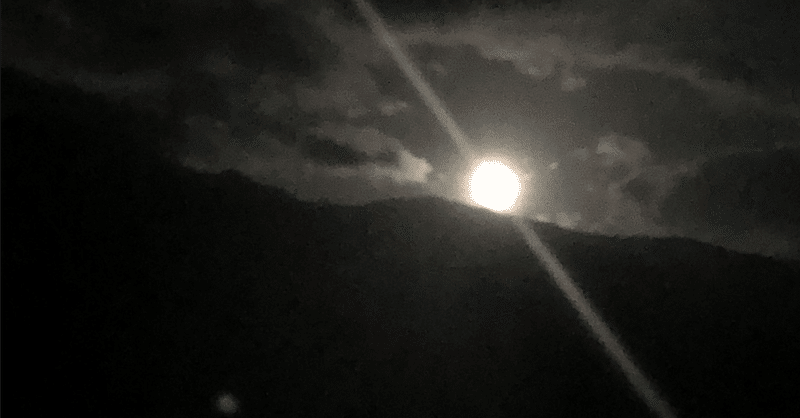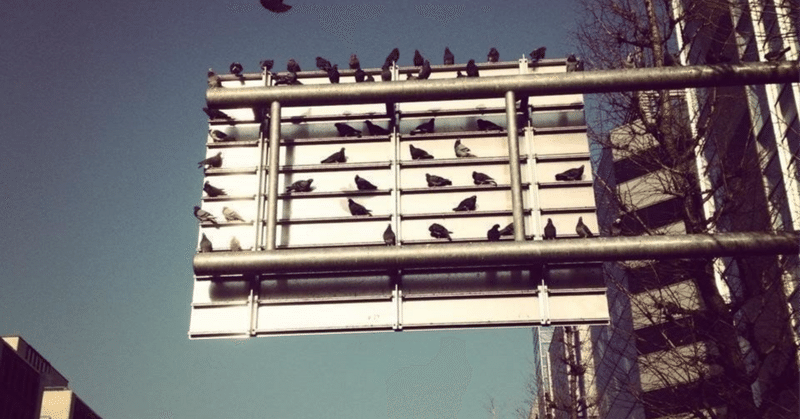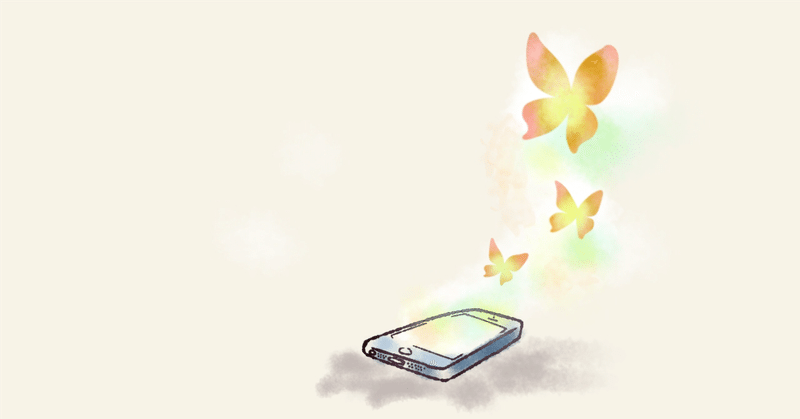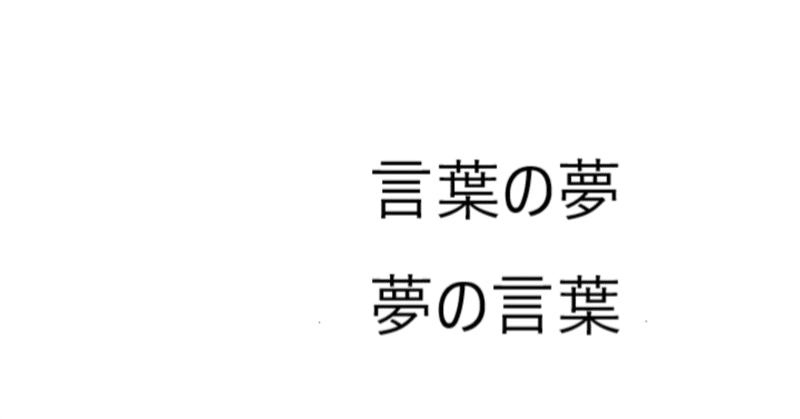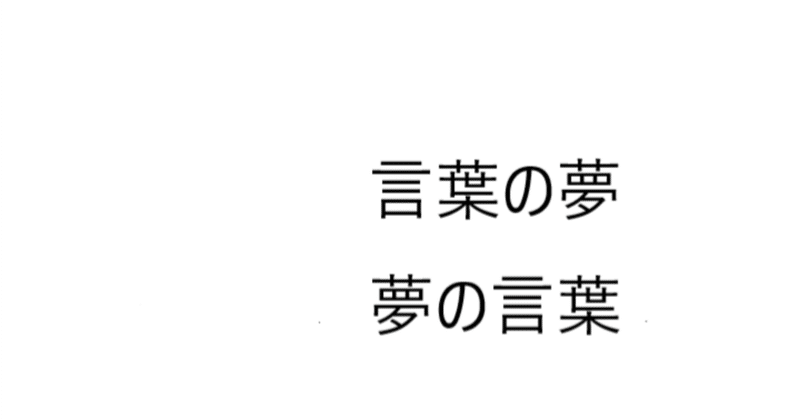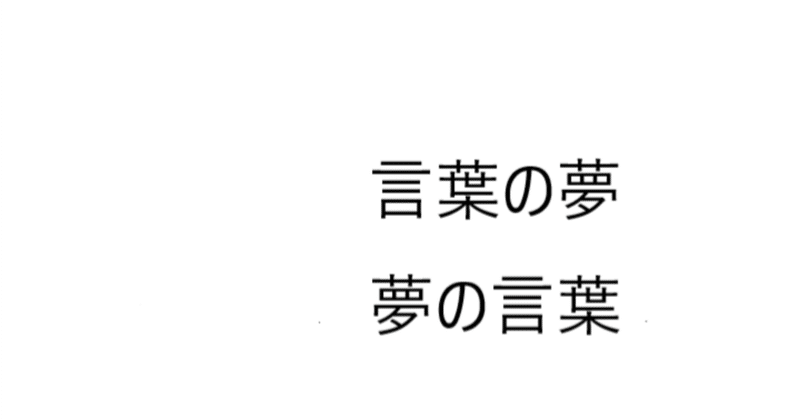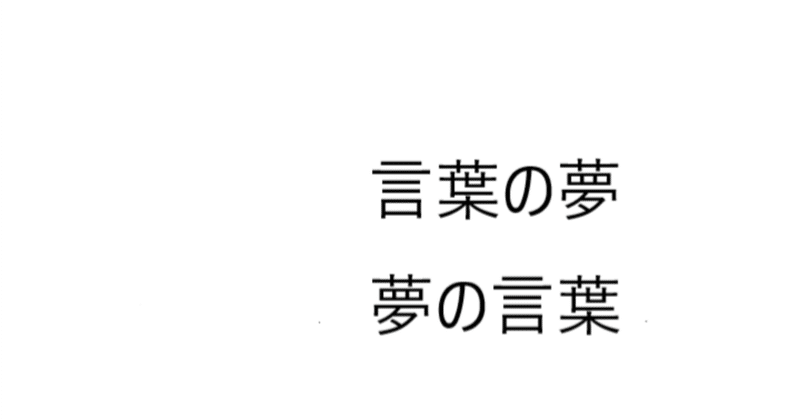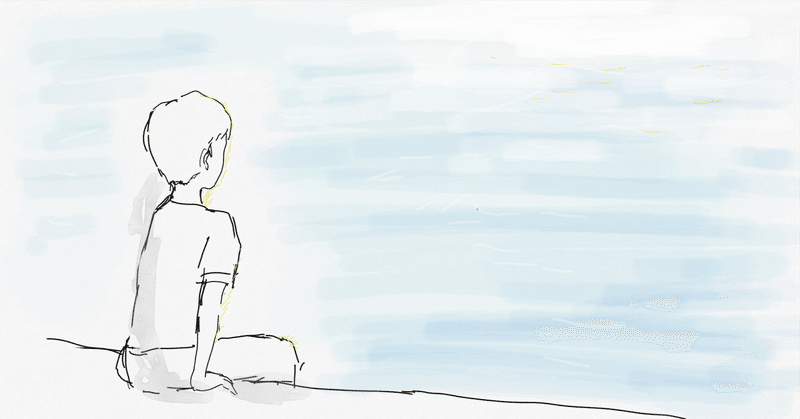#日本語
山の記憶、「山」の記憶
今回は、川端康成の『山の音』の読書感想文です。この作品については「ひとりで聞く音」でも書いたことがあります。
◆山と「山」
山は山ではないのに山としてまかり通っている。
山は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通っている。
体感しやすいように書き換えると以下のようになります。
「山」は山ではないのに山としてまかり通っている。
「山」は山とぜんぜん似ていないのに山としてまかり通って
とりあえず仮面を裏返してみる(断片集)
今回も断片集です。見出しのある各文章は連想でつないであります。緩やかなつながりはありますが、断章としてお読みください。今後の記事のメモとして書きました。
看板、サイン、しるし
街を歩くと看板がやたら目に付きます。目に付くと言うよりも、こちらが無意識に探しているのかもしれません。無意識に物色しているとも言えそうです。
たぶん、そのようにできているのでしょう。看板は人の目を惹いてなんぼだと
蝶のように鳥のように(断片集)
今回の記事では、アスタリスク(*)ではじまる各文章を連想だけでつないでありますので――言葉やイメージを「掛ける」ことでつないでいくという意味です――、テーマに統一感がなく結びつきが緩く感じられると思います。
それぞれを独立した断片としてお読みください。
*
ない。ないから、そのないところに何かを掛ける――。
何かに、それとは別の何かを見る――。これが「何か」との出会い。遭