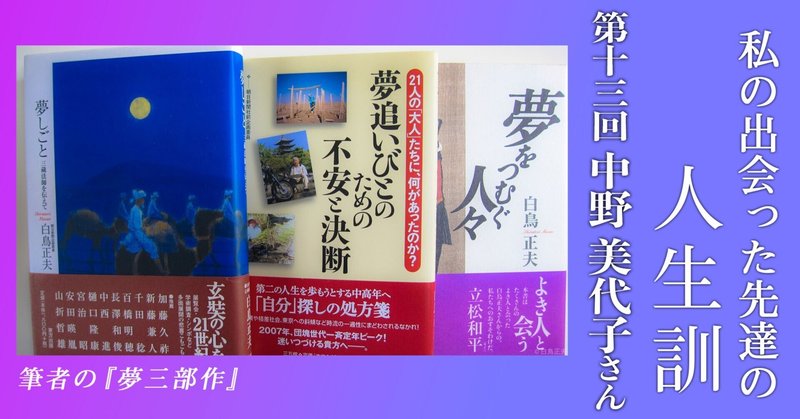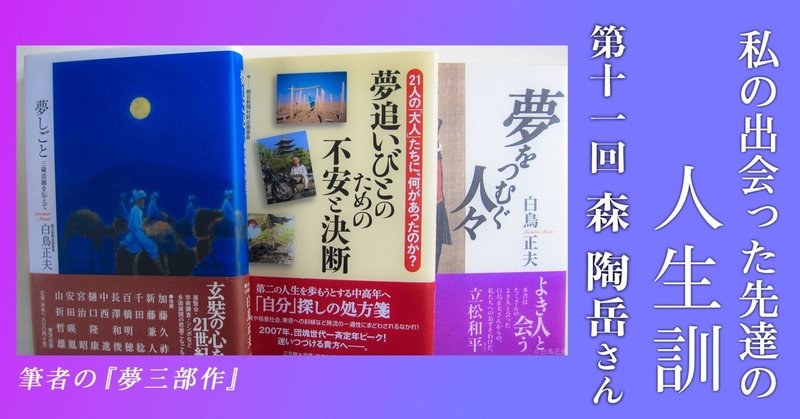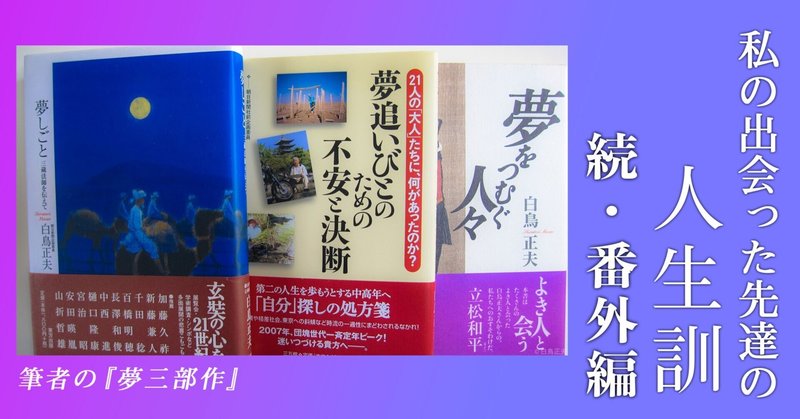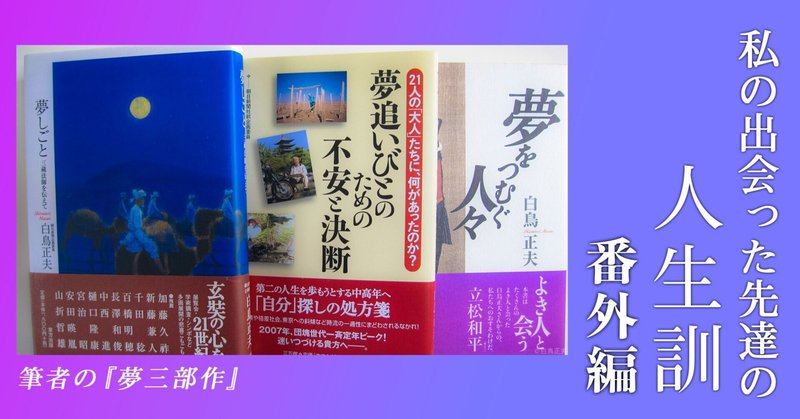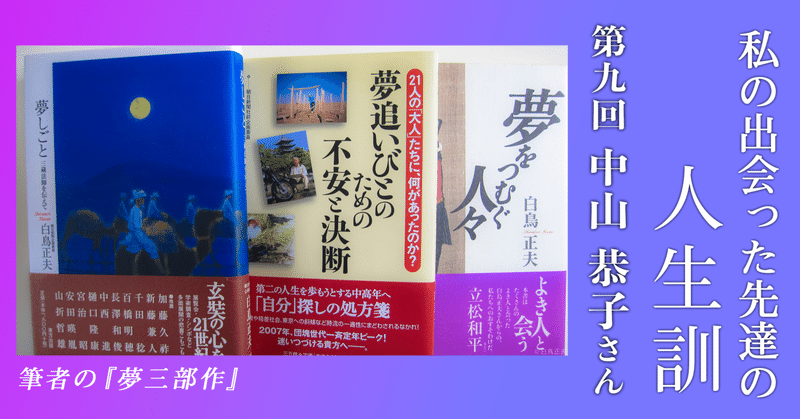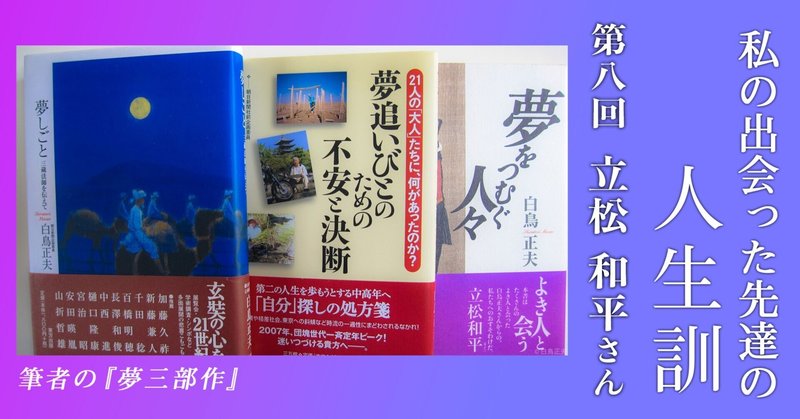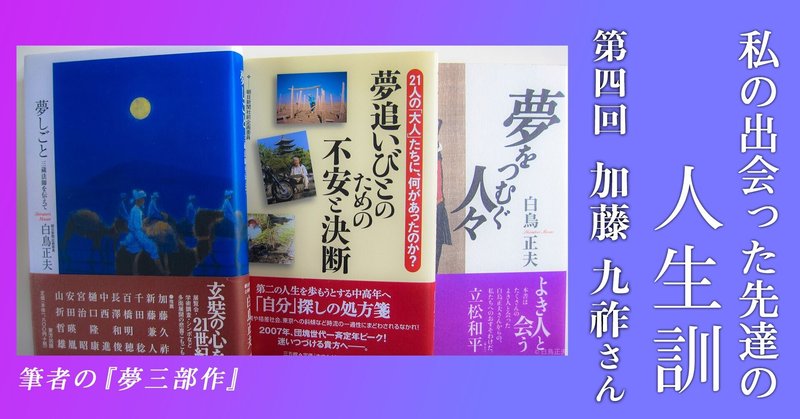- 運営しているクリエイター
#エッセイ
私の出会った先達の人生訓 はじめます
新型コロナ禍による世界の死者は、2021年6月現在380万人を超え、なお増え続けている。終戦の前の年に生まれた筆者は「戦争」を知らないが、まるで目に見えない敵との「戦争」のように思う。「人生80年」、それ以上の超高齢化社会の日本ゆえ、重症化や死亡率が高く予期せぬ難事となっている。昭和、平成、令和と生きてきたが、これほど命の儚さと、日常の大切さを思い知ったことはない。これまでの生とこれからの生を思
もっとみる文化財保存に貢献、日本画家の平山郁夫さん 〜平和を求め、仏の道を描いた平山芸術の足跡を追悼
日本画壇の重鎮であった平山郁夫画伯が2009年12月2日に逝去され、2021年13回忌を迎えた。生前は画家として《仏教伝来》や一連のシルクロードを描いた数々の名作を遺しただけでなく、ユネスコ親善大使、文化財保護・芸術研究助成財団理事長、東京藝術大学学長など、さまざまな立場での業績をはじめ、国際的な文化財保存や平和活動でも貢献された。1998年に文化勲章、2001年にマグサイサイ賞など国内外から数
もっとみる考古学者で文化人類学者の加藤九祚さん シベリア抑留を体験、老いて遺跡発掘の生涯
2002年に受章した「ドストリク」(友好)勲章を胸に正装の加藤九祚さん
(2008年、奥野浩司さん撮影)
■シルクロードの名著、90歳過ぎても現場へ
90歳を過ぎても、シルクロードの要衝の地、ウズベキスタンで遺跡の発掘調査を続けていた考古学者で文化人類学者の加藤九祚(きゅうぞう)さんが、発掘のため訪れていた南部・テルメズの病院で2016年9月12日に亡くなって5年になる。94歳だった。大半