
日本初のオスカー女優「ミヨシ・ウメキ」は、アメリカでどう見られているか
1957年の映画「サヨナラ」で、アジア人初のアカデミー賞(助演女優賞)を受賞した梅木美代志(うめき・みよし 歌手名ナンシー梅木)。
彼女の評伝的な動画がYouTubeにありました。
Miyoshi Umeki: The First East Asian Woman to Win an Acting Oscar(Be Kind Rewind 2022.4.1)
アップ主は、ニューヨークの映画研究家らしい。
「アジア人とアカデミー賞」といった内容で、おそらく2年前、韓国人のユン・ヨジョンが助演女優賞を受賞したのをきっかけに、製作されたのではないかと思います。
ウメキについての新情報(特ダネ)があるわけではありませんが、関連研究が要領よく紹介されており、わたしも勉強になりました。
なにより、現在のアメリカ人がミヨシ・ウメキをどう見ているか、よくわかる内容でした。映画史や女性史に関心ある方に、一見をおすすめする次第です。
字幕がないので、以下にざっと抄訳してみました。
今年のアカデミー賞授賞式での「アジア人差別」について、わたしはnoteでいくつか記事を書きましたが、その締めくくりとしても、ふさわしい内容だと思います。
(ただし、わたしの英語力だから誤訳があるかもしれないので、詳しくは動画を参照ください。小見出しはわたしが適当につけました)
「ミヨシ・ウメキ アジア人初のオスカー女優」の要旨
(上記動画のナレーションの大意)
大きな枠組み
アジア人初のオスカー女優、ミヨシ・ウメキのことを知るには、彼女を戦後政治の大きな枠組みのなかに置いて見る必要がある。
1945年、日本は敗戦し、アメリカ軍が駐留した。
アメリカの目的は、戦争を起こした勢力を一掃し、アメリカ式の民主主義を植え付けることだった。
数万のアメリカ人が駐留し、学校制度、法制度、そして女性の役割にいたるまで、あらゆるものがその影響を受けることになる。
公式な占領政策に負けず劣らず影響力をもったのが、映画などのアメリカ文化だった。
ミヨシ・ウメキにとっては、アメリカのポピュラー音楽の影響が大きい。
『ブルー・ニッポン』を書いたテイラー・アトキンスによれば、日本駐留のアメリア軍人が娯楽を欲したため、日本各地にアメリカ式のダンスホールやクラブができた。そこでは、日本人の音楽家がやとわれた。
それが、日本でジャズが大流行するきっかけになる。

ミヨシ・ウメキも、16歳のとき、北海道・小樽のGIクラブで歌手デビューした。

彼女は、ダイナ・ショアやペギー・リー、ドリス・デイの番組をラジオで聞き、彼女たちの歌を必死でコピーしていた。
ウメキの歌は、いまもネットでたくさん聴くことができるが、ダイナ・ショアらの影響がもろに出ているのがわかる。
日本の再定義
いっぽう、冷戦(朝鮮戦争)の始まりとともに、アメリカは日本の地政学的位置を重視するようになる。
日本は、アジアの共産主義の広がりを食い止める、防波堤の位置にあったからだ。

そこでアメリカは、アメリカ内の日本イメージを作り直す必要があった。
「日本は敵だったけど、いまやアメリカの友達だよ」
と、アメリカ国内に示す必要があったのだ。
そこで、アメリカでは、日本の文化が、スシから相撲まで、好意的に紹介され始めた。
そこでは、ポピュラー音楽が重要な位置を占めた。ベンジャミン・ハンが著書『白黒テレビを超えて』で示したように、日本とアメリカは、相互にお互いの音楽を流行らせた。
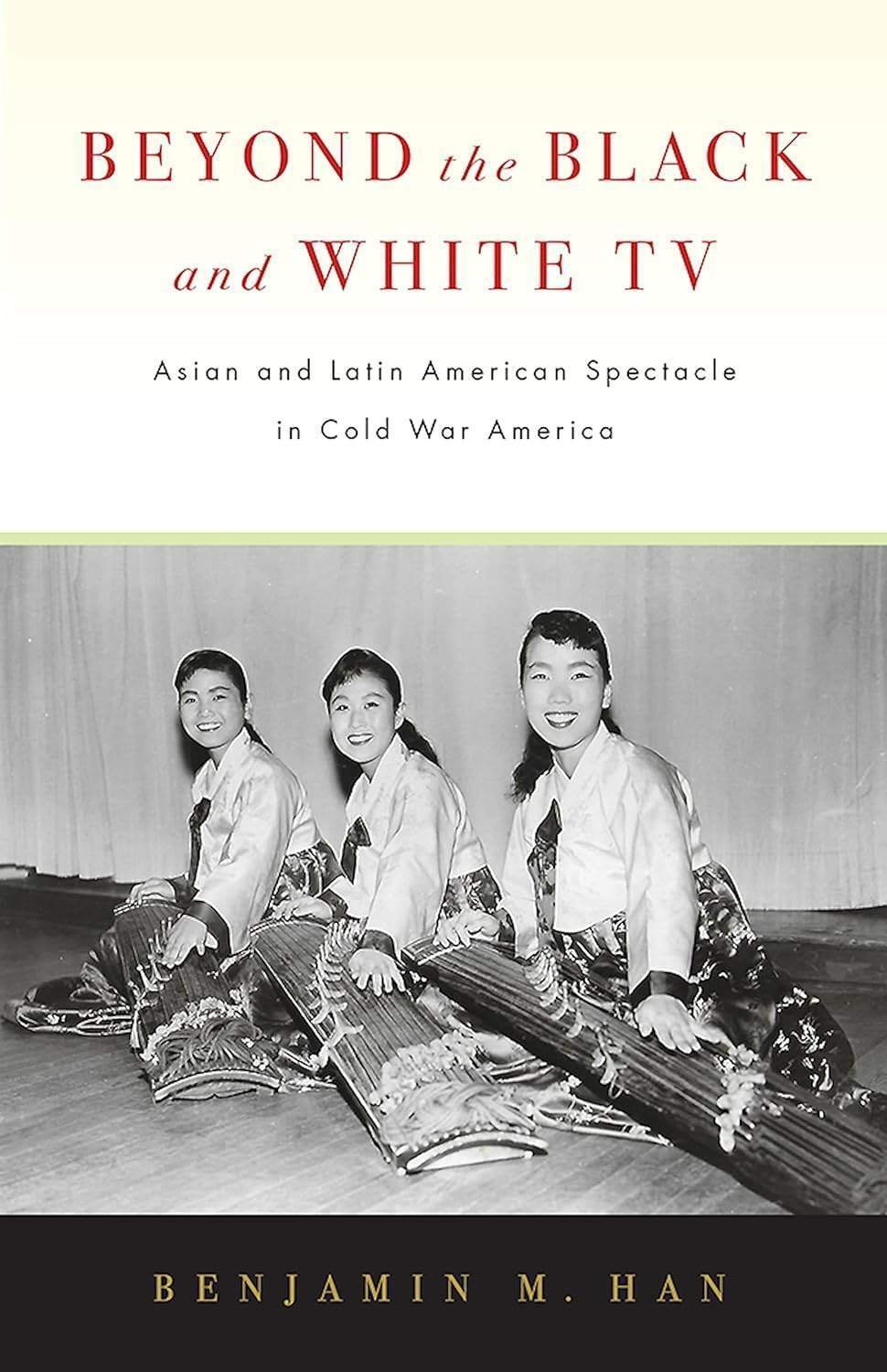
国際ロマンス
こうした状況下で、ミヨシが1955年にアメリカ・ツアーに乗り出したのは自然だった。
アメリカの小さな劇場やクラブで歌ううち、彼女はアーサー・ゴドフィーの目にとまって彼のバラエティーショーに出演した。
それを見たワーナーブラザーズのキャスティングディレクターが、映画「サヨナラ」に彼女を起用する。
「サヨナラ」は、日本に駐在する空軍パイロット(マーロン・ブランド)と彼の友人(レッド・バトンズ)が、ともに日本女性と結婚しようとする話である。

しかし、軍隊の冷酷な規則がわざわいして、かれらの結婚は暗礁に乗り上げ、「心中」を考えるようになる。
ジーナ・マルチェッティは、『ロマンスと「黄禍」』という本で、
「1947年6月22日から、1952年12月31日までで、おもに軍人であるアメリカ人10517人が、日本女性と結婚した。アメリカ人の75%は白人であった」
と書いている。

この国際結婚の流行は、朝鮮戦争にともなう「戦場の花嫁 war blides」として大いに話題になった。
だから、1950年代から60年代前半にかけて、日本女性とアメリカ人との恋愛は、「サヨナラ」以外でも多くの映画の題材になっている。
「やさしい狼犬部隊」「八月十五夜の茶屋」「黒船 The Barbarian and the Geisha」「クリムゾン・キモノ」「クライ・フォー・ハッピー」「マジョリティー・オブ・ワン」などだ。

これらの映画は、いっけん人種偏見を乗り越えたように見えるが、限界があった。
「サヨナラ」にしても、軍隊内での人種偏見を非難しているいっぽうで、戦中、アメリカが国内の日系人を強制キャンプに送って隔離したことは忘れられている。「サヨナラ」に主演した日系アメリカ人の高美以子は、実際にキャンプに拘留された人なのに。
アメリカを愛したウメキ
「サヨナラ」のなかの日本女性も、アジア人のステレオタイプで、召使い的で、お人形のように描かれる。
だが、ミヨシ・ウメキは、コミカルで印象的な演技により、アメリカの観客を魅了した。
アメリカを敵視しない、かわいくて好ましい新日本人の象徴となったのだ。
それは、ウメキが、実際にアメリカ文化に魅せられた人だったからでもある。
ウメキは、よくインタビューで、「敵だったアメリカ人をどう思っているのか」と本心を探られた。
著名ジャーナリストのマイク・ウォレスは、オスカー受賞後のインタビューでウメキに、
「アメリカ人は日本人を何万と殺し、原子爆弾を落としたのに、あなたはアメリカ人が憎くないのか」
と聞いた。
ウメキは、
「兵隊さんたちやそのご家族の気持ちはわかりませんが、わたしはアメリカ人スターの写真を切り抜いて見ていて、いい人たちにちがいないと思っていました」
と答えた。
アジアに目を向けたアメリカ
ウメキが受賞した1958年度のアカデミー賞では、助演女優賞の下馬評が高かったのは「青春物語(プレイトンプレイス)」のダイアン・バーシだった。

だが、ミヨシ・ウメキが勝者だった。
あらためて当時の候補をながめると、その理由はなんとなくわかる。
4つの演技賞にノミネートされた20人の候補者のうち、5人は外国人だった。
主要賞は、タイを舞台にした「戦場にかける橋」と、日本を舞台にした「サヨナラ」が分け合う形となり、アメリカ国内を舞台にした「プレイトンプレイス」は、多くノミネートされたにもかかわらず、主要賞は1つも受賞していない。
当時のハリウッドの関心が、アメリカの対外関係、国際交流に向いていたのがわかる。
1950年代から60年代のアメリカ映画界は、アジアに目を向けた。その傾向は、ミュージカルにも表れた。
ロジャーズ&ハマースタインは、アジア人をキャスティングした画期的な「王様と私」や「フラワー・ドラム・ソング」を製作する。
ミヨシ・ウメキは、「フラワー・ドラム・ソング」のミュージカル版と映画版の両方で中国人役を演じた。
アジア女性のイメージ
ウメキが演じるアジア女性は、アメリカナイズされるほど「独立した女性」になる。
それは、戦前は「永遠の異人」イメージだったアジア人が、伝統を捨てて、アメリカに同化するさまを描いていると評されている。
そのような役割を、ウメキはその後のテレビ出演でも果たすことになる。
ベンジャミン・ハンによれば、ウメキはその後、アメリカでの召使い的なイメージと、自立した市民としてのイメージのあいだで、揺れ動くことになる。
「ドナ・リード・ショー」でのエピソードが象徴的だ。
ドナが、自分の友人と、夫の同僚の家を訪問すると、その同僚の妻が日本人(ウメキ)だった。

着物姿のウメキに、ドナの友人たちは驚き、どうしていいかわからず、下手な言い訳でその場を去ろうとする。
しかし、ドナは、人種差別をいさめ、日本人女性(ウメキ)を受け入れる。
そこまではいいのだが、問題は、ウメキの夫に対する態度だった。
東洋の伝統にしたがい、夫にかいがいしく仕えるウメキの姿を見て、ドナたち白人女性は困惑する。
ウメキは夫にマッサージをほどこし、夫のうしろを歩き、夫がコーヒーを欲しがるとすぐにもってくるといった具合。
白人の女たちは、自分たちの夫にウメキを見てほしくないと思う。ウメキのマネをしろと言われるのが嫌だからだ。
ドナは、ウメキに、彼女の夫への態度に違和感があることを告げる。
ウメキが、
「どうしておかしいのですか。私がそうするのは、かれを愛しているからです。それは、私の母や祖母がしてきたことと同じです」
と言うと、ドナは、
「どっちの伝統が正しいという話ではないの。でも、とにかくここでは伝統がちがうのよ」
と答える。
つづけてウメキとドナは、次のような会話をかわす。
「ほかのアメリカ人と同じようにしたほうがいいということですか」
「あなたがしたくないことをする必要はないわ。あなたは自由なの。それがデモクラシーというものよ」
「デモクラシー・・すべての人(メン)は平等ということですね」
「ええ、そしてすべての女性(ウィメン)も平等よ。だからね、女は男たちから、公正に『選挙』されるべきなの」
そうドナにさとされて、ウメキは、洋服に着替え、アメリカ人女性と同じように振舞う、というエピソードだ。

このエピソードは、アメリカ人のアジア女性への見方を象徴している。
アジア女性は簡単に伝統を捨てる、と考えられていた。
日本の複雑な「文化変容」
しかし、実際の日本では事情は異なる。
伝統を捨てるのはそう簡単でなかったことが、溝口健二や成瀬巳喜男の映画を見ればわかるのだ。
キャサリーン・ラッセルは『成瀬巳喜男の映画 The Cinema of Naruse Mikio』(2008)で、成瀬の映画の主題は新世代の出現だと書いている。
成瀬の映画は、戦後の旧世代と新世代の共存、そして、旧世代が新世代へゆっくり交代していくさまを描いている、と。
たとえば1956年の映画「流れる」では、山田五十鈴が演じる旧世代の母と、高峰秀子が演じる新世代の娘の葛藤が描かれる。

こうした映画での高峰や田中絹代、原節子らの優れた演技は、アメリカ人が見逃していた、日本の文化変容のニュアンスを表現している。
西欧化はありがたいものと決めてかかっている米映画アカデミーは、そんな複雑さを理解していない。
「アカデミー賞は決して国際的な賞ではない。とてもローカルな賞だ (The Oscars are not an international film festival. They're very local.)」
というポン・ジュノ監督の言葉を胸にきざむべきである。
ミヨシ・ウメキは、テレビドラマ「エディの素敵なパパ」の家政婦役を最後に引退した。
ウメキの息子は、のちにウメキがオスカー像の自分の名前を消し、オスカー像を廃棄したと証言している。
息子によれば、そのときウメキは、
「自分のことは分かっている。自分のやってきたことも」
と言ったという。
息子は、
「母は、オスカー像のようなものに意味がないことを、私に教えたかったんだと思う」
と言っている。
ミヨシ・ウメキは偉業をなした。
でも、次のように考えないわけにいかない。
彼女は、アジア人としてのアイデンティティーをもっと素直に出せていたら、もっと輝いただろう、と。
(終わり)
<参考>
