
認知症で文体が変わったアガサ・クリスティ
加齢や認知症が作家の文体にどう影響するか、という面白い論文が、X(ツイッター)で紹介されていた。
この論文、おもしろい! アルツハイマーになった英作家の文章がどのように変化していくのかを定量的に示したもの。語彙の多様性や文章の複雑性が減少するのは予想できそうだけど、他にもさまざまな特徴が、しかも40代からそれは始まっている、と。(Joy Watson Taniguchi 社会言語学者)
この論文、おもしろい!
— Joy Watson Taniguchi (@JoyTaniguchi) September 16, 2023
アルツハイマーになった英作家の文章がどのように変化していくのかを定量的に示したもの。語彙の多様性や文章の複雑性が減少するのは予想できそうだけど、他にもさまざまな特徴が、しかも40代からそれは始まっている、と。https://t.co/olBcYTBsy4
面白そうなので、英語は苦手だが、私も紹介されている論文をざっと読んでみた。
Longitudinal detection of dementia through lexical and syntactic changes in writing: a case study of three British novelists (「書法の語彙的・構文的変化にみる認知症の縦断的痕跡:3人の英国作家における研究」)(Oxford Academic)
筆者は、カナダのトロント大学を中心にした Xuan Le, Ian Lancashire, Graeme Hirst, Regina Jokelの4人の研究者。
研究そのものは2011年、つまり12年前の発表である。
3人の女流作家を分析
取り上げられている作家は以下の3人。いずれも英国の女流作家で、晩年まで作品を発表した。
(いまのマスコミ表記原則では、「女性作家」と言うべきだろうが、ポリコレがしゃらくさいので、あえて「女流」と書くぜ。「閨秀作家」だと、もう意味が伝わらないだろうが)
アイリス・マードック(Iris Murdoch 1919ー1999)

アイルランド出身で、哲学的作風で知られる。「鐘」「黒衣の王子(ブラックプリンス)」など。1997年にアルツハイマー病と診断され、晩年の闘病の姿は映画「アイリス」に描かれた。
アガサ・クリスティ(Agatha Christie 1890-1976)

「ミステリーの女王」と呼ばれ、ポワロやミス・マープルを主人公とした作品で有名。「オリエント急行殺人事件」「そして誰もいなくなった」など。85歳で風邪をこじらせて亡くなったが、晩年は認知症を疑われた。
P・D・ジェイムズ(P.D. James 1920-2014)

「ナイチンゲールの屍衣」「女には向かない職業」などで知られる推理小説の巨匠。94歳で亡くなるまで心身ともに健康で、認知症の兆候はなかった。(上掲論文発表時はまだ存命だったが、2011年に、「秘密 The Private Patient」を最後の長編小説として、引退を表明していた。)
本研究の目的は、文章から認知の衰えを読み取り、アルツハイマー病早期発見の手助けをすることだ。
長命な作家は、継続的に文章を残しているから、たしかにこうした研究対象としてふさわしい。
冒頭の要旨(abstract)によれば、研究結果は以下となる。
研究の結果は、認知症の兆候が被験者の書法に経時的に表れるという我々の仮説を支持するものであり、くわえて、これらの作家への新たな理解の道を開くものである。とくに、アガサ・クリスティは、最後の小説群を書くさいにアルツハイマー病を発症していたらしい。また、アイリス・マードックは、のちのアルツハイマー病発症を予告するように、40代後半から50代にかけて、文中の語彙や語法の貧困という兆候を示していた。
Our results support the hypothesis that signs of dementia can be found in diachronic analyses of patients’ writings, and in addition lead to new understanding of the work of the individual authors whom we studied. In particular, we show that it is probable that Agatha Christie indeed suffered from the onset of Alzheimer's while writing her last novels, and that Iris Murdoch exhibited a ‘trough’ of relatively impoverished vocabulary and syntax in her writing in her late 40s and 50s that presaged her later dementia.
認知が衰えた文章の特徴
いま、ケネス・ブラナーがポワロを演じる映画「ベネチアの亡霊」が公開されたばかりだが、アガサ・クリスティが認知症だったという話は聞いたことがなかった。
多くの人は、そのことに驚くのではなかろうか。

認知症により認知機能が衰えると、話し言葉と同様、文章にさまざまな影響が出る。その特徴が先行研究で明らかになっている。
必ずしも認知症でなくても、加齢で大なり小なり同じような兆候が出るのだが、認知症では、それが劇的に表れる。
語彙が乏しくなり、複雑な構文が書けなくなる、というのは予測できるだろう。
語彙やフレーズの繰り返しが多くなる。
固有名詞が減り、「アレ things」といった代用名詞がふえる。
英語でいう「left-branching clauses」が減っていく。「left-branching clauses」とは、主文(主題)の前に、条件節などを置く文章だ。
たとえば、
お前がおれより先に起きたら、おれを起こしてくれ
ーーは「left-branching clauses」の文章だが、認知機能が衰えると、
起こしてくれ、おれを。お前が起きたら。先に。
ーーのように、主題(最も言いたいこと)を先に言うようになる。構文を頭の中で組み立てられなくなるからだ。
私が面白いと思ったのは、認知の衰えとともに、受動態がふえるらしいことだ。
つまり、主語がはっきりしない、ぼやっとした文章が多くなる。
John got fired
ーーのように、「get」が多用されるのも特徴らしい。
日本語で言えば「する」とか「やる」とかがふえるのかもしれない。
最後の2作にアルツハイマーの兆候
上のような、認知が衰えた兆候を、作家の文章のなかから探し出して、定量的に分析した、というのが、この研究だ。
その結果ーー。
P・D・ジェイムズは、80歳代で書いた「秘密 The Private Patient」(2008)にいたるまで、まったく認知的衰えを見せていない。
いっぽう、アガサ・クリスティが80歳代で発表した最後の2作、「象は忘れない Elephants Can Remember」(1972)と「運命の裏木戸 Postern of Fate」(1973)には、はっきりした認知の衰えが見られ、彼女がアルツハイマー病にかかっていた可能性を示唆しているという。(ただし、生前アルツハイマー病だと正式に診断されたわけではない)
私は、認知症の兆候が見られるという「象は忘れない 」と「運命の裏木戸」両作品を読んでいない。一般にも、有名な作品ではないと思うが、読んだ人の意見はどうなのだろう。
霜月蒼の『アガサ・クリスティー完全攻略(決定版)』は、クリスティのほとんどの作品を最高五つ星で評価している。

それによると、「象は忘れない」は、意外にも四つ星の高得点だ。
「ロジカルな謎解きの妙はない」としながらも、「非常に味わい深いのだ。これはとてもすぐれたクライム・フィクションだと思う」と霜月は評価している。

いっぽう、最後の長編小説「運命の裏木戸」には厳しい。
「残念ながら、クリスティーの老いを思わずにはおれない出来」と二つ星しか与えていない。
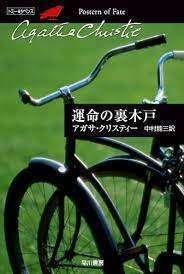
<余談>クリスティの最高作と最低作
霜月がクリスティの最低作としたのは、「フランクフルトへの乗客」(1970)だった。星は付かず、「Bomb(失敗作)」という評価だ。
私は、霜月の本でかえって興味を覚えて、「フランクフルトへの乗客」を読んだ。
本作は、ミステリーではなく、政治小説(政治スリラー)である。
アガサ・クリスティといえば、作品に執事やメイドが出てくる、ヴィクトリア朝のイメージだが、実際にはビートルズと同じ時代まで生きている。
本作は、60年代の若者文化への、クリスティの保守的反発が色濃く、そこが面白い。霜月によれば、この小説はクリスティの「ヘイトスピーチ」だという。

「フランクフルトへの乗客」も、晩年に近い作品だが、クリスティ全作品の中で例外的に「語彙が豊富」な小説だと上掲論文で指摘している。
だから、本作は「outlier 外れ値」として統計処理から除外している。これは、クリスティが特別に同ジャンルの小説をリサーチし、それらの語彙を大量に取り入れたかららしい。
なお、クリスティの死後出版された、ポワロ最後の事件「カーテン」(1975)と、ミス・マープル最後の事件「スリーピング・マーダー」(1976)は、亡くなる30年ほど前に書かれた作品である。だから、認知的な障害は見られない。
霜月は、「カーテン」を「ポワロの最後にして最高作」として五つ星を進呈している。「スリーピング・マーダー」は三ツ星半だ。
私は、どちらも最初に出たときに読んだが(当時大いに話題になった)、あまり覚えていない。
私が子供のころ好きだったクリスティ作品は、「アクロイド殺し」と「ABC殺人事件」。どちらも初期の作品だ。
ほかの作品はもうあまり覚えていないし、映画やドラマの印象と頭の中でごっちゃになっている。
「アクロイド殺し」を最初に読んだときの印象だけは鮮明なので、私はこれを最高作としたい。
映画、ドラマでは、最近になってケネス・ブラナーの「オリエント急行殺人事件」を見たが、もうひとつだった。
むしろ2015年の英ドラマ「そして誰もいなくなった」がよかった。アマゾンプライムで見られたやつ。

「ベネチアの亡霊」(原作は「ハロウィーン・パーティ」)はどうなのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
