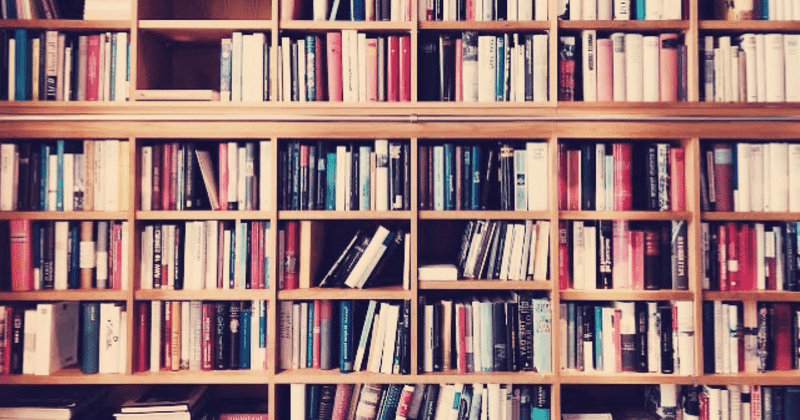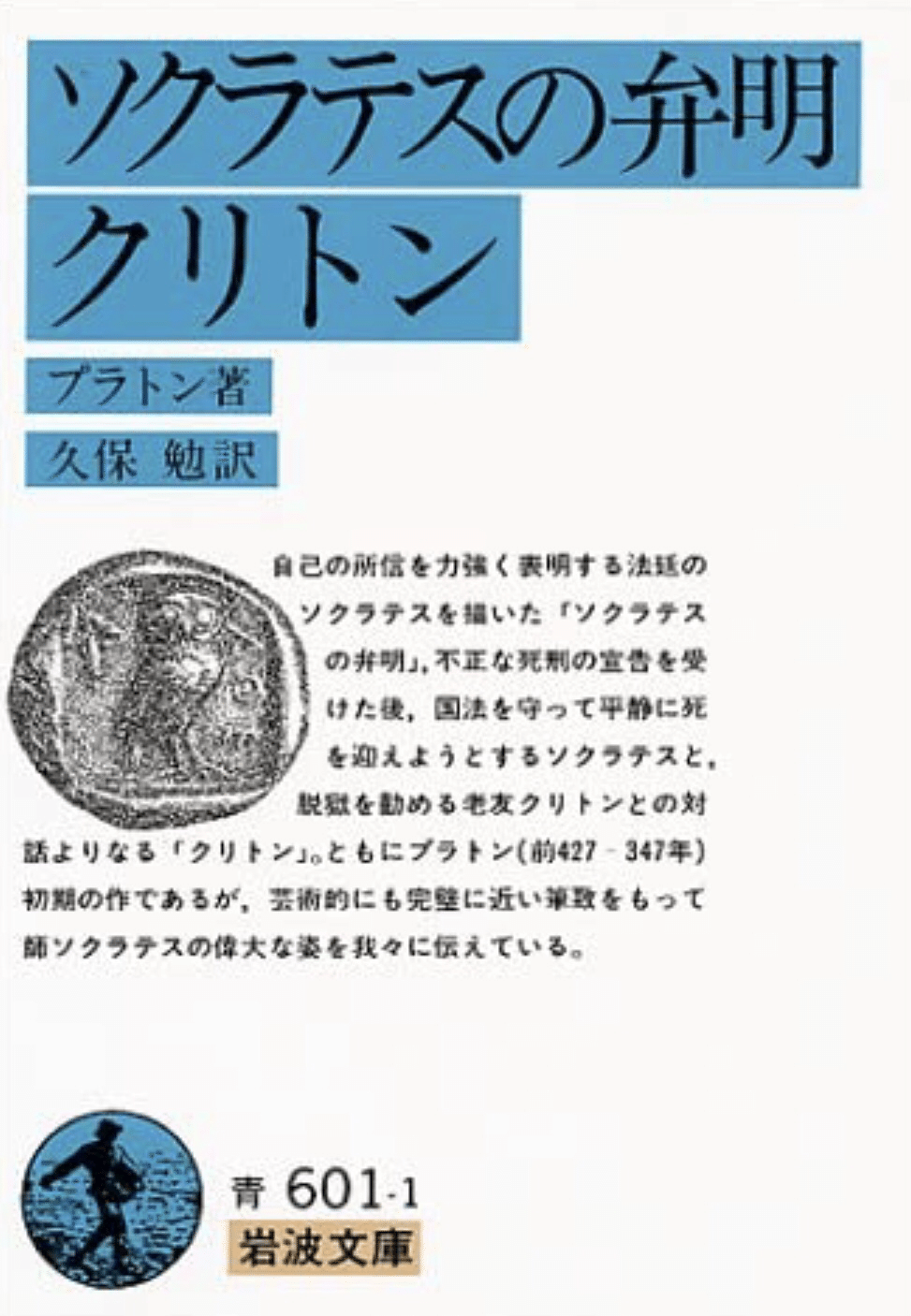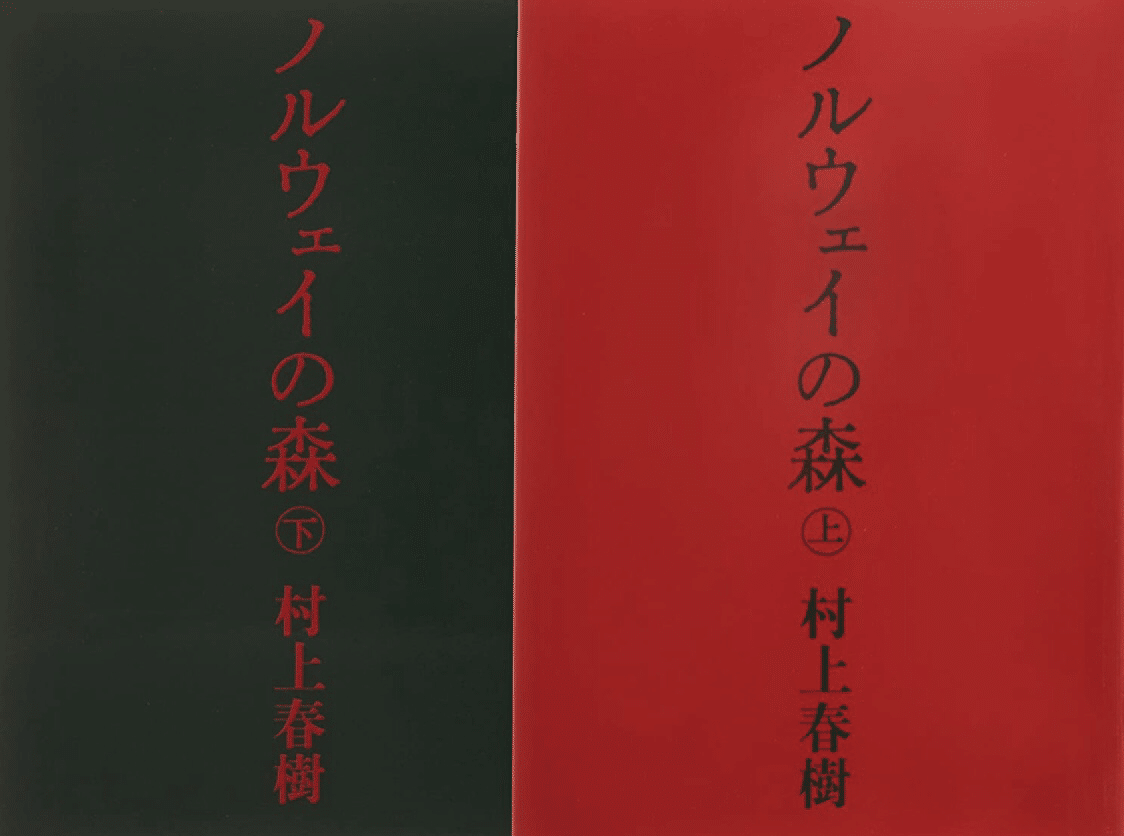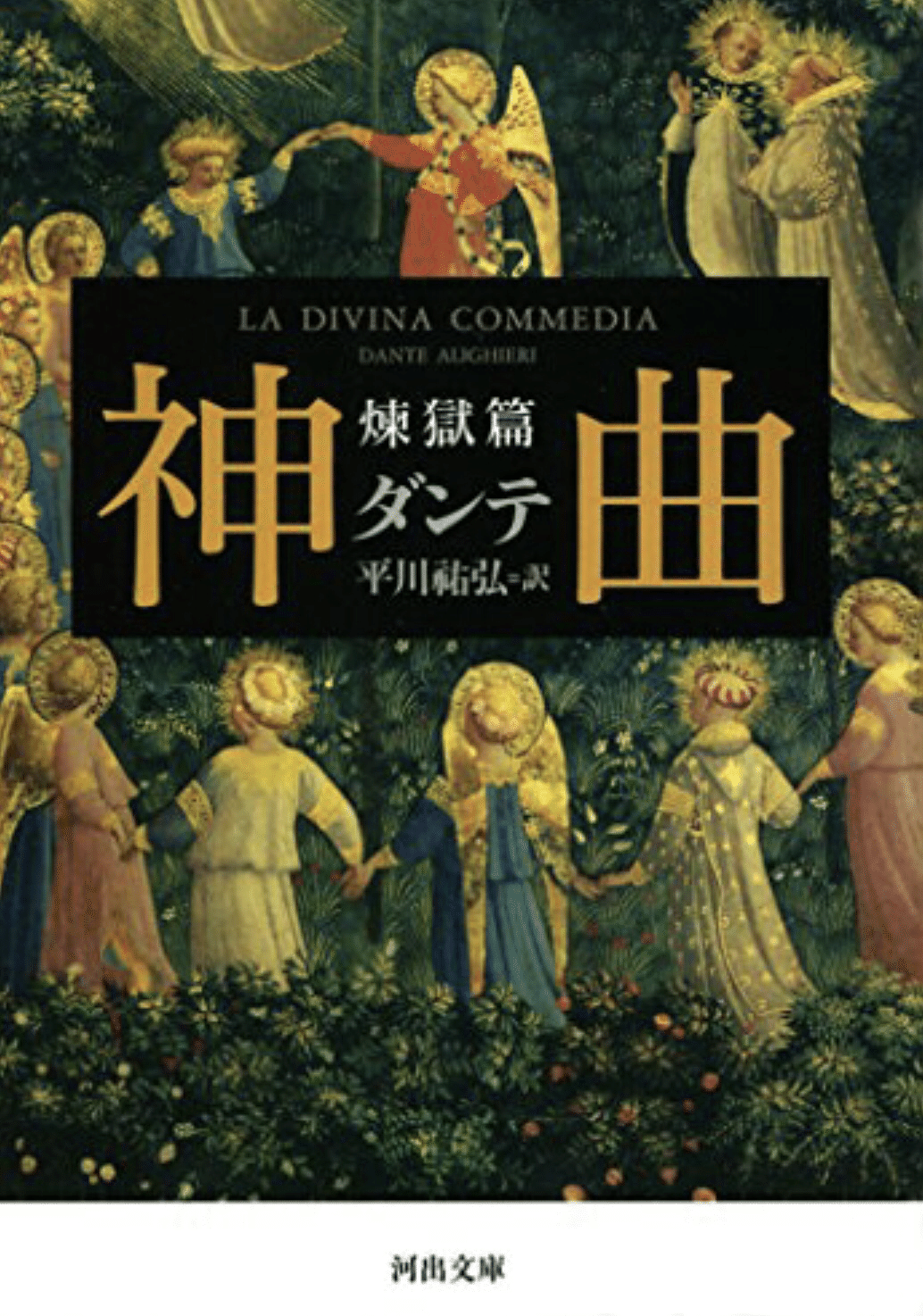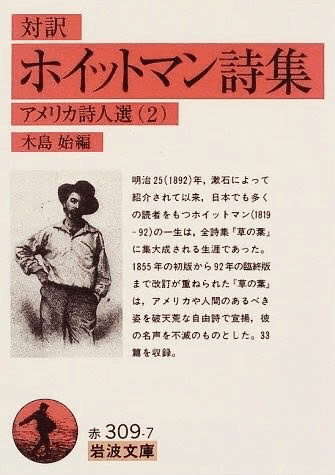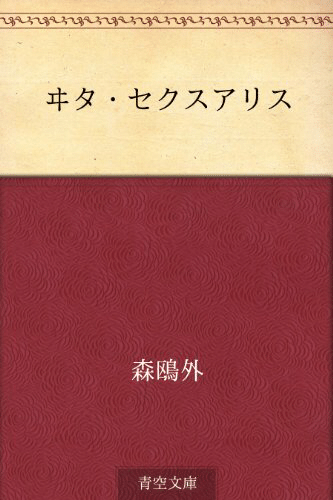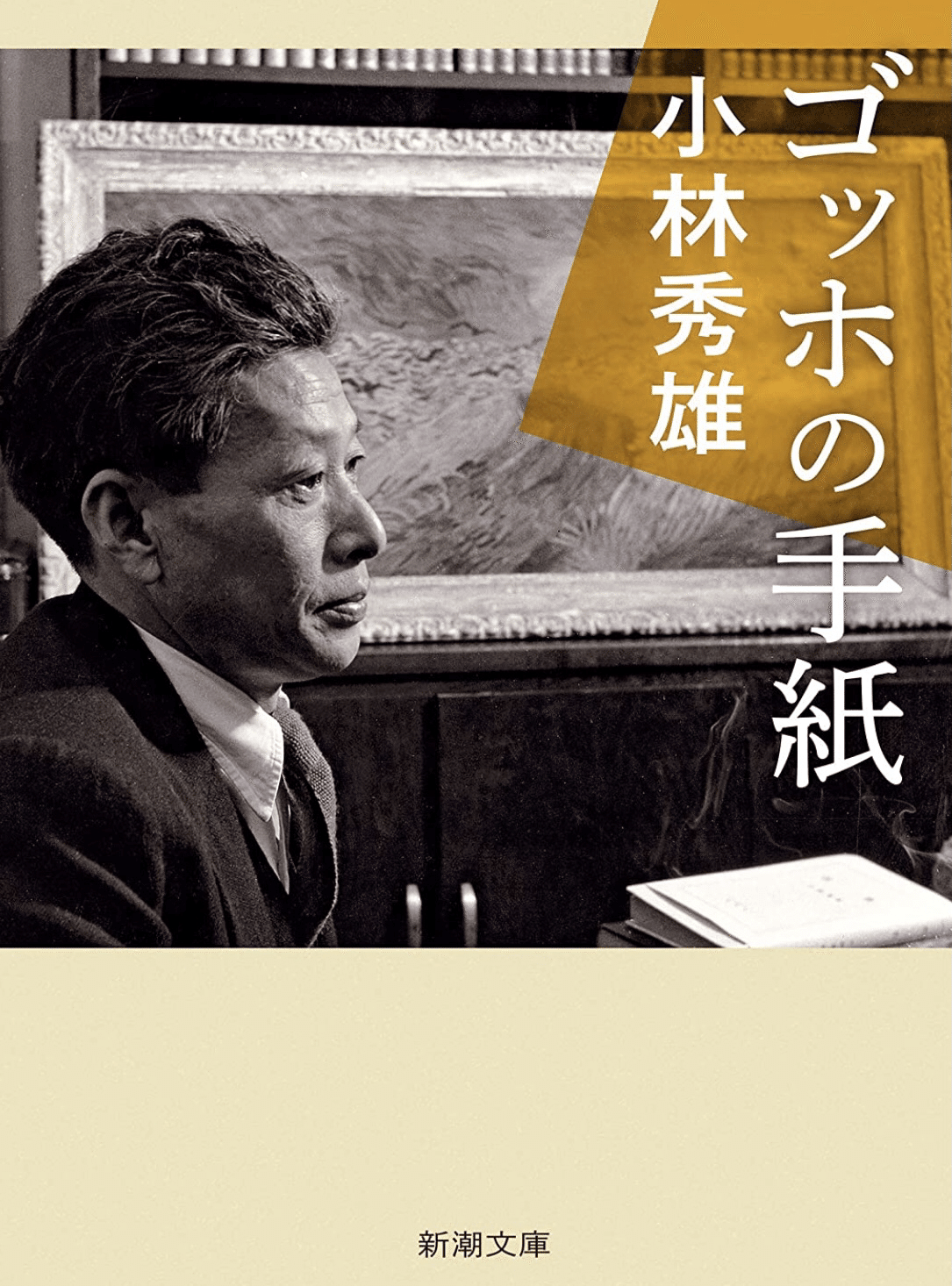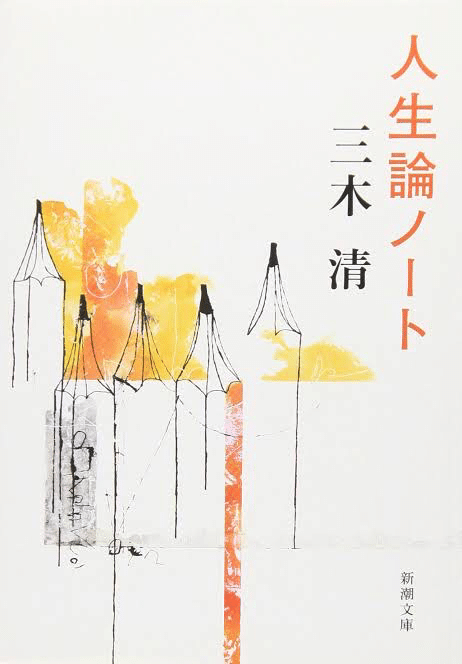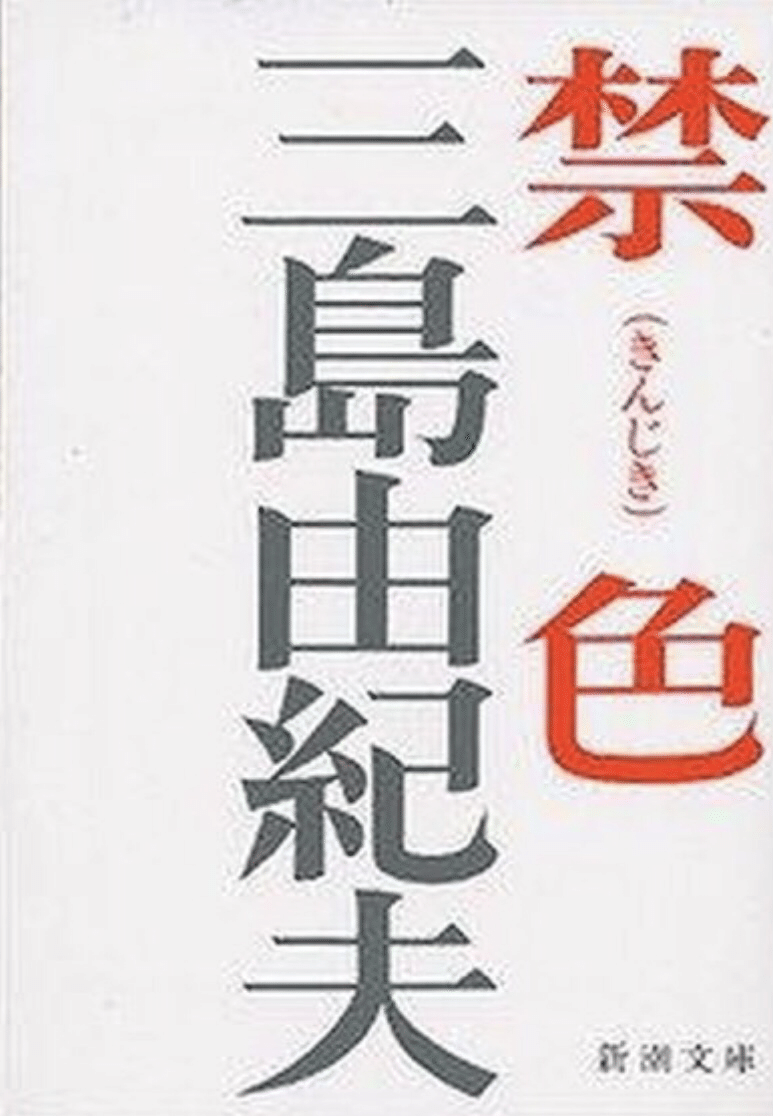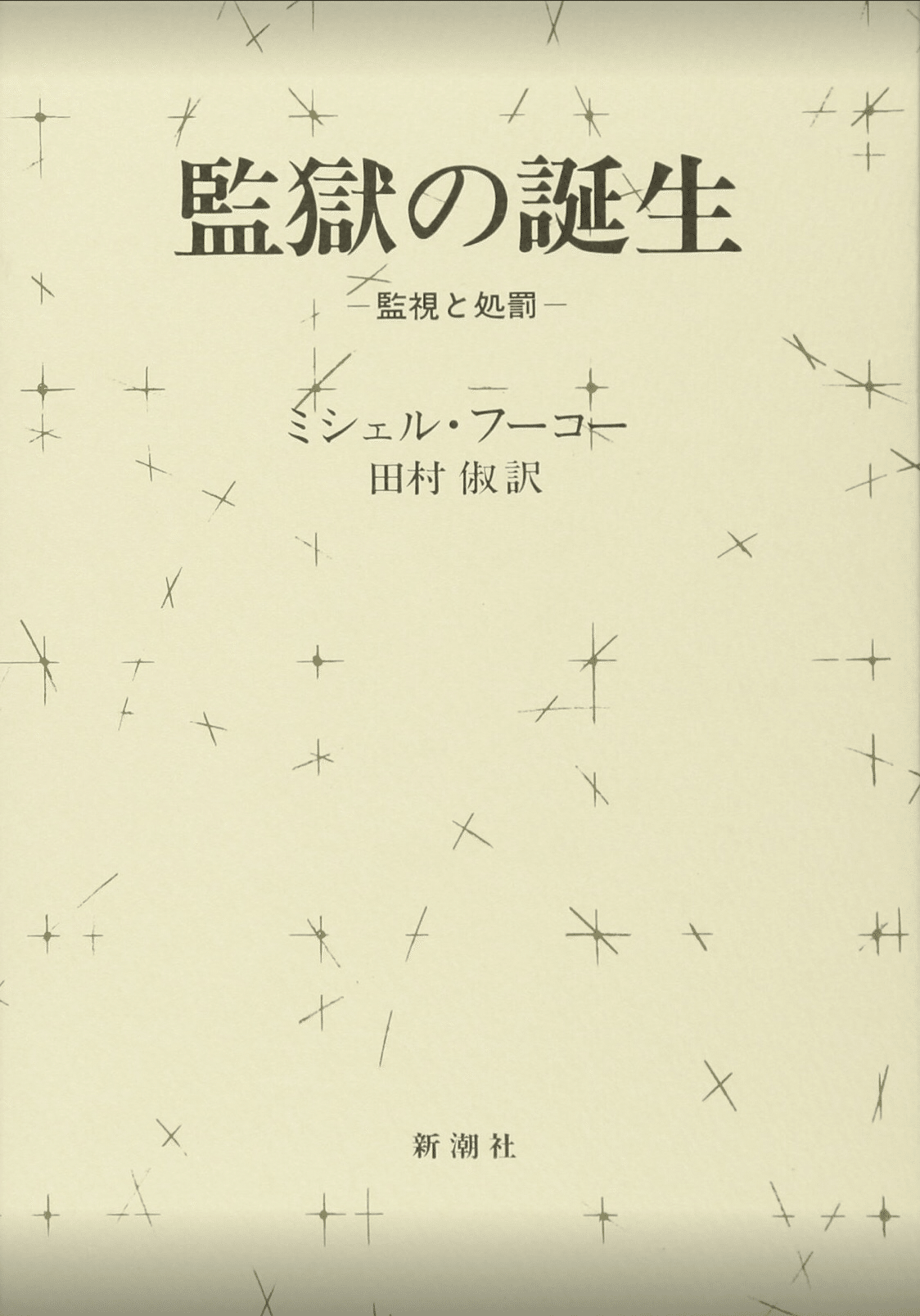#読書
「ライフシフト」リンダ・グラットン
人生という極めて個人的で限定的な所有時間は、マクロ的視点によって策略的に高齢化の実態と思考変化を求められる書。批判的かつ客観的に必読すべき。
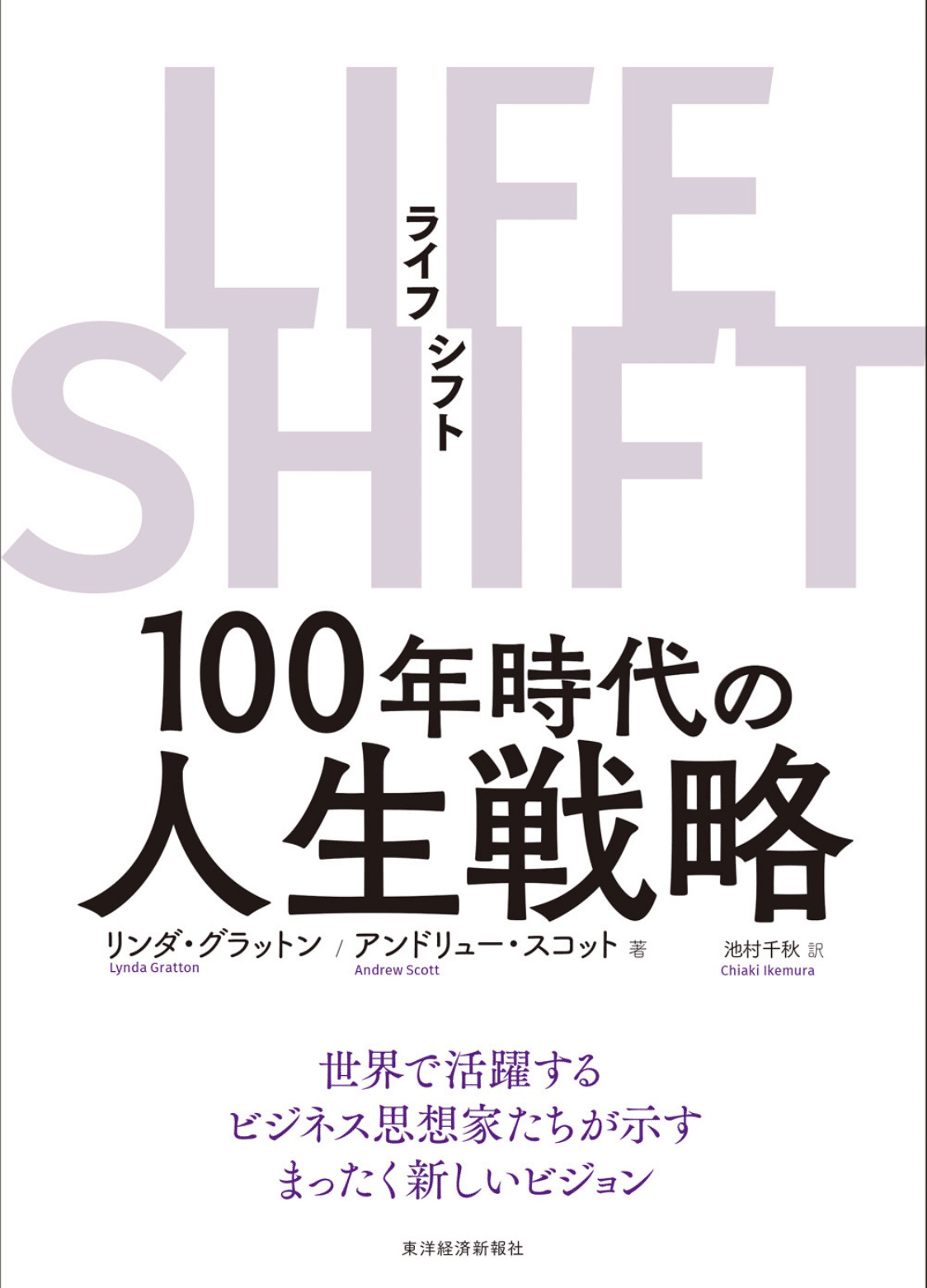
「ツァラトゥストラはこう語った」フリードリヒ・ニーチェ
ニーチェを単体で読んでいけない。
丹念にその遺伝子を辿ると、単なる発狂した変人ではなく、そこに至る軌跡があり、その頂上がある。それこそがツァラトゥストラ。
つまり、ニーチェの哲学と思想と詩が凝縮した孤高の傑作であるのだ。
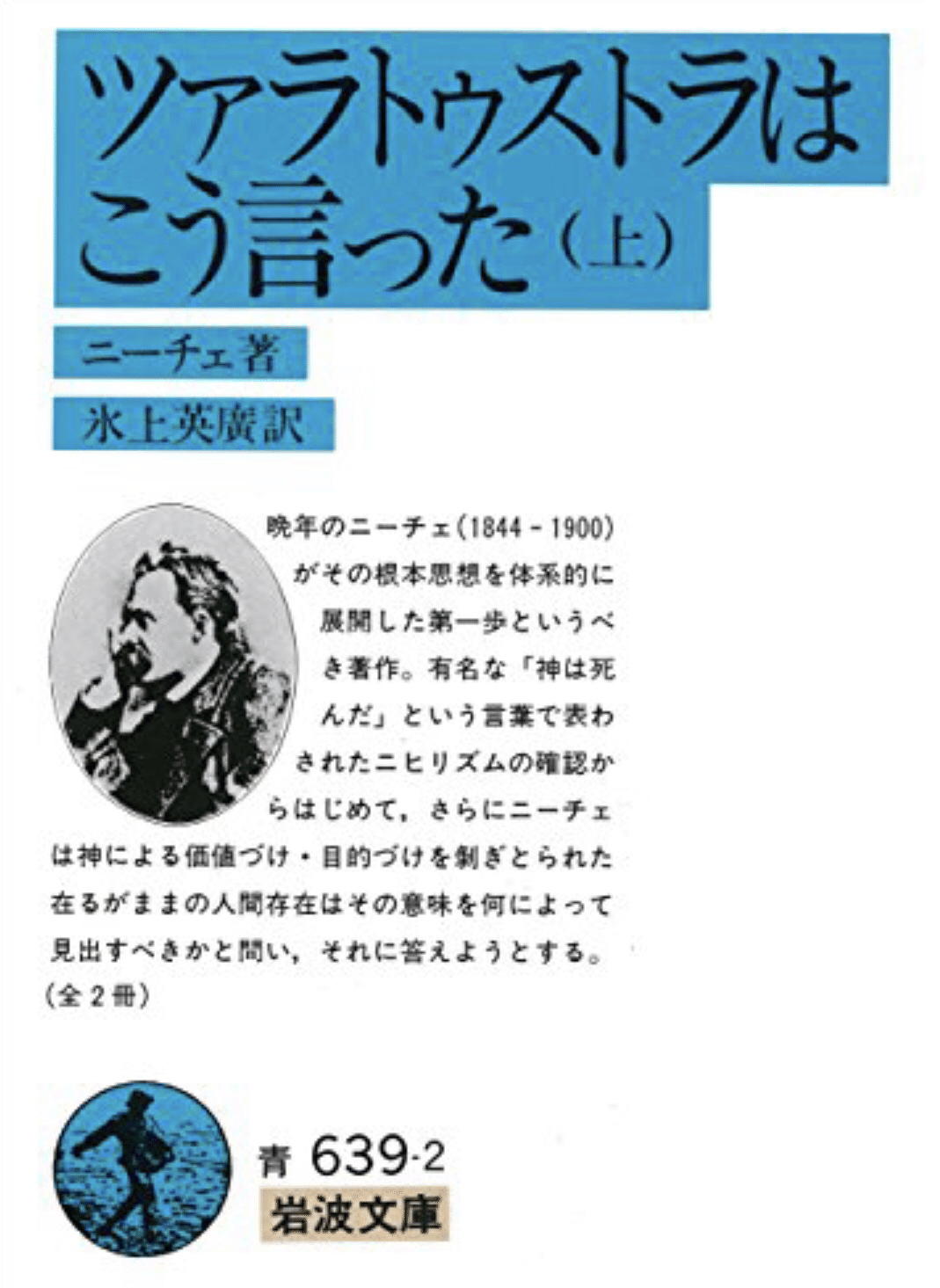
「トニオ・クレーゲル」トーマス・マン
20世紀のゲーテとも評されたドイツの大文豪の若き日の傑作。芸術家とは何か?市民とは何か?
芸術という結論なき理想と現実に揺れる主人公に、幾度自らを重ね合わせたことであろう。