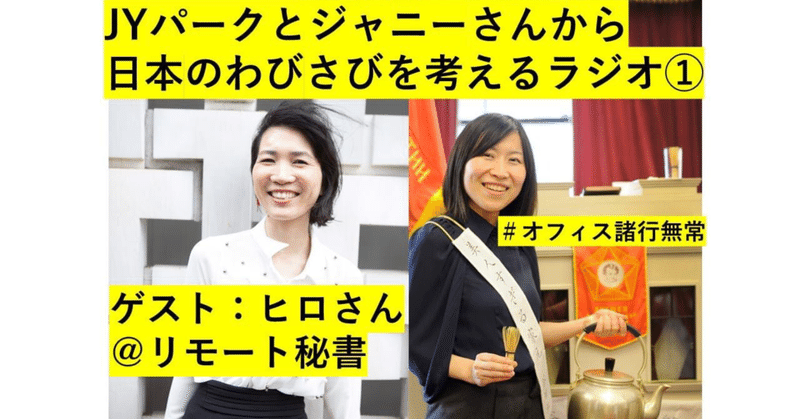#茶道
少年隊ニッキが語るジャニーさんが、ほぼ千利休である件
友達が教えてくれた、少年隊ニッキのインタビュー記事がすごい
https://ab.jcci.or.jp/article/758/
ニッキ 名言
「あの人(ジャニーさん)は、ちっともアイドルを
作ろうとしなかった」
かっけーー!
千利休が、陶芸家ではなく瓦職人に茶碗を発注したのを思い出しました!!!!
アイドルを育てるのが目的になっちゃダメ
ジャニーさんは、舞台から伝えたいことを表現できる
侘び寂びは日本にあって、中国には無いわけ
メモメモ
侘び=不完全な状態 点
寂び=時間経過 線
ワビサビとは
欠陥品や、劣化した陶磁器を愛でる日本の
狂気!
一方
台湾の国立故宮博物院で
中国の陶芸史の展示を見たら
中国の陶芸家、官僚みたいな顔して
完璧な納品を目指して作業してる絵があってビビった
少しでも不完全なところが見つかると
皇帝に捨てられちゃう中国
日本では、中国の皇帝たちに投げ捨てられるような器を珍重するトンデモ
茶道にのめりこんだ阪急社長・小林一三、戦時中に手に入れた壮絶な茶道具とは
阪急、宝塚、東宝など作りつつ茶人だった小林一三の記念館が大阪府池田市にある。2013年での展示レポ。
1945年6月。神戸大空襲でやられた店舗を見に行った小林社長が、焼夷弾をみつけた。
そしてのちに茶道で花をかざる入れ物にしたと!!
しかも名前を「復興」にしたんだと…!!!!!!!!
戦国武将の中で流行った茶の湯。本来はこういった世界観で構成されてたはずだ。戦国時代、敵の矢が飛びまくる竹藪
ラッパーを目指していたOLが、茶人に転向した理由
「もう来月から来なくていいよ」音楽仲間から声をかけられた。いつかそう言われるんじゃないかと思っていたセリフがどんぴしゃで降りかかってきた。
クラブ仲間にリストラされた!200年代前半、小さいクラブがたくさんあった時代。毎月1回平日の深夜、小さな音楽イベントを友達と企画していた。まだYOUTUBEもそんなに普及してなかった時代、DJは足繁くレコード屋に通い直接レコードを買っていたもんだ。今なら
秀吉にリストラされない工夫 #オフィス諸行無常
綿抜豊昭「戦国綿抜豊昭「戦国武将と連歌師」より
連歌エピ
●連歌会で秀吉が「蛍が鳴く」と詠む
●添削する連歌師が「蛍は鳴かない」と指摘→空気が悪くなる
●細川幽斎が咄嗟に「蛍が鳴くって古歌聞いたことある」とフォローして、場の空気なごむ
●実はそんな歌はなく、連歌師が殺されないように幽斎がでっち上げたデマw
#戦国武将の気苦労ww
↑
細川幽斎でさえ、上司のフォ