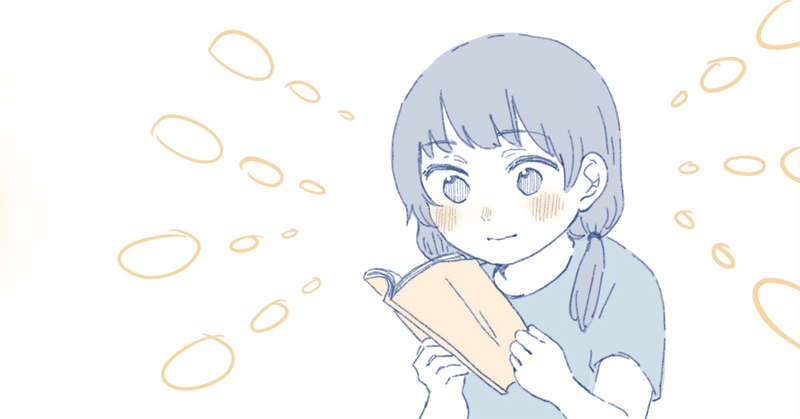
人間理解から自己理解、自己理解から自己充足へ|「私」ってなんだろう?(哲学・心理学)
私と呼べるものって一体なに?
下の一つ一つの言葉に対して、
「私の体とは言えるけど、
私イコールからだと言えるかどうか?」
「私の存在とは言える?
私イコール存在はどうだろうか?」
みたいな感じで考えてみてください!
しっくりくるかどうか直感で!
多分、私は私という存在っていう言葉だけは絶対しっくりくると思います。
私の体 私=体 私=私という体
私の脳 私=脳 私=私という脳
私の心 私=心 私=私という心
私の感情 私=感情 私=私という感情
私の思考 私=思考 私=私という思考
私の行動 私=行動 私=私という行動
私の存在 私=存在 私=私という存在
私が考えてみた結果、次のようになりました。
多分一人ひとり感じ方が異なると思うので、全然これとは違っても大丈夫です!
私の体◯ 私=体× 私=私という体△
私の脳◯ 私=脳× 私=私という脳×
私の心◯ 私=心× 私=私という心△
私の感情◯ 私=感情× 私=私という感情×
私の思考◯ 私=思考× 私=私という思考△
私の行動◯ 私=行動× 私=私という行動×
私の存在◯ 私=存在△ 私=私という存在◯
ということで、私の体(体は私を構成している)っていう風には言えるけど、私は(=)体というふうには言えない気がします。
そして、私の脳も心も感情も思考も行動も、私自身とイコールにはならないんですけれども、
「私」という存在は「私」とイコールで捉えられるんです。存在という言葉を用いると、私そのものを表すことができる。
つまり、私の
体
脳
心
感情
思考
行動
このようなものを全てひっくるめて
「私」全体として統合したものが
「私」という存在なんだというふうに
考えていきたいと思います。

人間理解を深めよう
身体を私という存在の構成要素として、
脳を私という存在の構成要素として、
心を私という存在の構成要素として、
感情を私という存在の構成要素として、
思考を私という存在の構成要素として、
行動を私という存在の構成要素とする。
このようにして多くの要素が
複雑かつ複合的に絡み合って
できあがった存在が、
他の生物とはかなり性質の異なった
ヒトという生き物ということです。
「幸せとは脳内物質のセロトニンやオキシトシン、ドーパミンの働きが促進された状態だ」というようにヒトという生き物の幸せをシンプルに定義していたのが『精神科医が見つけた3つの幸福』という樺沢紫苑さんの本なのですが、
そのようにシンプルに考えるのは「日々良い気分で楽しく過ごしていく」ためにとても有用だと思っていて、
でも「考える存在」である人間として、
もう少し幸せっていうのは
私の体
私の脳
私の心
私の感情
私の思考
私の行動
というようなその人自身の
たくさんの要素が複雑に
絡み合った状態なのではないかというふうにも考えられると思います。
なので、自分の身体を見つめ直す
気持ちや気分を見つめ直してみる
普段何を考えているか振り返ってみる
どんな行動をしていきたいか考える
そんな総合的な視点を持つことが
豊かな人生に繋がっていく、
そんな気がしています。
自分と自我と自己と他者|アイデンティティ=自我同一性とは
次に「自己」と「自我」
というものを考えてみます。

まず、「自分」という言葉は
他者と私を「分けられたもの」として
分類して捉えることで、
「他者」と「私=自分」に分けたもの
という、他者と私を区別するための
便利な言葉です。
そもそも、言葉というのは
もともと分けられていないこの世界の
あらゆるものに対して分類を行なって、
理性を通して何かを「分かる」ために
用いられるようになった、作られた道具。
この言葉を用いた思考を操ることで、
人は物理的なまとまった世界を
細かく区切って解釈・意味づけしています。
宇宙のまとまりの中で地球があって、
星・星座があって、
地球には塩水が張られた海があって、
空が見えて、
山があって、村があって、
動植物が存在していて、人もいる。
そんな風にして言葉を通して現実を
切り分けて考えていくことで
私たちの脳は発達してきたわけです。
そうして「他者」と「私」も区別するようになった。
さらにルール分けされた言葉を見ていくと、
私を自分から見たものを「自我」という風に
呼ぶ呼び方があって、
さらに他者から見た私も合わせると「自己」
というふうに呼びます。
自我同一性というのは
発達心理学の中で、
自分から見た私、「自分とは何者か?」
という問いへの答えを
青年期に獲得していくというもの。
自分自身が何者かということを
考えて、体感して、
「こうやって生きていく」という
イメージをなんとなく持っておく
というのが自我同一性。
その自我同一性(アイデンティティ)は
自分と他者と切り分けられる独自性や、
時間軸に沿った連続体としての自分を見つめられる一貫性・何かの社会に属している所属性
などの性質を含むと言われています。
アイデンティティ(自我同一性)は重要なもの?
ということで、
私という存在は体や脳、心・感情
思考・行動など様々な要素で成っていて
さらにそのような私という存在は
自分として他者とは切り分けられた「私」
として存在していると考えられます。
その中で、
他者から見た私と自分から見た私
など複数の視点から見た「私」が
存在しているわけですが、
自我同一性(アイデンティティ)の確立
すなわち自分から見た「私」をある程度
はっきりとした特有の「私」として自己認識
することが、青年期の課題とされています。
これがアイデンティティ(自我同一性)の確立と呼ばれるもの。

(図左上)
「自己」は他者からの自分の見え方なども
総合して考えられる概念で、
人が自然と他者からの評価や承認を意識したり
自我と人からの見え方の推測などを総合して
すり合わせられた自己認識というものができ、
こんなふうにして私という存在=自分が
自分自身から認識されるわけです。
ここまで人間観についてかなり長ったらしく
色々なことを言ってきましたが、
最終的に何を言いたいかと言うと
まずアイデンティティの確立っていうものは
めちゃくちゃ難しい気がするし、
自分って何?とか言われても
答えられない人が90%だと思います。
そして、その私=自分という存在は
行動・思考・感情・身体など本当に
色々な要素でできあがっているので、
そもそも何をしている人だとか、
どんな身体的特徴の人だとか、
こんな考え方を持っている人だとか、
一言で片付けることができないので
総合的に考えていく必要があるということです。
そもそも、確固とした絶対的な自分
みたいなものは無く、全て後から言葉で
付け足された解釈なので、
どんな言葉で自分を説明したっていいです。
言葉は万能でないので、
ただ自分自身を理性で捉えてみることに
挑戦する。そのことに価値があります。
また、自我同一性(アイデンティティ)
は自分で考えるのが凄く難しいものなんですが、
だからといって思考を放棄するのはもったいない
と思います。
なぜかというと、「自分軸」というものを
持って行動していくために、この「自我=自分から見た自分」
というものが必要になるからです。
仮に自我ではなく、
自己を形成している他者からの視点を
気にしすぎたりしたら、
全て周りの評価や承認・見え方に依拠した
「他人軸」で行動してしまうことになります。
これでは、コロコロと変化する周りからの
見る目、コントロールできない周りからの評価を
常に気にして、
不安定な承認欲求の報酬と
周りから認められない不安感と共に
生きていくことになります。
この周りから認められたいという気持ちが
悪というわけではないのですが、
その前に行動指針となる「自分軸」を
持っておらず他人軸だけを基準にしていると
外部の環境に気持ちを左右される辛い生き方に
なってしまうという可能性があります。
前を向いて生きていくために
自我同一性(アイデンティティ)の話に戻ると、
私=自分という存在を自分が現在どう捉えているか
という自我は、現在までの記憶の中にあるもので、
自分がこんな感情を感じて、こんな風に考えて
こんな行動をしてきて、こんな見た目で過ごしてきた
というイメージが記憶の中で
様々な連続した体験をもとに、
自分の意図的/無意識的な解釈を通しながら
形成されてきたものです。
そして、この瞬間どんな風に自分を見ているのか
ということはとりあえず言語化することで形に
することができます。
その言語化したものもあくまで解釈に過ぎない
ので、深く考え込まずになんとなくで大丈夫です。
簡単に考えて、自分を捉えてみれば良い。
(なんなら、別に自分が何者かなんて考える必要ないという人なら、アイデンティティについて深く考えなくても大丈夫です。)
「ありのままの私・自分らしさ・自分探し」
みたいな言葉って、なんかよくわからないし
言葉がひとり歩きしているような感覚で
必要なものなのかどうかも分からない、
そんな気がしていたんですが
今まで考察してきた人間観みたいな感じで、
私=自分という存在についてもっと
ちゃんと知っておきたいなら深掘って、
別に考える必要ないと思うなら考えなくてもいいんじゃないかなと思いました。考える余裕があるならちょっと考えてみてくださいね。
私がもっと重要だと思うのは、ここから
先で書いていくことや、下の記事で説明した
ようなことです。
自分にとっての「私」は自我なわけなんですが、
これは現在まで、もっと言うと全て過去の記憶で
できあがった自分像(自分から見た)になります。
そこで、今の自分に何が必要かと言うと、
自分が何を重要だと思っているのか、
自分が何を好きなのか、得意なのか、
自分がどんな人生を送っていきたいのかということです。
なぜこれを考えるのが必要かというと、今の自分にとって過去のことはもう過ぎ去ったことで、手を伸ばして触ることのできないもの。
自分の手が届くのはまだ確定していない現在から見た未来のことだけだからです。
今までの記憶の中で、
自分が何を大切にしたいのか
どのようなことを最優先事項としていきたいのか
ということが価値観として形成されてきているはずです。
ということは、私たちはただ
これらの価値観に従って、より良い未来を
作っていくということだけに集中すれば良いんです。
ということで、さっきまで話してきたことは過去に焦点を当てたアイデンティティの話だったんですが、大事なのは今この瞬間から先の、未来の自分のためにどうしていきたいかという「自分軸」の話です。これが行動指針となって、ある程度ブレない方向性を定めてくれます。
まとめ:終わりを思い描くことから始める
みなさんにお伝えしておきたいことをまとめると、
私という存在は
体
脳
心
感情
思考
行動
などの要素を色々総合してできています。
そこで、今の私という存在を
定義するのは過去から現在までのすべての要素。
そして、
今の私に唯一必要なのは
過去の出来事は関係なしに、
未来の私はどんな私であってほしいのかということ。
現在までに形成された自分の価値観を
見つめて、
すなわち自分が何を重要だと感じていて
何が好きで何を最優先事項としたいのか。
行動していく中で、
行動を決めていく思考の中で、
行動・思考の結果である感情の中で、
私という存在がどんなものであってほしいか
何を追求する人でありたいのか
というイメージを持つことです。
なんか難しいことを言っている気がするので、
最後に『7つの習慣』という本の第二の習慣
「終わりを思い描くことから始める」
という行動指針を提示しておきます。
自分が人生の最後、息を引き取る瞬間に、
人生を振り返ってどんな人生だったら
幸せだったと思えるのか、
逆に、絶対こんな人生は嫌だという人生
(最悪のパターン)や、
周りの、死を見守ってくれている人たちに
この人はどんな人だったねという風に言われたいのか(これは他人軸かもしれませんが良いと思います)
例えば家族を大事にして生きてきた自分とか
健康に常に気を使って生きてきた自分とか
野球一筋の人生だったとか
趣味の映画鑑賞を極めた人生だったとか
誰々とたくさん時間を過ごせて幸せだったとか
たくさん寝て、たくさん美味しいもの食べて、
良い人生だったとか
やりたかった仕事が後半やれて良かったなとか
ディズニーランドにたくさん行けたとか
病気がちだったけど気を使ってくれる人とか多くて悪くない人生だったなとか
いろんなことを学べて楽しかったなとか
くだらないことばっかやったけど、あんな毎日でも今の自分にとっては意味があったなとか
そんなふうにして人生最期の瞬間に
肯定的にマルを付けてあげられるような
人生にしていけるといいですよね。
そんなイメージを未来の私に続く
一本線の軸として持っておいて、
主体的に行動していくことで
自分がこんなふうがいいなと思う
人生を作っていくこと。
個人的にこれが大事だと思っています。
ぜひ、「終わりを思い描くことから始めて」
みてください!
趣味全開のダラダラとした文章を最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!(^_^;)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
