
地方映画史研究のための方法論(31)大衆文化としての映画⑤——鶴見俊輔による限界芸術/大衆芸術としての映画論
見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト
見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト
杵島和泉さんとの共著『映画はどこにあるのか——鳥取の公共上映・自主制作・コミュニティ形成』の刊行記念講座として、2024年6月8日(土)に鳥取県立図書館で、鳥取大学サイエンス・アカデミーVol.546「映画はどこにあるのか——鳥取の映像文化を支える人びと」を実施する。

講師|佐々木友輔(鳥取大学地域学部准教授)
杵島和泉(神戸大学大学院)
日時|2024年6月8日(土)10:30-12:00
一般向け、聴講無料、事前申し込み制
(申込〆切 6月7日(金)正午まで)
場所|鳥取県立図書館 2階 大研修室 ※各図書館へライブ中継あり
zoomを利用してご自宅でも視聴できます。
後日のオンデマンド配信はございません。
詳細|https://www.core.tottori-u.ac.jp/2024/05/24/12189/
講座では、県内に映画館が4館しかない鳥取で、自主的な上映活動を通じて豊かな映画文化を作り上げてきた人々を紹介すると共に、そうした草の根的な取り組みが、日本の映画史を考える上でも重要な価値や意義を持つことを論じる。SVODの普及、映画館の危機が語られる今、自主上映という営みを通して、あらためて映画を「見る場所」の問題を考える機会としたい。
見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト
「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」、「見る場所を見る3——アーティストによる鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」を開催した。
2024年3月には、杵島和泉さんとの共著『映画はどこにあるのか——鳥取の公共上映・自主制作・コミュニティ形成』(今井出版、2024年)を刊行した。同書では、 鳥取で自主上映活動を行う団体・個人へのインタビューを行うと共に、過去に鳥取市内に存在した映画館や自主上映団体の歴史を辿り、映画を「見る場所」の問題を多角的に掘り下げている。(今井出版ウェブストア/amazon.co.jp)
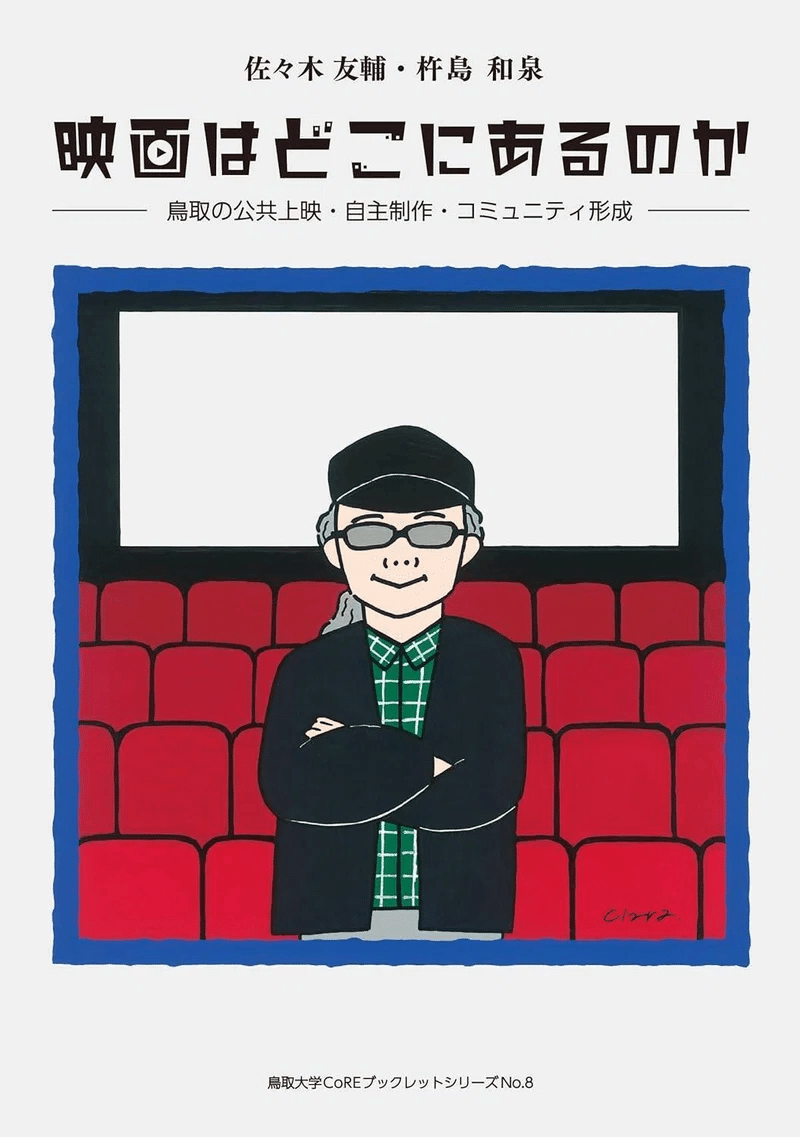
『映画はどこにあるのか——鳥取の公共上映・自主制作・コミュニティ形成』
今井出版、2024年
地方映画史研究のための方法論
「地方映画史研究のための方法論」は、「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」の調査・研究に協力してくれる学生に、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有するために始めたもので、2023年度は計26本の記事を公開した。杵島和泉さんと続けている研究会・読書会で作成したレジュメをに加筆修正を加えた上で、このnoteに掲載している。年度末ということで一時休止していたが、これからまた不定期で更新をしていく予定。過去の記事は以下の通り。
メディアの考古学
(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法
(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』
(03)エルキ・フータモのメディア考古学
(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論
観客の発見
(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論
(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論
(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」
装置理論と映画館
(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」
(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』
(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論
(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法
「普通」の研究
(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』
(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』
都市論と映画
(14)W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』
(15)W・ベンヤミン『パサージュ論』
(16)アン・フリードバーグ『ウィンドウ・ショッピング』
(17)吉見俊哉の上演論的アプローチ
(18)若林幹夫の「社会の地形/社会の地層」論
初期映画・古典的映画研究
(19)チャールズ・マッサーの「スクリーン・プラクティス」論
(20)トム・ガニング「アトラクションの映画」
(21) デヴィッド・ボードウェル「古典的ハリウッド映画」
(22)M・ハンセン「ヴァナキュラー・モダニズム」としての古典的映画
抵抗の技法と日常的実践
(23)ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』と状況の構築
(24)ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』
(25)スチュアート・ホール「エンコーディング/デコーディング」
(26)エラ・ショハット、ロバート・スタムによる多文化的な観客性の理論
大衆文化としての映画
(27)T・W・アドルノとM・ホルクハイマーによる「文化産業」論
(28)ジークフリート・クラカウアー『カリガリからヒトラーへ』
(29)F・ジェイムソン「大衆文化における物象化とユートピア」
(30)権田保之助『民衆娯楽問題』
鶴見俊輔『限界芸術論』
鶴見俊輔(1922-2015)

鶴見俊輔(つるみ・しゅんすけ、1922-2015)は、東京都出身の思想家・哲学者・評論家。アメリカのプラグマティズムを日本に紹介する仕事や、大衆文化の研究・評論など多岐にわたる執筆活動を行い、戦後を代表する知識人・文化人として知られる。
鶴見は16歳でアメリカに渡り、ハーバード大学で哲学を学んだ。在学中に太平洋戦争が勃発したため、捕虜交換船で帰国し、1943年に海軍軍属としてインドネシアのジャワ島に赴任。敵国放送の翻訳を任されたが、病のため帰国して敗戦を迎えた。1946年には、政治学者の丸山真男、経済学者の都留重人らと雑誌『思想の科学』を創刊。国外の思想動向の紹介、戦時中の知識人の「転向」問題に関する議論、生活綴方運動の推進、「普通の人々」からの論文募集など、敗戦後の日本が進むべき道を問う誌面作りを続けた。また1965年4月には、高畠通敏、小田実らと共にベトナム戦争に反対する運動団体「ベトナムに平和を!市民連合」(ベ平連)を結成。非暴力を原則とし、上下関係を作らず誰もが参加できる社会運動を目指した。
主な著作に、『大衆芸術』(河出新書、1954)、『限界芸術論』(勁草書房、1967)、『日常的思想の可能性』(筑摩書房、1967年)、『不定形の思想』(文藝春秋、1968年)、『戦時期日本の精神史』(岩波書店、1982年)、『戦後日本の大衆文化史』(岩波書店、1984年)、『アメリカ哲学』(こぶし書房、2008年)など。
限界芸術論の始まり——「芸術の発展」(1960)
鶴見俊輔が「限界芸術」という言葉を思いついたのは、1955年頃のことだという。1956年の座談会「文化と大衆のこころ」(日本読書新聞、1967年1月1日号)で初めて活字にし、その後しばらく構想を温め、1960年に刊行された『講座・現代芸術 第1巻 芸術とは何か』(勁草書房)所収の論考「芸術の発展」で、まとまった考えが示された。同論は1967年に単著『限界芸術論』(勁草書房)に収録された他、鶴見の著作集や文庫本、大衆文化に関するアンソロジー本などにも繰り返し掲載され、現在まで広く読まれている。本稿では、『限界芸術論』(ちくま学芸文庫、1999年)所収の「芸術の発展」を参照し、限界芸術とはいかなる概念かを確認した上で、それと鶴見の映画論との関係性を見ていくことにしたい。
純粋芸術/大衆芸術/限界芸術
「芸術の発展」の冒頭、鶴見は「芸術とは、たのしい記号」(p.10)であると言う。あるいはそれは、「美的経験を直接的につくり出す記号」(p.10)である。例えば、食事をするために労働して食費を稼ぐことは——労働行為そのものに価値があるのではなく、食事をすることに価値があるという意味で——間接価値的経験だが、町並や空を見て美しいと感じたり、歌謡曲を聴いたり、展覧会で美術作品を鑑賞することは——その行為自体に価値がある美的経験であるという意味で——直接価値的経験だと言えるだろう。人びとは美的経験によって日常的な利害を忘れ、日常的な世界の外部に連れ出され、休息を得ることができる。以上のように、美的経験を直接的に提供してくれるものであると共に、他の日常的経験と区別される「完結性」と「脱出性」を持つことが、さしあたり、鶴見の定義する芸術の特徴である。
またそのように考えるなら、人びとが日常的に出会う美的経験は——美術館やコンサートホールで味わうような——所謂「芸術作品」とは無関係なものが大半を占めることになるだろう。そのような、狭義の「芸術」の範囲をはるかに超えた美的経験の広がりを考察するために、鶴見は新たに三つの概念を導入することを提唱する。
一つは「純粋芸術 Pure Art」。これは従来の意味での「芸術」を呼び替えたもので、専門的芸術家によって制作され、分野ごとに精通した専門的享受者を持つことが特徴である。
続いて「大衆芸術 Popular Art」は、純粋芸術と同様に専門的芸術家によって制作されるが、その制作過程においては企業との合作というかたちが採られ、またその享受者は非専門的な大衆である。こうしたものは従来、純粋芸術と比べて俗悪で非芸術的なニセモノ芸術と見做されてきた。
最後に「限界芸術 Marginal Art」は、非専門的芸術家によって制作され、非専門的享受者によって享受される。前二者よりも広大な領域に広がっており、芸術と生活との境界(marginal)に位置するものが、限界芸術と呼ばれるのである。
根源的な芸術としての限界芸術
鶴見によれば、純粋芸術と大衆芸術の区別は、2000年前の古代ギリシャ時代に専門的芸術家が誕生した時から続いてきた見方であるが、20世紀におけるマス・コミュニケーションの発達や、民主主義的な政治・経済制度の世界的拡大に伴って、さらにその分裂が大きくなった。
他方、限界芸術は5000年前に描かれたアルタミラ洞窟の壁画以来、それほど大きな変化もないまま、現在まで続いてきた。要するに、限界芸術は人類史上最初に現れた芸術の形態であり、純粋芸術も大衆芸術も、そこから派生して生まれてきたのだ。さらには、現在に生きる私たちも、生まれて初めて接するのは純粋芸術や大衆芸術ではなく、新聞紙で作った兜や奴凧(やっこだこ)、コマやしんこ細工のような限界芸術ではないかと鶴見は言う。限界芸術はあらゆる芸術の根源にある。専門的芸術家や職業芸術家以外のすべての人びとにとって、積極的な仕方で参加する芸術のジャンルは、すべて限界芸術に属するのだ。
詳しくは後述するが、鶴見は、大衆が国家などの中央機関から押し付けられた芸術を受動的に享受するのではなく、自発的・能動的に芸術に関わることを求めていた。芸術のもっとも根源的な形式であり、誰もが参加できる限界芸術は、国家の統制をすり抜け、権力者が作り出した社会像を越え出て、自分たちの精神を自分たちの手で表現するという重要な役割を担うのである。
柳田國男——限界芸術の研究
鶴見は、限界芸術の先駆的な研究事例として、柳田國男の民俗学を挙げる。柳田は各地の盆踊りや民謡、こけし人形や刺青など、従来は好事家的趣味や骨董趣味として扱われてきたものを一つの体系として理解し、各時代の日本人の集団生活の様式を浮かび上がらせようとした。

例えば民謡であれば、日本の民謡はヨーロッパと比べて作業歌(労働歌)が多く、そこから別の領域に移されて、多重の意味を持つようになるという。衣食住を確保するための労働があり、それを楽しい作業にするための遊びとして、作業歌や狩りの成功を願う壁画のような芸術の最古の形式が現れたのではないか。だが明治以降の工業化によって労働の性質は変化し、労働から歌を、そして楽しみを奪ってしまった。この状況に対する抗議が、労働者による歌声運動を生み出したが、そこで歌われるのは純粋芸術として作曲されたものであり、また労働中ではなく休憩時間中に歌われるものとして、労働行為そのものとは切り離されていた。
鶴見は、あらゆる種類の限界芸術が総出演で出揃うのが「祭」の時であり、映画が総合的大衆芸術であるのと同じ意味で、総合的限界芸術であると言う。祭という儀式のかたちを借りた限界芸術は、各時代の芸術を生み出す源泉となった集団生活の実態を集約した表現なのである。
祭の力強さは、各時代における限界芸術の創造性を測るバロメーターになるため、柳田國男は大正から昭和期にかけての祭の衰退を憂い、いくつもの文章を書いて「小祭」の復興を唱えている。祭が衰えたのは、それを演じる者と見る者とに分離したためである以上、大衆芸術と化した大規模な祭ではなく、小祭のみが限界芸術としての役割を果たせるのだ。だが鶴見は、そうした小祭を昔日のように復元することは難しいと言う。柳田國男は限界芸術に関する適切な分析を行ったが、適切な処方箋を示すことはできなかった。小祭に代わる新しい仕方での国民的信仰、新しい仕方での祭を作ることが、今後の課題となるだろう。
柳宗悦——限界芸術の批評
続いて鶴見は、限界芸術の批評家として柳宗悦の名を挙げる。柳宗悦は民藝運動とそれに伴う執筆活動を通じて、限界芸術を考えることは、政治、労働、家族生活・社会生活、教育、そして宗教との関係において芸術を考えることであると示し、限界芸術の批評の一つの水準を作り上げた。

柳宗悦が民藝論を書くきっかけになったのは、朝鮮への旅の中で、李朝の陶磁器に関心を持ったことである。無名の陶工たちの無意識の手仕事は、名の知れた個人的天才の仕事を遥かに超えている。柳宗悦はそうした「雑器」の美が、民衆の日常生活の中で用いられているからこそ生まれる「用の美」であると指摘し、それを「民衆的工藝」(民藝)と命名。各地の手仕事の伝統を調査して一種の地理学を作り上げ、雑誌『工藝』の発刊、たくみ工藝店や日本民藝館の設立など、民藝の美学を全国的に普及させる道を切り拓いた。

しかし柳宗悦も、限界芸術の批評としては優れた成果を上げたが、実作への関わりは傍観的な立場に留まったと鶴見は言う。柳の民藝論を思想的背景として、1927年には京都市上賀茂に工藝家のギルド「上賀茂民芸協団」が設立されたが、その試みはわずか2年で終わりを迎えた。柳宗悦が理想とするような工藝ギルドは、中世的な信仰や道徳などの思考・生活形態が残っている地域でしか成立し得なかったのだ。
鶴見は、柳宗悦が近代日本を超えて遠い未来を見通していたことを評価する一方で、近代日本に背を向け、近代以前に固執していたことを問題視する。柳宗悦の手仕事への愛は機械の軽視と結びつき、それゆえ限界芸術を機械的生産に反対する力としてのみ評価する。だが鶴見にとっての限界芸術は、民藝や手仕事の枠に収まらない。それはカメラや映画、アマチュア放送なども含むものとして捉えられることが望ましいのである。
宮沢賢治——限界芸術の創作
そして最後に、鶴見は限界芸術の創作者として、宮沢賢治の名を挙げる。宮沢賢治は詩や童話の創作だけでなく、1926年に私塾「羅須地人協会」を設立するなど、生活あるいは人生そのものが芸術となるようなあり方を求めて、新しい限界芸術への道を開こうとした。その取り組みは短期間で終わり、失敗や挫折と捉えられているが、鶴見はそこに、現代の日本社会に限界芸術を生き返らせるための手がかりがあると考えるのだ。

鶴見によれば、宮沢賢治の芸術観は、①「芸術を作る状況」、②「芸術をつくる主体」、③「芸術による状況の変革」という3つの考えによって成り立っている(p.51)。第一に「芸術を作る状況」とは、芸術の創造は、自分自身が今いる日常的な状況から為されなければならないということ。次に「芸術をつくる主体」とは、職業芸術家ではない一人一人の個人を指す。宮沢賢治は、人間の数だけ個性があるのだから、珍しがられる才能ではなく、自分が当然に持っている個性を深めるべきだと考える。そしてそのためには、職業芸術家を模倣するのではなく、身近な環境そのものに手本を求めなければならない。そして「芸術による状況の変革」とは、各個人が自分自身の本来的な要求に沿って、状況を変革していくことである。その変革は、誰かに強制されて行うことではないし、自分自身が無理をして行う倫理的な行為でもない。あくまでその人にとって自然な要求に従い、喜びが伴う行為である。
こうした考え方は自ずと、人生をそのまま芸術として捉える見方に近づいていくだろう。ただし宮沢賢治は、各人の一挙手一投足がすべてありのままで芸術なのだという立場には立たなかった。どのような行為も芸術の素材となり得るが、その行為を磨き上げ、高めていくことや、その行為に対する見方を深めていくことによって、初めて人は自分の人生を芸術として見ることができるようになる。また一度でも自分の人生を芸術として認識すれば、その人は普段の行動に今まで以上の表現力を持たせようとするだろう。このように、柳田國男や柳宗悦のように過去の復興を目指すのではなく、遠い未来へと芸術による変革の意思を向ける宮沢賢治の思想を、鶴見は高く評価するのである。

(岩手県立花巻農業高等学校)
鶴見俊輔の映画論
『限界芸術論』における映画の位置
では『限界芸術論』において、映画はいかなる芸術として位置づけられているだろうか。「芸術の発展」文中の記述を確認すると、映画は「総合的大衆芸術」(p.34)と述べられているが、他方で鶴見は、同論末尾に掲載した分類表「芸術の体系」の中で、「記録映画」を限界芸術、「時代物映画」を大衆芸術、「前衛映画」を純粋芸術に振り分けている。すでに確認したように、鶴見は芸術の三分類を固定したもの・対立し合うものと見做すのではなく、純粋芸術と大衆芸術は限界芸術から派生して出来たものであり、また非専門的芸術家が積極的に参加する芸術はすべて限界芸術に属するのだという見方を示していた。従って、基本的には大衆芸術に分類される映画も、その形式やジャンルに応じて、限界芸術あるいは純粋芸術にも分類し得るものとして捉えられるのである。

(鶴見俊輔『限界芸術論』ちくま学芸文庫、1999年、p.88)
限界芸術としての映画
限界芸術としての「記録映画」に関して、鶴見がいかなる考えを持っていたのかについては、座談会「映画とはいかなるものか——映画とテレビそして大衆」(波多野完治・南博・鶴見俊輔・岩崎昶、『キネマ旬報』1959年1月 新年特別号(No.222)、キネマ旬報社)に手がかりを見出すことができる。そこで鶴見は、同じ映画を繰り返し見ることができないという当時の配給制度のあり方に疑問を呈し、テレビの台頭によってその状況が変革されることに期待を寄せる。一週間のプログラムを作って古い名作を流すなど、同じ映画をテレビで繰り返し放送することで、「映画の鑑賞方法がかわり、同時に映画の本質も変化し、新しい可能性が出て来る」(p.81)と言うのである。そして、その新しい可能性として挙げられるのが、大衆による映画・映像制作への参加である。
たとえば私小説のような私映画を、個室の中でテレビで見れば、ちょうど心境小説を読んでいるように、映画のちがった味が出て来るはずです。8ミリなんかそういう風に使われたらいい。またナポレオンとかナセルとか、やがて死んでしまう人間の映画をつくり、これを録音構成のようにしてテレビに流す。ニュース映画はもちろんです。見る論文みたいなものもできる。抽象的なものを絵画的に具象化する方法ですね。こうしてテレビは映画を革新するでしょう。(中略)8ミリなんかを使って、それを「ひととき欄」と同じ形でとって行く。投書して行く。それを大衆が番組として、コメントなんかつけて載せて行く。大衆社会において、非常に大きな循環がテレビを通じて映画産業の中に出て来る。これは全く新しい映画の発展形式だ。
「映画とはいかなるものか——映画とテレビそして大衆」
『キネマ旬報』1959年1月 新年特別号(No.222)、キネマ旬報社)、p.83
この時点ではまだ、「限界芸術」という語は用いられていない。だが8ミリ映画やニュース映画は、非専門的芸術家としての大衆によって制作され、非専門的享受者としての大衆によって享受されるという点で、まさに限界芸術の条件を満たすものであり、それゆえ鶴見の関心対象となったのも自然な流れと言えよう。
上記座談会で語られた私的な映画の私的鑑賞は、当時すでにアマチュアによる小型映画として実現していたが、その後のホームビデオの普及、地方ケーブルテレビ局などによる市民チャンネル、そしてインターネットの動画配信の普及によってさらに規模を拡大させていくことになる。また「ひととき欄」(『朝日新聞』くらし面の女性読者投稿欄)のように映画・映像を投稿したり、それにコメントを付けたりすることも、今日の動画配信サービスやブログ、SNS上のビジュアルコミュニケーションとして——鶴見が望んだかたちであるかどうかはともかくとして——すでに実現している。
マス・コミュニケーションとしての映画
他方、鶴見はちくま学芸文庫版『限界芸術論』所収の「ラジオ文化」(初出1950年)において、新聞や雑誌、ラジオなどマス・コミュニケーションの文脈からも映画について論じている。
さしあたり鶴見は、文化とは「まきちらされるもの」(p.119)であるという。ただし、あらかじめ特定の場所にすでに完成した文化なるものがあって、それが撒き散らされるのではなく、それが撒き散らされる手続きも含めて、初めて文化は形成されていく。「文化はまきちらされることによって文化となるのだ」(p.119)。
またそこで、決定的な役割を果たすのが「言語」である。人間は言語を用いるようになって初めて、自由に思索をし、その思索を他者に伝達したり、後世に伝達したりすることが可能になった——すなわち、文化を撒き散らすことができるようになった。その意味で、文化は言語と共に生まれたのだと言って良い。
鶴見によれば、文化の撒き散らし方の形態は、民謡に似た音声言語、盆踊りに似た身振り言語から始まり、その後、文字言語と紙、印刷技術の発明によって民衆も読み書きの能力を得るようになり、そこから新聞や雑誌のような新たな文化の撒き散らし方が現れてきた。さらには映画、ラジオと新たな複製技術が登場するにつれ、次第にマスメディアによる「コミュニケーションの強制力」(p.121)が高まっていく。新聞や雑誌を読むためには一定の能動性が必要なのに対して、映画は一度見始めたら受動的に最後まで見てしまうという点でコミュニケーションの強制力が働くが、それを見るためには自発的に映画館に通わなくてはならないという点では、まだ能動性を必要とする。だがラジオは、スイッチを押しさえすれば、自宅に居ながらにして受動的に情報を受け取ることができるのである。
鶴見は、ラジオが持つ強い強制力が国家などの中央機関によって利用され、大衆の思想を統制し、その行動を規定していくことを危惧する。オーソン・ウェルズが火星人の侵略を報じるラジオドラマ『宇宙戦争』(1938)を放送してパニックが起きたという都市伝説を引き合いに出し、ラジオは単純だがセンセーショナルな思想内容を撒き散らすことによって、人びとを爆発的な行動に駆り立てること力を持つことを指摘するのだ。

このように映画は、一方では、新聞や雑誌よりもコミュニケーションの強制力が強く働くが、他方では、ラジオよりも能動性を必要とするという、中間的なメディアとして捉えられている。そしてそれを、今後、どちらの方向に発展させていくかが問われるのだ。
大衆芸術としての映画
また鶴見は、時代物映画やチャップリンなどを中心とするアメリカ映画などの大衆芸術を論じる際にも、教養人・文化人である自分の中にもある一人の「大衆」としての視点を以て作品を鑑賞し、大衆の持つ制度批判的な側面や、創造的側面を見出していくことを批評の方針とする。
支配者のつくった制度のわずらわしさをすりぬけてたつ大衆の姿は、これまでもさまざまな国の大衆小説や大衆的映画の中にえがかれたことはあった。この動きは、これからも、国家の統制をすりぬけてさらにすすめられるであろう。(中略)大衆は替え歌や落書きや流言やおとし話の、いわば大衆文化の最も原始的な様式を通して、国家権力者のつくり出した社会像を超えようと努力するであろうし、権力者のつくりだした文化の諸様式の意味のあいまいさを転用して、自分たちの精神を表現する道を見つけるであろう。
こうした試みの初期の例として、「一つの日本映画論——「振袖狂女」について」が挙げられる(『限界芸術論』所収、ちくま学芸文庫、1999年、初出1952年)。
安田広義『振袖狂女』(1952)では、大阪の陣の後、豊臣家の家臣であった弥右衛門(長谷川一夫)ら3名が、君主・秀頼の娘である鶴姫を連れて逃亡生活を送る姿が描かれる。道中、弥右衛門は仲間からの密告に遭い、共に逃げてきた許嫁の佐枝(宮城野由美子)と離れ離れに。弥右衛門は鶴姫と落ち延びた先で人形使いの一座と出会い、座長の娘で宇津木(山根寿子)の婿として一行の旅に加わることになった。宇津木は以前夫を亡くしており、鶴姫と同い年の娘がいる。
人形使い一座は、徳川家康が主催する芸人の腕競べに参加するため駿府(すんぷ)城に向かう。弥右衛門はこの機に乗じて、家康への報復を図っていた。一方、女歌舞伎一座に加わっていた佐枝もまた、家康暗殺のため駿府城へ。再会した2人は互いの愛情を確かめ合い、共に計画を実行に移そうとするが、弥右衛門は事情を察した宇津木に引き止められる。
結局、1人で暗殺を試みた佐枝は捕らえられ、弥右衛門と宇津木にも追手がかかり、森の中に追い詰められた。宇津木は夫のために、自分の娘を鶴姫であると偽って徳川家に差し出し、子が処刑されたら後を追って自分も死ぬと言う。
鶴見は『振袖狂女』について、佐枝と宇津木の行動の一貫性を指摘する。宇津木は封建的な思考方式に基づき、思想そのものに殉じるのではなく、自分が愛する人が信じているからという理由で、その思想に殉じる。他方、佐江は愛する人が己の思想を手放しても、自分自身の意思でその思想に殉じることを選ぶ、新しい時代の女性像を体現している。一見、佐枝と宇津木は対照的な立場のように思えるが、最後まで己の信念を曲げない一貫性を持つ点においては共通していると言えるだろう。だが弥右衛門は、「善意の男」ではあるが2人の女性の間でぐらぐら揺れ、結果的に自分の安全を最優先して、双方を裏切ってしまう。鶴見はその姿に、現代の日本におけるインテリの男たちの姿を重ね合わせる。観念的には一貫性がありそうな思想を説きながら、実際の生活では、封建的な思考方式に囚われた女たちが持つ一貫性にさえ達することができていない。そのような、男と女に関わる現実社会の問題を、『振袖狂女』の物語は反映していると言うのだ。

同作の終盤、処刑されたかと思われた宇津木の娘は、官吏の配慮により処刑を偽装することで死を免れ、両親の元に戻ることができた。人形使いの子として今後の生活を送ることになった鶴姫と宇津木の娘の2人は、手をつなぎ、人びとが行き交う野道を歩き去っていく。鶴見はこの結末について、映画全編の思想的課題を解くものであると言う。すなわち、豊臣家の血筋は、権力者によって利用されるべき旗印として受け継がれるのではなく、民衆の中にその姿を沈めることによって受け継がれていくのである。
真に伝統をになうためには、伝統のにない手を、家元制度からときはなって、民衆の中に、かえすことがなければならぬ。そうでなければ、今日の日本文化のように、伝統は衰弱してゆくばかりであろう。
一人の大衆として書くこと
「一つの日本映画論」の冒頭、鶴見は、毎日新聞社が主催する映画コンクールの投票に参加した際に、自分が良いと思った作品と、他の識者が評価する作品との間に大きな隔たりがあったという経験について語っている。当時はまだ、文化人が好むような「高級」な映画ばかりが評価され、大衆娯楽的な映画は程度の低いものと見做されてきたため、専門的な雑誌などを除けば、本格的な評論や批評の対象となることは稀だった。映画研究における鶴見の最大の功績は、自身の執筆活動や『思想の科学』の出版を通して、大衆文化や大衆芸術を語ることの重要性を広く周知し、認めさせたことにあるだろう。
そして、同論を読む上でもう一つの重要な点は、その論述のスタイルである。鶴見は大衆娯楽的な作品の面白さを理解するには、自分自身が一人の「大衆」として経験してきたことを顧みる必要があると主張する。例えば子どもの頃、侠客の国定忠治や暗殺者の相馬大作、盗賊の鼠小僧次郎吉などが政府の手先に追われたり殺されたりする物語を漫画や講談本で読んだことで、警官や兵隊に憎悪や恐怖の感情を抱き、通学中に交番前をドキドキしながら通過したような経験は、「精神の「慣用語法」」(p.391)として、大人になった鶴見の心の最下層に残っており、現在の思想にも影響を与えている。「政府が悪いものだという考え、権力者が茶化さるべきものとしてあるという考えは、漫画と講談とが、ぼくの心の深くに植えてくれたものとして今日もあるのだ」(p.390)。
そうした影響が思想の成長を妨げている側面もあるかもしれないが、それを一度に捨て去ろうとしたり、無かったことにしようとしたりすることも、精神の発達の上で不健全であると鶴見は言う。例えば高校生の頃に哲学書を愛読していた青年が、大人になり出世してからは娯楽雑誌しか読まなくなったり、青年期の西洋主義者が、老年になって急に日本主義に転じるようなことがしばしばある。そうした逆戻りに陥らないためにも、精神に与えられた慣用語法を常に意識し、自分の今後の思想の問題を考えていくことが重要なのだ。
以上のような考えに基づき、鶴見は映画のあらすじを語りながら、その場面の鑑賞中に感じたことや、過去の人生経験、記憶などとの結びつきを、括弧に入れて記述していく。例えば以下のように。
宗右衛門。「姫をこのまま、かくしおおせるか。日本国中、太閤恩顧の大名は、ひとりとして徳川家康になびかぬものとて、ないのだぞ。」
弥右衛門。(しばらく、黙っていて急に)「おれは家康を討つ。」
(家康という名で、ぼくのきらいなものを考えて、心を動かされた。こどものころ、家康の名で思いうかべたいろんな絵姿とは別のものを今では心に描く。けれども、家康とか、豊臣の遺臣とか、そういう子供のころからつかいなれた慣用語法が、いまも、ぼくの感情にもっとも親しい。同じ慣用語によって今、ぼくは、別の対象についての感情をゆすぶられる。)
映画を見ている自分自身の心の動きや、その感情がいかなる過去の経験から生起するものなのかを不可欠な要素とする鶴見の映画論は、これまで紹介してきたクリスチャン・メッツやローラ・マルヴィ、ベル・フックス、ロバート・スタムやエラ・ショハットなど、映画の意味生産における「観客」の重要性に光を当てた研究や批評の先駆けであるとも言えるだろう。鶴見にとって「大衆」とは、皆が受動的に情報を受け取り、同じ思想や趣味・嗜好を持つ均質化した存在ではなく、個々人が異なる思想や経験を持ち、能動的・自発的に行動する「私性」を持つ存在であった。
地上を自分の足であるいている大衆のひとりが、飛行機の上から地上を見おろす官僚群にたいして、なんのひけ目も感じないで見かえす時が来る。そのありうべき政治の状態を、これらの大衆文化の諸様式は先どりして実現する。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
