
原一男 監督 『水俣曼荼羅』 : 捨て去られた人びとの 〈尊厳を賭けた闘い〉
映画評:原一男監督『水俣曼荼羅』
6時間に及ぶドキュメンタリー大作だが、原一男監督の代表作である『ゆきゆきて、神軍』のような、強烈なインパクトがあるわけではない。むしろ、長年「水俣病訴訟」を闘ってきた人たちの苦闘が、じわじわと息苦しく胸に迫ってくる作品だと言えるだろう。
水俣病のことをまったく知らない若い人ならばともかく、私のような昭和30年代生まれの人間にとっては、今や、水俣病の表面的な恐ろしさよりもむしろ、その後の裁判における「国家の恐ろしさ」、そして「人間の非情さ」というものの方に、あらためてショックを受けざるを得ない。「長年、報われない闘いに生きてきた、この人たちの一生とは、いったい何だったのであろうか」と。
『(前略)原一男が最新作で描いて見せたのは、「あの水俣」だった。「水俣はもう、解決済みだ」そう世間では、思われているかも知れない。でもいまなお和解を拒否して、裁判闘争を継続している人たちがいる一穏やかな湾に臨み、海の幸に恵まれた豊かな漁村だった水俣市は、化学工業会社・チッソの城下町として栄えた。しかしその発展と引きかえに背負った〝死に至る病″はいまなお、この場所に暗い陰を落としている。不自由なからだのまま大人になった胎児性、あるいは小児性の患者さんたち。末梢神経ではなく脳に病因がある、そう証明しようとする大学病院の医師。病をめぐって様々な感情が交錯する。国と県を相手取っての患者への補償を求める裁判は、いまなお係争中だ。そして、終わりの見えない裁判闘争と並行して、何人もの患者さんが亡くなっていく。
しかし同時に、患者さんとその家族が暮らす水俣は、喜び・笑いに溢れた世界でもある。豊かな海の恵みをもたらす水俣湾を中心に、幾重もの人生・物語がスクリーンの上を流れていく。そんな水俣の日々の営みを原は20年間、じっと記録してきた。
「水俣を忘れてはいけない」という想いで―壮大かつ長大なロマン『水俣曼荼羅』、原一男のあらたな代表作が生まれた。』
(『水俣曼荼羅』公式サイト、内容紹介文)
本作は3部構成で「第1部 病像論を糾す」「第2部 時の堆積」「第3部 悶え神」となっており、水俣訴訟に生涯をかけた人たちの姿が、多角的に捉えられていて、原監督個人の視点は抑制的だ。
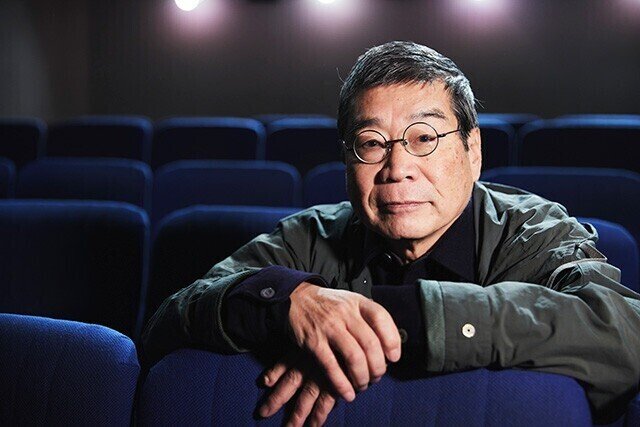
(原一男監督)
『「ゆきゆきて、神軍」「全身小説家」「ニッポン国VS泉南石綿村」などを世に送り出してきたドキュメンタリー映画の鬼才・原一男監督が20年の歳月をかけて製作し、3部構成・計6時間12分で描く水俣病についてのドキュメンタリー。日本4大公害病のひとつとして広く知られながらも、補償問題をめぐっていまだ根本的解決には遠い状況が続いている水俣病。その現実に20年間にわたりまなざしを注いだ原監督が、さながら密教の曼荼羅のように、水俣で生きる人々の人生と物語を紡いだ。川上裁判で国が患者認定制度の基準としてきた「末梢神経説」が否定され、「脳の中枢神経説」が新たに採用されたものの、それを実証した熊大医学部・浴野教授は孤立無援の立場に追いやられ、国も県も判決を無視して依然として患者切り捨ての方針を続ける様を映し出す「第1部 病像論を糾す」、小児性水俣病患者・生駒さん夫婦の差別を乗り越えて歩んできた道程や、胎児性水俣病患者とその家族の長年にわたる葛藤、90歳になってもなお権力との新たな裁判闘争に懸ける川上さんの闘いの顛末を記した「第2部 時の堆積」、胎児性水俣病患者・坂本しのぶさんの人恋しさとかなわぬ切なさを伝え、患者運動の最前線に立ちながらも生活者としての保身に揺れる生駒さん、長年の闘いの末に最高裁勝利を勝ち取った溝口さんの信じる庶民の力などを描き、水俣にとっての“許し”とはなにか、また、水俣病に関して多くの著作を残した作家・石牟礼道子の“悶え神”とはなにかを語る「第3部 悶え神」の全3部で構成される。』
(水俣曼荼羅 : 作品情報 - 映画.comより)
水俣病患者と「認定」されなければ、補償を受けることはできない。しかし、外見的に誰が見てもわかるような、わかりやすい症状が出ておれば、容易に水俣病患者と認定されるが、そこまでいかない、外見上はわからない患者、あるいは、生まれた時から神経が犯されていたがゆえに、本人すら気づきにくいような患者については、これまで認定がなされなかった。

そこで、熊本大学医学部の浴野教授は、水俣病とは「手足の抹消神経がおかされる病気」ではなく「有機水銀によって、脳の一部を損傷する病気」であることを立証する。つまり、外見的な障害が無く、本人にその自覚がなくても、脳を調べれば、その状態において水俣病であることがわかることになり、そうなれば、これまで認定されてこなかった多くの人について、認定の道が開けることになるはずなのだ。
ところが、これまでの表面的で限定的な病像論が覆され、多くの患者たちが、これで救われると喜んだのもつかの間、熊本県や国は、そうした新しい病像論に従った新基準での拡大認定を行おうとはしなかった。仮に、脳に損傷箇所が見つかったとしても、すでに事件からは相当な時間が経っているために、それがチッソの排出した有機水銀によるものであるとは特定できない、といった理屈である。
時には患者からの協力を拒まれてまで、苦労して画期的な病像論を確立した浴野教授は、それが直截に患者の救済に繋がらなくても、自身の研究は学術的な成果として正当に評価されるべきだと考えるが、そうした学者としての思いは、患者たちにはストレートには届かない。真実がわかったところで、救われなければ意味がない、と考えてしまうからだ。
しかしまた、そうであるからこそ、浴野教授の研究は、ある意味、孤立無援で、孤独なものであった。実際問題として、水俣病の研究を進めて、新しい事実を突き止めるということは、これまでの先輩学者たちの研究成果を覆すことであり、学会においても決して喜ばれることではなかったからだ。
浴野教授は、苦笑を浮かべながら語る。「水俣病の研究をしてても、何も良いことはないですよ。そこで成果を上げても、だからと言って、その後はどこからもお呼びなんかかからない。むしろ私は異端者です」(※ 趣旨)と。
だからこそ、せめて「学者としての実績」として認められたいと願うのだが、その願いは患者たちの「現実」とは、微妙にすれ違ってしまうのである。

(熊本大学医学部の浴野教授)
また、裁判に勝っても負けても、結果としては満足な成果が得られず、徒労感のみが募っていく「終わりの見えない裁判闘争」において、すべての人が「最後まで闘い抜く」という覚悟が持てるわけではない。
歳をとれば、疲れも出てくる。「もう、これ以上やっても、生きている間に救われることはないのだから、このあたりで妥協して、あとは平穏な生活を送りたい」と考える人も、当然出てくる。それに対し「ここで妥協したら、奴らの思うツボでじゃないか。もはやこの裁判は、勝ち負けの問題ではなく、死んでいった多くの人たちの無念を晴らすべく、正義を貫くものでなければならない」と、そう考える人もいる。

そうなると、患者間にも隙間風が吹き、対立的感情さえ生まれてくる。そしてそれは、一人の個人の中でだってそうなのだ。「最後まで闘い抜く」という意地と「もう、これ以上やっても無駄だ。楽になりたい」という葛藤が、私財を抛ち、全人生を賭け、裁判闘争の先頭に立って闘ってきた人の中でさえ、何十年と秘められていたのである。

胎児性水俣病患者・坂本しのぶさんは、一一あまりも可愛そうだ。
好きで水俣病患者として生まれてきたのではない。好きで、その「歪んだ外見」を選んだわけではない。彼女の内面は、ごく普通に、ロマンティックな「恋愛をしたい」と願う、そんな女性なのだ。
そして、周囲の支援者は、そのことを十二分に理解していながら、しかし、彼女の恋心に応えることはできない。その「外見」や「障害」を無視できず、個人的には支えきれないと感じるからだろう。そして、それを責めることは、誰にもできないのだ。


水俣病をめぐって、それぞれがそれぞれの立場で懸命に闘い、生きている。
だが、その苦労が十全に報われることは、決してない。そう断じても良いだろう。だから、そうした姿を見ているこちらだって辛いのだが、しかし、せめて見ることによる「苦しみの分かち合い」くらいは、私たちも担うべきなのではないだろうか。今の私たちの生活は、間違いなく、こうした人たちの犠牲の上に築かれているものなのだから。
いずれにしろ、これが私たちの住むこの世界の、動かしがたい「事実」なのである。
(2022年3月12日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
