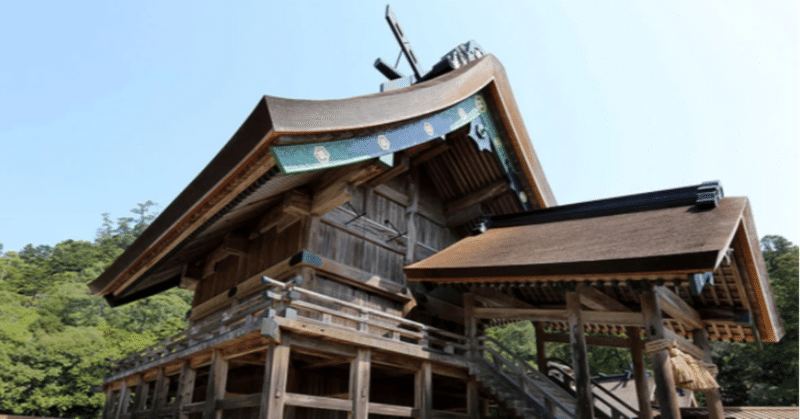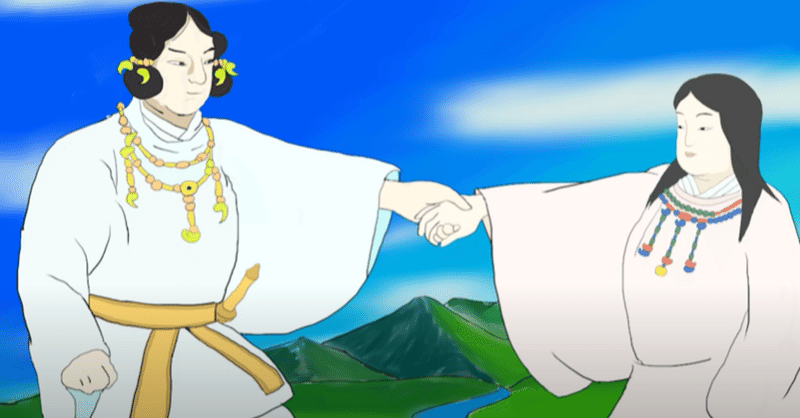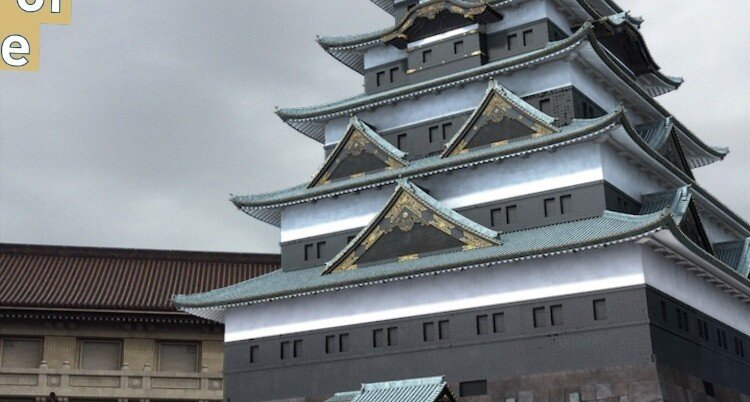
- 運営しているクリエイター
2022年3月の記事一覧
JW115 遅すぎる立后
【孝昭天皇編】エピソード6 遅すぎる立后
前回は、石津太神社(いわつのおおじんじゃ)について紹介させてもらった。
そして、あれから二十二年もの歳月が流れたのであった。
すなわち、紀元前447年、皇紀214年(孝昭天皇29)1月3日、立后(りっこう)がおこなわれたのである。
第五代天皇、孝昭天皇(こうしょうてんのう)こと、観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしね・のみこと)(以下、松彦)が上機嫌で
JW116 御長寿たち
【孝昭天皇編】エピソード7 御長寿たち
紀元前447年、皇紀214年(孝昭天皇29)1月3日、第五代天皇、孝昭天皇(こうしょうてんのう)こと、観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしね・のみこと)(以下、松彦)の立后(りっこう)がおこなわれた。
そして、大后(おおきさき)の一人、世襲足媛(よそたらしひめ)(以下、ヨッシー)が高らかに宣言するのであった。
ヨッシー「大王(おおきみ)が活躍してないおかげ