
JW113 塞がれた港
【孝昭天皇編】エピソード4 塞がれた港
紀元前473年、皇紀188年(孝昭天皇3)4月、无謝志国(むさし・のくに:今の埼玉県・東京都周辺)に氷川神社(ひかわじんじゃ)が創建された。






その解説の中で、第五代天皇、孝昭天皇(こうしょうてんのう)こと、観松彦香殖稲尊(みまつひこかえしね・のみこと)(以下、松彦)は驚愕する。
北陸地方に、先代の懿徳天皇(いとくてんのう)を祀った神社が有るというのである。
ヤマトまでやって来た、出雲(いずも)の先代君主、出雲櫛月(いずも・の・くしつき)(以下、月)と、新たに君主となった櫛瓺鳥海(くしみかとりみ)(以下、とりみ)の解説は続く。
松彦「なっ! 先代・・・父上の神社が、北陸地方に有ると!?」
とりみ「先代、懿徳天皇を祀る神社が有るんだに。」
松彦「出雲の勢力圏であるはずの北陸地方に、父上の神社・・・。」
月「どう考えても、おかしいよね?」
松彦「されど、これまでにも、富山県に、二代目の綏靖天皇(すいぜいてんのう)を祀った神社が有ると紹介されておるぞ。エピソード97じゃ。有礒正八幡宮(ありそ・しょう・はちまんぐう)という、高岡市(たかおかし)の横田町(よこたちょう)に鎮座する神社じゃ。」





月「その通り! 徐々に、勢力が弱まっていたんだろうね。」
とりみ「そして、生活に困った人たちは、坂東(ばんどう)に移住したんじゃなかろうか・・・。」
松彦「そ・・・そんなことが・・・。」
月「宍道湖(しんじこ)の西側が塞(ふさ)がったことで、出雲の海外交易が下火となり、職を失う者が出て来たのかもしれないね。」
松彦「塞がった?」
とりみ「太古の昔、宍道湖の西側は開けていて、海とつながっていたんだに。天然の良港として、海外貿易をおこなっていたみたいなんだっちゃ。」
松彦「それが塞がったと?」
月「地震で、地殻変動が起きたんじゃないかな。徐々に塞がっていったというよりも、一気に地面が隆起して、海と隔てられたのかもしれないね。」


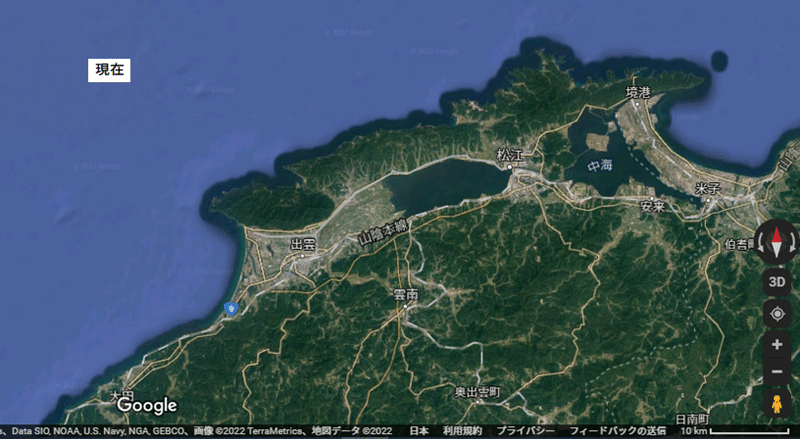

松彦「そ・・・それでは、海外と貿易できなくなる・・・。出雲だけでなく、我が国の損失となる。これは、ただごとではないぞ!」
とりみ「安心してほしいんだに。北九州が残っちょる。」
松彦「あっ! そうか、北九州が有ったな・・・。」
月「まあ、そういうわけで、北九州が主要港となり、出雲の勢力は弱まっていったんじゃないかな。それで、生活に困る人たちが出て来て、坂東(ばんどう)に移住したんだろうね。」
松彦「なるほど・・・。ところで、北陸地方にあるという、父上の神社紹介はしてくれぬのか?」
月「仕方ないなぁ。では、紹介します。その名も、櫟原北代比古神社(いちはらきたしろひこじんじゃ)だよ。」
とりみ「祭神は、懿徳天皇だっちゃ。二千年後の地名でいうと、石川県輪島市(わじまし)の深見町(ふかみちょう)に鎮座しちょるぞ。」








松彦「石川県・・・。二代目を祀る神社が、富山県。この辺りの人たちが、移住した可能性があるということか?」
月「そうかもしれないね。生活が苦しくなったことで、出雲文化圏に属していた、石川県や富山県の人たちが、出雲から分離独立し、ヤマト政権に参加したのかもね。」
とりみ「されど、参加したからと言って、すぐに暮らしが良くなるわけでもない。そこで、移住という対策を考え出したのではなかろうか。」
松彦「そして、移住者たちによって、无謝志国に氷川神社(ひかわじんじゃ)が創建されたと?」
とりみ「そげだ(そうです)。ちなみに、氷川(ひかわ)という名称も、出雲の斐伊川(ひいかわ)から来ているという説が有るんだに。」
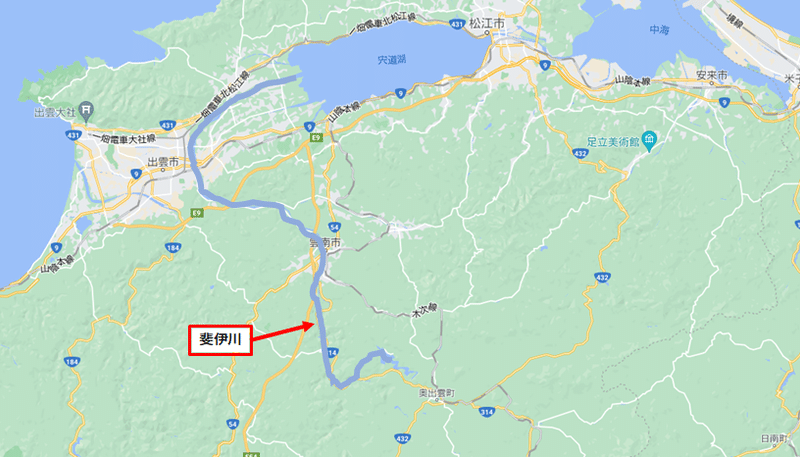
松彦「驚きの連続であったな・・・。」
とりみ「それでは、解説も終わったことだし、出雲に帰るとするか・・・。」
月「そうだね。」
こうして、出雲の君主親子は、帰っていったのであった。
そして、氷川神社が創建されて、四年の歳月が流れた。
すなわち、紀元前469年、皇紀192年(孝昭天皇7)8月10日、石津太神社(いわつのおおじんじゃ)が創建されたのである。
松彦「な・・・なんじゃ? 唐突過ぎぬか?」
そこに、中臣御食臣(なかとみ・の・みけつおみ)(以下、ミケツ)がやって来た。
ミケツ「石津太神社が創建されたのであらしゃいます。」
松彦「そ・・・そのようなことは分かっておる。どちらの神様を祀(まつ)ったのじゃ?」
ミケツ「それについては、我が息子、伊香津臣(いかつおみ)が解説致しますぅ。『イカ』とお呼びくださりませ。」
松彦「イ・・・イカ?」
イカ「はい。我(われ)が『イカ』にあらしゃいます。石津太神社は、大王(おおきみ)の勅願(ちょくがん)で建てられた神社にあらしゃいます。」
松彦「わ・・・わしが、お願いして、建ててもらったのか?」
イカ「忘れておられまするのか? 『いけず(意地悪)』ですなぁ。」
松彦「わ・・・忘れていたわけではないぞ。こ・・・これは、読者のためで・・・。」
ミケツ「では、大王。祭神は、説明せずとも、分かりますなぁ?」
イカ「分からないなどと『いけず』なことを仰られるとは思えませんが・・・。」
松彦「わ・・・分かっておる。『えびす様』をお祀りしたのじゃ。二千年後、福の神の一柱(ひとはしら)となっておる神様じゃぞ。」
イカ「その通りにあらしゃいます。右手に釣り竿、左脇に鯛を抱えた神様にあらしゃいますなぁ。」

松彦「福の神となった理由は知っておるか?」
イカ「それを説明するためには、まず『えびす様』が、海から流れ着く、漂着物の神様であるということを解説せねばなりませんなぁ。」
松彦「そうじゃ。漂着物の代表格が、クジラじゃ。クジラが流れ着いたことで、飢饉(ききん)から救われたという伝承が、各地に残っておるぞ。」
えびす様の解説は続くのであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
